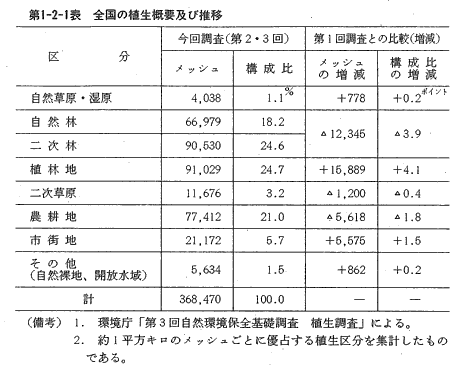
1 自然環境の現状
(1) 自然環境
南北約3,000kmに及ぶ日本列島は、数多くの火山、起伏の大きな山地、変化に富んだ海岸線等複雑な地形を持ち、気候的には亜寒帯から亜熱帯まで広がり、四季を通じて降水量も豊富である。このような気候風土から、我が国は豊かで多様な植生とそこを主な生活基盤とする各種の野生動物、多様な植生と複雑な地形がおりなす優れた景観がみられるなど、豊かな自然に恵まれている。
しかし、これらの自然は人間活動の長い歴史の中で各種の影響を受け、国土の自然環境は自然性の高い地域から低い地域まで、様々な状態となっており、完全に自然の状態を保っているものは極めて少なくなっている。
また、近年の自然改変の広域化、大規模化あるいは逆に、かつての薪炭材やカヤの採取のような自然利用の衰退による遷移の進行などに伴い、我が国の自然環境は著しく変ぼうしつつある。
このように急速に変ぼうしていく自然環境を適切に保全するためには、まず第一に自然環境の現況とその変化の方向を的確に把握することが必要である。
このため、自然環境保全基礎調査(「緑の国勢調査」)では、陸域(植物、動物、地形、地質)、陸水域(河川、湖沼)及び海岸域(海岸線や干潟、サンゴ礁などの浅海域の生態系)について、自然環境に関する情報を体系的かつ時系列的に収集、蓄積しており、これまで昭和48年度の第1回調査以降、概ね5年ごとに3回の調査を終えたところである。そのうち、ここでは第3回調査のうち結果の明らかになった「植生調査」及び「特定植物群落調査」によって陸域の緑の状況をみてみることとする。
ア 全国の植生の状況
第2回・第3回調査における「植生調査」(昭和54・58〜61年度)により、全国をカバーする縮尺5万分の1の植生図が完成したところであり、ここでは、この植生図について、約1平方キロのメッシュごとに該当する植物群落を読み取り集計した結果をもとに、全国の植生の状況をみてみる。
全国の植生概要は第1-2-1表のとおりで、自然草原と自然林を合わせた自然植生は、国土の19.3%と2割を切っている。そのうち、約6割が北海道に集中しており、北海道を除く地域では、その約1割にすぎず、大規模なものは標高の高い山地部に限られている。自然植生の割合を地方別にみると、北海道(49.7%)、東北(15.5%)、中部(15.2%)、沖縄(48.2%)で高く、その他の地方、特に中国(1.6%)、近畿(3.5%)、四国(3.9%)では低い。
森林は、木材生産のほか、国土保全、自然環境の保全等の多面的な機能を有しているが、その森林全体についてみると、国土の67.5%と高い割合を保っている。その内訳は自然林(18.2%)、二次林(24.6%)、植林地(24.7%)となっており、雑木林やマツ林のように薪炭材採取などの利用により生じた二次林やスギ、ヒノキ、カラマツなどの植林地が多くの部分を占めている。国土に占める構成比を第1回調査(昭和48年度)と比較すると、森林全体ではあまり変化していないものの、自然林、二次林は減少し、植林地は増加している。また、農耕地が減少している一方、市街地は増加した。
次に、かつては自然林として国土を広く覆っていたと考えられる、北海道渡島半島から東北・中部地方にかけての東日本を中心とするブナ林と西日本を中心とする照葉樹林の分布状況をみてみる(第1-2-2図)。
ブナ林は、クマ、カモシカなど多くの野生動物の生息の場としても重要であるが、そのうちブナ自然林についてみると、国土の3.9%となっている。これを林床植物の違いなどにより日本海側型と太平洋側型に分けてその分布をみると、日本海側型は、北海道渡島半島から本州中部までの日本海側に比較的大面積の分布域が残っているが、それらは山地部に限られ、それぞれが分断されたものとなっている。一方、太平洋側型では、さらにその分布域は限られ、大半が標高1,000m以上の山地帯上部に小規模に残るのみである。
シイ、カシ、タブなどの照葉樹林は、国土の1.0%とブナ林よりもさらに少ない。照葉樹林の分布域は、古くから高密な土地利用がなされてきた地域であり、様々な人為干渉により分布が狭められ、現在では離島、傾斜地など人間が利用しづらい場所や社寺林などに極めて小面積で断片的に残存するにすぎない。
イ 代表的な植物群落の変化状況
「特定植物群落調査」(昭和60年度)では、前回調査(53年度)で選定された地域の代表的、典型的な群落や希少な群落(3,835件)を対象として、前回調査以降の変化状況を調査した。
その結果、面積や群落構成が変化したり、消滅するなどの変化のあった群落は、全体の11.0%であり、そのうち主な群落の変化状況は次のとおりである。
(ア) 冷温帯落葉広葉樹林(ブナ林等)
ブナ林をはじめとするこの群落では、9.8%に変化があり、面積が減少した例が多い。
(イ) 暖温帯常緑広葉樹林(照葉樹林)
照葉樹林の主体を成すこの群落では、5.6%に変化があり、比較的都市地域に近いところにも分布していることから、各種の影響を受けている。特に大都市圏では、宅地開発や道路建設等都市的な土地利用に伴い、消滅又は面積が減少した例が多い。
(ウ) 湿地植生
ミズゴケの発達した高層湿原やヨシなどの低層湿原などの湿地植生では、19.0%に変化があり、農地造成や草地造成による消滅又は面積減少や植物の侵入による群落構成の変化など各地で様々な原因による影響を受けている。
(エ) 暖温帯常緑針葉樹林
マツ林やスギ林などのこの群落では、12.6%に変化があり、マツクイムシ被害による群落構成の変化や面積減少の例が多い。
(オ) 海浜植生
砂浜などの海岸に生育する海浜植生では、30.2%に変化があり、海浜の埋立てや護岸工事による消滅又は面積減少の例が多いほか、海水浴などの過剰利用やオートバイの乗り入れなど人の立ち入りによる影響を受けている例もみられた。
(2) 野生生物
我が国は、アジア大陸の東端にあってモンスーン気候帯に位置することから雨量が多く、亜寒帯から亜熱帯までにわたっているため、気温の変化も著しく、多様な動植物相を有している。同じく大陸に端にある島国英国と比較すると、面積は英国の1.5倍程度であるのに対し、種数では植物が2.2倍、哺乳類が同じく2.2倍、鳥類が2.4倍、爬虫類に至っては、15.2倍が生息している(第1-2-3表)。
なお、鳥類の中には国境を越えて渡りをするものが多いが、これらの種にとっても我が国は、繁殖地、越冬地又は中継地として重要な位置にある。
このように人口密度の高い国土に様々な野生生物が生息していることから、各種の開発事業、環境汚染、乱獲、外来種の移入等の人間活動が、生息域の減少や種の絶滅のおそれ等野生生物に対し種々の影響を与えるとともに、人間の側にも農作物被害等の問題を生じている。このため、野生生物との共存を図る必要がある。