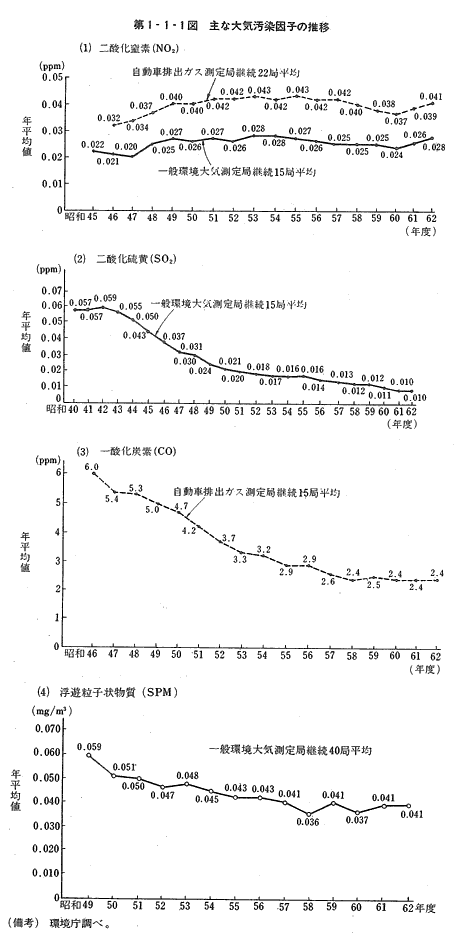
1 大気汚染
(1) 二酸化窒素
大気中の窒素酸化物はその大部分が燃焼に伴って発生するものであり、発生源としては工場などの固定発生源とともに、自動車などの移動発生源の占める割合も大きい。例えば、東京都特別区等の地域において67%、横浜市、川崎市、横須賀市の地域において32%、大阪市等の地域において47%を占めている(それぞれ昭和60年度)。
二酸化窒素の濃度をみると、昭和54年度以降改善の傾向がみられていたが、大気汚染の一般的状況を把握するため全国に設置されている一般環境大気測定局(以下「一般局」という。)においても、自動車排出ガス測定局(道路周辺における大気汚染を把握するため、沿道に設置されている測定局。以下「自排局」という。)においても、62年度は、61年度より悪化している。62年度の一般局における二酸化窒素濃度の年平均値をみると、61年度の0.026ppmより0.002ppm増加し、0.028ppmとなり、自排局における年平均値も61年度の0.039ppmより0.002ppm増加し、0.041ppmとなった(第1-1-1図)。
また、環境基準(1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。)との対応状況をみると、昭和62年度において基準の上限を超える局は、一般局で6.0%(61年度2.6%)、自排局で37.4%(同24.8%)と大きく増加している(第1-1-2図)。
これを、窒素酸化物の削減が特に緊要であるとして固定発生源について総量規制制度が導入されている3地域についてみると、環境基準の未達成の局が一般局101局のうち57局(昭和61年度98局中29局)、自排局68局のうち62局(同68局中52局)あり、汚染状況の悪化が認められる。
(2) 二酸化硫黄
大気中の硫黄酸化物は、主として石油、石炭などの化石燃料の燃焼に伴い発生するものであるが、硫黄酸化物低減のための諸対策が進められた結果、大気中の二酸化硫黄の濃度は、昭和43年度以降年々減少傾向を示してきた。
一般局における二酸化硫黄の年平均値をみると、昭和42年度の0.059ppmをピークに減少しており、62年度は0.010ppmとなっている(第1-1-1図)。
また、環境基準(1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。)の達成状況をみると、長期的評価による環境基準の達成率は、昭和62年度は99.6%(61年度99.5%)とほとんどの地点で環境基準が達成されている。
(3) 一酸化炭素
大気中の一酸化炭素は不完全燃焼により発生するもので、主に自動車排出ガスによるものとみられている。自動車に対する規制が昭和41年に開始され、逐次強化されてきた結果、自排局における一酸化炭素の濃度の推移を年平均値でみると、年々減少する傾向にあったが、ここ数年はほぼ横ばいであり、62年度は2.4ppmとなっている(第1-1-1図)。環境基準(1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。)の達成状況をみると、長期的評価による環境基準は59年度以降自排局、一般局ともすべての測定局で達成されている。
(4) 光化学オキシダント
光化学大気汚染は窒素酸化物と炭化水素類の光化学反応から二次的に生成される汚染物質によって発生するもので、その汚染状況は光化学オキシダント濃度を指標として把握されている。
昭和63年度における光化学オキシダント注意報(光化学オキシダント濃度の1時間値が0.12ppm以上で、気象条件からみてその状態が継続すると認められる場合に発令される。)の発令日数は、延べ86日であり、低温多雨だった夏の影響を受け、空梅雨だった昨年の約半分、一昨年と同レベルとなっている。これをブロック別にみると東京湾地域(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)で45日、大阪湾地域(京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県)で14日と両地域で全国の発令延日数の70%近くを占めている。
一方、昭和63年の光化学大気汚染による被害届出人数は全国計で延べ132人で過去最低であった一昨年に次いで少ない人数となっている(第1-1-3図)。
(5) 浮遊粒子状物質等
浮遊粒子物質は大気中に浮遊する粒子状物質のうち粒径10ミクロン以下のもので、大気中に比較的長時間滞留し、高濃度の場合には人の健康に与える影響が大きいものである。一般局の年平均値でみると、ここ数年は横ばいである(第1-1-1図)。また、一般局における環境基準(1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。)の達成率は、依然として低く、昭和62年度は52.6%と61年度(56.8%)に比べさらに低下している。
また、近年ディーゼル車の増加に伴い、ディーゼル黒煙等ディーゼル排出ガスによる環境への影響が問題となっている。
さらに、近年、積雪寒冷地におけるスパイクタイヤの使用に伴う粉じん等が問題となっており、例えば仙台市においては、スパイクタイヤの装着時期に合わせて降下ばいじん量が高くなっている(第1-1-4図)。
(6) その他の物質
以上の物質のほか、石綿(アスベスト)、水銀、ホルムアルデヒド及びダイオキシン類についてモニタリング事業が行われている。昭和62年度には石綿、水銀についての調査が行われた。
このうち、石綿は建材等に幅広く使用されているが、高濃度の石綿を長期間吸入することにより石綿肺、肺がん、悪性中皮腫等の健康障害が生じることが知られている。環境庁においては昭和60年度より住宅地域等の大気中の石綿濃度や石綿の発生減となる石綿製品等製造工場、廃棄物処分場などの周辺の大気中濃度についてモニタリングを行ってきた。加えて、62年度には石綿発生源の精密調査を行った。これによれば建築物の解体工事現場、廃棄物処分場については概ね問題となる事例はみられなかったものの、一部の石綿製品等製造工場の周辺で高濃度が散見されている(第1-1-5表)。
また、酸性雨は、欧州諸国、北米等において森林の枯死、湖沼の魚の死滅等様々な形で生態系に深刻な影響を与え、国際問題となっている。我が国では諸外国でみられているような生態系に対する影響は現段階では顕在化していないが、昭和58年度から行ってきた調査によるとpHが4台で、欧州並みの酸性物質を含む雨が全国的に観測されている(第1-1-6表)。