

滋賀県南東部の愛知川(えちがわ)流域に、株式会社IHIと東近江市が連携して、生物多様性保全活動や環境教育の場を提供している『東近江市建部(たてべ)いきものの水路』があります。
この地域は、山地を流れる河川が運んできた砂礫が堆積する扇状地が発達し、水が地下にしみ込んで伏流しやすいという特徴があるため、昔から水の確保に苦労していました。このため、愛知川上流に農業用のダムが造られ、今では関西有数の水田地帯となっています。この農業用ダムからの排水路のひとつが、今回紹介する水路です。愛知川は、扇状地を流下することも相まって、昔から流れが途切れる『瀬切れ』現象が発生します。瀬切れは、例年ほぼ同じ区間で発生し、愛知川と琵琶湖を行き来する魚類などの生息に大きな影響を与えます。愛知川と接続する今回の水路は、その瀬切れ発生区間に位置しているため、愛知川本流の魚の避難場所として活用することができます。さらに、この水路を生き物がすみやすい環境に整えることで、琵琶湖の固有亜種であるビワマスやアユの生育環境が改善し、里にすむ身近な魚類などの生息環境も守られます。

通常の愛知川(左)と『瀬切れ』が起きた状態の愛知川(右)。

水路に石を置いて流れに変化を生じさせる「バーブ工(こう)」と呼ばれる手法で、魚がすみやすい環境を作ります。
IHI社会基盤事業領域 事業推進部 防災・減災ソリューショングループの吉田公亮さんにお話を伺いました。
「愛知川流域にはIHIグループのIHIインフラ建設の工場があります。IHIインフラ建設は橋梁や防災・水門事業を行っており、愛知川から取水した農業用水の管理システムを土地改良区に納入したことがあります。そのつながりで、2022年に滋賀県の治水のリスク評価に携わっている大学の先生から愛知川の問題解決に取り組もうと声をかけられ、活動が始まりました。
この活動にはIHIの社内副業メンバーが参加しており、水路の調査や清掃、魚の生息環境の改善を行っています。社内副業とは、自分の業務時間の最大2割までを別の業務にあてることができる制度で、現在は9名ほどのメンバーが定期的に現地を訪れています」

愛知川の支流、渋川でビワマスを観察する様子。

愛知川から水路にアユが流入していることを確認しました。
「生物多様性保全活動に加え、環境教育にも力を入れています。農業排水路に隣接して、東近江市の環境教育拠点施設『河辺いきものの森』があり、市が委託するNPO法人遊林会によって自然体験活動が行われ、年間1万8,000人が訪れています。今後は『河辺いきものの森』と農業排水路の一体的な利用も視野に入れ、 森と川のつながりを意識した自然体験活動の場として活用してもらいます」

『河辺いきものの森』では、川を使った自然体験教室が行われています。
吉田さんは、この活動を進めるうえでの難しさについても話してくれました。
「川や水路は公共のものなので、漁業や農業、遊びなど、多様な利用者の調整が必要です。例えば、農業用の取水や排水を考慮しすぎると魚類の生息環境が悪くなる可能性が出てきます。特定の意見だけを採用すると、他の人が困ることがあるため、各所の調整は非常に難しいと感じています。ただ、そのような関係者間の調整を通じて、さまざまな視点から物事を見ることができるようになりました。生物多様性保全の活動がすぐに事業につながるとは言い難いので社内の理解を得るのは難しいですが、自然共生サイトに認定されたことで社内の理解も深まりました。また、事業の持続性という観点では、生物多様性の損失に関わる事業リスクや、生物多様性の保全に伴う事業機会を探索することは重要ですので、自然再生の活動を通してアンテナを高めることが大事だと思います」
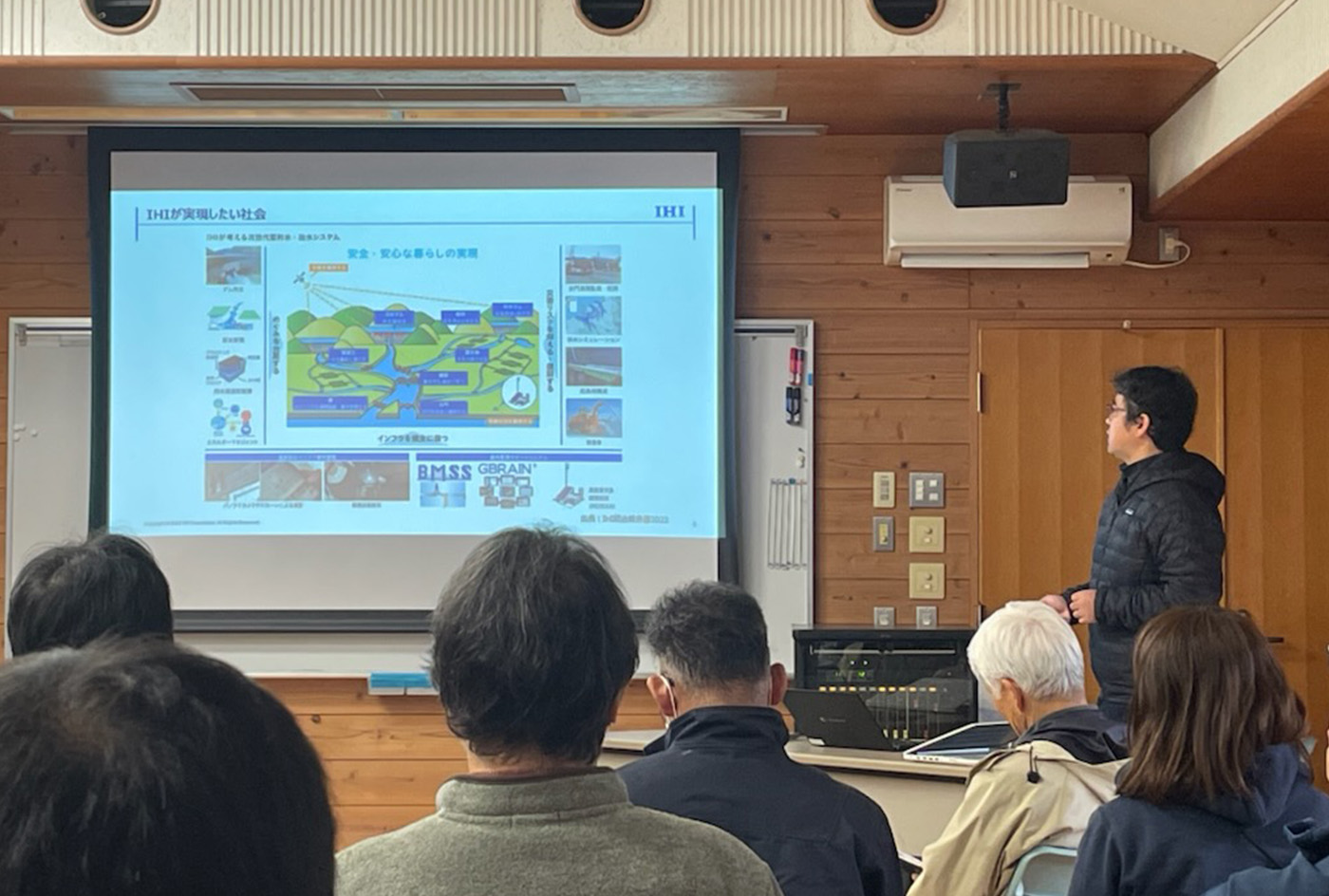
2023年11月に行われた現地研修会では、IHIの担当者たちが漁業者や行政の人たちと愛知川の自然再生について話し合いました。生き物のより良い生育環境を作るための具体的な改善策が分かり、今後の活動の方向性が明確になりました。
「生物多様性保全活動は大規模な団体が行うものと思われがちですが、個人単位で十分なお金や高度な専門知識がなくてもできることはあります。資源の制約があるなかで、自分が活用できる資源を最大限活用して行う『小さな自然再生』の考え方は、新しい事業を起こすためにも大切な考えです。小さな活動が広がり、共通の目的を持つ人々が集まることで、社会に大きな影響を与えることができると思います」
最後に、今後の目標についても伺いました。
「私たちの取り組みによって、水路の自然環境を改善し、地域の人々に利用してもらいたいと考えています。また、子どもたちが自然環境を学び、成長する機会を提供することを目指しています。さらに、インフラを提供する会社として、利便性だけでなく、自然と調和するインフラが当たり前になることを願っています」
下記の「関連リンク」に「株式会社IHIのサステナビリティ活動」「水辺の小さな自然再生」に関連するホームページがありますので、興味がある方はご覧ください。
【データ】
| 名前 | :東近江市建部いきものの水路 |
|---|---|
| 住所 | :滋賀県東近江市 |
| TEL | :03-6204-7316(株式会社IHI) |

