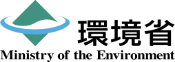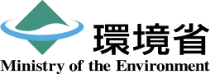エコ・ファースト制度実施規約
平成22年9月10日制定
平成26年1月23日改正
令和元年10月23日改正
令和2年11月30日改正
令和6年9月18日改正
-
第1条(目的)
この規約は、エコ・ファーストの認定等に関し必要な事項を定めることにより、企業における環境保全に関する自主的な取組を促進することを目的とします。
-
第2条(認定の申請)
- エコ・ファーストの認定を求める企業(以下「申請企業」といいます。)は、当該企業の環境の保全に係る取組に関する約束案(以下「約束案」といいます。)を作成し、環境大臣の認定を申請することができます。
- 約束案には、次に掲げる事項を記載しなければなりません。
- 環境の保全に関する明示的な目標
- 環境大臣への報告及び公表に関すること
- 約束案には、次に掲げる書類を添付しなければなりません。
- 申請企業の概要(設立年月日、資本金、事業所の名称、従業員数及び主要製品(又はサービス)名)を示す資料
- 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
- 第3条第1項(1)及び(2)に該当する根拠となる資料(年次計画等の約束案の実現に向けた具体的取組、同業他社との比較分析等を含みます。)
- 環境大臣は、原則として年1回定期的に申請企業を募集するものとし、その開始日及び終了日について環境省ウェブサイトにおいて公表するものとします。
-
第3条(認定等)
- 環境大臣は、前条による認定の申請があった場合において、次に掲げる全ての要件に該当すると認められるときは、その申請に係る約束がエコ・ファーストである旨の認定をすることができます。
- 申請企業が別表に掲げる要件を全て満たすこと。
- 約束案に記載された目標が、次に掲げる分野のうち1つ以上において、先進性(トップランナー足り得る高い目標であること)、独自性(業界の特色を生かしたオリジナルな目標であること)及び波及効果(業界にインパクトを与え、当該業界における取組の向上を促すような目標であること)を有し、原則として、申請の日から5年後又はそれ以降を目標年次とするものであり、かつその達成が見込まれること。
- 気候変動対策
- 循環経済(サーキュラーエコノミー)への移行
- 自然再興(ネイチャーポジティブ)
- 大気、水又は土壌などの環境への負荷の低減
- 化学物質の適正な管理及びリスクコミュニケーションの促進
- 環境教育の振興
- 環境金融
- その他の環境保全
- 申請企業の約束案の実現に向けた取組が、環境省が実施する施策の推進に寄与するものであること。
- 申請した日又はその後において第7条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
- 環境大臣は、前項の認定に当たって必要があると認めるときは、学識経験を有する者の意見を聴くことができます。
- 環境大臣は、前条による認定の申請があった場合において、次に掲げる全ての要件に該当すると認められるときは、その申請に係る約束がエコ・ファーストである旨の認定をすることができます。
-
第4条(エコ・ファースト・マークの使用)
前条第1項の認定及び第6条第5項の認定の更新を受けた企業(以下「認定企業」といいます。)は、「エコ・ファースト・マーク使用規約」に従い、エコ・ファースト・マーク(商標登録第5239241号)を使用することができます。
-
第5条(報告及び公表等)
- 認定企業は、約束された取組の進捗状況を定期的に把握することとし、その結果を環境大臣に報告するとともに、これを公表するものとします。
- 認定企業が約束の変更を行おうとする場合には、変更した約束案を作成し、環境大臣に対してその旨を申し出ることができます。
- 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の申出について準用します。
- 環境大臣は、第2項の申出に係る約束の変更が、第3条第1項各号に掲げる全ての要件を満たし、かつ当該認定企業の環境保全に係る取組をより前進させるものであることを確認することができます。
-
第6条(認定の有効期間及び更新等)
- 第3条第1項の認定の有効期間は、認定を受けた日から起算して5年とします。
- 認定企業は、前項に規定する認定の有効期間(当該認定の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた認定の有効期間)の満了までに新たな約束案を作成し、認定の更新を申請することができます。
- 第2条第2項の規定は、前項の申請について準用します。
- 第2項に規定する認定の更新の申請に当たり、約束案には次に掲げる書類を添付しなければなりません。
- 第2条第3項各号に規定する書類
- 現在の約束の実現状況が分かる書類
- 現在の約束が実現できない場合にあっては、その理由及び新たな約束案の実現を確実にするための方策を記載した書類
- 環境大臣は、第2項に規定する認定の更新の申請があった場合において、次に掲げる全ての要件に該当すると認められるときは、認定を更新することができます。
- 第3条第1項各号の要件に該当するものであること。
- 現在の約束を実現していること、又は実現できない場合であってもその理由に妥当性があり、かつ新たな約束案の実現が見込まれること。
- 第3条第2項の規定は、前項の認定の更新について準用します。
- 第2項に規定する認定の更新の申請があった場合において、当該更新の前の認定の有効期間の満了の日までにその申請について認定又は不認定がされないときは、当該更新の前の認定は、その有効期間の満了後も当該更新の認定又は不認定がされるまでの間は、なおその効力を有します。
- 前項の場合において、認定の更新がされたときは、その認定の有効期間は、当該更新の前の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算して5年とします。
-
第7条(認定の取消し等)
- 環境大臣は、次に掲げる場合には、認定を取り消すことができます。
- 不正の手段により第3条第1項の認定、第5条第4項の確認及び第6条第5項の認定の更新を受けたとき。
- 認定企業の約束実現に向けた取組が不十分であると認められたとき。
- 認定企業に重大な法令違反又は公序良俗違反が認められたとき。
- 合併その他の理由により、認定企業が第3条第1項の基準に適合しないこととなったと認められるとき。
- 前各号に掲げるもののほか、認定企業として不適切であると認められたとき。
- 次に掲げる場合には、認定企業に対する認定は、有効期間内であってもその効力を失います。
- 認定を受けた約束のうち、第3条第1項(2)の目標の目標年次が経過し、先進性、独自性及び波及効果を有さないと認められたとき。
- 合併その他の理由により認定企業が消滅したとき。
- 認定企業が認定を辞退したとき。
- 認定企業は、第1項及び第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その旨を環境大臣に報告しなければなりません。
- 環境大臣は、次に掲げる場合には、認定を取り消すことができます。
附則(平成22年9月10日)
第1条
この規約は、平成22年9月10日から施行します。
第2条
「エコ・ファースト・マークの使用認定に関する基準」は、廃止します。
第3条
この規約が施行される際に、既に「エコ・ファースト・マークの使用認定に関する基準」に基づきエコ・ファーストの認定を受けている企業は、本規約の施行の日より一年以内に、この規約に準じて認定を受けなければ、認定の効力を失います。
附則(平成26年1月23日)
第1条(施行期日)
改正後の新規約(以下「新規約」といいます。)は、平成26年1月23日から施行します。
第2条(改正前の規約による認定企業に対する経過措置)
改正後の新規約が施行される際に、既に改正前の規約本則に基づきエコ・ファーストの認定を受けている企業は、新規約による認定を受けたものとみなします。
第3条(平成22年9月10日附則第3条の認定を受けた約束の変更)
平成22年9月10日附則第3条の規定に基づき改正前の規約に準じて認定を受けた企業が、その認定を受けた約束中のすべての目標年次の経過に伴いその約束を変更する場合、その変更の申請は、新規約第2条第1項の認定の申請とみなします。
附則(令和元年10月23日)
第1条(施行期日)
改正後の新規約は、令和元年10月23日から施行します。
第2条(改正前の規約による認定企業に対する経過措置)
改正後の新規約が施行される際に、既に改正前の規約本則に基づきエコ・ファーストの認定を受けている企業は、改正後の新規約による認定を受けたものとみなします。
附則(令和2年11月30日)
第1条(施行期日)
改正後の新規約は、令和2年11月30日から施行します。
第2条(改正前の規約による認定企業に対する経過措置)
改正後の新規約が施行される際に、既に改正前の規約本則に基づきエコ・ファーストの認定を受けている企業は、改正後の新規約による認定を受けたものとみなします。
附則(令和6年9月18日)
第1条(施行期日)
改正後の新規約は、令和6年9月18日から施行します。
第2条(改正前の規約による認定企業に対する経過措置)
- 改正後の新規約が施行される際に、現に改正前の規約本則に基づきエコ・ファーストの認定を受けている企業の認定は、その有効期間の満了の日までは、なおその効力を有します。
- 改正後の新規約が施行される際に、現に改正前の規約本則に基づきなされている更新の申請は、改正前の規約に基づき審査を継続するものとします。
別表(第3条第1項(1)関係)
| (ア)環境マネジメントシステムに係る要件 |
企業がその運営や経営の中で、効果的に環境保全に関する取組を進められるよう、ISO14001、エコアクション21、エコステージ、その他の適切な第三者機関が策定したと認められる環境マネジメントシステム、又はそれらに準ずると認められる社内独自の環境マネジメントシステムを導入し、それに基づいた環境経営の推進体制を構築していること。 |
|---|---|
| (イ)気候変動対策に係る要件 |
気候変動対策に係る取組において、以下の(1)から(4)までを全て満たし、かつ、(5)から(12)までのうち1つ以上を満たすこと。
|
| (ウ)循環経済(サーキュラーエコノミー)への移行に係る要件 |
循環経済への移行に係る取組において、以下の(1)及び(2)のいずれも満たし、かつ、(3)から(10)までについても該当するものを全て満たすこと。
|
| (エ)自然再興(ネイチャーポジティブ)に係る要件 |
生物多様性国家戦略2023-2030(令和5年3月31日閣議決定)に掲げる「ネイチャーポジティブの実現」を念頭に、ネイチャーポジティブ分野に係る取組において、以下の(1)から(5)までのうち2つ以上を満たすこと。
|