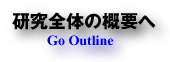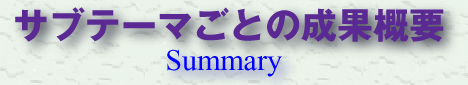
検索画面に戻る Go Research
[H−3 サヘル農家の脆弱性と土壌劣化の関係解明および政策支援の考察]
(3)村落レベル・地域レベルの土地利用、植生の時系列解析
独立行政法人国際農林水産業研究センター
|
|
国際開発領域
|
内田 諭
|
〈研究協力者〉
|
|
独立行政法人国際農林水産業研究センター
|
|
国際開発領域
|
平野 聡
|
[平成15〜17年度合計予算額]
平成l5〜17年度合計予算額 6,988千円
(うち、平成17年度予算額 1,773千円)
[要旨]
西アフリカに位置するブルキナ・ファソ国では、限られた土壌および水資源を利用した天水農業が営まれている。農地として開墾された土地は、一般に土壌肥沃度が高くないため、適当な期間休閑することで、土地生産性を維持するのが一般的である。こうした耕作の頻度については、立地条件を考慮して適正なものにすることが必要とされるが、土地利用の広域かつ詳細な調査データは存在しない。ことに、2003年に隣国コートジボワールで勃発した戦乱(以降、「危機」)の影響で、出稼ぎ農民の帰還による大規模な人口変動が見られ、土地利用、特に耕作面積に大きな影響があったと考えられる。こうした実態を把握する手法の開発が待たれている。本研究は、衛星リモートセンシングデータを活用し、耕作地の判別とその空間分布および経年変動に関する客観データを提供すること目的とした。異なるピクセルサイズの衛星データを用いて、異なる時空間スケールでの村落周辺での耕作地の面積推移を推定・評価した。対象地域、対象期間に安定して広域の客観データを提供できたのはピクセルサイズ1kmのSPOT/VEGETATION(フランスの地球観測衛星搭載のセンサ)であった。年降水量によるブルキナ・ファソの農業生態区分(4つあり、北からスーダン・サバナ北部と南部、ギニア・サバナ北部と南部)ごとに、収穫期前後の植生指数の変動パターンに見られる特徴をもとに、村落周辺の耕作利用強度(Cropland Use Intensity)を推定し、階級区分を行った。階級区分の年々変動から、耕作面積に対する危機の影響は多様で、空間変動パターンの単純な類型化は難しいことがわかった。しかし、概して危機以降の変動が顕著に見られたのは降水量の比較的少ない北部のスーダン・サバナ区分と、やや湿潤なギニア・サバナ北部であることと、耕作利用強度の上昇に時差が見られることが判明した。さらに、危機から2年経った2004年にはこの傾向も概ね収束し、以前の耕作面積に戻る方向で推移したことが推察された。
[キーワード]
衛星リモートセンシング、耕作面積、分類手法、経年変動、人口圧
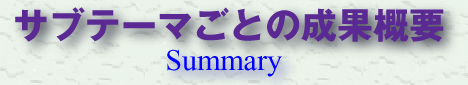
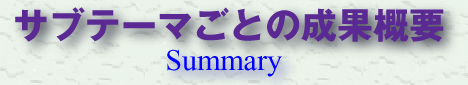
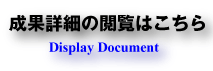 (4.18MB)
(4.18MB)