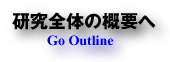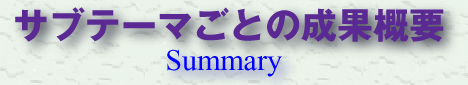
検索画面に戻る Go Research
[H−3 サヘル農家の脆弱性と土壌劣化の関係解明および政策支援の考察]
(2)農家の土壌保全技術採用の規定要因の解明とその評価
京都大学 大学院地球環境学堂
|
田中 樹
|
大学院農学研究科
|
真常 仁志
|
[平成15〜17年度合計予算額]
平成l5〜17年度合計予算額 6,441千円
(うち、平成17年度予算額 1,638千円)
[要旨]
コートジボワール危機(「危機」)以降、ブルキナファソへの出稼ぎ者の帰村による一時的な人口の急増や送金停止による家計の圧迫が起こり、それに伴う資源環境の劣化などの影響が懸念された。本サブテーマでは、スーダン・サバナ地帯南部に位置するKolbila村に対象地域を絞り込み、在来農法を含む土地利用の状況、土壌特性および「危機」以降の農民による土地利用レベルでの対応方法と実態を明らかにし、その土壌保全上の意味を考察した。調査村では、「危機」に伴う帰村者による一時的な人口増加に対して、休閑地を耕地化することにより「ショック」を吸収するという対処行動が確認された。その結果、世帯が所有する土地のうち休閑地の割合が0〜20%程度となり、また、既存の農耕地でも連続耕作が長期化する傾向が顕著であった。土壌調査および土壌分析から休閑地の地上部バイオマス量と休閑年数の関係を見ると、地上部バイオマス量が最大レベルに達するのに7〜10年間、その半分のレベルに達するのに少なくとも4年間の休閑年数が必要であった。草本休閑により土壌の肥沃度は若干の回復をみせるものの、作物の収穫により持ち出される養分量を補うには程遠いことが明らかになった。このことは、今後も予想される「ショック」に対する緩衝力や復元力が非常に脆弱な状態になっていることを意味する。一方で、農民は収量の減少傾向から農耕地の肥沃度低下を経験的に認識しながらも、土壌保全や肥沃度維持に向けた対処行動は鈍く、自給肥料を生産するための家畜頭数の増加や土壌保全対策としての石列や草列の設置は、「危機」の有無とは一見すると無関係であった。休閑地が担っていた緩衝機能や土壌の肥沃度が潜在的に失われつつあることの深刻さや地域住民による対処行動が必ずしも土地や土壌の保全に向かわないことを考えると、すでに破綻している休閑システムにかわる土地利用システム(肥料など外部資材の獲得への便宜、家畜飼養や乾季の手汲みかんがい耕作への支援、土壌保全対策への支援)への転換を外部からサポートすることが必要である。
[キーワード]
土地利用、土壌劣化、農民の対処行動、土壌保全、肥沃度維持
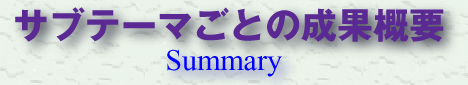
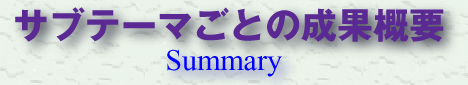
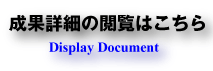 (2.39MB)
(2.39MB)