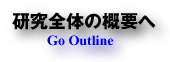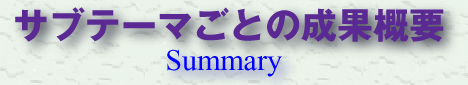
検索画面に戻る Go Research
[F−5 サンゴ礁生物多様性保全地域の選定に関する研究]
(1)保全すべきサンゴ礁生物多様性の探索
独立行政法人水産総合研究センター
|
|
西海区水産研究所石垣支所生態系保全研究室
|
澁野拓郎・高田宜武
|
東京大学大学院農学国際専攻
|
佐野光彦
|
東京海洋大学海洋生物資源学科
|
大葉英雄
|
島根大学汽水域研究センター
|
堀之内正博
|
(財)自然環境研究センター
|
木村 匡・下池和幸
|
[平成15〜17年度合計予算額]
平成l5〜17年度合計予算額 42,579千円
(うち、平成17年度予算額 11,183千円)
[要旨]
石垣島周辺の、岸近くに裾礁が発達した宮良湾、石西礁湖中心部のシモビシ、外洋に面した堡礁外縁部のカタグヮーの計223地点で、サンゴ礁生物群集(サンゴ・魚・海藻(草))を対象に潜水調査を行った。サンゴでは、被度は底質が岩礁で水深の浅い所ほど高かった。出現種数と多様度指数(H’)は水深が深い所で高かった。分布パターンは宮良湾とカタグヮーで明瞭な帯状分布を示したが、シモビシでは不明瞭であった。魚類では、宮良湾では様々な地形的環境に対応して狭い範囲に多様な種類が生息していた。シモビシでは宮良湾の礁池内とほぼ同じ種組成がみられた。カタグヮーでは出現種数が最も多かったが、礁湖内は水深が深く、宮良湾礁池内の種組成とは大きく異なった。海藻(草)類では、分布には「着生基質の種類と安定度」、「波当たりの強さ」、「干出(+水深)」が大きく影響していることがわかった。安定した着生基質が少ないサンゴ礁では、枝状サンゴの枝間が海藻の優れた着生基質となっていた。枝状サンゴ群集域はサンゴ礁生物群集の関連性からみると保全すべき重要なサンゴ礁生態系の一っであるといえる。置換不能度の解析で優先的保全地点を抽出したところ、生物群によって地点の分布が異なった。生物群集の組成を調べると223地点は12の群集に類別され、これら群集の指標種を抽出した。群集の分布は環境傾度(岩盤被度、砂被度、SPSS、水深)によってある程度は説明できた。群集要素を保全単位にして置換不能度を得点化することで、保全地域のデザインの優劣を比較できた。
サンゴ域とともに海草藻場を保全することで魚類の多様性を高く維持できることがわかった。その場合、保全対象となる海草藻場には必ずしもサンゴ域が隣接する必要はなく、また、外洋の影響が強い場所、陸域の影響が強い場所のどちらかで代償可能である。石西礁湖内で海草藻場魚類の多様性を高く維持するためには、西表島東岸・小浜島西岸・小浜島東岸・竹富島西岸、あるいは西表島東岸・小浜島西岸・小浜島東岸・竹富島西岸・竹富島東岸の組み合わせが適していた。
[キーワード]
サンゴ礁保全地域、造礁サンゴ、海藻、魚類、海草藻場
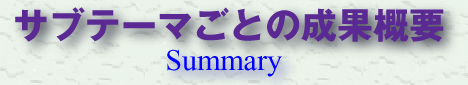
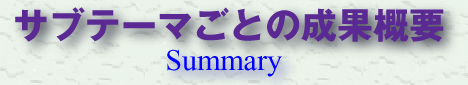
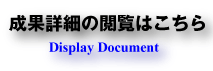 (5.30MB)
(5.30MB)