

|
|
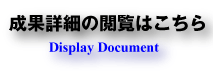 (490Kb) (490Kb)
|
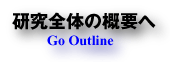
|
独立行政法人産業医学総合研究所 |
作業環境計測研究部 |
奥野 勉 |
研究協力者 |
||
秋田大学医学部 |
岩田豊人 |
|
金沢医科大学医学部 |
幡育穂・小島正美・佐々木一之 |
平成11〜13年度合計予算額 4,061千円
(うち、平成13年度予算額 1,041千円)
紫外放射(紫外線)は多くの種類の障害を引き起こすが、そのほとんどの場合、実際に、正確なリスク評価を行うことは難しい。その原因は、どの程度の紫外放射へ曝露したときに障害が発生するのか(量−反応関係)、あるいは、どの波長の紫外放射がどの程度の作用をもつのか(作用スペクトル)、障害を発生させる紫外放射の強度と曝露時間は反比例するのか(相反則)などの基礎データが不足しているためである。一般に、このような高度に定量的なデータを得る目的には、培養細胞を用いた実験が適している。そこで、本研究では、波長と強度、時間を正確に制御した紫外放射へ培養細胞を曝露させ、その影響を定量的に調べる2種類の実験を行った。
(1)表皮細胞のモデル系であるKB細胞を用い、紫外放射曝露後のアポトーシス(細胞死)を、細胞の剥離の観察、および、テトラゾリウムアッセイ法の2種類の方法で定量化した。アポトーシスの割合は、紫外放射の照度ではなく、その時間的な積算値(radiant exposure)によって決まること、波長270nmから330nmの間では波長が短いほどアポトーシスの割合が高いこと、酸化ストレス性因子の例としての過酸化水素と紫外放射へ複合曝露したときには両者の影響は相加的であることなどを明らかにした。
(2)紫外放射曝露後のヒト水晶体上皮細胞の生存率をクリスタルバイオレット染色によって定量化した。その量−反応曲線をマルチヒットモデルに基づいて解析し、LD50を求めた。これを260.5nmから301nmまでの8種類の波長の紫外放射について行うことにより、正確な作用スペクトルが得られた。本研究で得られたデータは、紫外放射の有害性の評価方法を決める際の基礎になると思われる。その例として、この作用スペクトルに、ヒトの角膜と房水の分光透過率をかけることにより、白内障に関する作用スペクトルを求めた。白内障発生に関する紫外放射の有害性は、波長300nm以上で強くなることが示唆された。
紫外放射、紫外線、培養細胞、量−反応関係、作用スペクトル