生活排水処理施設整備計画策定マニュアルの概要
1.概要
合併処理浄化槽、下水道、農業集落排水施設の3事業について、建設費用、維持管理費用、施設の使用実績等を、当時の厚生省、農林水産省及び建設省の三省連名通知により明らかにしたことを受け、これに基づき、集合処理と個別処理をどのようにエリア分けし、生活排水処理施設の整備を進めて行くべきか、経済的効率性の観点からマニュアルを示したものである。
この中で、個別処理と集合処理の経済分岐点を1世帯当たりの管渠距離で計算する「家屋間限界距離」といった考え方を用い、これにより個別処理と集合処理のエリア分けを検討することを提示した。
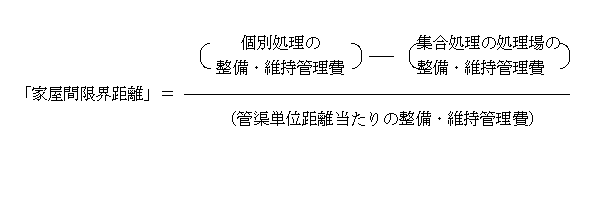
2.整備計画策定の手順
整備マニュアルにおいては、以下のような策定手順を想定しているが、具体的内容は主に[1]~[4]を対象としている。
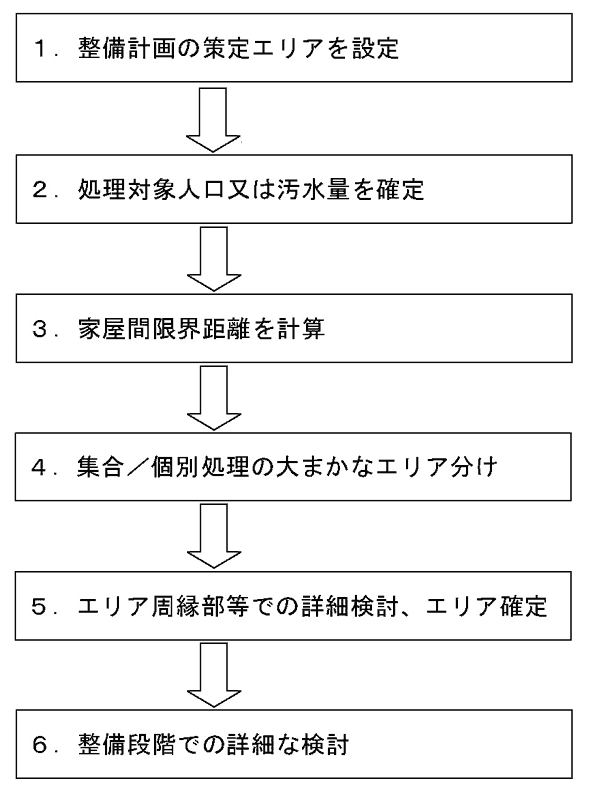
3.家屋間限界距離の計算の例
家屋間限界距離は、その地域の地形等にも影響されるため、一つの値には確定しない。ここでは、処理対象人口や施設の耐用年数等の条件をいくつか与えた上で三省通知で提示された内容に沿って計算した場合の例を示す
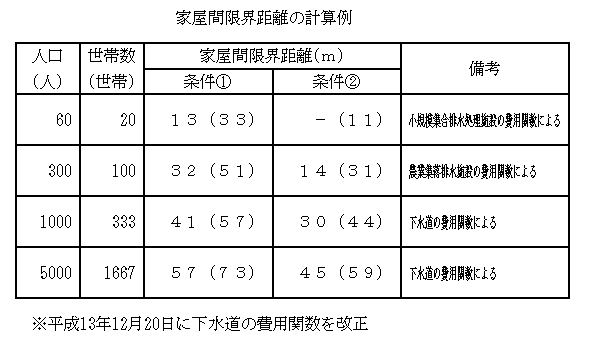
- 表中の家屋間限界距離は、5人槽による算定と( )中に7人槽による算定を示した。計算上家屋間限界距離がマイナスになるものについては-で表示。
-
- 条件[1]:
- 個別処理の耐用年数:躯体30年、機械10年
集合処理の耐用年数:処理場躯体60年、機械23年、管渠60年 - 条件[2]:
- 個別処理の耐用年数:躯体30年、機械7年
集合処理の耐用年数:処理場躯体50年、機械15年、管渠50年
- 平均世帯人数を3人/世帯で設定
- 下水道の日最大汚水量:0.300m3/(人・日)、日平均汚水量:0.225m3/(人・日)と設定
- 個別処理の本体費用、設置工事費用と付属機器設備類費用の比を55:40:5、集合処理の処理場土木費用と機械類費用の比を1:1と設定