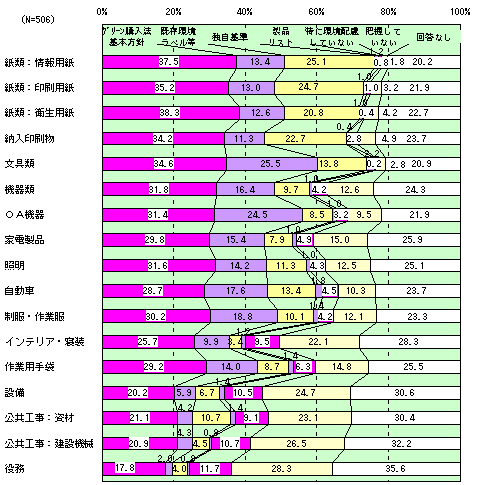3.調査結果の概要
(1)グリーン購入に取り組む意義
グリーン購入に取り組む意義については、「非常に意義のあることであり、積極的に推進すべき」とする回答が82.2%を占め、平成11年度調査における79.5%より更に高い割合となっている。また特に、都道府県・政令市では100%に至っており、グリーン購入の推進の重要性に対する認識が浸透している。
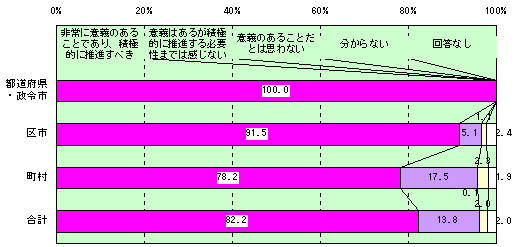
(2)グリーン購入に際して参考にしているもの
グリーン購入に際して参考にしているものは、全体平均で、「メーカー等が配布している製品カタログ・パンフレット」が72.9%、「環境ラベリング制度」が64.8%、次いで「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」が36.8%を占めている。
また、都道府県・政令市では、「環境ラベリング制度」が98.3%、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」が91.5%と高くなっており、市区、町村では、「メーカー等が配布している製品カタログ・パンフレット」の順位が次第に高くなる傾向にある。
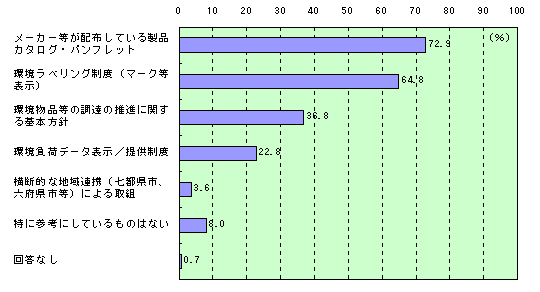
(3)グリーン購入への取組状況
「組織的に取り組んでいる」と回答している地方公共団体は、都道府県・政令市では94.9%であるのに対して、区市で46.3%、町村で12.7%となり、全体では、平成11年度調査の7.9%より増加し23.6%となっているが、「組織的ではないが担当者のレベルで配慮している」との回答が66.6%と引き続き最も多くなっている。
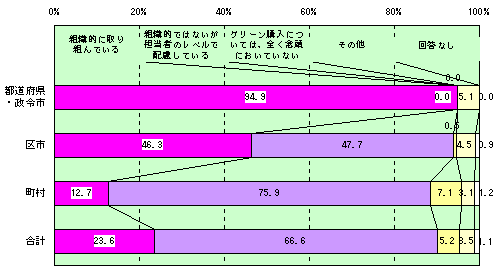
(4)グリーン購入への取組の進展状況
「全庁的な取組にまで発展した」「多くの部署での取組に発展した」「一部の部署で取り組まれるようになった」と回答した地方公共団体が、それぞれ、12.2%、14.2%、29.3%、合計で55.7%となり、平成11年度調査の合計44.2%より10%以上増加しており、取組の進展が見られた。
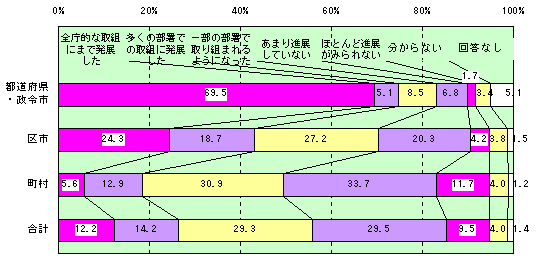
(5)グリーン購入に取り組む上での阻害要因
平成11年度調査同様に「組織としてグリーン調達に対する意識が低い」「価格が高い」と回答した地方公共団体が多く、それぞれ、50.7%、49.6%となっている一方、「グリーン購入に関する情報がない」と回答した地方公共団体は、平成11年度の45.1%から16.0%に大幅に減少した。
「組織としてグリーン調達に対する意識が低い」と回答した割合は、町村では最も多くなっているが、区市、都道府県・政令市においては、次第に回答割合及び順位ともに低くなっている。
また、今回調査において追加した「各課毎の物品調達のため一括でグリーン購入ができない」と回答したところが区市、町村に多く、全体では44.1%を占めている。
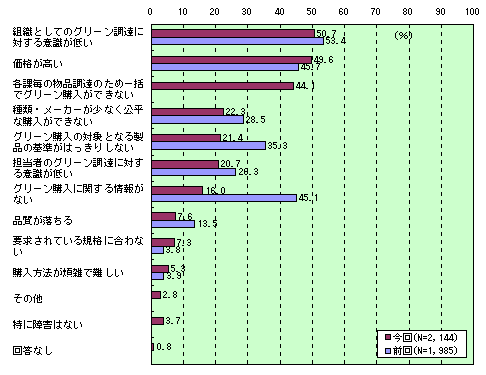
(6)グリーン購入進展のために必要な仕組み
「環境物品等に関する情報提供システム、広報活動の拡充」が61.5%と最も多く、平成11年度調査において最も回答の多かった「グリーン購入の対象となる製品の基準の明確化」の割合は減少し45.0%と二番目となっている。
また、これらの項目に次いで、今回調査において追加した「担当職員等への研修、啓発の実施」と回答した地方公共団体が40.6%を占めている。
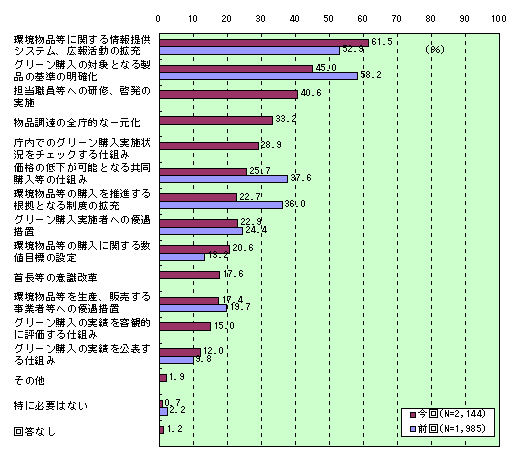
(7)製品選択時の情報提供制度拡充に必要な仕組み
グリーン購入進展のために必要な仕組みとして、「環境物品等に関する情報提供システム、広報活動の拡充」と回答した割合が最も高かったところであるが、その具体的な仕組みとしては、「環境物品等を認定し一目でわかるマークを表示する制度」が78.4%と最も高く、次いで、「環境負荷に関する様々な項目についての総合的情報提供」「製品情報等の比較方法や表現方法の標準化、共通化」「再生素材含有率等具体的数値を表示し情報提供する制度」の順で高くなっており、それぞれ4割前後となっている。
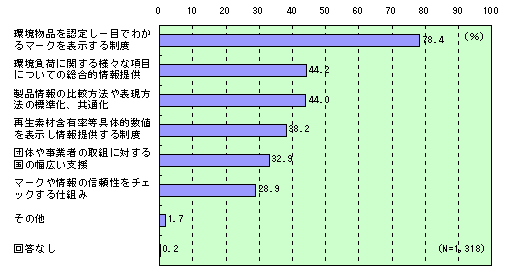
(8)環境物品等の「価格」
通常の製品と比較した環境物品等の「価格」について、紙類、納入印刷物、文具類、OA機器、作業用手袋では「同等」以下と回答した割合が45〜55%程度と高いが、自動車、設備、公共工事では、「同等」以下に対して「やや高い」「高い」との回答の比率が高く、中でも自動車については非常に高くなっている。また、設備、公共工事、役務については、回答がない地方公共団体も多い。
調達量の多い都道府県・政令市では、「同等」と回答した割合が、全般的に全体平均より高い傾向にあるが、自動車、設備では、「高い」「やや高い」と回答した割合が更に高くなっている。
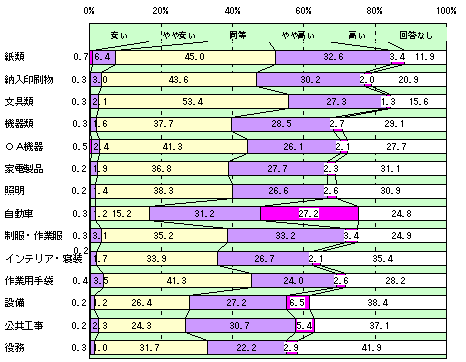
(9)環境物品等の「品質」
通常の製品と比較した環境物品等の「品質」については、紙類などで「悪い」「やや悪い」と回答している割合が若干高くなっているが、全ての分野について「同等」と回答している割合が過半を占めている。
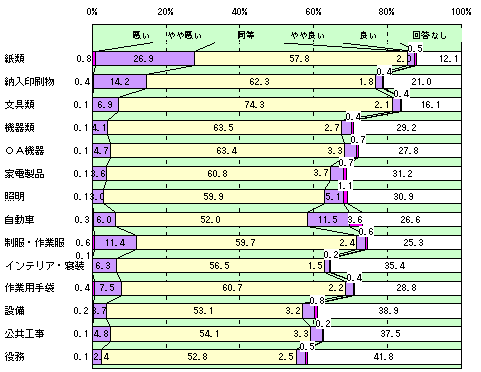
(10)環境物品等の「コストアップ許容度」
全ての分野について、通常の製品より環境物品等が「10%程度高くても購入」と回答した最も多く、3割〜5割弱を占めている。更に「20%程度、30%以上高くても購入」を合わせると4割〜6割弱を占める結果となっている。
平成11年度調査では、紙類、文具類、機器類、OA機器、家電製品、自動車、制服・作業服、公共工事について調査を行っているが、いずれの分野でも同等以下の価格であれば購入すると回答した割合が5割前後を占める一方、10%程度以上高くても購入すると回答した割合は2割〜4割弱に止まっていたところであり、環境物品等であれば多少割高でも購入するというように意識が変化してきている。
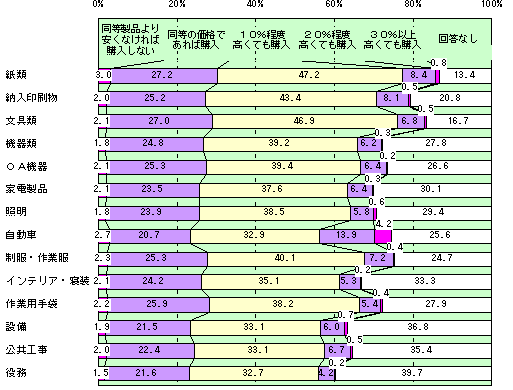
(11)「調達方針」の策定の有無
都道府県・政令市については、全ての地方公共団体で「調達方針」(グリーン購入法第10条に定められる環境物品等の調達の推進を図るための方針)を策定済み又は策定予定であり、計画的なグリーン購入の推進が図られているところであるが、策定済み又は策定予定の地方公共団体は、区市では約半数、町村では約4分の1にとどまっており、全体で約6割が調達方針の策定予定がないと回答している。
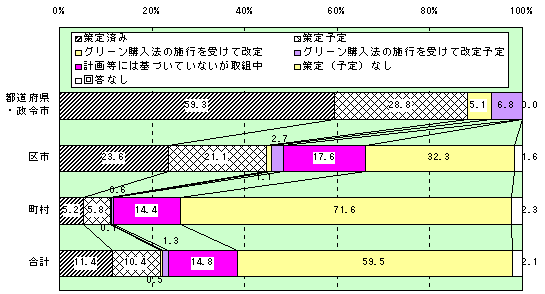
(12)グリーン購入の対象品目
紙類、文具類等については7割以上が、機器類、OA機器、家電製品、照明、自動車、制服・作業服については6割前後が「調達方針」においてグリーン購入の対象品目としている。
一方、インテリア・寝装、設備、公共工事、役務については、対象品目としている割合が2割〜4割弱と低くなっており、「対象品目から除外」「把握していない」と回答した割合がそれぞれ2割以上を占めている。これらの分野を対象品目から除外した理由については、分野によって傾向が異なるが、「全くまたはほとんど購入していないため」「把握していない」「対象とする基準が明確でない」などが多かった。
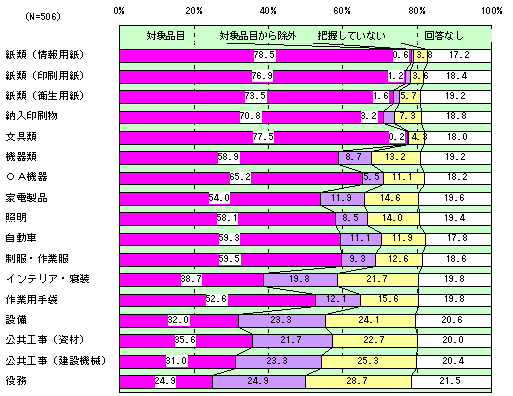
(13)「調達方針」におけるグリーン購入の判断基準
「調達方針」におけるグリーン購入の判断基準については、「把握していない」と回答した割合の高いインテリア・寝装、設備、公共工事、役務を除き、グリーン購入法基本方針を参考としている割合が高く3割程度以上を占めている。また、文具類、OA機器については、既存の環境ラベル等を参考としている割合も25%程度と高くなっている。