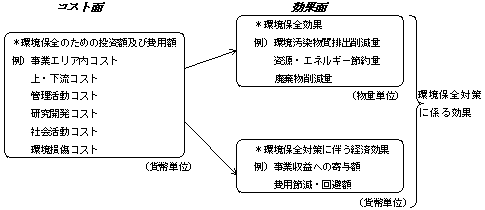
| [1] | 生産・サービス活動により事業エリア内で生じる環境負荷を抑制するための環境保全コスト(略称:事業エリア内コスト) ※ここで、事業エリアとは、物流・営業活動を含む企業等が直接的に環境への影響を管理できる領域のことをいう。 |
| [2] | 生産・サービス活動に伴ってその上流又は下流で生じる環境負荷を抑制するための環境保全コスト(略称:上・下流(じょうかりゅう)コスト) |
| [3] | 管理活動における環境保全コスト(略称:管理活動コスト) |
| [4] | 研究開発活動における環境保全コスト(略称:研究開発コスト) |
| [5] | 社会活動における環境保全コスト(略称:社会活動コスト) |
| [6] | 環境損傷に対応するコスト(略称:環境損傷コスト) |
| [1] | 環境保全効果 事業活動による環境負荷を抑制又は回避する「環境保全効果」は、物量単位で把握され、企業等の環境保全対策の費用対効果を検討する際には、まず初めに把握すべき項目である。環境保全コストの項目と可能な限り対応する形で把握(測定)すべきであり、本ガイドラインでは事業エリア内で生じる環境保全効果(事業エリア内効果)、上・下流で生じる環境保全効果(上・下流効果)、その他の効果の三つに分類した。 それぞれの効果について、単純な物量指標による経年変化の表示のみでは企業努力の実態を正しく伝えられない場合があり、比較指標の例についても提案している。 |
| [2] | 環境保全対策に伴う経済効果 事業収益に貢献する効果を金額ベースで把握する「環境保全対策に伴う経済効果」の算定については、確実な根拠に基づいて算出される経済効果と仮定的な計算に基づく経済効果とに分類した。ここで、確実な根拠に基づいて算出される経済効果とは、実質的に発生する経済効果であり、環境会計に盛り込むことが望まれるが、仮定的な計算に基づく経済効果については、推定計算を含むため、あえて公表は求めていない。 |