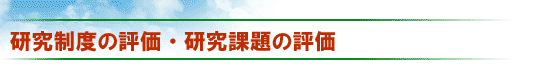|
地球環境研究総合推進費 平成18年度中間・事後評価の
手順と評価基準
平成18年6月 環境省地球環境局研究調査室
※本資料は、評価の実施に先立ち、評価者・被評価者へ共通に配布する資料です。
Ⅰ 今回の改正点
平成18年度の中間・事後評価については、ピアレビューを強化することとして課題ごとに関連性が高く、
専門知識を持つ分科会委員等3名~4名程度を基本とするワーキンググループ(WG)を設置し、
効率的及び効果的に書面評価や中間ヒアリング評価を行うこととしました。既存の分科会委員に加え、
より関連性及び専門性の高い方に審査を行っていただくという趣旨で、今年度新たに中間・事後評価専門部会を設置し、
委員(評価委員)9名の委嘱を行う予定です。
なお、評価手順や評価基準等は昨年と変更ありませんが、参考として昨年行った改正について、再度お知らせいたします。
【平成17年度に行った中間・事後評価の手順と評価基準の改正(抜粋)】
① 評価指標における基準の明確化
(非常に高い評価、やや高い評価、といった抽象的基準からより具体的な基準の提示)
② 中間評価についてはサブテーマ単位の評価の導入
(総合評価のみ)
③ 評価の低い課題に対する措置の厳格化
(程度に応じて減額、サブテーマ構成の見直し、課題の打ち切り)
④ 問題対応型の延長可否の評価についてはA評価のみ延長
(従来はB評価以上)
⑤ 資源配分のメリハリの強化
(高評価の資源配分は従来より多く、低評価はより少なく)
改正の理由として、昨年度の中間・事後評価以降、下記の指摘を受けていることから、これらの改善として実施するものです。
(1)「平成17年度概算要求における科学技術関係施策の優先順位付けについて」
(平成16年10月21日 科学技術政策担当大臣・総合科学技術会議有識者議員)
「政策支援研究として、政策形成に役立ったかどうか、実際の政策への反映等の視点から評価すべきである。また、政策支援研究としての性格から、低評価の課題については減額ではなく、研究者の交替を主とすべきである。」
(2)平成17年度財務省予算協議時(平成17年3月)における指摘事項
「他省庁の競争的資金については低評価の課題について課題の打ち切り、サブテーマの変更等の措置がとられている。地球環境研究総合推進費については制度創設以降、サブテーマレベルも含めて課題の打ち切り等の措置は行われていないが、
真に優秀な課題ばかりであるが故に打ち切り実績がないのかどうか精査すべき。期間延長の是非の評価についても、過去すべての延長審査対象課題が延長となっている。2年目にA評価をとった課題が3年目の延長可否の評価でB評価にランクダウンしても延長できてしまう基準はおかしいのではないか。」
Ⅱ 具体的な評価手順
1.評価対象課題と目的
○ 事後評価
17年度で研究が終了した課題を対象。評価結果は研究制度全体の見直し等に活用。
○ 中間評価
予定される研究の中間年に当たる課題について、評価結果を以降の研究実施の可否の判断、研究計画の検討、研究費への反映に活用するため実施。
課題(プロジェクト)全体の評価のほか、構成するサブテーマ単位に評価を実施。
○ 中間評価(第2回目)
昨年度に実施した中間評価(1回目)でA評価を得た「地球環境問題対応型研究領域」課題に対して、研究期間延長の可否判断及び研究計画の見直しに資するため実施。
2.評価者(利害関係者の排除、守秘義務等)
(1)評価者の選定
○ 地球環境研究企画委員会第1~第4研究分科会(以下「研究分科会」)委員及び新たに委嘱する中間・事後評価専門部会委員を評価者として、
評価課題の専門性により、分科会横断的に評価を実施。
○ 書面評価における評価者
評価対象課題の研究内容と特に関連のある専門分野の委員に評価依頼。
○ ヒアリング評価の評価者
評価対象課題の研究内容と特に関連のある専門分野の委員に評価依頼。その他、環境省行政部局担当者数名。
(2)利害関係者の排除
○ 評価者が評価対象の研究課題に関し、利害関係がある場合は、当該研究課題の評価を棄権。何らかの利害関係とは次の場合。
① 当該研究課題の研究参画者(代表者及び研究に参加している全ての研究者)と直接の上司・部下の関係にある場合
② 当該研究課題の研究代表者の所属する機関において、役職に付いている場合
③ 自らが研究課題に参画している場合
④ 研究代表者と血縁関係にある場合
(親子・兄弟ほか、社会通念上の親戚づきあいがある場合)
⑤ 研究代表者の学位取得時の指導教官であった場合
(師弟関係と判断)
○ 評価者が、各研究課題の検討会委員やアドバイザリーボードなどの委員を担当している場合は、中立的見地から指導・助言していることから、
上記①~⑤に該当しないことを条件に、利害関係者に含めず。
(3)評価に関する守秘義務
○ 評価者は、評価内容及び評価結果について守秘を徹底。
3.評価の方法と結果の開示・反映
(1)評価の方法
○ 事後評価に関しては、
「終了研究成果報告書」により書面評価のみ実施。
○ 中間評価研究課題(1回目)は、「中間成果報告書」について書面評価を実施した後、ヒアリング評価を実施。
○ 中間評価研究課題(2回目)に関しては、今後の研究計画等に関するヒアリング評価のみ実施。
(2)評価結果の取りまとめと開示
○ 平成19年度の研究計画の作成へ反映。各研究分科会終了後、評価結果を地球環境研究企画委員会にて報告・審議。
○ 評価結果は被評価者に通知するとともに、地球環境研究総合推進費ホームページにて公開。
(3)評価結果の反映
① 評価結果は、各研究課題の平成19年度研究費に反映。評価結果に応じて、対前年比プラス数十%~マイナス数十%の範囲(プラス、マイナスとも昨年度の反映よりも強く反映)で増減する予定。
② 中間評価(第1回目)においてE評価の課題は、18年度限りで中止。D評価の課題は研究計画の大幅な見直し、研究体制の再編(成果が見込まれないサブテーマの除外)等を実施。
課題全体の評価がC以上でも、サブテーマによって評価がD以下のものは当該サブテーマについて研究計画からの除外等の措置。
③ 中間評価(第1回目)において、A評価の課題は、研究代表者が希望する場合、期間を延長(最長2年)するか否かの検討を、来年度、第2回目の中間評価として実施。
④ 中間評価(第2回目)において、A評価の研究課題のみ当初の研究期間を延長(最長2年)。
⑤ 「戦略的研究開発領域」のプロジェクトについては、上記①及び②に準拠。プロジェクトを構成する各研究テーマ単位で、研究費への反映、研究計画の見直し。
4.評価にあたっての留意事項
(1)中間評価を実施する趣旨
○ 中間評価を実施する趣旨
① 研究課題の進捗と成果の達成状況、今後の目標達成可能性の把握
② 研究計画の改善等の指導
○ 評価ランクは、上記①の趣旨を踏まえた結果。励ましの意味合いの甘めの点数付けは行わず、客観的・中立的に達成状況及び今後の達成見込みについて評価。
○ 評価コメントは、客観的な評価結果としての意見のほか、上記②の趣旨を踏まえた、研究改善のための助言を、可能な範囲で記載。
(2) 地球環境研究総合推進費の目的
○ 目的は、地球環境保全のための政策を科学的側面から支援。
○ 本目的に照らして貢献・寄与の大きい、又は今後大きな貢献・寄与の可能性の高い研究課題には、高い評価(科学的水準高さも不可欠)。
5. 評価の基準と評価結果の集計方法
(1) 評価の観点と基準
○ 評価の観点と基準は、別紙「平成18年度中間・事後評価における評価項目と評価区分」に示すとおり(評価基準について具体的な例を提示)。
○ 各評価者は、別添の評価シートに結果を記入し、事務局へ提出。
○ 評価項目のうち「総合評価」は、他の評価項目と独立して記入。総合評価を記入する場合、個別評価項目で重視するポイントは、評価者の判断。
○ 評価コメント欄は、評価の根拠、研究計画の改善方向等を記入。
○ 戦略的研究開発領域(S-3課題)の中間評価においては、担当サブテーマごとに評価を行い、各サブテーマ担当主査のみプロジェクト全体の「総合評価」を行うこととする。
(2) 評価結果の集計方法
○ 各評価者が記入した評価ランク(A,B等の段階評価)は、数字に換算した上で全体の平均点を算出し、再度段階表示(A,B等)に変換して、評価結果ランクとして開示。
・ A評価5点、B評価4点、C評価3点、D評価2点、E評価1点
・ 平均点の段階表示換算は下記のとおり
4.5以上A、3.5以上4.5未満B、2.5以上3.5未満C、1.5以上2.5未満D、1.5未満E
○ 事後評価は、委員による書面評価結果が最終的な評価結果。
○ 中間評価(1回目)の場合の最終的な評価ランクは、
① 委員による書面評価時の評価ランク、
② 委員によるヒアリング評価時の評価ランク、
③ 行政部局担当者によるヒアリング評価時の評価ランク
を、重み付けせず合計したものから算出。
○ 中間評価(2回目)の場合の最終的な評価ランクは、
① 委員によるヒアリング評価時の評価ランク、
② 行政部局担当者によるヒアリング評価時の評価ランク
を、2:1で重み付けし合計したものから算出。
|