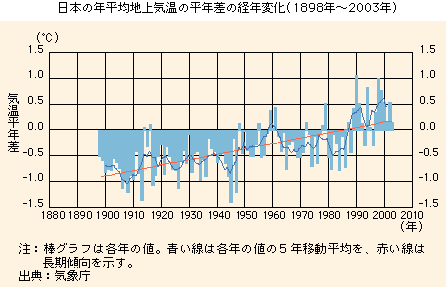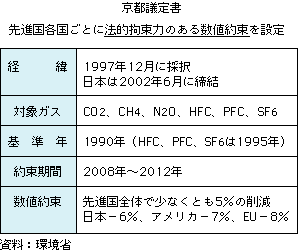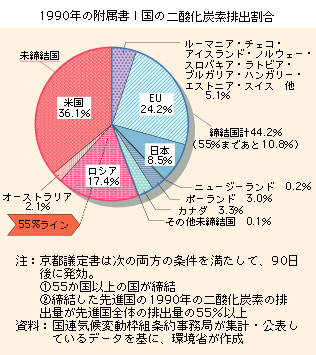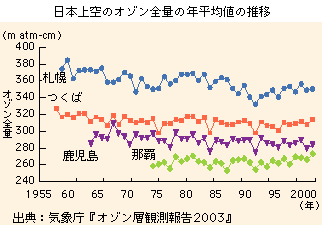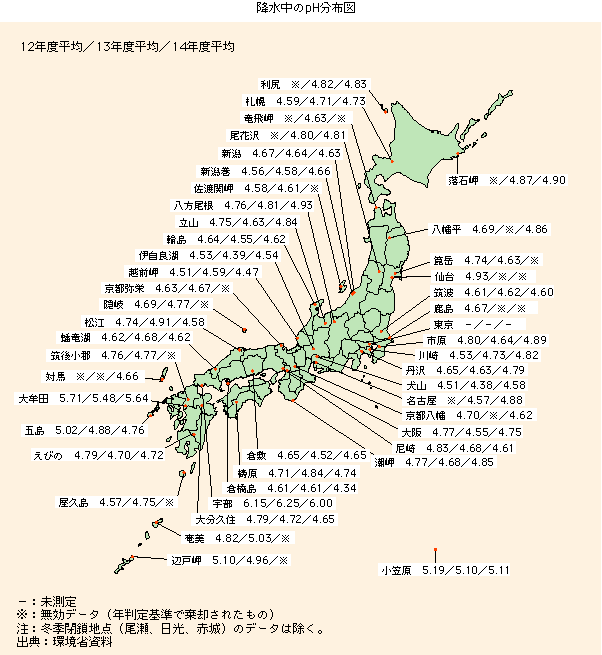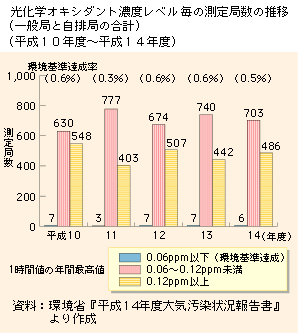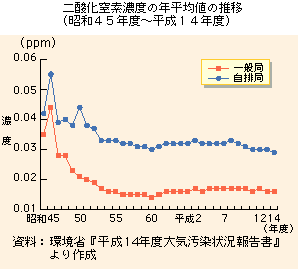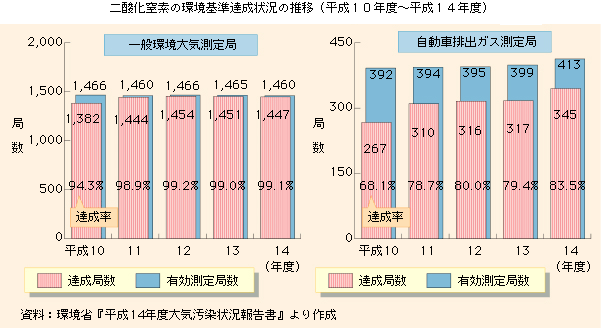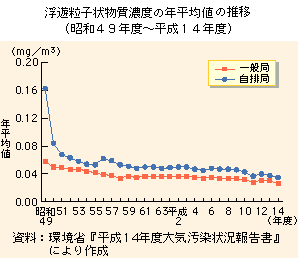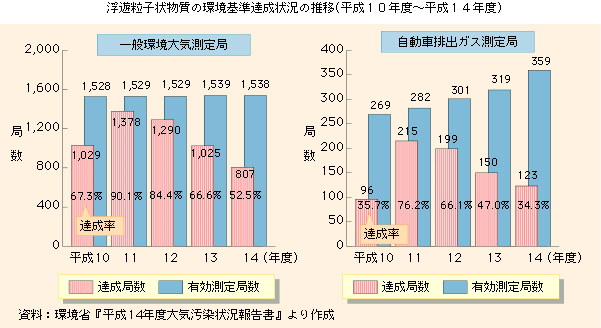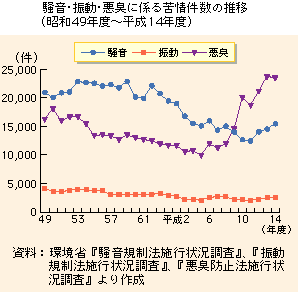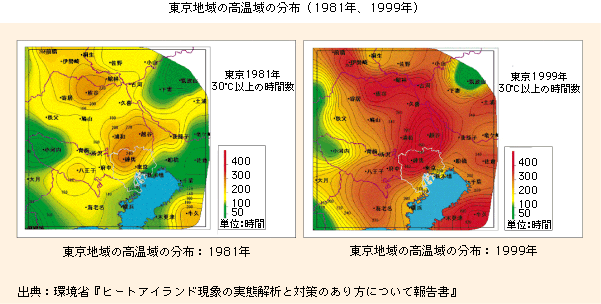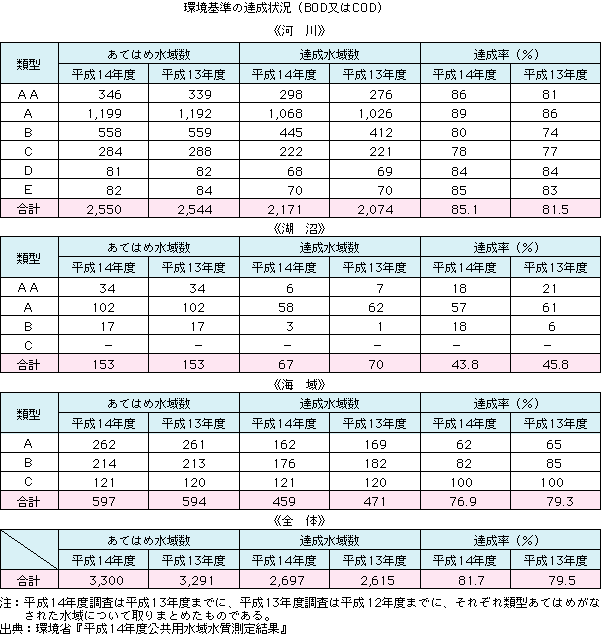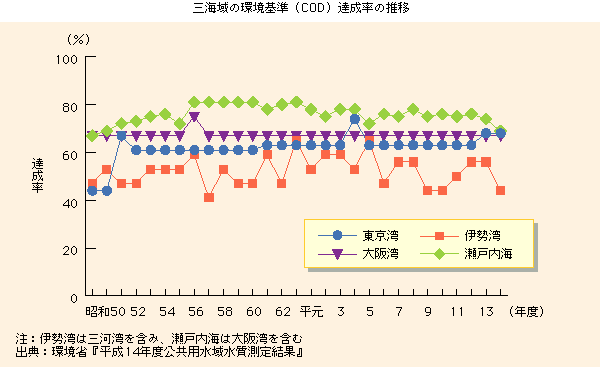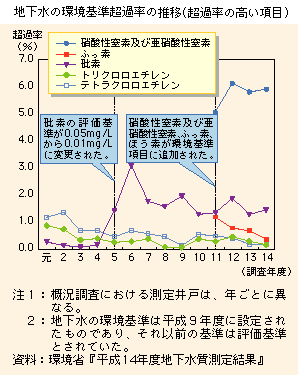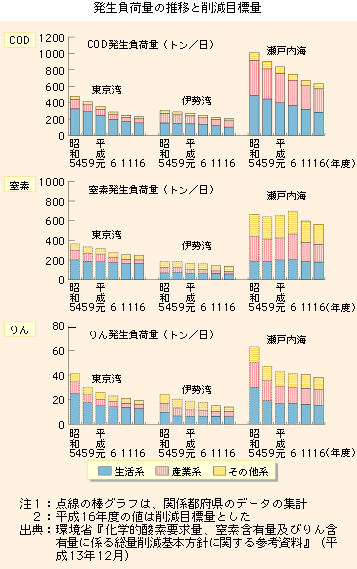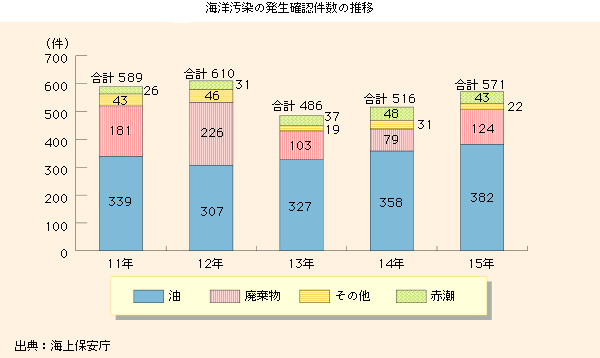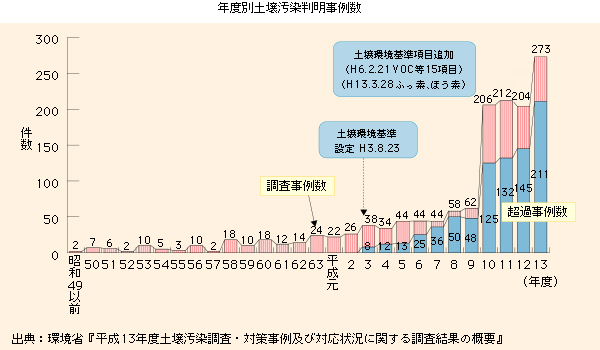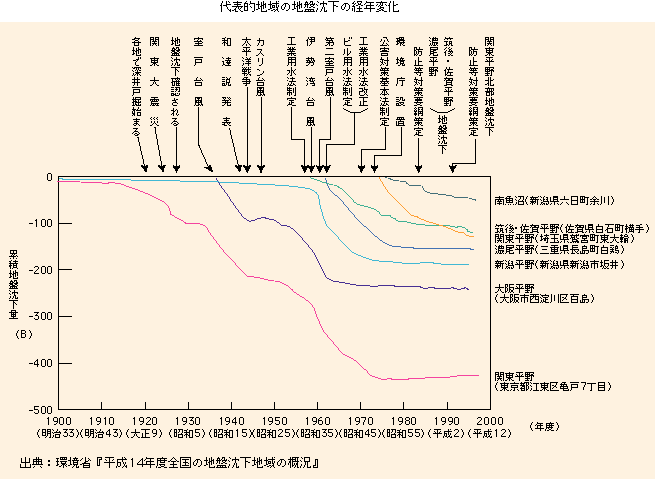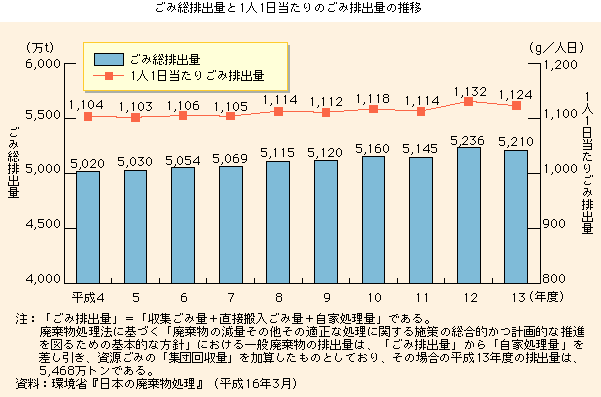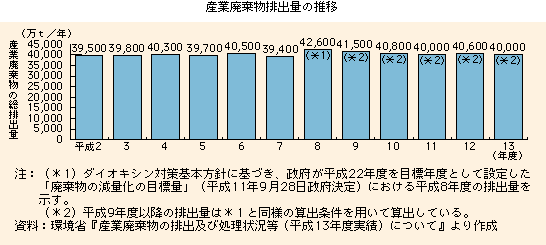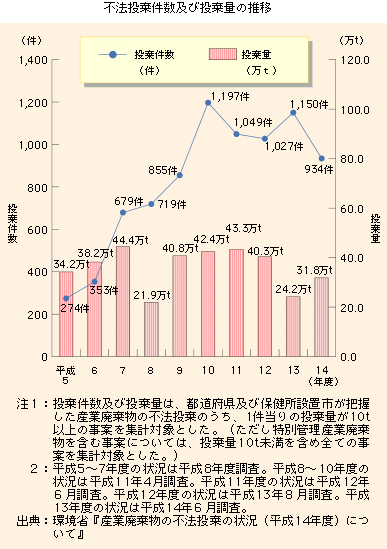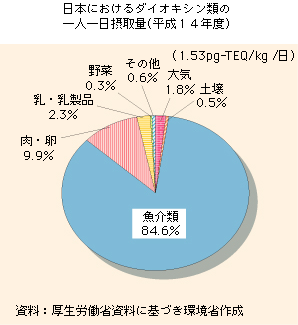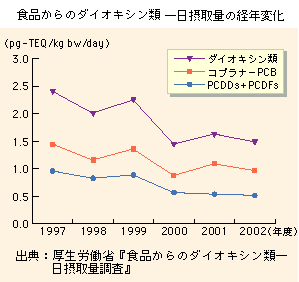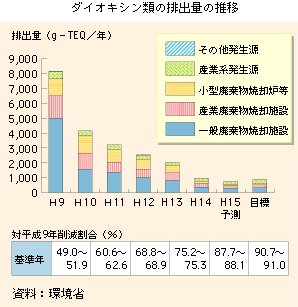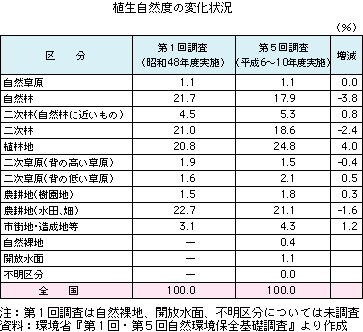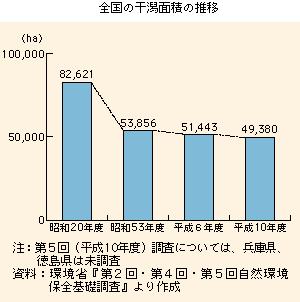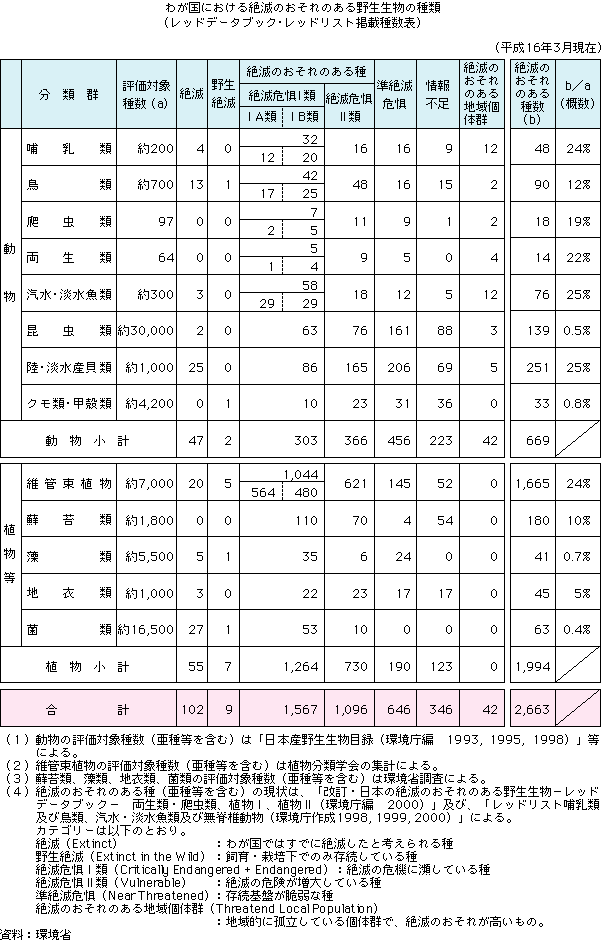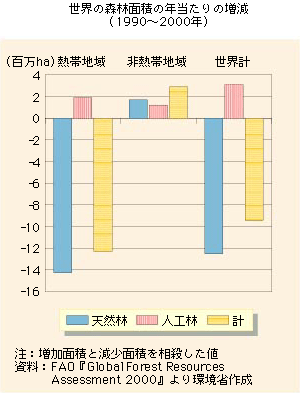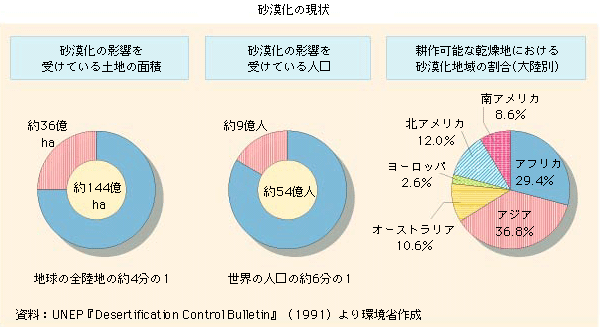(3)窒素酸化物
高濃度で呼吸器に悪影響を及ぼす窒素酸化物の主な発生源には工場等の固定発生源と自動車等の移動発生源があります。
二酸化窒素濃度の年平均値は、長期的に見るとほぼ横ばいの傾向にあります。二酸化窒素に係る環境基準の達成状況は、平成14年度99.1%(一般環境大気測定局)となっています。自動車NOx・PM法(自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法)に基づく対策地域全体における環境基準の達成状況は、平成10年度から14年度まで43.1%~69.3%(自動車排出ガス測定局)と低い水準で推移しています。 |
|
|
|
(4)浮遊粒子状物質(SPM)
大気中に浮遊する粒径が10μm以下の浮遊粒子状物質は、工場等から排出されるばいじんやディーゼル自動車から排出されるディーゼル排気粒子、土壌の巻き上げ等の一次粒子と、窒素酸化物等のガス状物質が大気中で粒子状物質に変化する二次生成粒子からなります。微小なため大気中に長時間滞留し、肺や気管等に沈着して高濃度で呼吸器に悪影響を及ぼします。
浮遊粒子状物質濃度の年平均値は、近年ほぼ横ばいからゆるやかな減少傾向が見られましたが、環境基準達成状況は、平成12年度から低下しています。
平成13年には、自動車NOx・PM法において粒子状物質を規制対象物質に加えるとともに、近年健康影響との関係が懸念されている粒径2.5μm以下の微小粒子状物質やディーゼル排気粒子についての検討を進めています。
|
|
|
|
(5)有害大気汚染物質
有害大気汚染物質対策については、低濃度ながら、多様な化学物質が大気中から検出されていることから、長期暴露による健康影響が懸念されています。ベンゼンについては、平成14年度は、409地点中の8.3%で環境基準値を超過しました。
大気汚染防止法に基づき、ベンゼン等の指定物質の抑制基準を設定し、排出抑制を図るとともに、事業者の排出抑制に係る自主管理の取組を促進しています。平成15年度の自主管理計画に基づく対象12物質の総排出量は、単純加算で11年度の約3.8万トンから14年度の約1.9万トンと、49%の削減率と大幅な減少となりました。
(6)騒音・振動、悪臭
騒音や悪臭は、各種公害の中でも日常生活に関係の深い問題であり、また、その発生源も多種多様であることから、例年、その苦情件数は公害に関する苦情件数のうちの多くを占めています。騒音の苦情件数は、ここ10年ほどは減少傾向にありましたが、平成12年度から増加に転じています。悪臭苦情についても平成9年度以降、特に野外焼却に係る苦情が急増しており、また、サービス業や個人住宅に係る苦情の割合も増加する傾向にあります。
工場・事業場、自動車、航空機等の騒音・振動については、「騒音規制法」、「振動規制法」などに基づき、許容限度や環境基準などを定め、規制を実施しています。
|
|
(7)ヒートアイランド現象
ヒートアイランド現象は、都市部の気温が郊外に比べて高くなる現象です。この現象により、夏季においては、熱帯夜の出現日数が増加していることに加え、冷房等による排熱が気温を上昇させることにより、さらなる冷房のためのエネルギー消費が生ずるという悪循環が発生しています。
平成16年3月に、人工排熱の低減、地表面被覆の改善、都市形態の改善、ライフスタイルの改善の4つを対策の柱とするヒートアイランド対策大綱を関係府省で取りまとめました。
|