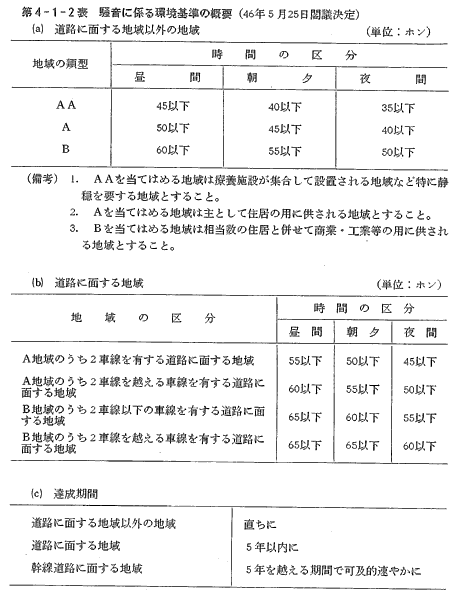
2 騒音の対策
(1) 騒音に係る環境基準
「公害対策基本法」第9条の規定に基づき、「騒音に係る環境基準」が地域の類型ごとに定められている。(第4-1-2表)。
都道府県知事は、類型をあてはめる地域の指定を行うこととなっており、昭和60年度末現在で38都道府県において、498市、597町、78村、23特別区について地域指定が行われている。
(2) 騒音規制法による規制
「騒音規制法」では、騒音を防止することにより生活環境を保全すべき地域を都道府県知事(政令指定都市にあってはその長に委任)が指定し、この指定地域内にある工場・事業場における事業活動と、建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音を規制するとともに、環境庁長官が自動車から発生する騒音の許容限度を定め、さらに、都道府県知事は、道路交通に起因する自動車騒音について対策を要請できることとしている。
都道府県知事(政令指定都市にあってはその長に委任)による地域指定は、60年度末現在で、47都道府県において、646市、1,107町、185村、23特別区について行われており、全市区町村数の約60%である。
ア 工場・事業場騒音
指定地域内にあって金属加工機械等の政令で定める特定施設を設置している工場・事業場(特定工場等という。)が規制の対象となるが、指定地域内の特定工場等の数は60年度末現在で19万1,546である。
指定地域内の特定工場等には、規制基準の遵守義務が課せられており、都道府県知事(市町村長に委任。以下同じ。)は、特定工場等から発生する騒音が規制基準に適合しないことにより、周辺の生活環境が損なわれると認められる場合に、計画変更勧告や改善勧告、さらには改善命令を行うことができる。60年度中には、改善勧告が25件行われた。また、これらの騒音規制法に基づく措置のほか、苦情に基づく報告徴収等の調査後における騒音防止に関する行政指導が2,311件行われた。
なお、住工混在の土地利用により、現に騒音公害が発生し問題となっている地域では、遮音壁の設置等の騒音防止対策、当該地域からの工場・事業場の移転等が公害対策の重要な手段となっている。しかし、騒音が問題となる工場・事業場の多くは中小規模であり、資金的な面等から対策が困難な場合が多いので、中小企業金融公庫等による工場移転についての融資、公害防止事業団による共同利用建物の建設あるいは工場団地の造成が行われている。
イ 建設作業騒音
指定地域内において行われる建設作業であって政令で定めるくい打作業等の特定建設作業が規制対象となるが、60年度の特定建設作業実施の届出件数は4万5,904件である。
都道府県知事は、特定建設作業に伴い発生する騒音が一定の基準に適合しないことにより生活環境が著しく損なわれると認める場合においては、騒音の防止の方法等に関し改善勧告又は改善命令の措置を行うことができる。60年度においては、これらの措置に至ったものはなかったが、苦情に基づく報告徴収等の調査後における騒音防止に関する行政指導が749件行われた。
建設作業騒音については、低騒音建設機械・工法の開発・普及が進められている。
(3) 近隣騒音
「騒音規制法」では、飲食店営業等に係る深夜騒音、拡声機を使用する放送に係る騒音等の規制については、地方公共団体が必要な措置を講じなければならないとされている。
近年、カラオケ等に代表される深夜営業騒音に対する苦情が増加し、このため、環境庁では55年10月30日、都道府県知事に対し、規制についての留意事項を示し、条例改正等必要な措置を講ずるよう要請した。これまでのところ深夜営業騒音について31都府県が音量規制等の具体的な規制内容を条例で定めている。また、60年2月13日より改正施行された「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に基づいて、各都道府県において設けられた同法の施行条例により、風俗営業及び深夜飲食店営業について、清浄な風俗環境を保持する等の観点から、音量規制等の対策が講じられている。60年度においては深夜営業騒音に対する苦情件数の減少が顕著だった。
商業宣伝用の拡声器の放送については、時間規制、音量規制、航空機からの拡声機放送の制限といった規制内容を有する条例が、43都道府県において制定されている。環境庁では、条例の適切な運用による対策の充実に資するため技術指針を作成し、地方公共団体に配布したところである。
なお、近隣騒音のうち、生活騒音等の問題については、騒音防止に関する知識の普及を通じて国民の意識の向上を図ることとしており、このため、61年度の環境週間においては、地方公共団体の広報及び環境庁が作成したポスター等を通じて近隣騒音の防止の呼びかけを行った。