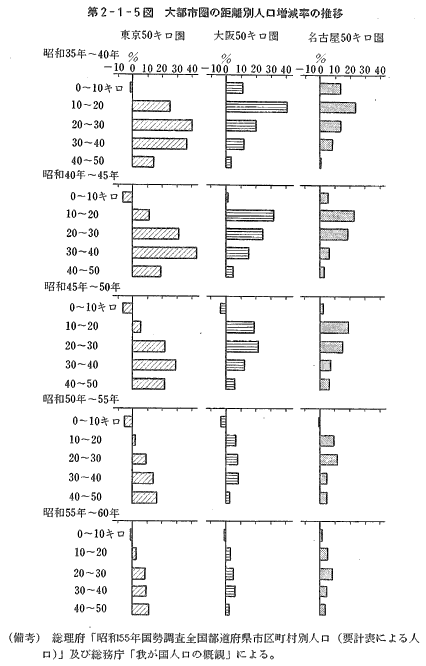
2 第一次石油危機以降
(1) 人口集中の沈静化と産業の地方分散
第一次石油危機以降、経済が安定成長へ移行し、省資源・省エネルギーが進展したが、国土利用構造の面では人口集中の沈静化と産業の地方分散がみられた。
高度成長期に特徴的であった大都市圏への人口大量流入は、地方圏における就職機会の拡大、所得格差の縮小、長男・長女化、定住志向の高まり等を背景に40年代後半から減少に転じ、50年代に入ると大都市圏と地方圏の人口移動はほぼ均衡化している(第2-1-2図)。
産業についても、第一次石油危機以降、地方分散の傾向がみられる。工業出荷額についてみると、大都市圏の占める割合は45年の60.5%から、50年代には55%程度に低下している(第2-1-3表)。また、工場立地件数についても同様の傾向がみられる。こうした国土利用構造の変化は大都市圏への大規模な人口の集中と産業の集積がみられた高度成長期とは対照的であり、環境政府の進展や企業の公害防止、省資源・省エネルギー努力、さらには、人口、産業の地方分散をめざした国土政府ともあいまって産業公害の沈静化に資するものであった。
(2) 都市型環境問題の増大
しかしながら、この時期には、高度成長期に進行していた都市化やモータリゼーションが更に進展し、消費活動の高度化、国民意識の多様化が進むなかで、都市活動や国民生活に付随して発生する都市・生活型公害や身近な自然とのふれあいの喪失、都市環境の質といった都市型の環境問題が次第にクローズアップされてきた。
50年代以降スピードは緩やかなものになっているものの、都市化は引き続き進展している。大都市圏においては8割以上の人がDID地域に居住するようになっており、地方圏においても4割以上の人がDID地域に居住している(第2-1-4図)。
市街地の拡大についても、高度成長期ほどではないが引き続き進んでいる。第2-1-5図は、大都市圏内の人口を中心部から10km帯別にみたものである。これをみると、人口増加率が最も高い地域が中心から遠距離にある地域に移動してきており、市街地が外延的に拡大していることがわかる。例えば、東京圏については、30年代後半には20km〜30km帯が最高の人口増加率を示していたが、40年代には30km〜40km帯、50年代には40km〜50km帯に移っている。
モータリゼーションの動向についてみると、自動車保有台数は、45年度末の1,892万台から、55年度末には3,899万台、60年度末には4,824万台に増加している。
以上のような状況の下で、高度成長期に既に人口の集中、産業の集積が進んでいた大都市圏においては、交通公害、廃棄物の処理・処分問題、生活排水による水質汚濁、近隣騒音等の環境問題のウェイトが高まっていった。また、地方圏においては、モータリゼーションの進展ともあいまって低密度、拡散的な市街地が形成され、加えて都市的生活様式が普及したこともあって、生活排水による水質汚濁等の環境問題が発生している。
一方、高度成長期を通じ、急速な都市化や人口移動に伴いともすれば効率優先の地域振興や画一的な都市形成が行われた面があり、身近な緑、水辺や個性的な街並み等が減少し、人々と環境とのかかわりが稀薄化したのに対して、この時期には、生活水準の向上、定住志向の高まりや精神的な豊かさの重視といった国民意識の変化等を背景に、身近な自然に目が向けられるとともに、都市環境の質の向上に対する関心も高まっていった。