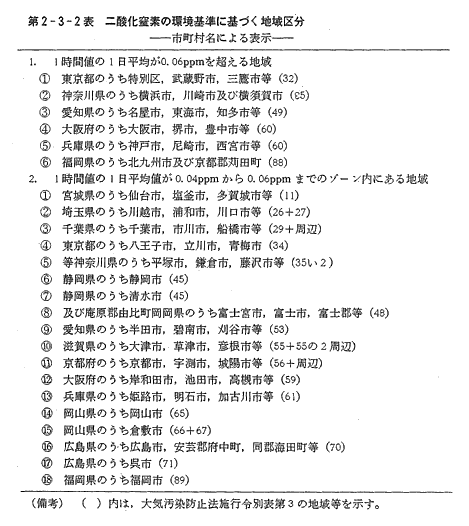
2 窒素酸化物対策
(1) 二酸化窒素の環境基準の運用等
二酸化窒素に係る環境基準については、53年7月に環境庁告示第38号(以下、単に「告示」という。)をもって「1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること」と改定されるとともに、1日平均値が0.06ppmを超える地域にあっては原則として7年以内に0.06ppmが達成されるよう努め(告示第2の1)、また、1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域にあっては、原則として、このゾーン内において、現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努める(告示第2の2)ものとされた。
環境庁では、環境基準の具体的な運用を図るために、告示に規定する「1時間値の1日平均値が0.06ppmを超える地域」及び「1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域」が具体的にどの地域に該当するかの区分を行い、54年8月その結果を各都道府県知事・政令市長あて通知した(第2-3-2表)。
この地域区分は、大気汚染防止法施行令別表第3に規定する地域(K値地域)の区分を参考に、52年度における1日平均値の年間98%値について、一般環境大気測定局のうち上位3局の平均値が0.06ppmを超えるか、又は0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にあるかによって区分することを基本的考え方とし、更に、地域の個別具体的事情に即して検討を加え、行われたものである。
また「1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域」については、「原則として、このゾーン内において、現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする」との原則が示されている。この地域における二酸化窒素濃度の動向の評価については、当面、「現状程度の水準」を当該地域内の52年度における一般環境大気測定局の1日平均値の年間98%値の上位3局平均値とすることとした上で、各年の一般環境大気測定局の1日平均値の年間98%値の上位3局平均値によることとしている(第2-1-8表参照)が、今後、同原則の具体的な運用方針については、関係地方公共団体とも緊密な連絡をとりつつ、決定していくこととしている。
(2) 固定発生源対策
ア 全国一律の排出規制の実施
固定発生源に対する全国一律の窒素酸化物の排出規制については、昭和48年8月の第1次規制以降、昭和50年12月の第2次規制、昭和52年6月の第3次規制、昭和54年8月の第4次規制と4次にわたり排出基準の強化及び対象施設の拡大を行ってきたところである。
更に、58年9月には、近年、エネルギー情勢の変化に伴って窒素酸化物の発生率が高い石炭等の固形燃料への燃料転換等が進みつつあり、今後更に進むことが見込まれること等の事情変化を背景として、固体燃焼ボイラーに係る排出基準の強化等を行い、59年度には、円滑かつ確実な排出規制の実施を図った。
窒素酸化物の排出基準値については、参考資料のとおりである。
イ 総量規制の導入
(ア) 総量規制の導入
工場、事業場が集合し、ばい煙発生施設ごとの排出規制では環境基準の確保が困難であると認められる地域については、総量規制の導入を図ることとし、56年6月、大気汚染防止法施行令の一部改正を行い、窒素酸化物に係る総量規制制度を導入し、60年までに環境基準を確保するために所要の削減対策を実施することが特に緊要であると認められた東京都特別区等地域、横浜市等地域及び大阪市等地域の3地域を総量規制地域として指定した。
総量規制の導入を保留した名古屋市等地域並びに検討を続けることとした北九州市等地域及び神戸市等地域については、地方公共団体が独自に要綱等による窒素酸化物対策の推進を図っているところである。
(イ) 総量規制の実施等
56年6月に総量規制地域に指定された3地域においては、神奈川県(横浜市等地域)では57年4月1日から、大阪府(大阪市等地域)では同年11月1日から、東京都(特別区等地域)では同年11月30日から、それぞれ60年度までに環境基準を確保することを目途として総量規制が実施されている。
また、総量規制の導入に伴い、特定工場等に設置されている一定規模以上のばい煙発生施設については、窒素酸化物に係るばい煙濃度の測定を原則として常時行うこととされている。
なお、3地域の総量削減計画及び総量規制基準の概要は参考資料のとおりである。
ウ 窒素酸化物排出低減技術の開発状況
固定発生源から排出される窒素酸化物の低減技術については、排煙脱硝技術、低NOx燃焼技術等があり、50年以来その開発状況等を継続して調査し、把握に努めている。
最近における低NOx燃焼技術の進歩には著しいものがあり、二段燃焼法、低NOxバーナーの採用等により、相当程度の窒素酸化物排出低減効果を得る燃焼技術が既に普及している状況にある。
排煙脱硝装置の設置基数及び処理能力は、第2-3-3図にみるように着実に増加している。技術開発の状況についてみると、方式としては大半が乾式選択接触還元法であり、それ以外に無触媒還元法、湿式直接吸収法、湿式酸化吸収法がある。クリーン排ガスやセミダーティ排ガスについては、実機が順調に稼動している。石炭の燃焼排ガスのようなダーティ排ガスについても、従来の集じん装置と組合せた低ダスト脱硝方式のみならず、高ダスト脱硝方式についても実機の運転の段階に入っているなど、技術の信頼性が向上している。このように石炭の性状、集じん特性、経済性、用地等各施設の実情に応じた方式の選択が行えるようになりつつある。
(3) 自動車排出ガス対策
自動車から排出される窒素酸化物については、ガソリン・LPG車に対しては48年度から、ディーゼル車に対しては49年度からそれぞれ規制が開始された。その後、ガソリン・LPG乗用車については、50年度規制、51年度規制を経て53年度には47年10月の中央公害対策審議会の中間答申に示された当初目標値(窒素酸化物平均排出量0.25g/km)に沿った規制(53年度規制)が実施され、未規制時に比べ10分の1以下に低減されるという世界的にみても厳しい基準となっている。
ガソリン・LPG乗用車以外の車両(トラック・バス等)に対する規制は、48〜49年度に開始された後、軽量・中量ガソリン車及び軽貨物車については50年度規制により、重量ガソリン車及びディーゼル車については52年度規制により、それぞれ強化された。
さらに、トラック、バス等の窒素酸化物に係る排出ガス規制を一層強化するため、52年12月に中央公害対策審議会から自動車排出ガス許容限度長期設定方策について答申がなされ、2段階の目標値が示された。これに基づく第1段階の規制は全車種54年規制として実施するとともに、第2段階の規制については、自動車公害防止技術評価検討会を設け、自動車排出ガス低減技術の開発状況の評価検討を行い、技術開発の促進を図りつつ、技術的に対応の見通しの得られた車種から逐次規制を実施しており、58年までにすべての車種に実施した。(第2-3-4表)
また、ディーゼル乗用車については、現在トラック、バス等と同様の濃度規制が実施されているが、近年における増加傾向を踏まえ、規制の強化とともに重量規制への移行を図るため、56年5月に自動車公害防止技術評価検討会において、新たな二段階の目標が示されたことから、現在その早期達成に向け技術評価を進めており、このうち手動変速機付車両については、第一段階目標値に基づく規制を61年規制として実施すべく59年10月許容限度等の強化を行った。(第2-3-5表及び第2-3-6図)
さらに、排出ガスのない電気自動車の開発、普及促進が引き続き図られているほか、窒素酸化物排出量の少ないメタノール自動車の導入のための調査研究等が行われている。
また、窒素酸化物による大気汚染に対処するには自動車に対する個別発生源対策のみでなく、交通管理、道路構造の改善等の諸対策についても併せて実施していくことが必要であり、52年12月の中央公害対策審議会答申においても、「交通の集中に伴う大気汚染が著しい都市において、個々の自動車に対する排出ガス規制に加えて、自動車交通総量の抑制と自動車交通流の円滑化を図る」ための諸対策が提言されている。