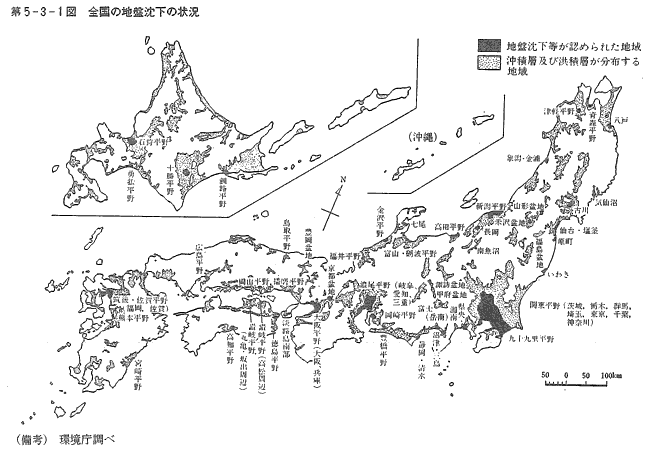
1 地盤沈下の現況
地盤沈下の歴史は古く、東京都江東区では大正の初期、大阪市西部では昭和の初期から注目され始め、その後急速に沈下が進行するにつれて建物等の抜け上がりや高潮等による被害が生じ、大きな社会問題となった。これらの地区では戦災を受けた昭和20年前後には一時的沈下が停止したが、25年頃から再び沈下は激しくなり、その範囲も拡大してきた。30年以降地盤沈下は大都市ばかりでなく、新潟平野、濃尾平野をはじめ全国各地において認められるようになった。現在までに、地盤沈下が認められている主な地域は36都道府県60地域となっている(第5-3-1図参照)。
最近における我が国の地盤沈下の特徴をあげると次のようになる。
(1) 昭和57年度においては、横浜市において年間26.3cmの地盤沈下が生じ、最大沈下量が年間20?を超える地盤沈下は、昭和50年度以来認められなかったものである。横浜市のケースは地下掘削工事に伴う一過性のものとして特異なケースであり、これに次ぐ沈下量は札幌市の年間5.9cmとなっている。その他の地域における最近の地盤沈下の傾向としては、かつてのように全国的に著しい沈下を示すような状況はみられなくなっている。
しかし、年間2cm以上沈下した地域の面積の合計は、ここ4年ほど横ばいであるなど、地盤沈下は依然として多くの地域でゆるがせにできない問題となっている。
全般的にみると関東平野のうち埼玉県北東部から茨城県西部にまたがる地域及び筑後・佐賀平野で広域的に顕著な沈下が続いており、また、前述の横浜市及び石狩平野のほか、諏訪盆地においても年間5cmを超える著しい地盤沈下が認められた。このほか、宮城県塩釜市及び千葉県九十九里平野における年間4cm以上の沈下が目立っている。
(2) 大都市圏地域においては、東京都区部、大阪市、名古屋市等のような既成都市区域では、かつて著しい沈下を示したが、その後の地下水採取規制の結果、地盤沈下の進行は鈍化あるいはほとんど停止している。一方、大都市近郊地域では、地盤沈下の状況は長期的には改善傾向にあるものの、首都圏近郊の一部の地域等で依然として沈下が続いている。
(3) 大都市圏以外の地域においては、青森市や石川県七尾市等では、一時期激しい沈下が生じていたが、その後の地下水採取規制の結果、以前に比較して地盤沈下の進行がかなり鈍化あるいはほぼ停止している。一方、秋田県金浦町、新潟平野のように依然として地盤沈下が断続的に続いている地域もある。
長年継続した地盤沈下により、多くの地域で建造物、治水施設、港湾施設、農地及び農業用施設用に被害が生じており、ゼロメートル地域では洪水、高潮、津波等による甚大な災害の危険性のある地域も少なくない。
代表的な地域の地盤沈下の経年変化は、第5-3-2図に示すとおりである。
地盤沈下は、地下水の過剰な採取が原因となるものであるが、その地域の地形、地質、土地利用等の状況いかんによってもその現れ方が著しく異なり、極めて地域的特性の強い公害となっている。また、地下水の採取を用途別に見ると、工業用、建築物用のみならず、水道用、農業用、水産養殖用、消雪用等多岐にわたっている。このほか水溶性天然ガスを溶存する地下水及び温泉水の採取によっても地盤沈下が生ずることが明らかにされている。
地下水を中心とした水利用状況については、既存統計資料等により把握されているものは第5-3-3表のとおりである。