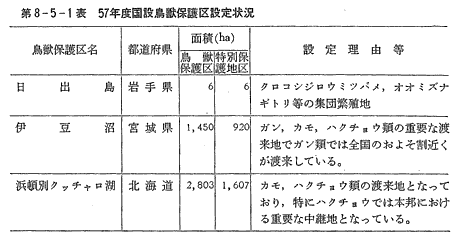
近年、国民の野生鳥獣保護に関する関心が急速に高まってきた。これは各種の開発等によって、鳥獣の生息環境が減少し我々の周辺から鳥や獣が姿を消しつつあることが広く国民の関心の的となってきたことによるものと考えられる。
このような気運は、国際的な潮流となっており、渡り鳥や絶滅のおそれのある動植物を保護するための各種の国際条約の締結となって現われている。
野生鳥獣は、自然環境を構成する重要な要素であり、野生鳥獣が持つ多様な価値は豊かな生活環境を形成する上で欠くことができないものである。また、野生鳥獣は農林業等の振興の面においても多くの恵沢をもたらすが、反面、一部の鳥獣は農林水産業に被害を及ぼしている。
一方、狩猟についてみると、狩猟鳥獣は減少する傾向にある。こうした近年の鳥獣の保護及び狩猟の実態に対応するため鳥猟保護の一層の充実を図るとともに狩猟の適正化を図っている。
(1) 第5次鳥獣保護事業計画の策定
「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」に基づき、都道府県知事は鳥獣の保護繁殖に関する事業を実施するための計画を樹立することとされているが、第4次鳥獣保護事業計画は昭和56年度をもって期間が満了したため、57年度から向う5か年間を計画期間とする第5次鳥獣保護事業計画が開始された。各都道府県においては、国が定めた基準に基づき、それぞれの地域の実態に応じた事業計画を樹立した。
(2) 鳥獣保護区の設定等
環境庁長官又は都道府県知事は鳥獣の保護繁殖を図るため、鳥獣保護区を設定しているほか、特に必要とする場合には保護区内に特別保護地区を指定している。
鳥獣保護区内では鳥獣の捕獲が禁止されているほか保護繁殖施設の設置等が行われている。また、特別保護地区内では、水面の埋立、立木竹の伐採、工作物の設置等について許可が必要となっている。
54年度から国設鳥獣保護区の設定は特に絶滅のおそれのある鳥獣の生息地、主要な渡り鳥の経路上にある渡来地等で、全国的視野から鳥獣保護上重要な地域について重点的に行うこととしており、57年度においては既設定の34国設鳥獣保護区に加えて、3保護区の設定を行った(第8-5-1表)。
なお、54年度までに設定されていた国設鳥獣保護区のうち、上記の条件を満たさないところにあっては都道府県設の鳥獣保護区に設定替を行っている。
56年度末の鳥獣保護区の設定状況は第8-5-2表のとおりである。
(3) 特定鳥獣の保護管理
鳥獣保護区等に生息する特定鳥獣の保護管理及び増殖対策を進めるため、次の保護措置等を講じた。
ア トキについては自然条件のもとでは繁殖が困難であることから、56年1月に全鳥を補獲し、人工増殖事業に着手したところであるが57年度においても引き続き増殖に向けて4羽の飼育を行った。
イ イリオモテヤマネコについては49年度から3か年にわたる調査研究によって、30〜40頭が生息すると推定された。54年度以来増殖対策の一環として給餌を実施しているが、更に、イリオモテヤマネコの恒久的保護対策を検討するため57年度から生息分布、生息数及び生態に関する調査を開始した。
ウ 56年度に60年ぶりの新種として発見されたヤンバルクイナについては、保護対策を検討するための生息状況等の調査及び生態映画の製作を行った。
エ エゾシカ、ホンシュウジカ及びツキノワグマについてその個体群分布、行動様式、個体群構造等の調査及びセンサス手法の開発のための基礎的研究を行った。
オ その他、下北半島のサル、ライチョウ、ニホンカワウソ、アホウドリについて、前年度に引き続き、監視、環境保全等の保護措置を講じた。
(4) カモシカの保護及び被害防止対策
カモシカについては、その保護と農林業被害対策との適切な調整を図る必要があるため、文化庁、林野庁及び環境庁が協議の上定めたカモシカの保護と被害の防止を図るための方針に基づき、各種の措置がとられている。57年度は5か所目のカモシカ保護地域として、北上山地カモシカ保護地域の設定を行うともに、鈴鹿山系、北奥羽山系、紀伊山地及び四国山地の保護地域設定の検討を進めている。また特に被害の著しい地域を主体に、前年度に引き続き防護柵の設置、ポリネットの装着等による被害防止策を講じるとともに、岐阜県及び長野県において個体数調整を認めた。また、カモシカによる森林被害の防止に関する調査研究を前年度に引き続き実施した。
(5) 渡り鳥観測体制の整備
我が国における渡り鳥の標識調査は、小規模ながら戦前から行われてきたが、日米、日豪及び日中間の渡り鳥等保護条約等の締結により、従前にも増して標識調査データは貴重な情報となっている。このため渡り鳥の特に多く集まる渡来地、越冬地等のうち重要な地点を1級観測ステーションとして9か所、その他を2級観測ステーションとして46か所それぞれ選定し(58年3月末現在)、標識調査を実施している。
また、標識調査を充実するため、第5次鳥獣保護事業計画においては、都道府県による標識調査の実施を推進することとしており、一部の県においてはこれに着手した。
(6) 狩猟の適正化と鳥獣管理の推進について
ア 狩猟鳥獣の捕獲の禁止について
主要な狩猟鳥獣であるキジ、ヤマドリの生息数の減少傾向をくい止め保護繁殖を図るため、58年11月1日から62年10月31日までの間、メスキジ、メスヤマドリの捕獲を禁止することとした。
イ 猟区の設定について
人工増殖した狩猟鳥獣を放鳥獣し、これを捕獲することを目的とした放鳥獣猟区として、諌早(長崎県)、茅ヶ岳(山梨県)など6か所の設定を認可した。
また、一般猟区についても、古殿(福島県)及び三陸葉山(岩手県)の2か所の設定を認可した(第8-5-3表)。
ウ 密猟の防止について
カスミ網によるツグミ等の密猟防止及びワシタカ類の密猟防止の推進については、環境庁、警察庁の連携の下に取締りの実効を図るとともに、都道府県に対し、その推進方を指導した。
(7) 鳥獣保護に関する国際協力の推進
鳥獣保護の分野における国際協力推進のため現在、米国、豪州及び中国との間で渡り鳥等保護条約等を締結しているが、渡り鳥保護に関する資料等の交換、標識調査に関する技術の交流等を行うため、57年度においては第1回目豪会議(57年5月、東京)及び第1回日中会議(58年2月、東京)を開催したほか、日米間においても保護会議を開催(58年3月、ワシントン)した。
また特にトキの保護増殖を推進するため我が国と中国の間においてトキの保護に関する資料の交換、保護増殖技術の交流等を実施するため、57年8月、第2回日中トキ保護会議を北京で開催した。
(8) 鳥獣保護思想の普及啓蒙
鳥獣保護思想の普及啓蒙を図るため、愛鳥週間行事の一環として大分県県民の森において「第36回愛鳥週間全国野鳥保護のつどい」を開催したほか、愛鳥モデル校を中心に行われている野生鳥獣保護の実践活動の現状、効果等を発表するための「全国鳥獣保護実績発表大会」を前年度に引き続き開催した。