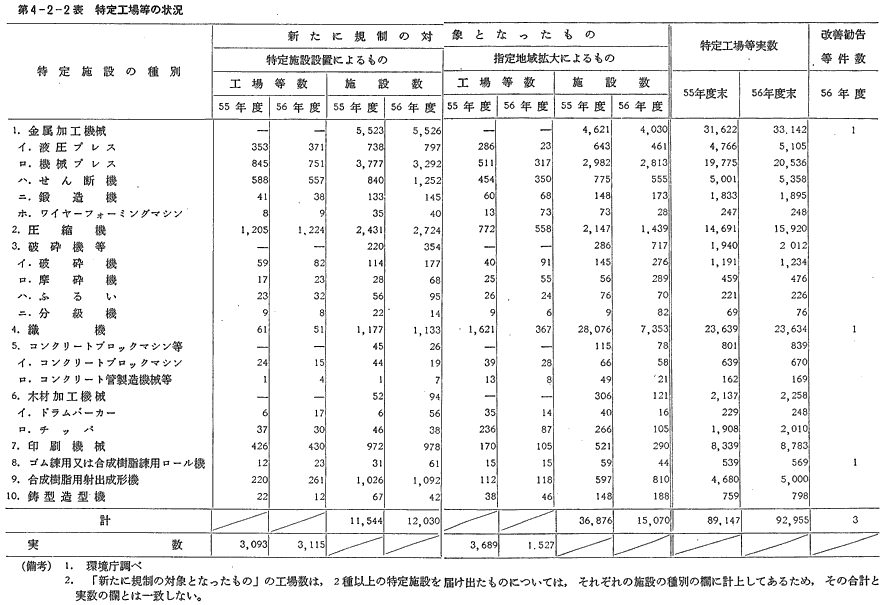
2 振動の対策
(1) 振動規制法による規制
「振動規制法」では、都道府県知事が振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を指定し、この指定地域内において工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる振動について必要な規制を行うとともに、道路交通振動に係る要請の措置を定めている。
都道府県知事による地域指定は、56年度末現在で、47都道府県において604市635町98村23特別区について行われており、全市区町村数の42%である。
ア 工場・事業場振動
工場・事業場振動について規制の対象になるのは、指定地域内にあって、政令で定める特定施設を設置している工場及び事業場(特定工場等という。)である。
規制対象となっている特定工場等の数は56年度末現在において92,955に及んでいる(第4-2-2表)。
特定工場等には、規制基準の遵守義務が課せられており、都道府県知事(政令で市町村長に委任されている。以下同じ。)は、特定工場等から発生する振動が規制基準に適合しないことにより周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、振動の防止の方法等に関し、改善勧告及び改善命令を行うことができる。56年度中に行われた改善勧告は3件であった。これらの改善勧告を受けた特定工場等では振動の防止方法の改善等が行われている。
なお、振動防止対策として、工場施設については、低振動機械の採用、吊基礎、浮基礎、直接支持基礎(板ばね、コイルばね等を使用するもの)などの防振装置の設置、機械基礎の改善等により防振対策が行われている。
また、住工混在地から工場・事業場の移転、工場周辺における住宅建築の回避の指導等、土地利用の適正化を図っていくことが今後の公害対策の一つの重要な手段となっている。このため、中小企業金融公庫等による工場移転についての融資、公害防止事業団による共同利用建物の建設あるいは工場団地の造成が行われている。
イ 建設作業振動
建設作業振動について規制の対象となるのは、指定地域内において、行われる建設作業であって、政令で定める特定建設作業である。
特定建設作業には、届出義務が課せられており、56年度の特定建設作業の届出件数は29,649件であった(第4-2-3表)。
都道府県知事は、特定建設作業に伴う振動が一定の基準に適合しないことにより周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、振動の防止の方法等に関し、改善勧告及び改善命令を行うことができるが、56年度中には行われていない。
建設作業については、振動を発生する建設機械の改良とともに、低振動工法の開発が積極的に進められている。
(2) 低周波空気振動対策
近年、人の耳には聞きとりにくい低い周波数の空気振動(低周波空気振動)がガラス窓や戸・障子等を振動させたり、人体に影響を及ぼしたりするとして苦情が発生している(第4-2-4表)。しかし、低周波空気振動は、その発生源が多種多様(第4-2-5表)であり、その適切な防止対策も十分には確立されていないため、環境庁では、低周波空気振動発生施設周辺での実態調査、低周波空気振動の生理的影響等に関する調査研究を行っている。
低周波空気振動のレベルと、物的・心理的・生理的影響等との相関のは握については、評価方法が定まっていないこと、個人差が大きいこと等もあって、基準等の設定に至るまでには、さらに調査研究が必要と思われるが、現実に被害があるとの苦情が発生していることにかんがみ、これらの調査研究を進めるとともに、適切な防止対策を講ずる必要がある。