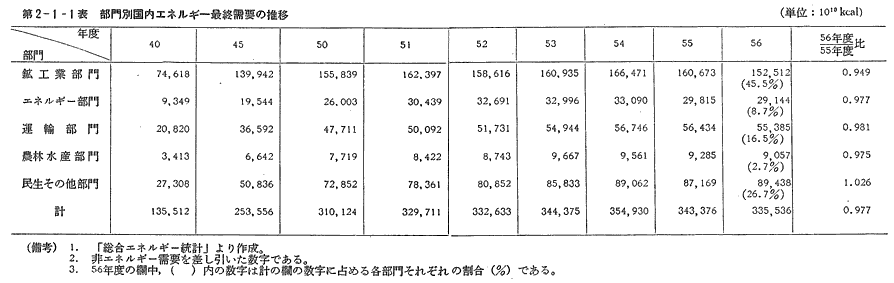
1 大気環境をとりまくエネルギー構造の変化
大気中の硫黄酸化物、窒素酸化物等の大気汚染物質の多くは、物の燃焼過程から生ずるものであり、エネルギー消費の動向は大気汚染の動向と密接な関係を持っている。
エネルギー消費は、昭和48年度まで一貫して拡大し、石油危機をきっかけに49年度、50年度と、2年連続して減少したが、51年度以後再び増加に転じた。
しかし、56年度のエネルギー消費は55年度に引き続き減少した。
この動向を部門別にみると、エネルギー国内最終需要の推移は第2-1-1表のとおりである。
次に、1次エネルギーの供給量の推移をみると、第2-1-2図のとおりである。30年代以降48年の第1次石油危機が勃発するまでの間は、高度経済成長に伴って石炭から石油へのエネルギー転換が大規模に行われたが、第1次石油危機降石油供給量は横ばいで推移し、53年末からのイラン政変を契機とした第2次石油危機以降の石油価格の大幅な上昇によって、石炭等の石油代替エネルギーの利用が拡大しており、中でも低廉な石炭、LNG及び原子力への転換が急速に進行している。
また、輸入原油の重質化が進んでいる。
石炭利用については、一般に石油の場合に比べて硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじん等の発生量が多く、また、貯蔵・運搬に伴い粉じんが飛散しやすいという問題がある。また、重質油についても、窒素酸化物やばいじんの発生量を増加させる窒素分や残灰分を多く含んでいる。したがって、これらの燃料転換、燃料油の質的変化等が大気保全上の問題を起こさないよう、その動向を十分注視する必要がある。