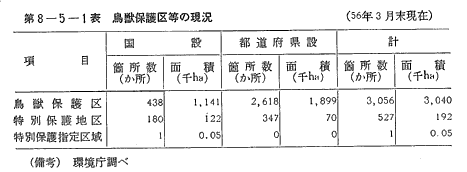
近年、我が国においても野生鳥獣保護に関する関心が急速に高まってきた。これは各種の開発によって我々の周辺から鳥や獣が姿を消しつつあることが広く国民の関心の的となってきたことによるものと考えられる。
このような気運は、国際的な潮流となっており、渡り鳥や絶滅のおそれのある動植物を各国が保護していくための各種の国際条約の締結となって現われている。
野生鳥獣は、自然環境を構成する重要な要素であり、自然環境をより豊かにする上で欠くことのできないものであると同時に、その減少は、人間にとってもその生活環境の悪化を示す指標の一つであるという意味において、決して見過ごしにできない問題となっている。
こうした近年の鳥獣の生息環境及び狩猟の実態の変貌に対応するため、「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」が53年度に改正され、54年度からこの改正が全面施行されたので、これに基づき鳥獣保護の一層の充実を図るとともに、狩猟の適正化を図っている。
そのほか、野生鳥獣の生息環境の保全を図るため、鳥獣の生息状況の把握、鳥獣保護区の設定等保護措置の充実に努めている。
(1) 鳥獣保護区の設定
鳥獣保護区は鳥獣の保護繁殖を図るため、環境庁長官が定める鳥獣保護事業計画の基準にそって、環境庁長官又は都道府県知事が設定するものであって、その区域内では鳥獣の捕獲が禁止されているほか、保護繁殖施設の設置等が行われているが、特に絶滅のおそれのある鳥獣の生息地、主要な渡り鳥の経路上にある渡来地等で、全国的視野から鳥獣保護上重要な地域については、重点的に保護管理を強化することとしている。
56年度に設定された特色のある鳥獣保護区を挙げると、まず、オオミズナギドリ、ウミネコ、ウミウ、ヒメクロウミツバメ、オオセグロカモメ等が集団で繁殖している岩手県三貫島の全島22ヘクタールを鳥獣保護区に設定するとともに特別保護地区に指定した。また、特殊鳥類であるトキの生息地として新潟県佐渡に設定されていた鳥獣保護区は、56年10月設定期限が満了したため、これを更新するに当たり、これまで313ヘクタールであったものを740ヘクタールに区域を拡大して設定するとともに、同区域を特別保護地区に指定した。
55年度末の鳥獣保護区等の設定状況は第8-5-1表のとおりである。
(2) 貴重動物の保護
鳥獣保護区等に生息する貴重な動物でその保護を生息環境の保全と一体として行う必要があるものの保護増殖対策を総合的に実施するため、トキ、北限のサル、ライチョウ、カモシカ、ニホンカワウソについて給餌、監視保護設備の整備等の保護措置を講じた。
また、種の存続が危ぶまれている特定の鳥獣については人工増殖等の特別保護を講じる必要があり、このため、特定鳥獣増殖検討会において、トキ、イリオモテヤマネコ等絶滅のおそれのある鳥獣について、人工増殖に必要な対策の検討等を行った。
このうち、トキについては、自然条件のもとでは、繁殖が困難であることから56年1月に全成鳥を捕獲し、人工増殖事業に着手したところであるが、56年度においても引き続いて増殖に向けて飼育を行った。
更に、56年5月、中国陜西省泰嶺において7羽のときの生息が確認され、このうちの幼鳥1羽が北京動物園で飼育されているが、トキの保護及び増殖の分野においても、日中間の技術協力を進めるため、56年9月に中国の専門家を招き、意見交換等を行った。
また、イリオモテヤマネコについては、49年から3か年にわたる調査研究により、30〜40頭が生息すると推定されているが、これ以上の減少を防ぐため、増殖対策の一環として給餌を実施している。
なお、カモシカについては、その保護と農林業被害対策との適切な調整を図る必要があるため、文化庁、林野庁及び環境庁において協議を行い、白山カモシカ保護地域の設定を行うとともに北上山地における保護地域設定の検討を進め、特に被害の大きい岐阜県及び長野県において前年度に引き続き個体数調整を認めた。
(3) 渡り鳥観測網の整備
渡り鳥の生態をは握する上で標識調査は最も効果的であるとされている。我が国においても日米渡り鳥等保護条約の調印を契機として積極的にその拡充を図っており、渡り鳥の渡来地、越冬地等重要な地点に1級ステーション9か所、その他渡り鳥通過地点に2級ステーション46か所を設け、計55か所において渡り鳥の標識調査及び生態調査を実施している。
(4) 鳥獣保護に関する国際協力
鳥獣保護の分野における国際協力推進のため、関係国の間で渡り鳥保護条約の締結を進めているが、56年度においては56年4月30日に「渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類並びにその環境の保護に関する日本国政府とオーストラリア政府との協定」(日豪渡り鳥協定)が、また、同年6月8日に「渡り鳥及び生息環境の保護に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定」(日中渡り鳥協定)がそれぞれ批准された。
(5) ヤンバルクイナの保護
昭和56年11月、財団法人山階鳥類研究所は、沖縄県本島北部の山間地でクイナ科の新種の鳥(ヤンバルクイナと命名)を発見した旨発表した。ヤンバルクイナは環境庁の行った現地概況調査及び専門家の意見などから考察すると、生息数は比較的少なく、また、その生息域も沖縄県本島北部に限定されていると見られることから早急に保護対策を確立する必要があるため、環境庁では同年12月「ヤンバルクイナ保護対策検討会(座長黒田長久)」を設置し、ヤンバルクイナの学術的評価、生息状況等調査手法の検討等を行ったところである。
なお、同検討会の意見も踏まえ、当面ヤンバルクイナの国内における譲渡等の規制及び輸出入の規制を行うため57年3月6日ヤンバルクイナを特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律に基づく特殊鳥類に指定した。