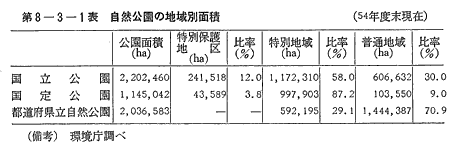
2 自然公園における自然保護
(1) 自然公園内における行為規制
自然公園の優れた風致景観を保護するため、自然公園内に特別地域、特別保護地区及び海中公園地区(都道府県立自然公園の場合は、特別地域のみ)を指定し(第8-3-1表参照)、当該地域、地区内における風致景観を損なうおそれのある一定の行為は、環境庁長官又は都道府県知事の許可を受けなければならないこととされている。また、普通地域においても一定の改変は都道府県知事に届け出させ、必要な規制を加えることができることとされている。
国立公園及び国定公園の特別保護地区、特別地域及び海中公園地区内におる各種行為については「国立公園内(普通地域を除く。)における各種の行為に関する審査指針」の適用により、保護適正化と事務処理の円滑化に努めている。
国立公園内の特別地域及び特別保護地区における工作物の新、改、増築、鉱物の掘採、土石の採取等の行為の環境庁長官に対する許可申請件数は第8-3-2表のとおりである。
また、今日のエネルギー問題において、石油代替エネルギーの開発が重要な課題となっており、その一分野として、国産エネルギーである地熱発電への期待が高まりつつあるが、地熱発電の候補地が国立・国定公園内に多く、もしこの中で建設がなされれば、各種の巨大工作物が設置されるばかりでなく、樹林の伐採、地形の改変が行われ、優れた風致景観に与える影響は大である。この問題に対しては、先頃自然環境保全審議会より「地熱開発計画地の選定に当たっては国立、国定公園内の自然環境保全上重要な地域を避けることを基本とすべきである。」との意見書が提出されている。
(2) 管理体制の強化
国立公園内における風致景観を保護管理するとともに、公園事業者に対する指導、公園利用者に対する自然解説等広範な業務を行うため、阿寒、十和田八幡平、日光等主要な10公園の主要な地区に国立公園管理事務所を置き、その他の公園の各地区についても単独で駐在する国立公園管理員を配置している。54年度末現在の国立公園管理員定数は99人である。
(3) 国立・国定公園内指定植物の改定調査
国立公園及び国定公園の特別地域内に生育する植物については、風致景観の重要な構成要素であることから、環境庁長官の指定する植物は許可を受けなければ採取できないこととされているが、全国一律指定であったこと、また、亜熱帯性、暖帯性の特徴的な植物が指定の対象からもれている等必ずしも各国立・国定公園の実情に合った指定がなされていないことから指定植物の改定を行う必要が生じ、52年度より3か年度計画で改定のための調査を行い、54年度においては、この調査結果に基づき、各国立・国定公園別に実体に合わせた植物を指定するための作業を進めた。
(4) 自然公園におけるごみ処理体制
近年、自然公園は利用シーズンには過剰利用の状況を呈しており、主要利用地域においては、公園利用者がもたらす空きかん等による汚れが目立ってきている。
これらのごみは、地理的特性からその収集と終末処理が極めて困難であり、単に美観の損傷のみならず悪臭などの汚染を引き起こすことがある。
国立公園内の総理府所管の集団施設地区とその周辺の美化については、従来から国立公園内集団施設地区等美化清掃事業を関係都道府県の協力の下に実施してきた。それ以外の地域においても日常生活圏域から遠隔地にあること及び数市町村にまたがる場合が多いこと等により、その清掃活動に円滑さを欠くこととなる。そこで、特に利用者の多い国立公園内の主要な地域の美化清掃を積極的に推進するため、現地における美化清掃団体の育成強化を図り、またそれらの団体が行う清掃活動事業に対し補助を行っている。
54年度においても前年度に引き続き、総理府所管の集団施設地区の清掃を直轄事業で行うとともに、それ以外の主要な利用拠点地区についても、清掃活動費に対して補助を行う等国立公園内の清掃活動の充実を図った。
また、北アルプス等の冬山登山によるごみ問題について、山岳団体等へごみ持ち帰りを励行するよう指導を行った。
(5) 自然公園内における自動車利用の適正化対策
近年、自然公園内の優れた自然環境を有する地域への自動車の乗り入れが増大し、これにより自然公園の保護と利用の両面にわたり種々の障害が生じてきている。
例えば、自然保護の面では、道路の拡幅、駐車場の拡張等による地形、植生の改変、路傍等への違法な乗り入れによる植生の破壊、排ガス汚染等による植生の衰弱、夜間の通行による動物の殺傷、生息環境の悪化等の問題である。
また、自然公園の利用の面では、多くの車両の通行により、静穏な環境や安全な利用が損なわれ、また、交通渋滞が生じるなど、快適かつ効果的な公園利用に支障を来たす等の問題が生じ、各方面からその対策が要請されている。
このため、環境庁では、国立公園内における自動車利用の適正化対策を講ずることとし、十和田八幡平国立公園奥入瀬地区、日光国立公園尾瀬地区、中部山岳国立公園上高地地区、立山地区及び乗鞍地区並びに富士箱根伊豆国立公園富士山地区の6か所をモデル地区として選定して、国立公園管理事務所、地元関係機関及び関係団体による対策協議会を設置し、各地区の特性に応じた適正化方針を定め、これにより警察等関係機関の協力によって「道路交通法」に基づく交通規制や、代替バスの運行などの対策が講じられている。54年度においてもこれらの地区について引き続き適正化対策を推進した。
各地区における適正化対策の概要は次のとおりである。
十和田八幡平国立公園奥入瀬地区においては、国道102号線の夏期及び紅葉期の車利用に対処するため、渋滞箇所において交通整理及び駐車禁止を行ったほか、植生保護及び歩道利用者の安全快適な利用確保のため、林内及び歩道への車両の侵入を防止した。
日光国立公園尾瀬地区においては、群馬県三平峠口の大清水ですべての車両をストップし、大清水以奥は徒歩利用とした。また、富士見峠口、鳩待峠口もそれぞれ対策を実施した。一方、福島県側のルートでは、特に車利用の著しいいわゆる「ミズバショウシーズン」に、沼山峠駐車場が満車になる時点で御池で規制を開始し、代替輸送バスを運行させた。
富士箱根伊豆国立公園富士山地区においては、スバルライン終点、五合目駐車場の利用状況に応じ、入口ゲートで乗り入れる台数を規制し、また車止め等の施設を設けることにより、駐車場以外の地域への車両の乗り入れを禁止した。
中部山岳国立公園上高地地区においては、これまで7月から8月の夏の利用最盛期の1か月間及び秋の利用シーズンである10月の半月間、中の湯(国道158号線からの分岐点)以奥について厳しい規制が実施されてきた。
54年度は、秋の利用シーズンについて、9月も加え10月中旬まで混雑の著しい週末及び休日に規制を行い、平日は規制を行わないという、過去の実施状況を踏まえより利用の実態に即したきめの細かい規制を実施した。
上高地における規制の内容は、バス、タクシー等を除くすべての自動車について、規制期間中、中の湯以奥への進入を禁止するという画期的なもので、この規制により、上高地一帯は、利用シーズン最盛期にもかかわらず、静穏な環境が保たれ自動車に煩わされない自然公園の利用環境が確保された。
また、乗鞍地区においては、乗鞍スカイラインの鶴ヶ池、畳平を中心に夜間の通行を禁止したほか、終点部の公共駐車場以外における駐車禁止、園路への乗り入れ禁止などを実施した。
立山地区においては、山ろく桂台から上部の美女平、室堂方面へは、定期バス及び観光バスに限り乗り入れを認めた。
以上の各地において講じられた対策の6年にわたる実績及び広報による自動車利用適正化対策の趣旨の浸透により無秩序なマイカー利用が減少してきたため、歩行者に対する安全確保、静穏の維持といった公園利用上の効果及び自然植生の破壊(踏圧、盗採等)の減少、野生鳥獣の生息環境の破壊の防止といった効果があらわれてきている。
(6) 財団法人自然公園美化管理財団の発足
増大する自然公園利用者に対応して、環境美化の推進と公園施設等の維持管理の徹底及び自然公園利用者に対する自然保護思想の教化普及等を図ることが緊急な課題となっているが、これを円滑に実施するため、財団法人自然公園美化管理財団が54年6月29日に設立され、7月から支笏洞爺国立公園支笏湖畔、十和田八幡平国立公園休屋、日光国立公園湯元及び中部山岳国立公園上高地の4地区において事業を開始した。
これらの4地区については、事業の実施によってこれまで以上に清掃が徹底し、歩道、便所、休憩所等の公共施設の清掃、補修が円滑に行われたほか、集中する自動車の整理・誘導により混雑の緩和と事故の未然防止等に役立ち、自然公園としての清潔で快適な環境の保持に顕著な効果がみられた。
(7) 財団法人本州四国連絡橋自然環境保全基金の発足
本州四国連絡橋(児島・坂出ルート)が建設される児島・坂出間の島々の一帯は、瀬戸内海国立公園の核心部として世界に誇るべき多島海景観を有している地域である。
この大規模な架橋を瀬戸内海の自然環境に融合させ、新しい景観を創出し国民的資産として永く子孫に継承していくためには、同ルートの建設や利用者の増加などのために生ずる自然環境への影響を最小限に防止し、又は、その回復を図る等、架橋周辺部における総合的な自然環境保全対策を強力に推進することが緊急な課題である。このため、国や地方公共団体等において格段の努力をすることが緊要であるが、更に、これらによっては十分に対応しえないようなきめの細かい架橋周辺部における自然環境保全対策を円滑に実施するため、関係各方面の協力を得て、55年3月15日に財団法人本州四国連絡橋自然環境保全基金が設立されたところである。
(8) 富士山クリーン作戦の実施
富士山は、我が国の象徴ともいうべき優れた風景であり、また国民の心のふるさととして古くから広く親しまれている。ところが、毎年利用者が増加するにつれ、ごみや空カンも増え、特に汚れが目立っている。このため、昨年度環境庁、静岡県、山梨県の三者で「富士山自然環境保全対策会議」を設立し、当面の対策としては、富士山に投棄されているごみを54年度の登山シーズン前に徹底して回収することとなり、各界、各層の協力のもとに「富士山クリーン作戦」運動を展開することとなった。54年6月23日「富士山クリーン作戦」はボランティア、地元山岳会、高校生、消防団及び自衛隊等2万4,000人に及ぶ人々の奉仕作業で早朝6時より午後3時まで行われ、197トンのごみ(うち空カン数170万個)を回収し終了した。
この富士山クリーン作戦の成果としては、(1) 富士山がみちがえるほどきれいになったことばかりでなく、(2) 2万人を超すボランティアの組織化の過程で、富士山のごみ処理問題の認識が地域社会において飛躍的に高まったこと、更に、(3) 新聞等へ激励の投書が多数にのぼったことなどクリーン作戦が全国民的な関心を呼び起こし、全国各地に同種のミニクリーン作戦が実施されたことが挙げられる。
(9) 特殊植物等の保全事業
国立公園等内に生育している貴重な植物等で、その保護を生育環境の保全と一体として行う必要のあるものの保護増殖対策を総合的に実施するため、尾瀬湿原(日光国立公園)、大瀬崎ビャクシン樹林(富士箱根伊豆国立公園)、白馬連山高山植物帯(中部山岳国立公園)等について、植生復元、環境等調査、病虫害防除に要する経費を関係県、市町村に対し補助した。
(10) オニヒトデ駆除事業
国立公園、国定公園の海中公園のサンゴ礁景観を保護するため、オニヒトデが異常発生している足摺宇和海国立公園、西表国立公園、奄美群島国定公園等の海中公園地区について、オニヒトデの駆除に要する経費を関係県、市町村に対し補助した。