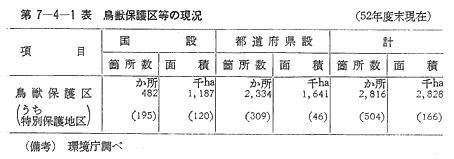
1 鳥獣保護の現況
近年、我が国においても野生鳥獣保護に対する関心が急速に高まってきた。
これは各種の開発によって我々の周辺から鳥や獣が姿を消しつつあることが広く国民の関心の的となってきたことによるものと考えられる。
このような気運は、国際的な潮流となっており、渡り鳥や絶滅のおそれのある動植物を各国が保護していくための各種の国際条約の締結となって現れている。
いうまでもなく、野生鳥獣は、自然環境を構成する重要な要素の一つであり、自然環境をより豊かにする上で欠くことのできないものであると同時に、その減少は人間にとっても生活環境の悪化を示す一つの指標ともなるものであるので、昭和53年度においても以下のとおりその保護施策の強化を図った。
(1) 野生鳥獣保護のための諸措置
第84回国会において、鳥獣保護の充実、狩猟者資質の向上及び秩序ある狩猟の確保を主眼として「鳥獣保護乃狩猟ニ関スル法律」の改正を行った。その主な内容は次のとおりである。
ア 鳥獣保護のより一層の充実を図るため、鳥獣保護区特別保護地区において鳥獣の繁殖に影響を及ぼすおそれのある一定期間及び一定地域における車馬の使用、たき火等の行為を許可の対象とする。
イ 狩猟事故の防止、鳥獣保護と狩猟の調整を図るため、狩猟に関する適性、技能、知識について行う狩猟免許試験に合格した者でなければ狩猟免許を与えないこととするとともに、鳥獣の生息状況等を勘案した狩猟が行われるよう狩猟に関する登録を要することとする。
ウ 集中狩猟による危険を防止するため、銃猟制限区域を設け、承認を受けなければその区域では銃猟ができないこととする。その他、秩序ある銃猟の確保を図るため、国及び地方公共団体以外の者も猟区を設定することができることとする。
改正事項のうち、狩猟免許制度等については、その円滑な実施を期するため、54年4月16日から施行することとされた。
野生鳥獣の保護を図るために、その捕獲を禁止又は制限することによって保護するだけでなく、生活環境を保全し、生息に悪影響を及ぼす行為を規制すること等が必要である。そのため「鳥獣保護乃狩猟ニ関スル法律」により狩猟の規制、鳥獣保護区の設定等を行っているほか、絶滅のおそれのある鳥類については「特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律」により一層厳しい譲渡等の規制を行っている。
また、種の存続が危ぶまれている特定の鳥獣については、人口増殖等の特別保護策を講じる必要があり、このため、特定鳥獣増殖検討会を設置し、トキ、ハハジマメグロ等絶滅のおそれのある鳥獣について、人口増殖に必要な対策の検討等を行った。
(2) 鳥獣保護区の設定
鳥獣保護区は、鳥獣の保護繁殖を図るため、環境庁長官又は都道府県知事が設定するものであって、その区域内では鳥獣の捕獲が禁止されているほか、保護繁殖施設の設置等が行われている。
53年度に設定又は指定された特色のある国設鳥獣保護区又は特別保護地区を幾つか挙げると、次のようになる。まず、特殊鳥類であるタンチョウの繁殖地として北海道釧路湿原に設定されているクッチャロ太鳥獣保護区を5,012haに拡大するとともに、3,833haを特別保護地区に指定した。
また、特殊鳥類であるイヌワシの生息地として岩手県の早池峯山鳥獣保護区並びに山形県の御所山鳥獣保護区及び朝日鳥獣保護区にそれぞれ特別保護地区を指定した。
更にシギチドリ類の渡来地である兵庫県西宮市の干潟に浜甲子園鳥獣保護区30haの設定及び特別保護地区12haの指定をした。
52年度末の鳥獣保護区等の設定状況は、第7-4-1表のとおりである。
(3) 貴重動物の保護
鳥獣保護区等に生息する貴重な動物でその保護を生息環境の保全と一体として行う必要があるものの保護増殖対策を総合的に実施するため、トキ、北限のサル、ライチョウ、カモシカ、ニホンカワウソについて給餌、保護設備の整備等の保護措置を講じた。
(4) 渡り鳥観測網の整備
渡り鳥の生態をは握する上で標識調査は最も効果的であるとされており、我が国においても従来から小規模ながら行われてきたが、日米渡り鳥等保護条約の調印を契機として積極的にその拡充を図っており、渡り鳥の渡来地、越冬地等重要な地点に1級ステーション9か所、その他渡り鳥通過地点に2級ステーション21か所を設けてきたが、53年度においては、更に一層の拡充を図るため新たに10か所の2級ステーションを設け、計40か所において渡り鳥の標識調査及び生態調査を実施した。