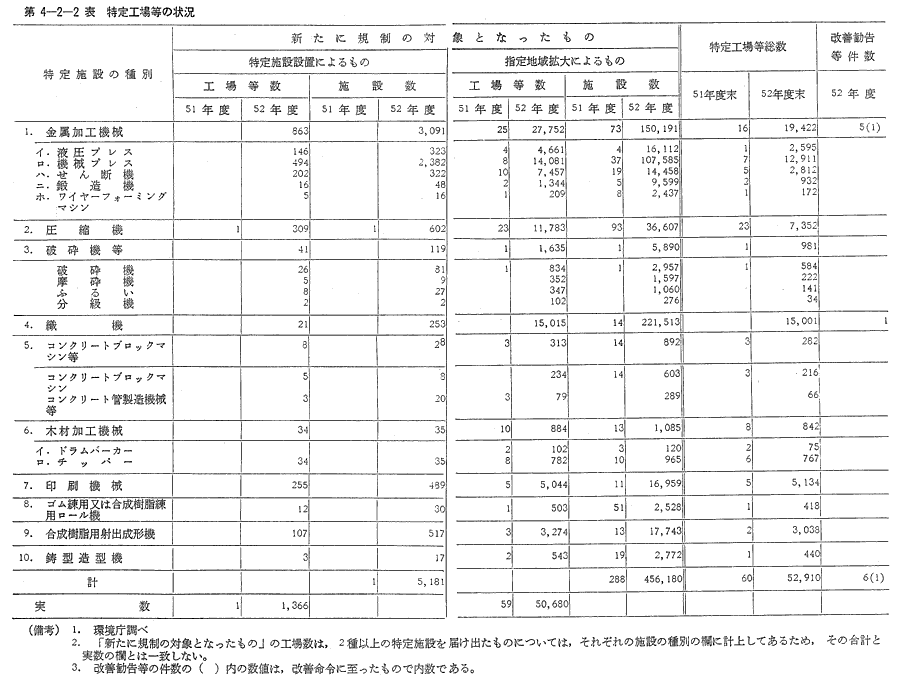
2 振動の対策
(1) 振動規制法
51年12月1日に施行された振動規制法では、都道府県知事が振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を指定し、この地域内において、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる振動について必要な規制を行うとともに、道路交通振動に係る要請の措置を定めることなどにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としている。
都道府県知事による地域指定の実施は、53年3月末現在で、1都2府18県において296市276町29村23特別区に及んでいる。
ア 工場振動
工場、事業場振動についての規制の対象になるのは、指定地域内にあって、政令で定める特定施設を設置している工場及び事業場(特定工場等という。)である。
規制対象となっている特定工場等の数は52年度末現在において、52,910に及んでいる(第4-2-2表)。
特定工場等には、規制基準の遵守義務が課せられており、都道府県知事(政令で市区町村長に委任されている。以下同じ。)は、規制基準に適合しない振動を発生することにより周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、振動の防止の方法等に関し、改善等の勧告及び改善命令を行うことができる。52年度中に実施された改善勧告は6件、そのうち改善命令に至ったものは1件あり、これらの改善勧告等を受けた特定工場等は、機械施設の改善、作業方法・使用方法の改善、配置の変更等を行っている。更に抜本的な対策として、自主的に操業停止や工場の移転をした例もある。
なお、振動規制法の事務を行うために必要な振動レベル計は、法に基づく指定地域を有する市区町村全体で992台(53年7月現在)が整備されている。
イ 建設作業振動
建設作業振動についての規制の対象となるのは、指定地域内において施工される建設作業であって、政令で定める特定建設作業である。
特定建設作業には、届出義務が課せられており、52年度の特定建設作業の届出件数は、10,654件であった(第4-2-3表)。
都道府県知事は、一定の基準に適合しない特定建設作業に伴う振動を発生することにより周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、振動の防止の方法等に関し、改善勧告及び改善命令を行うことができる。
52年度中には、6件の改善勧告が実施され、勧告を受けた施工者においては、機械・施設の改善、作業方法の改善、使用方法の改善、操業時間の変更・短縮等を行っている。
ウ 振動防止対策
工場施設については、低振動機械の採用、吊基礎、直接支持基礎(板ばね、コイルばね等を使用するもの。)、空気ばねなどの防振装置の設置、機械基礎の改善等により、防振対策が行われている。
また、騒音と同じく振動が問題となる工場、事業場の多くは中小規模であり、資金的な面から移転が困難な場合が多いので、公害防止事業団などにおいて、共同利用建物の建設、あるいは、工場団地の造成を行い、中小工場にあっせんしている。
建設作業については、振動を発生する建設機械の改良のみならず、低振動工法の開発が積極的に進められている。
振動防止対策としては、以上のような対策が行われているが、今後は、発生源対策のみならず、振動の伝播減衰特性や家屋防振構造等を勘案して周辺対策を含めた総合的な土地利用計画等を検討する必要がある。
なお、環境庁では、行政担当者等の防振技術の参考に資するため、51年度から振動規制技術マニュアルを作成しており、53年度には、「振動規制技術マニュアル(建設作業振動編)」と取りまとめた。
また、通商産業省では、業種ごとの振動防止対策指導書を毎年作成してきており、53年度には鍛工品製造等について技術指導書をまとめ、当該業種における企業に対する指導の基とした。
(2) 低周波空気振動対策
近年、低周波空気振動による影響がクローズアップされてきている。しかし、低周波空気振動は、その発生源が多種多様(第4-2-4表)であり、その防止対策も十分になされてはいないため、環境庁では51年度において、低周波空気振動発生施設周辺地域での実態調査を実施したのに続き、52年度から低周波空気振動の生理的影響等に関する実験研究に着手している。
低周波空気振動のレベルと、物的・心理的・生理的影響等との相関のは握については、個人差が大きいことなどもあって、基準等の設定に至るまでには相当の年月を要するものと思われるが、現実に苦情・被害が発生していることにかんがみ、早急に防止対策を進めるため、53年度から具体的な対策事例の収集を主体とした調査を行っているところであり、低周波空気振動の防止に資することとしている。