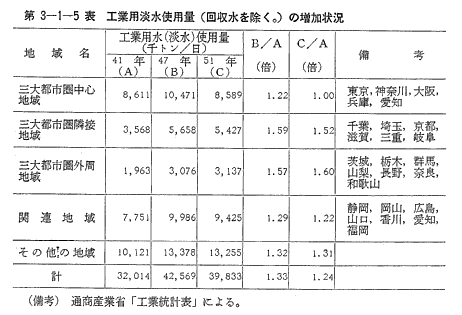
2 水質汚濁の特徴と要因
(1) 水質汚濁の特徴
最近における公共用水域の水質汚濁の特徴を、有害物質による汚濁、有機物による汚濁、その他の諸問題に大きく分類してみると次のとおりである。
ア 有害物質による汚濁
カドミウム等人の健康に有害な物質による水質汚濁は、有害物質による環境汚染の未然防止を図ることの重要性が認識され、排出水の水質規制が整備されたことにより、工場からの排水に起因すると見られるものがほとんどなくなり著しく改善された。
また、休廃止鉱山周辺における水質汚濁についても、その実態のは握に努めているほか、坑廃水の中和処理、鉱さい等の堆積物の河川への流出の防止等の汚濁源対策が講ぜられ、監視体制の整備等が進められているが、引き続き監視体制の整備等を図り、鉱害防止対策を推進することとしている。
イ 有機物による汚濁
有機物による水質汚濁については、次の2点が顕著な特徴として指摘される。
第1は、大都市圏内の河川及び沿岸海域において、改善の傾向にあるもののいまだに水質汚濁が著しいことである。特に、都市内の多くの中小河川の水質汚濁が著しく、悪臭を発する等都市環境を損なっている。また、多摩川、大和川等の水道の水源となっている河川においては、水質がおおむね改善の傾向にあるものの水道の水源として良好な水質といえる程度には至っていない。
第2は、内湾、内海、湖沼等の閉鎖的な水域においては、一部の水域で改善が見られるものの依然として水質汚濁の程度が高いことである。例えば、海域では東京湾、伊勢湾、大阪湾が、湖沼では琵琶湖、霞ヶ浦、諏訪湖等が挙げられる。
これらの水域においては、水の交換が悪いため、家庭排水、工場排水に含まれるリン等の栄養塩類が流入し、蓄積して富栄養化が進行し、植物プランクトン等有機物の増加が見られる。また、閉鎖的な水域においては、水中の汚濁物質が沈降しやすいため、海底や湖底に堆積した汚濁物質が底質を悪化させることに伴って水質も悪化するということが多い。
ウ その他の問題
近年、発電所の建設計画は大規模化するとともに、既存の工業地帯から離れて水質汚濁が著しくない水域に新たに立地する場合が多くなってきたため、発電所から排出される温排水による海洋生物や漁業へ与える影響が懸念されている。
また、合成洗剤中のリン酸塩については、水域の富栄養化を促進する一因と考えられているが、日本工業規格の改正(JIS-K3303)等により配合量の削減が進められている。
(2) 水質汚濁の要因
水質汚濁の基本的な要因は、工場・事業場排水、生活排水等が下水道整備の立ち後れ、し尿浄化槽の維持管理等の問題等により、水域の浄化能力の限界を超えて公共用水域に流入することである。
工業用水(淡水)の1日当たりの使用量を見ると、41年の3,210万トンから51年の3,983万トンへ24%の増加を示しているが、47年に比べ、約6%減少している。これを地域別に見ると、京浜、阪神、中京の三大都市圏では、47年に比べかなり減少し、ほぼ41年の使用量に等しくなっている。
その隣接地域及び外周地域での伸びは、現在は頭打ちの傾向にあるものの、47年までは三大都市圏の伸びよりはるかに高く(第3-1-5表)、これらの地域の工業の伸びが都市部からその周辺部に水質汚濁の広がりをもたらすこととなったと考えられる。
更に、業種別にこれを見ると、用水型工業のうち汚濁負荷量の大きい紙・パルプ及び化学工業については全体に占める割合は低下しているものの51年には48.4%であり、なお高い割合を占めている(第3-1-6表)。
用水型工業の用水の使用量の内訳は、近年、主要な汚濁発生源となる製品処理及び洗浄水の使用量の伸びは頭打ちとなっており、その反面、回収水の使用量の増加が顕著となっている。この傾向は水質汚濁の防止という観点から望ましい方向といえる。
また、最近9か年の人口と上水道の給水量の動向を地域的に見ると、東京・大阪等周辺の新興住宅地域における伸びが著しいことが特徴的である(第3-1-7表)。家庭の生活排水も、ほぼ給水量に比例して増加していると考えられるが、これに対し我が国の下水道普及率(処理人口/総人口)は52年度末で26%にすぎず、欧米諸国の60〜90%と比較していまだ立ち後れているので、下水道整備の促進が図られている。