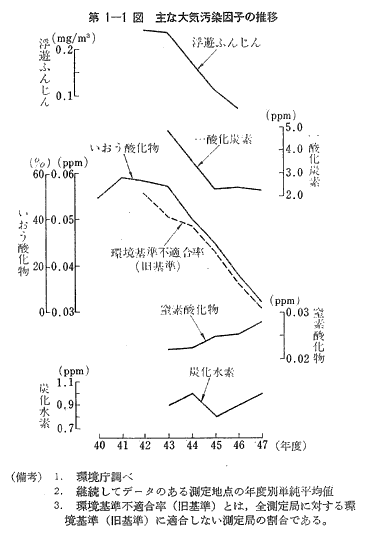
最近、我が国の環境汚染問題は新しい展開をみせている。
各方面の努力により、大気関係ではいおう酸化物、一酸化炭素等一部汚染因子において、水質関係ではかなりの公共用水域の水質において、汚染は改善の傾向にある。しかし、他方において、新しい形態の汚染問題が国民生活を脅かすものとして最近我々の前に大きくクローズアップされてきた。
昨年5月、それまでの各種実態調査や熊本大学水俣病研究班の研究発表を契機として,水銀、PCB等の蓄積性有害物質による公共用水域の底質等の汚染が全国的な問題となった。環境中に蓄積された汚染による影響は、日常摂取する魚介類等の食物の安全性にもかかわるものだけに国民生活に大きな不安を投げかけた。その後、国の総合的な汚染対策が実施され、この事態は一応の落着きをみせたが、こうした蓄積性汚染問題の顕在化は、排出源における汚染の未然防止とともに過去に環境中に放出された有害物質の処理の必要性を我々に痛感させるものであった。
騒音問題について、本年2月、大阪国際空港訴訟事件の第1審判決があり、原告、国とも控訴したため、目下、上級裁判所で争われているが、本件は、輸送機関として内外ともに大きな役割を果たしている航空輸送による公害が問題とされたものであった。
近年、光化学オキシダントによる被害が増加しており、しかも従来の東京、大阪等の大都市圏のみならず、地方都市にまで広がっていく傾向にある。こうした都市型大気汚染の特徴は、発生条件、発生源の構成等が複雑であり、その発生機構の解明に種々の技術的困難性が伴うことであり、最近の汚染問題の解決に科学技術の英知を総結集して進める必要があることを示している。
このような環境汚染問題の新しい展開を背景に、最近の汚染状況がどのように推移してきたかについて、以下、公害の種類別にみることとしよう。
(1) 大気汚染
因子別の汚染状況の推移は第1-1図に示すとおりである。
いおう酸化物による汚染状況は、総体的にみて41年度頃をピークに減少の傾向をたどっており、環境基準の適合状況をみても47年度には旧基準適合率は95%となった。また、いおう酸化物濃度の経年変化を都市計画法上の用途地域別にみると第1-2図のように、42年度当時は住居地域、商業地域に比べて工業地域の汚染が著しかったが、工業地域において近年改善が急速に進み、最近ではこれらの地域間の差が狭まってきている。
こうした改善傾向は、排出規制の強化、重油脱硫、排煙脱硫、低いおう原油の輸入等各種の低いおう化対策の効果によるものとみられるが、昨年5月に改定強化された新環境基準の適合状況については、47年度に測定を行った248都市のうち、新基準に適合しない測定局を有する都市が約7割を占めており、いおう酸化物対策の一層の推進を必要としていることを示している。
浮遊粉じんについては、規制の強化等を反映して改善傾向にあり、一酸化炭素も主たる発生源である自動車排出ガス規制の効果等によって、大都市においては、減少を示す傾向にある。
これに対して、窒素酸化物については、昨年5月に新たに環境基準が認定され、その排出規制も自動車に対しては昨年4月、固定発生源に対しては昨年8月と比較的最近実施されたこともあって、これまでのところ総体的にみて悪化の傾向にある。
炭化水素は、限られた測定局のデータでみるとほぼ横ばいの傾向にある。自動車からの炭化水素の排出規制は従来から逐次強化されているが、その他の有機溶剤等による炭化水素の排出もかなりの比重を占めるものと推定されるで、これら個々の発生源別の対策の方向を早急に明らかにする必要がある。
光化学スモッグの発生状況は、オキシダント注意報発令回数でみると、第1-3図のとおり、悪化の傾向を示している。48年においては従来から発生をみていた東京、大阪等大都市圏においてその発生件数が増加しているばかりでなく、測定網の拡大もあって、岡山、静岡、愛媛等の地方都市にもかなりの規模で発生していることが認められる。これに伴い被害届出人数も増勢を示し、48年(4月〜10月)は45年の1.8倍の約3万2千人となったが重篤被害はほとんどみられなくなった。
(2) 水質汚濁及び土壌汚染
水質汚濁は、全国的にみると、最近の排水規制の強化等を反映して、汚濁の進行は鈍化しかなりの水域では改善のきざしがみえはじめている。全国の主要公共水域95か所における48年までの最近5年間における平均水質の推移をみると、水質が悪化する傾向にあるものが約3割であるのに対し、約7割の水域の水質は改善ないし横ばい状況にある。
しかしながら、第1-4図からもうかがわれるように大都市内及びその近郊河川は、人口や産業の都市集中に対して、下水道の整備や排水処理施設の整備が十分でなかったこと等を反映して、依然として汚濁が著しい状況が続いている。また、内海、内湾及び湖沼等閉鎖的な水域においては、水質汚濁の改善のきざしのまだみられないところが多い。
これら閉鎖性水域では、有機物による汚濁のほかに、窒素、リンの流入による富栄養化の問題が生じている。例えば瀬戸内海では、富栄養化に起因するとみられる赤潮被害が問題となっており、これによる被害発生件数は47年23件、48年18件と減少しているが、赤潮発生件数は増大しており、47年の164件に対して、48年は210件に達している。昨年瀬戸内海の水質保全等を図るために瀬戸内海環境保全臨時措置法が制定され、同海域に流入する産業排水の汚濁量を半減させるための規制等が行われることとなり、同海域の水質改善の効果が期待されることろである。
一方、水質汚濁に係る環境基準の適合状況をみると、健康項目に関しては、国の行った調査対象検体数のうち環境基準を超えるものの割合は45年度1.4%、46年度0.6%、47年度0.3%と年々大幅に減少している。生活基準に係る環境基準の達成状況をみると、環境基準値を超える検体数の全体に占める割合は、47年度において河川23.8%、湖沼45.3%、海域15.8%となっており、この面では下水道の整備を中心に今後一層の汚濁防止努力が要請される。同時に、健康項目に係る有害物質については、過去に排出されたものが公共用水域の底質や農用地の土壌中に依然として蓄積されているとみられる。特に、水銀については水俣湾、徳山湾等で底質汚染が問題となっている。これら低質汚染水域においては、昨年国の定めた水銀に係る暫定底質除去基準等に照らして、所要水域の二次公害防止に配慮した、汚染底質除去工事等を更に推進し、環境の回復を図らねばならない。
カドミウム等による農用地の土壌汚染によっても、公共用水域の底質汚染と同様に、休廃止鉱山や化学工場等の過去の排水等に伴う有害物質が蓄積することにより人の健康を阻害するおそれがある農作物が生産され、また、農作物等の生育が阻害されることがある。これに対処するために、休廃止鉱山の鉱害防止事業及び農用地土壌汚染防止事業を今後一層推進する必要がある。
(3) 騒音、振動等による公害
騒音は各種公害のなかでも日常生活に極めて関係の深い問題であり、その発生源も多種多様である。従来騒音公害は、工場、事業場によるもの及び建設に伴うものが大部分を占めていたが、最近では自動車に加え、航空機、新幹線等輸送機関からの騒音が大きな問題となっている。航空機騒音に係る環境基準は昨年12月に設定され、その基準値は、一定の達成期間において、専ら住居の用に供される地域については、WECPNL(加重等価感覚騒音レベル)70以下、それ以外の地域については、WECPNL75以下とすることとされており、各地域についての基準値の具体的なあてはめは都道府県知事が行うこととされている。
航空機騒音を防止するため、現在、学校、病院等の防音工事の補助、建物等の移転の補償、土地の買取り等の施策が講じられており、新幹線騒音に対しても、線路構造物、軌道、車両の改良等の音源対策が実施されているが、今後、これらの施策を一層拡充させることにより、高速輸送機関による騒音被害を防止していく必要がある。
振動公害の発生源は、主として、工場、建設作業、交通機関等であり、騒音と同様に住民の日常生活に大きな影響を及ぼしている。48年4月1日現在、14都府県において、主として工場、事業場から発生する振動について規制措置が講じられており、これに対処するため、防振ゴム、空気バネ等の防振装置等の開発が急がれている。
これらの騒音や振動は国民の日常生活に最も関連の深いものであるだけに、都道府県の公害苦情受理件数においても騒音、振動に関する苦情の全体に占める割合は、3割を超えており、件数も年々増加し、47年度は約2万8千件に及んでいる。
悪臭公害は、主として工場、事業場からのアンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素等の悪臭物質により発生するものであり、これに対する住民の苦情もかなりの数にのぼっている。このような悪臭を規制するため、悪臭防止法が制定されており、49年2月末現在、30都府県、8指定都市において、規制地域の指定、規制基準の設定等が行われている。
最後に、地盤沈下についてみると、大阪市、尼崎市等のように地下水の採取規制により沈下がほぼ停止した地域もあるが、一方で、首都圏南部地域をはじめ多数の地域において地盤沈下が進行しつつあり、そのうち、一部の地域では建造物、港湾施設、農地等にかなりの被害が発生しており、地盤沈下防止のための規制の強化等対策の拡充が必要となっている。