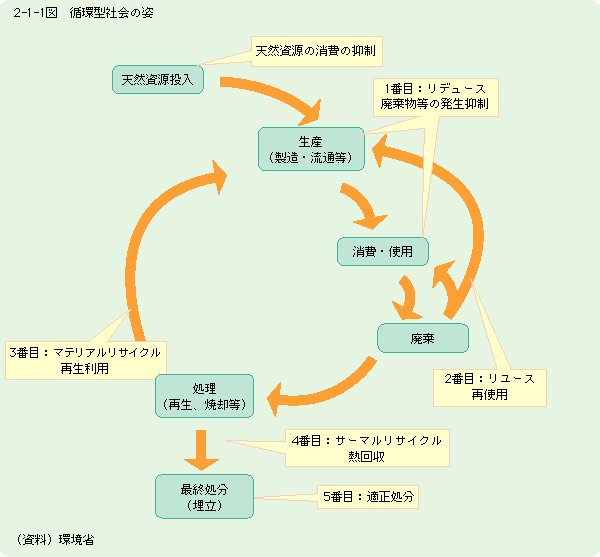
|
第2章
|
循環型社会の形成に向けた国の取組
|
|
第1節 循環型社会の形成に向けた法制度の施行状況
|
|
1. 循環型社会形成推進基本法(循環型社会基本法)
|
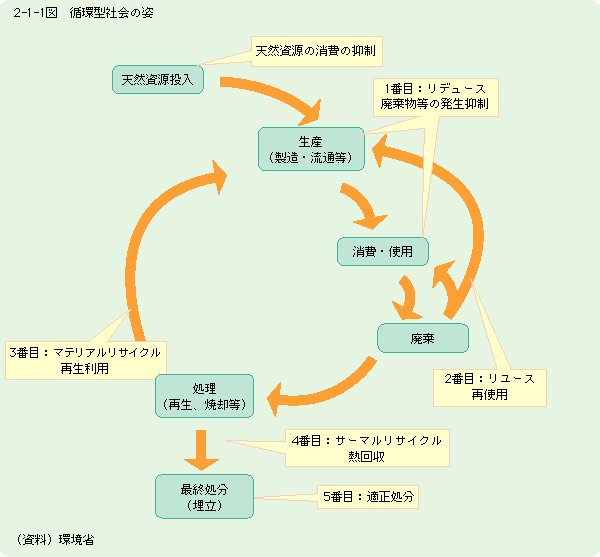
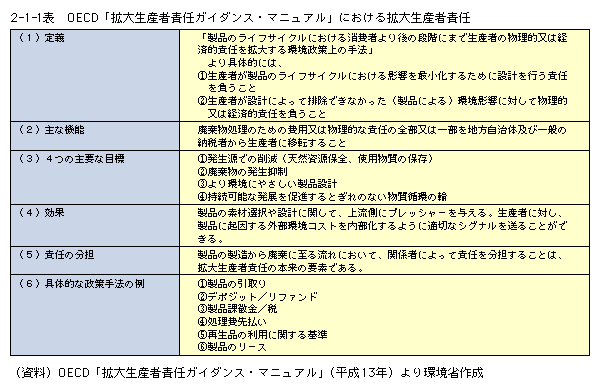
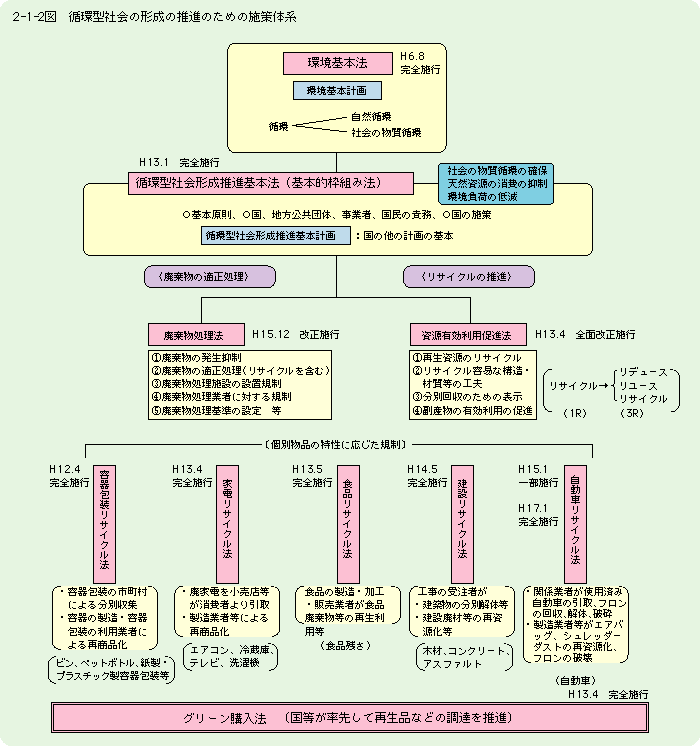
|
2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)
|
|
3. 資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)
|
| コラム 10 | パソコン1台を作るために必要なもの |
情報技術(IT)の進展に伴い、事業所はもちろん家庭でもパソコンの需要は著しく上昇していることから、我が国では資源有効利用促進法により、パソコンの回収・再資源化を製造等事業者に義務付けています。他方、EUは平成15年2月にWEEE(廃電気電子機器)指令を公布し、これに基づいて、加盟国は平成16年8月までに廃電気電子機器(パソコンを含む)の引取り・リサイクルをメーカーに義務付ける制度を策定し、平成17年8月までに引取りを開始することになっています。 国際連合大学のプロジェクトは報告書「コンピューターと環境」の中で、デスクトップパソコン1台を製造するには、240kgの化石燃料(パソコン本体の約10倍の重量)、22kgの化学物質、1,500kgの水など全体で1.8tの原材料・エネルギーが必要という調査結果を示しています。 このような結果を踏まえ、私たちは環境負荷の低い商品を購入したり、できる限り長く使用するように努めなければなりません。パソコンの性能は向上し続けていることから、アップグレード等の機能(サービス)の購入や、使用済パソコンの再販制度の活用などによって、パソコン本体のライフサイクルを延ばすことが求められます。また、メーカー等においては、製品が環境に及ぼす影響についての情報・科学データの開示や、本体の長寿命化のための技術・サービスの開発や普及が望まれます。 なお、我が国の物質フロー会計では、水は総物質投入量には含まれません。また、国内で製品を製造する際に投入された化石燃料や化学物質は総物質投入量に含まれますが、海外から製品として輸入された場合は、製品だけが計上されます。 |
|
|
4. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)
|
| (1)施行状況 ア 分別収集の状況 平成14年度における施行状況をみると、分別収集を実施した市町村数は前年度に比べ、全品目にわたり着実に増加しています。また、分別収集量、再商品化量についても生産量が減少しているガラスびん、スチール缶を除くすべての対象品目において増加しており、制度の浸透、定着が図られています。 ペットボトルについては、分別収集量は前年度比で約1.2倍であり、回収率は45.6%(事業系回収量を含めると53.4%)と年々着実な伸びを見せています。平成11年には収集量に対する再商品化の能力が不足する事態が発生しましたが、現在では再商品化能力は大幅に向上しており、分別収集量の増加にも十分に対応できる状況となっています。 また、ペットボトルをペットボトルの原料に戻す、いわゆる「ボトルtoボトル」の再商品化施設も昨年秋に操業が開始され、リサイクルの一層の進展が期待されます。 平成12年4月から新たに対象品目に追加されたペットボトル以外のプラスチック製容器包装及び紙製容器包装については、制度施行4年目を迎えましたが、分別収集量は順調に伸びており、実施市町村数についてもプラスチック製容器包装の場合、平成15年度では50%を超える見込みです。しかしながら、他の品目と比べるとまだ低く、今後更に分別収集計画の実施市町村数の増加を図ることが課題となっています。 |
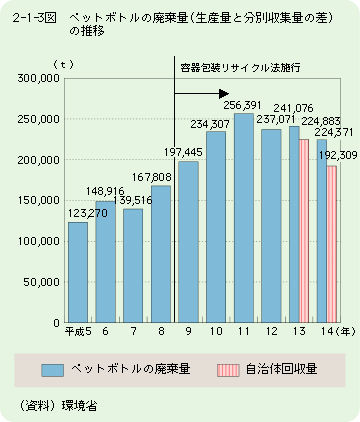 |
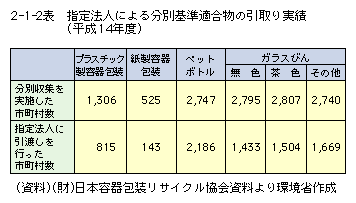 |
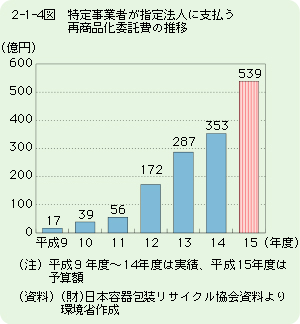 |
|
5. 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)
|
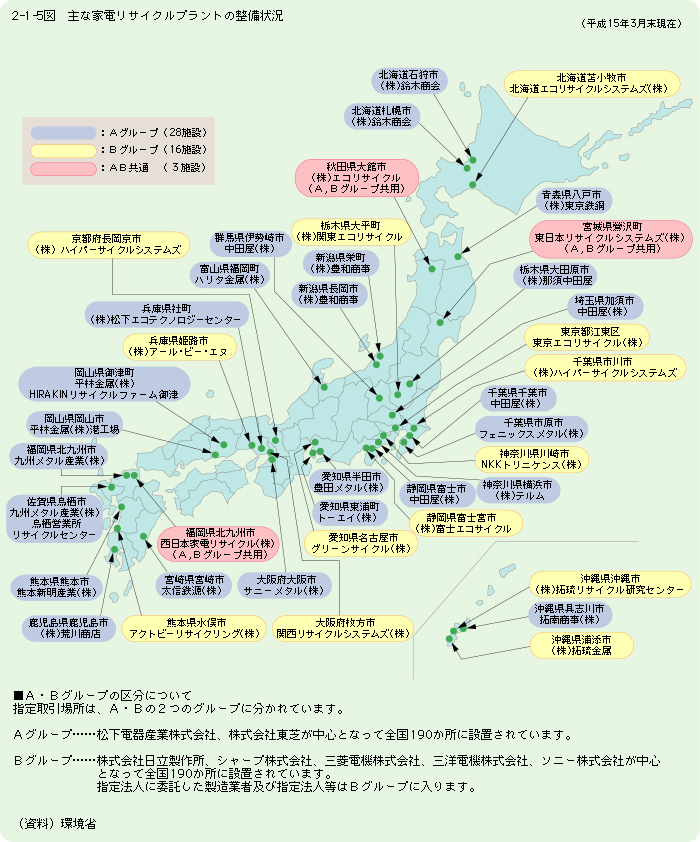
|
6. 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)
|
|
7. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
|
|
8. 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法) |
|
9. 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法) |
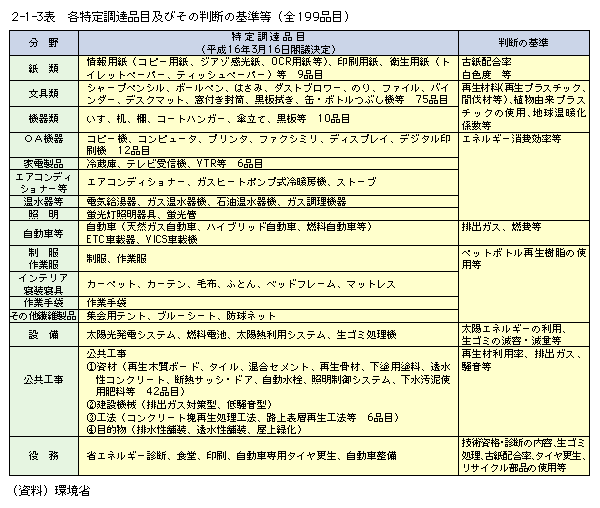
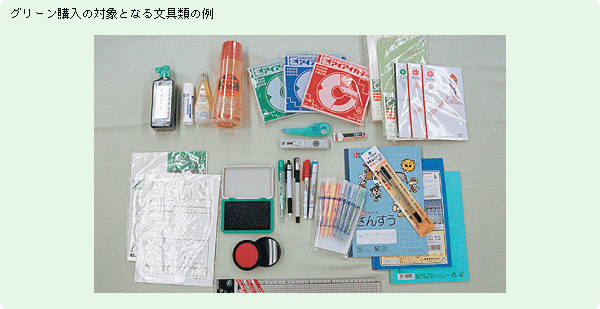
|
10. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法) |
|
11. 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(産廃特措法) |
|
第2節 循環型社会を形成する基盤整備
|
|
1. 財政措置等 |
|
2. 循環型社会ビジネスの振興 |
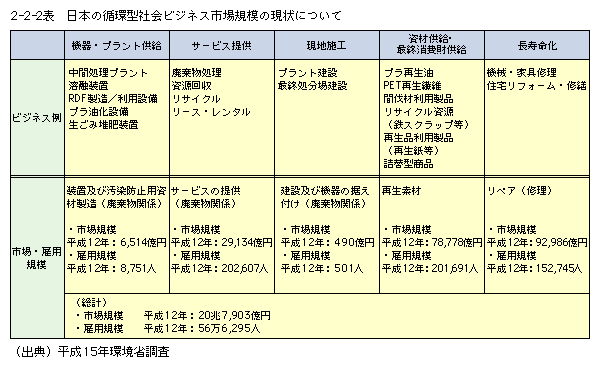
| コラム 11 | 多様化するリサイクル |
リサイクルは、役目を終えたもの(廃棄物等)を、埋立てなどの最終処分をせずに何らかの形で再利用することを言いますが、一口に再利用と言ってもその手法にはいろいろなものがあります。 リサイクルを大きく2つに分類すると、マテリアルリサイクルとサーマルリサイクルとに分けることができます。 マテリアルリサイクルとは、廃棄物等を溶かすなどしてもう一度原材料の形に戻してから再利用するリサイクルのことです。通常は不純物の影響でリサイクルの回数が増えるごとに原材料としての品質が低下していくことが普通でしたが、最近では、ほとんど品質が低下しないリサイクル技術(ケミカルリサイクル)が開発されています。この技術を使った代表的な例として、ペットボトルをペットボトルに再生する技術があげられます。 サーマルリサイクルとは、廃棄物等を燃料として活用し、熱エネルギーを回収するリサイクルのことです。代表的な例として、ごみ発電やRDF、焼却施設周辺における冷暖房等への廃熱利用などがありますが、サーマルリサイクルをすると残るのは焼却灰のみとなってしまうため、その後は路盤材などに活用される一部を除き、これ以上のリサイクルはされずに最終処分場に埋め立てられています。 リサイクルには上記の分類とは違った分類の仕方もあり、ケミカルリサイクルのように品質の低下をほとんど伴わずにまた同じ製品に再生できるものは、一般的には完全リサイクル、クローズドループリサイクル等と呼ばれています。これに対し、品質の低下を伴うリサイクルはカスケードリサイクルとも呼ばれています。 このようにリサイクルにもいろいろな分類の仕方がありますが、一般的には、サーマルリサイクルよりはマテリアルリサイクル、カスケードリサイクルよりはクローズドループリサイクルの方が環境負荷が小さくなります。 |
|
|
3. 経済的手法の活用 |
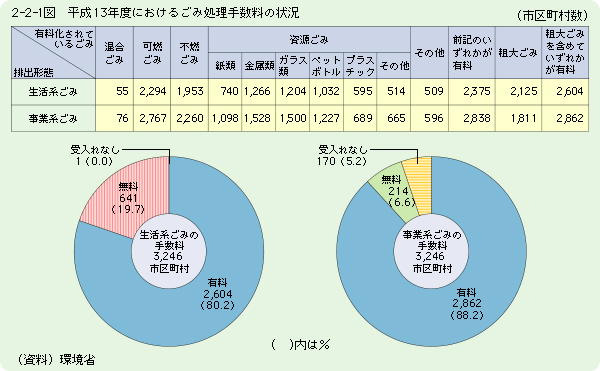
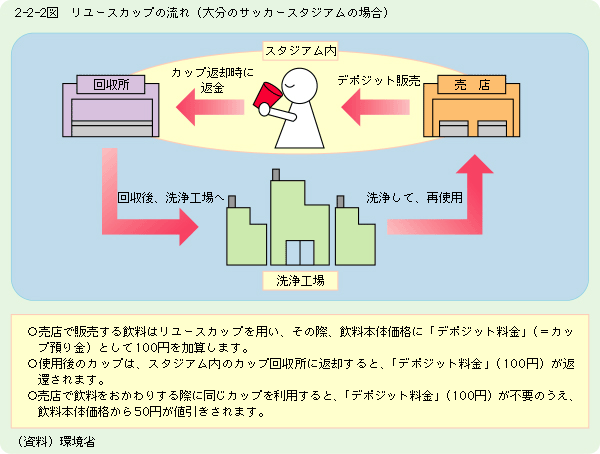
| コラム 12 | ドイツのデポジット制度について |
平成15年10月1日よりドイツで包装廃棄物の発生抑止とリサイクルに関する命令に基づく強制デポジット制度が完全施行されました。 これは、平成3年の全飲料のリターナブル容器の使用率(72%)を基準として、これを下回った場合、さらに12ヶ月間の調査を行い、その結果も72%を下回ったときに、調査結果の公示6か月後に平成3年のリターナブル容器の使用率を下回った飲料に対して強制デポジットを発動するというものです。 ドイツ連邦環境庁の調査では、平成9年、10年の調査で全飲料のリターナブル容器の使用率が72%を下回ったことから、それぞれについて再調査が行われました。再調査の結果も72%を下回っていたため、平成14年7月に調査結果が公示され、平成3年のリターナブル容器の使用率を下回ったビール、ミネラルウォーター、炭酸清涼飲料に対して平成15年1月1日より強制デポジットが発動されました。 こうした政府の動きに対して小売事業者や飲料メーカー等の業界団体が激しく抵抗したため、全国的な容器の回収システムは現在でも実質的に整備されていません。 現在の制度は、ビール、ミネラルウォーター、炭酸入り清涼飲料水の使い捨て飲料容器に対し、1.5L未満の容器には25セント/本、1.5L以上の大型容器には50セント/本のデポジットが課されています。しかし、これだと炭酸を含まないソフトドリンク類、ワインや牛乳などにはデポジットが課されず、飲料間の不公平が生じているため、連邦政府は改正案を議会に提出しています。 また、ドイツのデポジット制度をめぐる国内の混乱は、欧州委員会でも問題になっており、ドイツ国内外の業界団体は欧州司法裁判所への提訴や、同委員会へのロビー活動を行うなど、欧州委員会も巻き込んだ混乱へと発展しています。 一方消費者は、デポジット制度そのものには賛成する人が多いものの、購入店まで容器を返しに行かなくてはならない現在の回収システムには不満を持っている人が多く、大半の使い捨て容器は回収されずに廃棄されているようです。 また、制度の導入以来の半年間でリターナブル容器の使用率が9ポイント向上し、59%になったと連邦環境大臣が述べており、制度の導入よる一定の効果は確認されています。しかし、制度の効果に疑問を投げかける業界団体もあり、今後公表される公式な調査結果が注目されます。 |
|
|
4. 教育及び学習の振興、広報活動の充実、民間活動の支援及び人材の育成 |
| コラム 13 | エコ・コミュニティ事業 | ||||||||
平成15年3月に策定された循環型社会基本計画では、国の取組として、地域におけるNGO・NPOなどの様々な主体による協働の取組で、先駆的な取組について国が支援していくこととされています。 これを受けて環境省では、NGO・NPOや事業者が地方公共団体と連携して行う循環型社会の形成に向けた取組で、他の地域のモデルとなるような事業を公募してエコ・コミュニティ事業として行うことにより、地域からの取組の展開を促すこととしました。 平成15年度は、全国から239件の応募があり、5件を採択しました。採択事業の概要は以下のとおりです。
○PETリサイクルシステム構築による循環型社会形成実証プロジェクト 大手飲料メーカーC社と同社の環境マネジメントを担当する監査法人A社は、実用化段階に入ったペットボトルのボトルtoボトルのリサイクル技術を活用してペットボトルの完全リサイクルシステムを構築することとしています。このため、本事業を活用して九州北部地区において地元の自治体、NGO・NPOと協働してごみとして廃棄されているペットボトルの回収率を向上させる働きかけを住民に対して行い、クローズドループリサイクルの入り口であるペットボトルの回収について、効率的な回収の仕組みづくりのための実証試験を行っています。 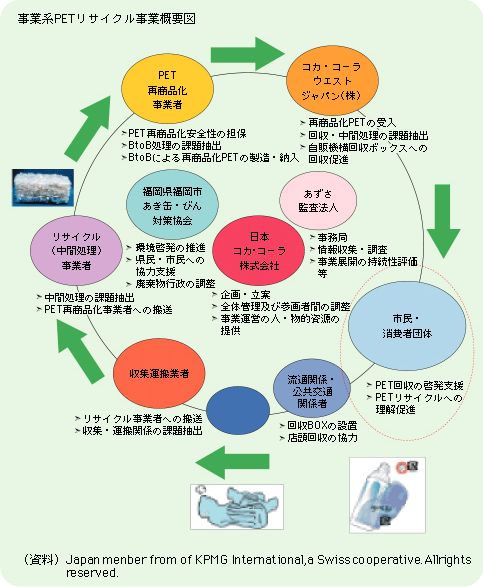
|
|||||||||
| コラム 14 | リ・スタイルで行こう! |
環境省では、平成14年版の循環型社会白書で、ごみを減らす暮らし方である「リ・スタイル」を提唱しました。このリ・スタイルを広く周知するため、Webマガジン「Re-Style」(http://www.re-style.jp)を発行し、著名人へのインタビューやイベント等のレポート、暮らしやビジネス等に関する情報を提供しています。 また、アニメの人気キャラクター「パワーパフガールズ」を使用して、循環型社会の理解のための入門書として活用できる小中学生向けパンフレット「パワーパフガールズと挑戦しよう!ごみゼロ大作戦」を小中学校やこどもエコクラブ、環境省の主催イベント等で配布を行ったほか、実費での頒布(※)も行っています。 さらに、パワーパフガールズには、リ・スタイルを広く知ってもらうためのポスターや宣伝用ポストカード、エコバッグでも活躍してもらっています。 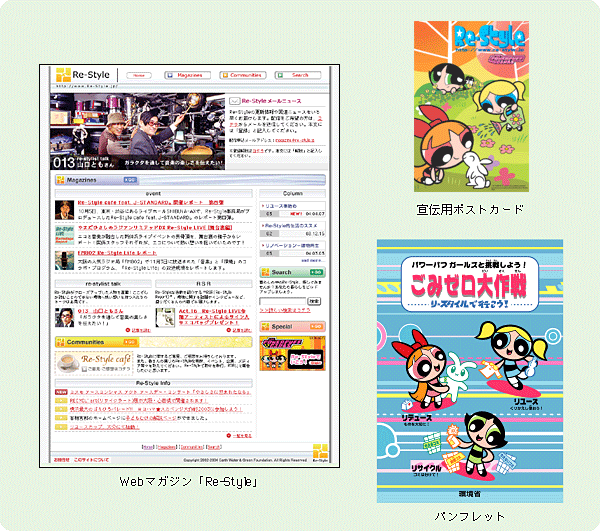 ※問合せ先:(財)日本環境協会出版物担当 TEL:03-5114-1251 FAX:03-5114-1250 E-mail:jea@japan.email.ne.jp |
|
|
5. 調査の実施・科学技術の振興 |
|
6. 施設整備 |
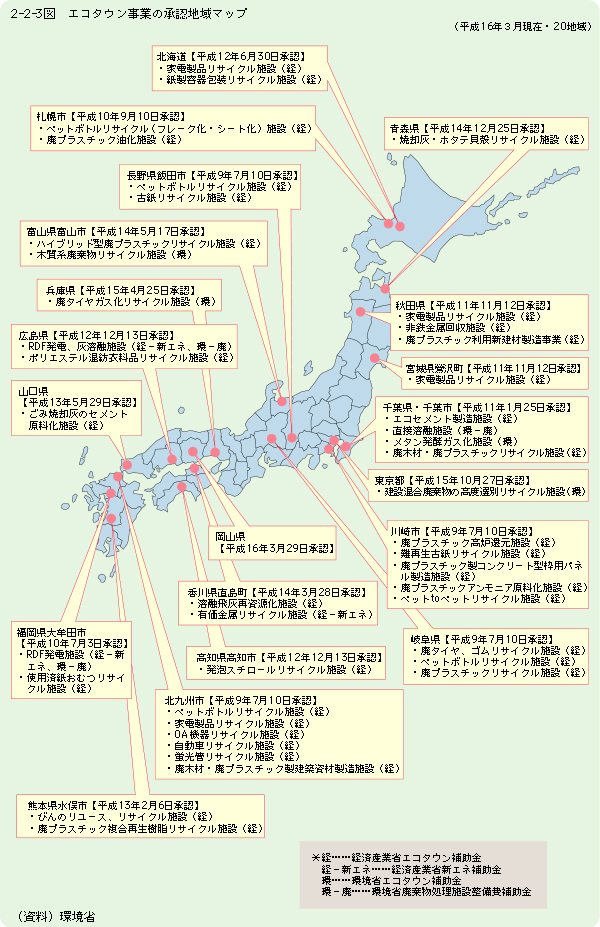
|
7. その他の政府の取組 |
|
第3節 循環型社会の形成と地球環境問題
|
|
1. 廃棄物と温暖化対策 |
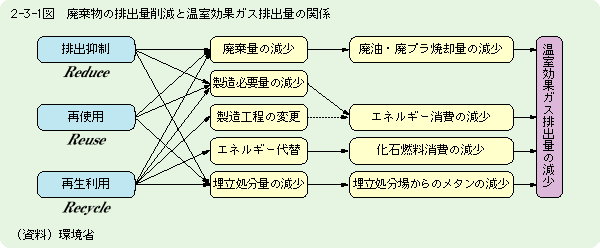
|
2. 国際的な取組 |
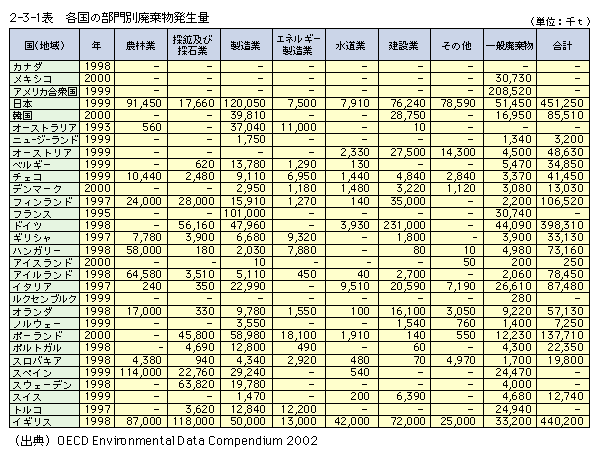
| コラム 15 | スリランカにおける開発調査 |
インドの南に位置する島国、スリランカ民主社会主義共和国の地方都市では、廃棄物に起因する保健衛生面及び環境面での問題が深刻化しています。そこで、我が国は、持続可能な廃棄物管理を行うための地域計画を策定することが重要であるとの認識の下、スリランカ政府の要請を受け、スリランカ国地方都市環境衛生改善計画調査を実施しました。 この調査の目的は、1)7つのモデル市それぞれに廃棄物管理計画を策定するとともに、全国地方市に適用可能なガイドラインを策定すること、2)実効的なパイロット・プロジェクト(試験事業)を実施すること、3)中央政府機関へ提言を行うこと、4)カウンターパート(相手機関の行政官)に技術移転を行うことです。 具体的には、ごみ量、ごみ質、住民意識といった基礎調査や技術移転セミナーの実施、モデル条例の制定などを実施しました。また、パイロット・プロジェクトとして、ベル収集(収集車につけたベルの音楽を合図に住民にごみを持ってきてもらうシステム)による収集改善、学校を集団回収拠点とすることによる分別排出、再資源化といった環境教育の実践、環境教育を推進するための教材の作成や各種プログラムの実施、既存最終処分場の改善や衛生埋立ての実施を行いました。 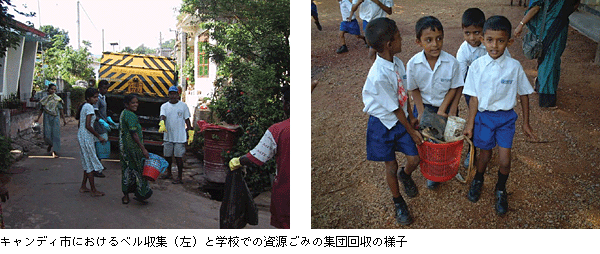 |
|
| コラム 16 | 物質フロー会計及び資源生産性に関する国際専門家会合の開催 |
平成15年4月にパリで開催されたG8環境大臣会合において、我が国は物質フロー会計及び資源生産性に関する共通計測手法の確立を検討するための国際共同研究プロジェクトを開始することを提案しました。これを受けて、環境省は昨年11月に東京で国際専門家会合(東京会合)を開催し、10か国、3国際機関、国内外の研究機関等に加え、地方公共団体や企業からの参加がありました。 我が国より物質フロー会計を政策に適用した循環型社会基本計画を紹介したのを始め、各国・機関における物質フロー会計に関する取組についての報告があり、続いて国際的な重点課題について議論されました。具体的には、物質フロー会計とは何を示すのか、どのような長所・短所があるのかなどについての認識が示されるとともに、国際的な循環や隠れたフローの把握手法といった我が国が抱えている課題も含め、需要(政策利用)及び供給(手法)の両面から意見が出されました。 今後の国際共同研究では、OECDをはじめとする国際機関と連携し、各国における物質フロー会計の取組等に関する調査の実施や、各主体の理解を深めるための冊子及び技術的なガイダンスマニュアルの策定といった成果物の作成を目指すことが提案されました。 なお、OECDにおいて、「物質フロー及び資源生産性に関する理事会勧告」が採択される見込みであり、我が国としては先導的な役割を果たすべく、これらの国際的な取組に積極的に参加していきます。 |
|