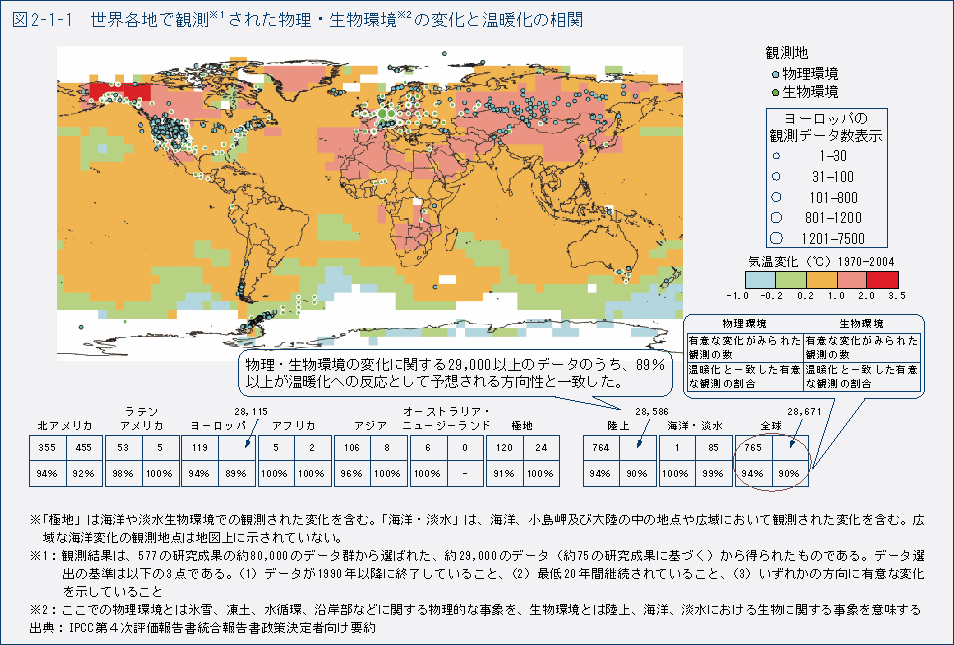
地球温暖化については、人為起源による気候変化、影響、適応及び緩和方策に関し、科学的、技術的、社会経済学的な見地から包括的な評価を行うことを目的として、1988 年(昭和63年)に世界気象機関(WMO)と国連環境計画(UNEP)により設立された「気候変動に関する政府間パネル(IPCC:Intergovernmental Panel on Climate Change)」などを中心に、科学的な知見の集積が進められてきました。最新の報告書であるIPCC第4次評価報告書では、「気候システムの温暖化には疑う余地がない。このことは、大気や海洋の世界平均温度の上昇、雪氷の広範囲にわたる融解、世界平均海面水位の上昇が観測されていることから今や明白である。」とされています(図2-1-1)。
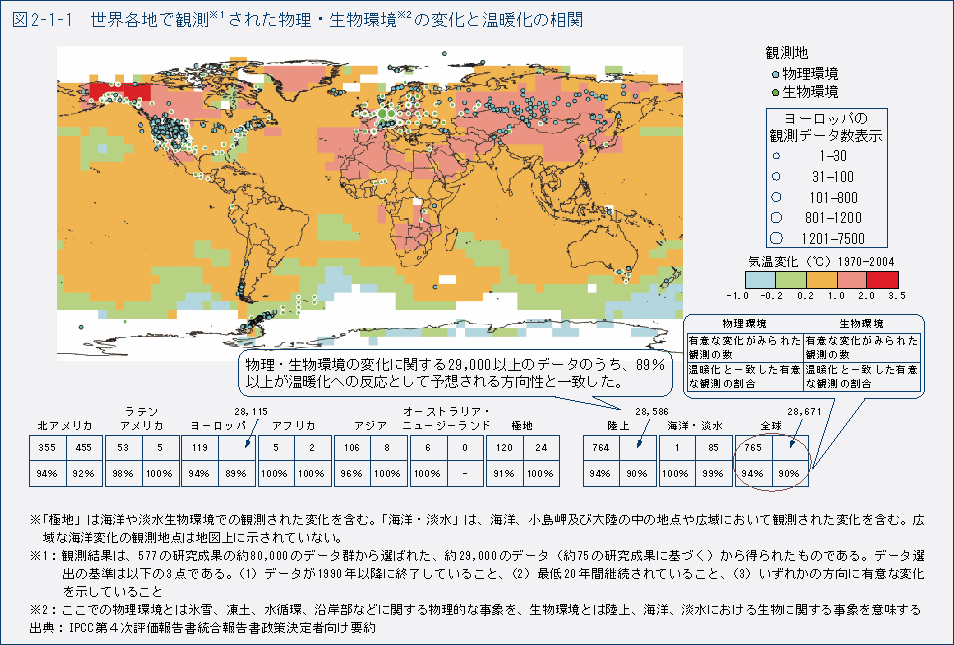
地球温暖化による影響の可能性がある事象として、極地や高地の雪氷の減少、森林火災や干ばつの増加、強い台風の増加などが挙げられます。例えば、北極の年平均海氷面積が10年当たり2.7[2.1~3.3]%縮小し、特に夏季においては10年当たり7.4[5.0~9.8]%と、大きな縮小傾向にあります([ ]の中の数値は最良の評価を挟んだ90%の信頼区間)。
図2-1-2からも海氷の減少傾向が読み取れます。図2-1-4は、衛星観測による昭和54年9月と平成19年9月の海氷の状況を比べたもので、平成19年は、北極の海氷面積が観測史上最小となりました。IPCC第4次評価報告書では、北極の晩夏の海氷は、21世紀後半までにはほぼ完全に消滅するとの予測もあるとされています。アフリカ大陸最高峰のキリマンジャロでは、太陽の日射量の変化、植生変化、人間の干渉など複数の要因も重なって、氷河と積雪面積が後退していることは明らかです(図2-1-3)。
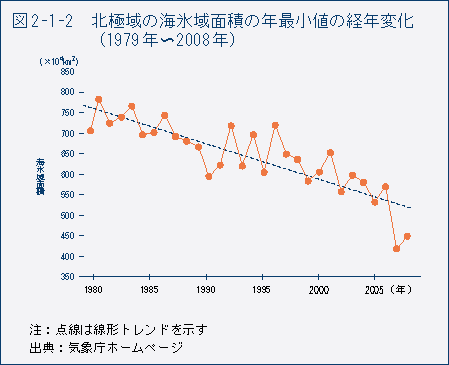
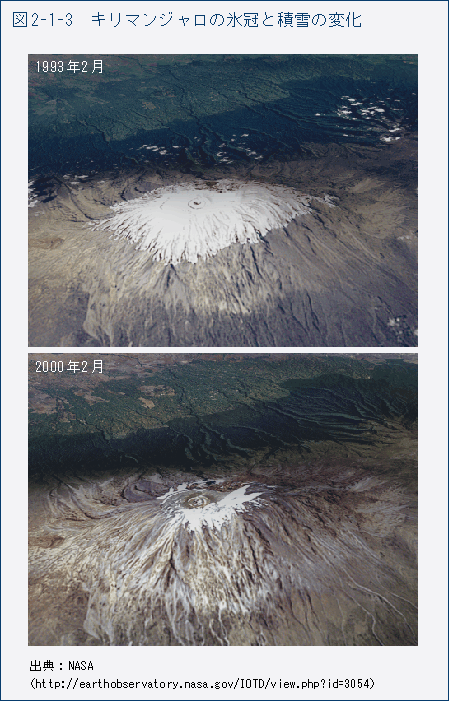
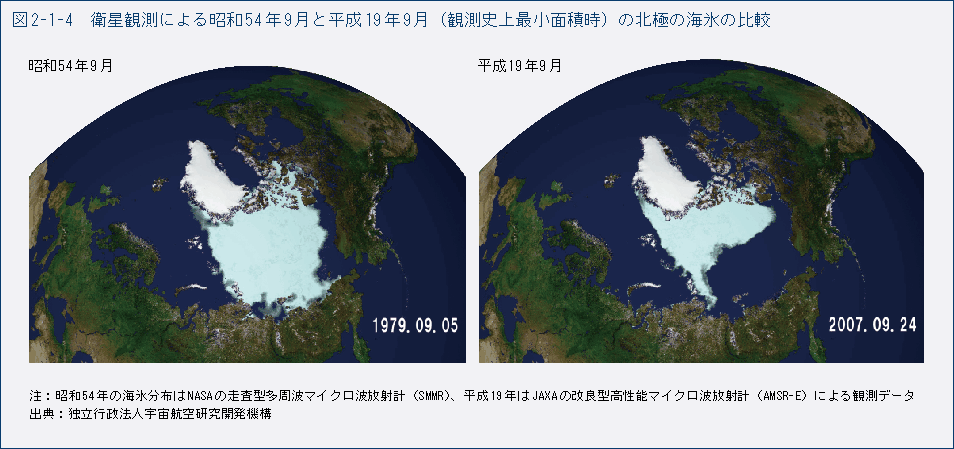
森林火災に関するカリフォルニア大学等の研究では、アメリカ西部において1970年代以降に春から夏にかけての気温が2℃程度高くなる年が増加しているとの結果が示されています。このため、1980年代半ばから森林火災が急増しており、1970~1986年(昭和45~61年)の平均と比べて、火災の頻度が約4倍、焼失面積が6.7倍以上となっていることが分かっています。
森林火災の原因は、地球温暖化を一因とする気温上昇、干ばつや降雨の状況などさまざまですが、アメリカ航空宇宙局(NASA)の統計では、多い年で年間約50万平方キロ(=5,000万ha)の森林が世界で焼失しているとされています(図2-1-5)。これは、植林、植生の修復、森林の自然回復による増加等を差し引いて年間に減少する森林面積約730万haの7倍にも相当します。また、アメリカ国立大気研究センターの研究では、アメリカ本土とアラスカでの森林火災で年間約2.9億トンの二酸化炭素が排出されると推定しています。IPCC第4次評価報告書によると、森林火災による地球全体の年間の二酸化炭素放出量は、62~150億トンと見積もられています。さらに、オーストラリアでは、2000年代に入ってから干ばつが頻繁に起こり、小麦の生産量が大きく変動しています(図2-1-6)。
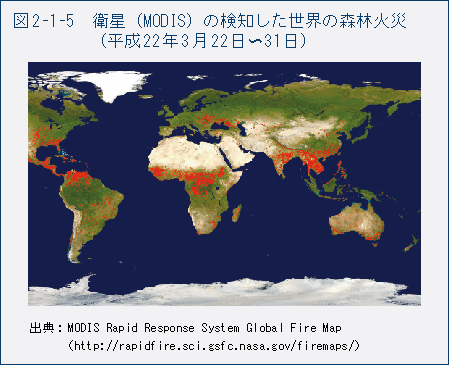
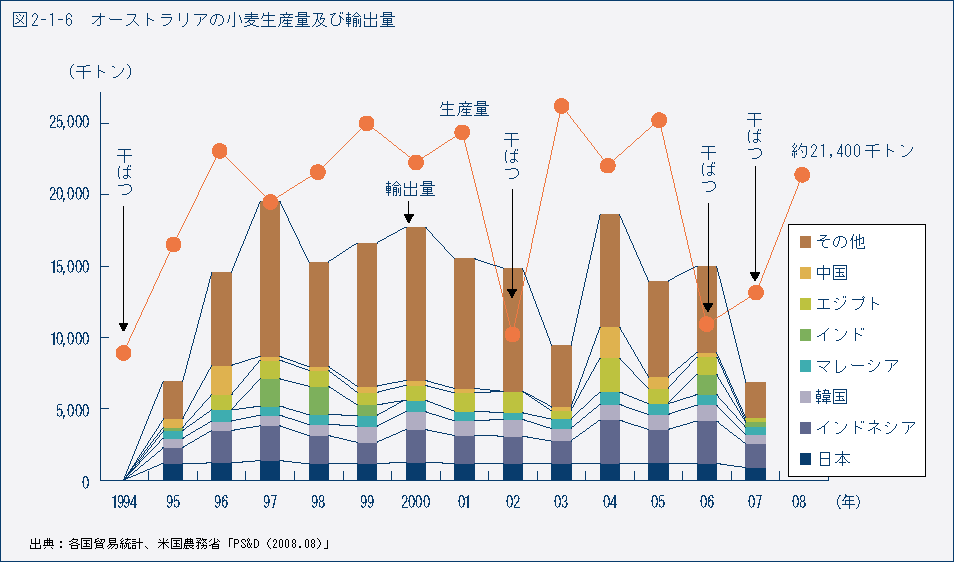
国内において、地球温暖化が寄与していると考えられる事例として、熱中症患者の増加、デング熱等を媒介するヒトスジシマカの分布拡大、生物の分布が北方あるいは高標高に変化する現象、コメや果実の品質低下などがすでに起きています。
熱中症患者の推移をみると、多くの都市で平成19年に過去最大の熱中症患者(救急搬送数)を記録するなど、熱中症患者の増加が報告されています(図2-1-7)。
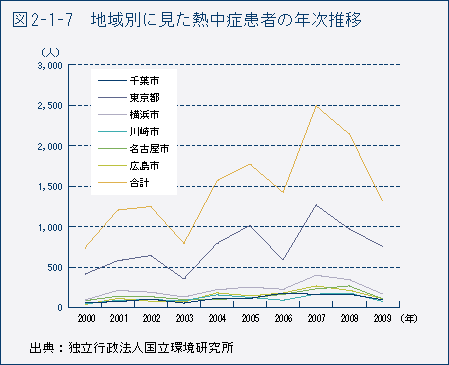
また、健康に影響を与えることとして、感染症を媒介する蚊などの分布拡大も確認されています。ヒトスジシマカが生息する条件として年平均気温がおよそ11℃程度とされており、1950年代には栃木県が分布の北限でしたが、2000年代には東北北部にまで分布拡大が確認さています(図2-1-8)。
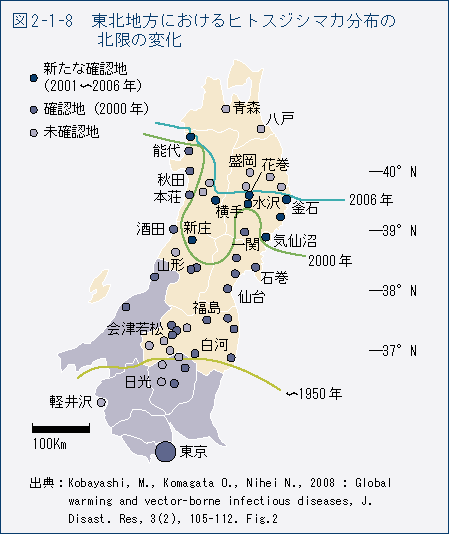
生物への影響としては、生物の分布が北方あるいは高標高に変化する現象が報告さています。例えば、ナガサキアゲハは、分布の北限地の平均気温が15℃程度とされており、1950年代から2000年代にかけて分布の北上が確認されています(図2-1-9)。また、高山植物群落の衰退やサンゴの白化なども確認されています(図2-1-10)。
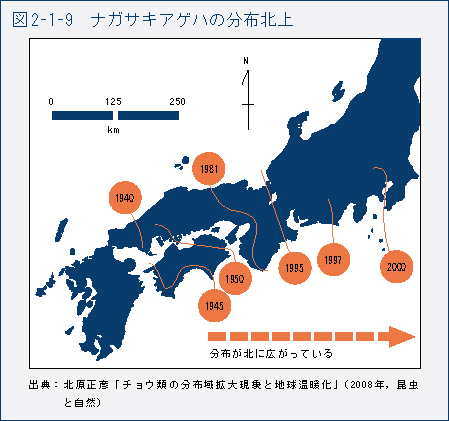
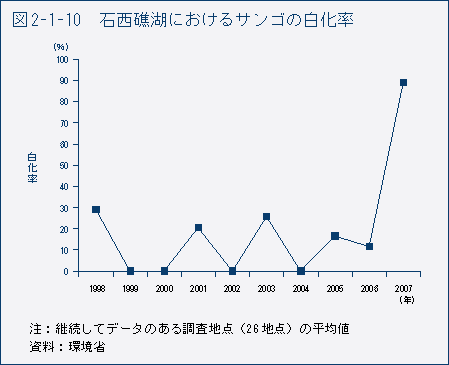
さらに、農作物への影響をみると、高温により、コメでは白未熟粒(白濁した玄米)や胴割れ(玄米に亀裂が生じる)、ミカンでは日焼け果の発生などの影響が生じています(図2-1-11、12)。
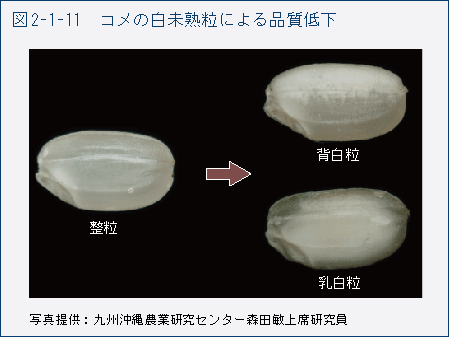
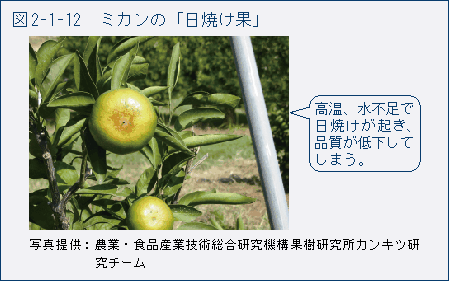
これらの現象が地球温暖化によるものか、短期間の単発的な高温の影響によるものか断定することはむずかしいと言えます。これは、日本全国の平均気温を見ても、長期的には過去100年間で約1.1℃上昇していますが、短期的には平成16年に平年差で+1.00℃を記録することもあり、どちらが原因かを見分けることがむずかしいためです。これらの被害の原因が、直接的には短期的な高温の影響であっても、背景としては、長期的な地球温暖化が影響している可能性が高いと考えられています。
近年、地球温暖化の将来予測に関する研究が進み、一定の不確実性を含みつつも50年、100年後の地球の姿が描かれるようになってきています。ここでは、気候の変化として強い台風の増加、大雨の発生頻度、海面の上昇、熱帯夜や冬日の増減、また、地球温暖化の影響としてブナ林の適域の減少、マツ枯れ危険域の拡大について、まず、わが国に関する将来予測について取り上げます。
台風の将来予測については、高解像度の全球大気気候モデルを用いることで台風の再現性が向上し、地球温暖化に伴う台風の変化予測の信頼性が向上しています。このモデルを用いた結果、地球温暖化に伴って発生する熱帯低気圧の総数は減少するものの、全球的に「非常に強い(最大風速44m/s以上)」熱帯低気圧(台風を含む)の数が増え、これに伴う雨も強くなる傾向が示されました(図2-1-13)。また、高解像度の地域気候モデルによる大雨の頻度の予測として、日降水量が100mm以上に達する大雨の日数は、21世紀末の20年間と20世紀末の20年間を比較して、九州の南部を除き、多くの地域で増加すると予測されています(図2-1-14)。
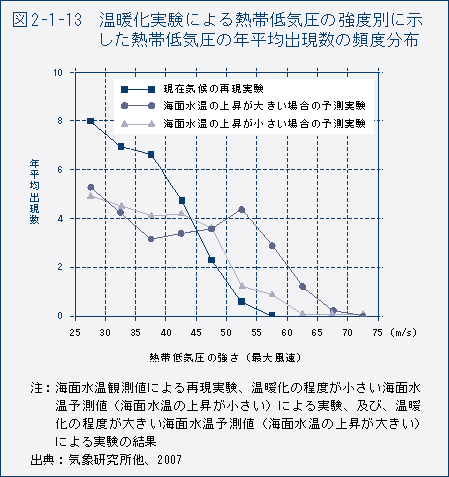
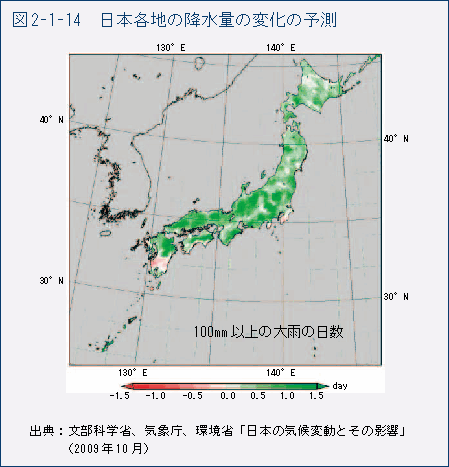
環境省地球環境研究総合推進費による戦略的研究開発プロジェクト「温暖化の危険な水準及び温室効果ガス安定化レベル検討のための温暖化影響の総合的評価に関する研究(以下「温暖化影響総合予測プロジェクト」という。)」によると、地球温暖化に対して何も対策をとらない場合2100年までに世界平均で海面水位が約25cm上昇すると予測されています。また、同シナリオで西日本の高潮浸水面積を予測したところ、21世紀末には年間約200km2増加することが示され、これまで相対的に海岸の防水水準が低かった地域に浸水の危険があると試算されました(図2-1-15)。
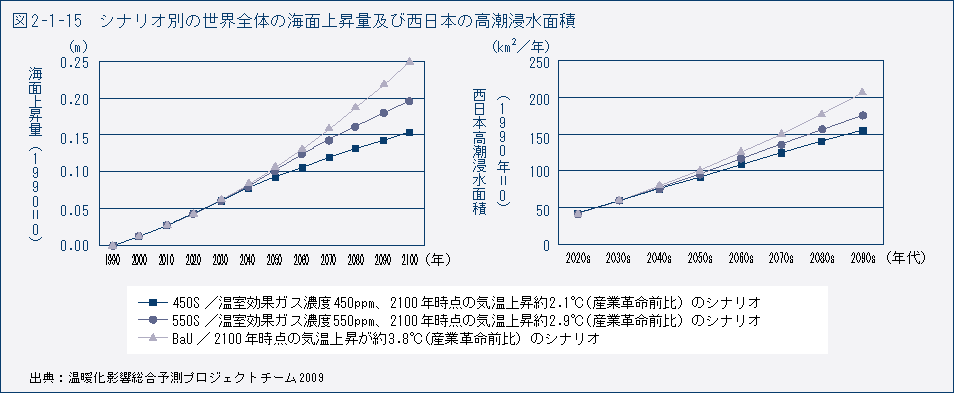
すでに、熱帯夜の増加や冬日の減少は肌で感じるようになってきていますが、文部科学省・気象庁・環境省が2009年10月にまとめた温暖化の観測・予測及び影響評価統合レポート「日本の気候変動とその影響」によると、日本各地の100年後の冬日(日最低気温0℃未満)の日数は、特に、本州の山間部や東北地方、北海道で減少が大きく、熱帯夜(日最低気温25℃以上)の日数は関東地方と近畿以南での増加が大きいと予測されています(図2-1-16)。
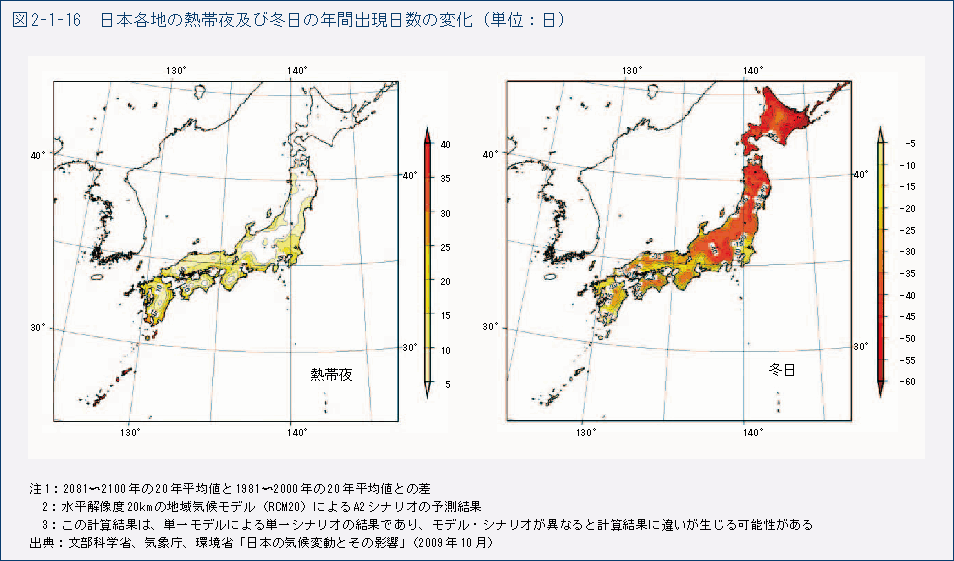
こうした気温の変化は、植生などに大きな影響を及ぼします。温暖化影響総合予測プロジェクトでは、何も対策を行わない場合、21世紀末にはブナ林の分布適域が7割弱減少すると予測されており、また、マツ枯れの危険域についても、20世紀末にはマツ枯れ危険域ではなかったマツ分布地域のうち約5割が新たに危険域となると予測されています(図2-1-17)。
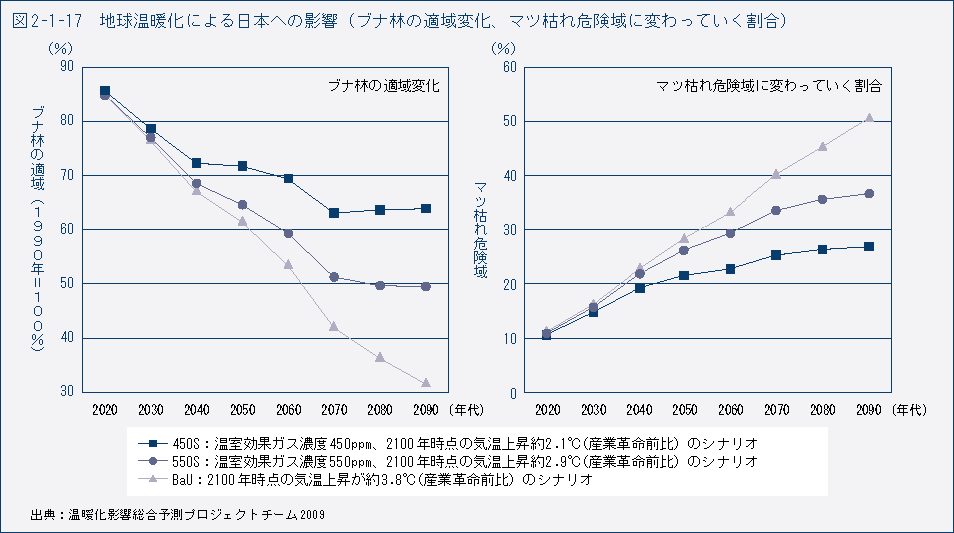
一方、諸外国に関しても、将来の地球温暖化の影響についてさまざまな予測がなされています。地球温暖化の影響には、洪水リスクの増大や水供給量の低下など「水」を介したものが多く、その被害は、地球温暖化が進むにつれて急激に増加するものと考えられます。また、気候変動は、特に開発途上地域において大きな脅威となります。これらの地域はもともと温暖な場合が多く、降雨パターンの大きな変化によって被害を受けやすい状況にあります。また、開発途上国の経済は、気候変動の影響を強く受ける農業に依存している場合が多く、このことも大きなリスク要因となっています。最後に、貧困ゆえに、自力では気候変動への対応策を講じることが困難な場合が多いのです。
以下、表2-1-1に、IPCC第4次評価報告書に示されたアフリカ、アジア、ラテンアメリカ及び小島嶼地域に関して予測されている気候変動の影響事例をまとめました。
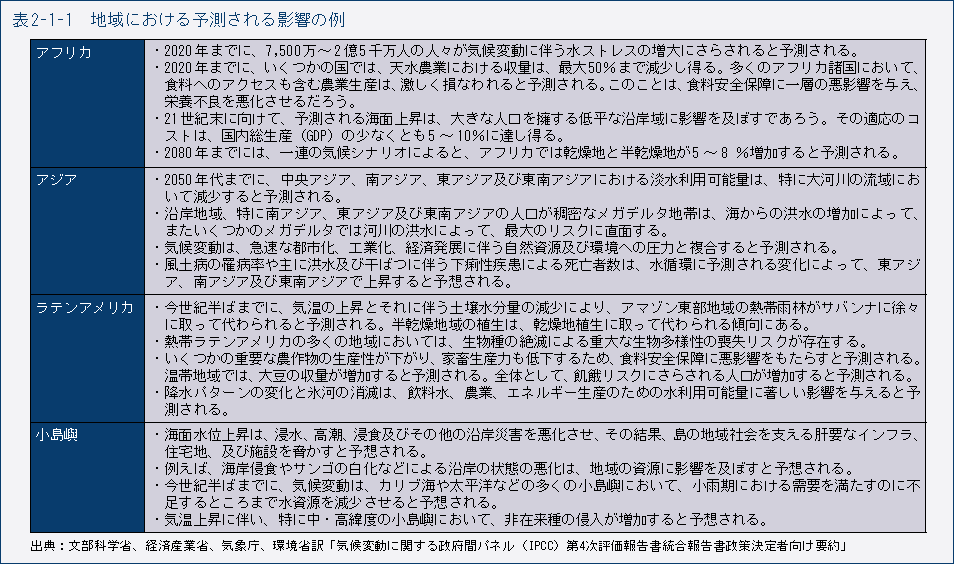
これまでみてきたように、地球温暖化が寄与していると考えられる被害はすでに現実のものとして発生し始めており、適切な適応策(気候の変動やそれに伴う気温・海水面の上昇などに対して自然や人間社会のあり方を調整することで悪影響を軽減するための方策)を講じることが必要になっています。
具体的には、水災害・沿岸分野における高潮被害を防ぐための防波堤や堤防の整備、局地的大雨による洪水被害を軽減するための一時貯水施設の整備、自然生態系分野における地球温暖化によって生息・生育地を失う動植物の避難場所の確保、森林の枯損の早期発見と防除、食料分野における高温耐性のある農作物の開発等が挙げられます。
英国で財務大臣の下で検討を進めた結果を取りまとめた「スターン・レビュー」では、今後、地球温暖化に対して特別に対策をしなかった場合には、気候変動による総被害額は、1人当たりの消費額に置き換えると5~20%の減少に相当するとしています。一方、排出量削減のための対策コストは、わが国の掲げる中期目標で想定される対策強度よりも低い水準である2050年に大気中の温室効果ガスの濃度を500~550ppmでの安定化のために必要な年間の排出削減コストについて、GDPの1%程度ですむと予測しています。
表2-1-2は、国内の地球温暖化影響による被害コストを見積もった環境省による温暖化影響総合予測プロジェクトの研究結果です。緩和策によって世界的に温室効果ガスの排出を削減した場合、影響・被害も相当程度に減少すると見込まれますが、追加的な対策を行わなかった場合(BaU)には、2090年代には毎年、洪水氾濫で8.3兆円、土砂災害で0.94兆円、ブナ林の適域喪失被害コスト2,324億円、砂浜の喪失被害コスト430億円、高潮浸水被害コスト7.4兆円(西日本)、熱ストレス(熱中症)死亡被害コスト1,192億円が最大見込まれることが分かりました。
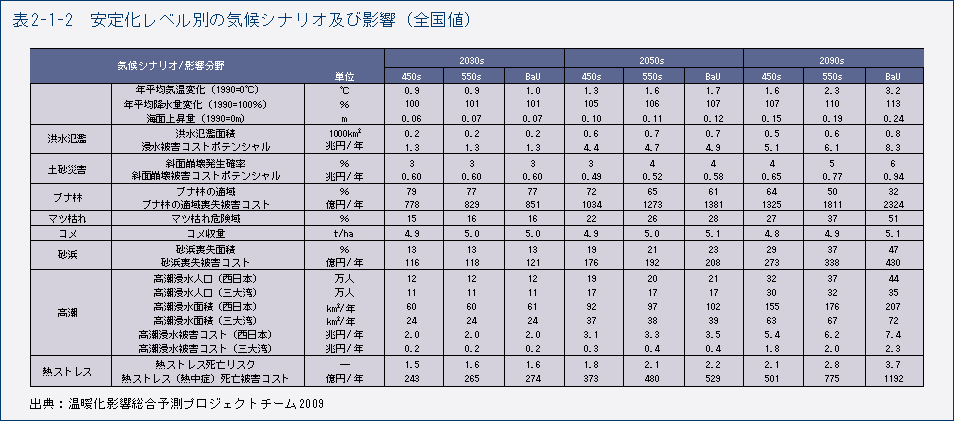
温暖化への疑問にお答えします。
今般、IPCC第4次評価報告書に関して、記載の誤りなど、報告書の信頼性について議論が起きています。
しかし、これらの誤りは約1,000ページに及ぶ報告書の一部におけるものであり、報告書の地球温暖化をめぐる科学的根拠の信頼性は、依然として変わりはないものです。なお、IPCCでは今般の問題を受け、IPCC報告書作成プロセス及び手続の独立したレビューをインター・アカデミー・カウンシル(Inter Academy Council:IAC)に要請しました。IACのレビュー結果は、本年のIPCC総会で議論され、第5次評価報告書(平成25年~26年に公表予定)の作成に反映される予定です。
ここでは、IPCC第4次評価報告書等による科学的知見をもとに、地球温暖化に関する疑問について解説します。
[1] 地球温暖化の主要な原因は、人為起源の温室効果ガスの増加であるという証拠は十分なのか。
世界平均気温を変化させる要因には、温室効果ガスの排出等の人為要因だけではなく、太陽活動、火山噴火によって排出されるエアロゾル等の自然要因も含まれ、これらさまざまな要因が組み合わさって気温の上昇や低下がもたらされます。20世紀中頃には、大気中の温室効果ガス濃度が増加していたにもかかわらず、ほかの要因との相殺で世界平均気温が横ばいとなった時期がありました。IPCC第4次評価報告書では、1906年から2005年の気候のシミュレーションを行った結果、人為的な温室効果ガスの増加を考慮しないと、最近数十年に観測された急激な地球温暖化を再現できないとしており、20世紀半ば以降に観測された世界平均気温の上昇のほとんどは、人為起源の温室効果ガスの観測された増加によってもたらされた可能性が非常に高いとしています。
[2] 温室効果が一番大きいのは水蒸気であり、二酸化炭素が少し増えるくらいでは影響はないのでは。
現在の大気において、水蒸気が最も大きな温室効果を有する(約6割)のは事実ですが、二酸化炭素もその寄与分は約3割と重要な役割を果たしています。大気中の水蒸気の量は、大気と海洋・陸面との間の交換(蒸発・降水)によって決まります。直接的に人間活動の有り様によって、その量が大きく増減することはありません。また、水蒸気は、気温が上昇すると、大気中でその量が増加し、ますます地球温暖化を促進すると考えられていますが、その気温上昇への寄与については、人間活動による二酸化炭素の排出に拠るところが大きいのです。つまり、水蒸気は現状において温室効果を有しており、将来、地球温暖化を増幅させる可能性をもつという点において、確かに注視しなければなりませんが、その増加をもたらさないためには、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出を抑えることが有効です。
[3] 地球温暖化の主な原因は、温室効果ガス濃度の増加ではなく、太陽活動の活発化などにあるのでは。
地球の平均気温を変化させる要因には[1]で示したとおり、温室効果ガス濃度の増加だけでなく、太陽活動の活発化(太陽の放射エネルギーの増加)なども挙げられます。しかし、太陽活動のよい指標である太陽黒点数の最新の観測データを見ると、20世紀半ば以降はほぼ横ばいか減少傾向で、太陽活動が活発化している可能性は小さいと考えられます。また、地球に到達する宇宙線(宇宙空間を漂っている電気を帯びた原子核)は雲を形成するといわれ、太陽活動が活発な時はこの宇宙線が減少し、これに伴い雲量が減って気温が上昇する、との説がありますが、現段階では宇宙線と雲量の相関については明瞭な対応が見られず、物理的な機構も解明されていません。IPCC第4次評価報告書では、このような太陽活動や宇宙線等の自然要因に関する科学的議論も踏まえ評価した上で、20世紀後半の気温上昇の主要因は人為起源の温室効果ガスの増加である可能性が非常に高いと結論づけています。
| 前ページ | 目次 | 次ページ |