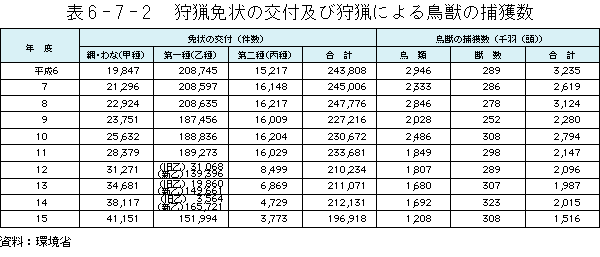
2 野生鳥獣の保護管理
(1)鳥獣保護事業及び鳥獣に関する調査研究等の推進
長期的ビジョンに立った鳥獣の科学的・計画的な保護管理を促し、鳥獣保護行政の全般的ガイドラインとしてより詳細かつ具体的な内容とした鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針(平成15年4月16日〜19年3月31日)に基づき、鳥獣保護区の指定、被害防止のための捕獲及びその体制の整備、違法捕獲の防止等の対策を総合的に推進しました。
また、渡り鳥の生息状況等に関する調査として、「鳥類観測ステーション」における鳥類標識調査、ガンカモ科鳥類の生息調査、シギ・チドリ類の定点調査等を実施しました。
また、野生生物保護についての普及啓発を推進するため、愛鳥週間行事の一環として宮崎県において第59回「全国野鳥保護のつどい」を開催したほか、野生生物保護の実践活動を発表する「全国野生生物保護実績発表大会」等を開催しました。
(2)適正な狩猟と鳥獣管理
狩猟者人口は、昭和45年度の約53万人が平成15年度には約19万人にまで減少しており、しかも高齢化が進んでいるため、被害防止のための捕獲に当たる従事者の確保が困難な地域も見受けられます(表6-7-2)。
適正な管理下での狩猟は、鳥獣を適正な生息数にコントロールする手段として一定の役割を果たすことから、都道府県及び関係狩猟者団体に対し、事故及び違法行為の防止を徹底し、適正な狩猟を推進するための助言を行いました。
(3)鳥獣保護管理制度の見直し
近年、シカやイノシシなどの鳥獣が地域的に増加し、農林業や自然植生に深刻な被害を与えており、他方、これら鳥獣の捕獲の担い手である狩猟者数の減少が進んでいます。
一方、鳥獣の生息環境の悪化により、渡り鳥の飛来数が減少している事例や、地域的に鳥獣の個体数が減少している事例が見られます。
また、国内で違法捕獲された鳥獣(メジロ等)を輸入した鳥獣と偽って飼養している事例などが見られることから、これら鳥獣の適切な管理が必要とされています。
このような状況を踏まえ、平成17年9月、中央環境審議会に対し「鳥獣の保護及び狩猟の適正化につき講ずべき措置について」諮問を行い、検討を重ねた結果、狩猟を活用した鳥獣の保護管理及び鳥獣の保護施策の一層の推進等の方策がとりまとめられ、平成18年2月に環境大臣に対して答申がなされました。
これを受け、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部改正法案を第164回通常国会に提出しました。
(4)農林漁業被害の防止対策
農林業被害の著しい地域において、環境省、農林水産省、林野庁が連携して鳥獣被害対策連絡会議等を引き続き実施しました。また、特定鳥獣保護管理計画等による適切な鳥獣の保護管理を推進するとともに、関東地域におけるカワウの保護管理について、関係機関等と協議会を設置し、広域保護管理指針を策定しました。さらに、適正な技術を有する鳥獣管理の中核的な担い手を育成し、将来にわたる鳥獣管理体制の構築を図るための「野生鳥獣管理技術者育成事業」の実施や、都道府県の特定鳥獣保護管理計画に基づく保護管理実施状況を調査・分析したほか、特定鳥獣保護管理計画の目的推進のため、モニタリング手法等に関する調査を実施しました。
鳥獣を適正に管理し、農林業被害を軽減する農林生態系の管理技術の開発等の試験研究、防護柵等の被害防止施設の設置、効果的な被害防止システムの整備等の対策を推進するとともに、新たに農業被害防止に必要な知識の普及を図り、鳥獣との共生にも配慮した多様な森林の整備等を実施しました。
また、近年、トドによる漁業被害が増大しており、トドの資源に悪影響を及ぼすことなく、被害を防ぐための対策として、被害を受ける定置網の強度強化を促進しました。
(5)鳥獣の生息環境の整備
国指定宮島沼鳥獣保護区の周辺において、渡り鳥の渡来地である湖沼の保全と環境学習などへの活用のための拠点施設の整備を平成18年度までの2か年で実施しています。
渡り鳥の保護対策としては、生息状況調査を実施したほか、出水(いずみ)平野に集中的に飛来するナベヅル、マナヅルについて、その生息環境を改善し、越冬地を分散するために遊休地の確保等の事業を実施しました。また、ツル類について、集中して越冬することで生じる伝染病などの発生による種の絶滅の危惧や農業被害を軽減するために調査を実施し、分散化などについて学識経験者やNPO、地域の関係者等と具体策を検討しました。
(6)高病原性鳥インフルエンザ対策
高病原性鳥インフルエンザと渡り鳥等の野鳥との関係について、渡り鳥を含む野鳥のウイルス保有調査等を実施しました。