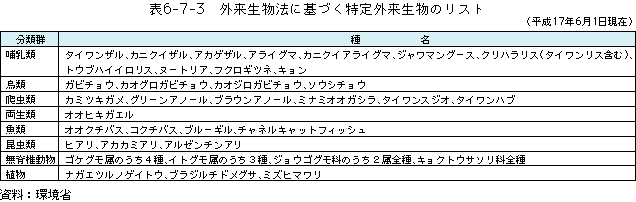
4 外来生物等への対応
(1)外来生物対策
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号。以下「外来生物法」という。)が平成16年6月に公布され、17年6月1日に施行されました。外来生物法は、特定外来生物の輸入、飼養等を規制するとともに、防除を促進することで生態系、人の生命もしくは身体、農林水産業に係る被害を防止することを目的としています。16年10月には、被害の防止に関する基本構想等を盛り込んだ特定外来生物被害防止基本方針が策定されました。これに基づき、37種類の生物が特定外来生物に選定されるなど、具体的な対策を進めています(表6-7-3)。
また、鹿児島県の奄美大島、沖縄やんばる地域において希少動物に影響を及ぼしているマングースの排除のための事業、沖縄県の西表島において生態系に影響を及ぼすおそれのあるオオヒキガエルの監視のための事業を進めました。
河川においては、平成15年6月に、全国の取組事例を「河川における外来種対策の考え方とその事例」として取りまとめ、現地における適正な外来種対策に活用されています。
(2)遺伝子組換え生物対策
遺伝子組換え生物については、生物の多様性に悪影響を及ぼす可能性が懸念されるため、遺伝子組換え生物の輸出入に関する国際的な枠組みを定めたカルタヘナ議定書が平成12年1月に採択され、15年9月に発効しました。この議定書を締結するための国内制度として、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)を15年6月に公布し、16年2月に全面施行しました。17年3月現在、同法に基づき26件の遺伝子組換え生物の環境中での使用について承認が行われています。また、日本版バイオセーフティクリアリングハウス(http://www.bch.biodic.go.jp/)を立ち上げ、法律の枠組みや承認された遺伝子組換え生物に関する情報提供などを行っています。