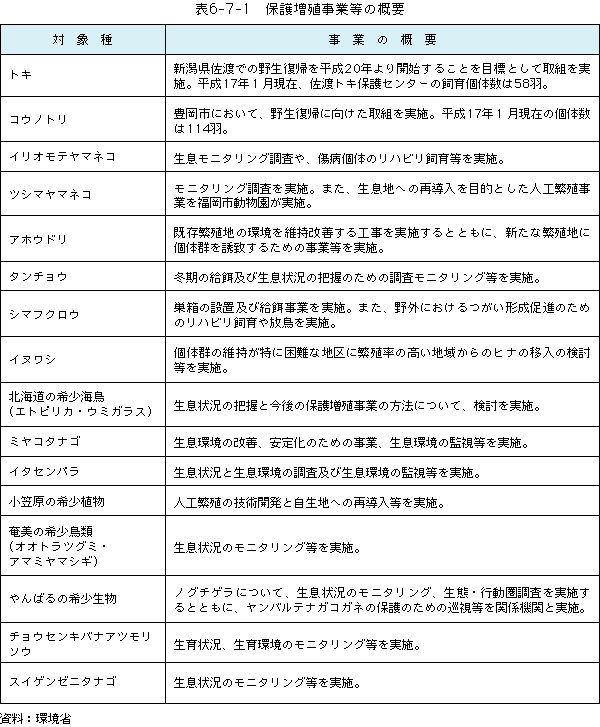
1 絶滅のおそれのある野生動植物の保全
(1)レッドリスト・レッドデータブックの作成
絶滅のおそれのある野生動植物について、各分類群についてそれぞれレッドリストを公表し、これに基づき平成17年1月までに、「爬虫類・両生類」、「植物I(維管束植物)」、「植物II(維管束植物以外)」、「哺乳類」、「鳥類」及び「汽水・淡水魚類」について、改訂版レッドデータブックを公表しました。また、これらのレッドリストを見直すための検討を行っています。
(2)絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に基づく取組
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号。以下「種の保存法」という。)では、日本に生息・生育する絶滅のおそれのある種を国内希少野生動植物種に、また、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(以下「ワシントン条約」という。)及び二国間の渡り鳥等保護条約等に基づき国際的に協力して保存を図るべき絶滅のおそれのある種を国際希少野生動植物種に指定し、個体や器官・加工品の譲渡し等を規制しています。国内希少野生動植物種については、譲渡し等の規制のほか、捕獲の規制や必要に応じ、その生息・生育地を生息地等保護区として指定し、各種の行為を規制しています。また、個体の繁殖の促進や生息・生育環境の整備等を内容とする保護増殖事業計画を策定し、保護増殖のための事業を推進することとしています。
平成16年度末現在、国内希少野生動植物種として、哺乳類4種、鳥類39種、爬虫類1種、両生類1種、汽水・淡水魚類4種、昆虫類5種、植物19種の計73種を指定しており、国際希少野生動植物種として、約650分類群を指定しています。また、8か所の生息地等保護区を指定しており、保護区内の国内希少野生動植物の生息・生育状況調査、巡視等を行いました。
保護増殖事業計画については、ツシマヤマネコ、シマフクロウ等34の計画が策定されています。平成16年度は、ヤンバルクイナ、アマミノクロウサギ、及び小笠原諸島に生育する希少植物など合計13種について、保護増殖事業計画を策定しました。また、絶滅のおそれのある野生動植物の保護増殖事業や調査研究、普及啓発を推進するための拠点となる野生生物保護センターが、16年度末現在8か所に設置されています。主な事業、調査等は表6-7-1のとおりです。
日本でのコウノトリの最後の繁殖地があった豊岡市では,兵庫県と文化庁が中心となり、兵庫県立コウノトリの郷公園で野生復帰に向けた事業を取り組んでいます。コウノトリの郷公園では、平成17年度から試験放鳥を開始する計画で、野生での生活に必要な能力を高めるための飼育個体への馴化訓練、生息地となる周辺環境の整備等について、地域住民等と連携して実施しています。
(3)猛禽類保護への対応
絶滅のおそれがある猛禽類のうち、イヌワシ、クマタカ及びオオタカについて、生息状況のモニタリング、好適な生息環境の創出のための実証モデル調査等を実施しました。また、これまでの調査で得られた知見の取りまとめを行い、全国の推定個体数(イヌワシでは400〜650羽、クマタカでは最低でも1,800羽)や全国分布等を公表しました。
(4)海棲動物の保護と管理
北海道沿岸に回遊又は生息するアザラシ類については、地元関係者等の協力を得つつ、生息状況や漁業被害等について調査を実施しました。
平成15年度に引き続き、沖縄本島周辺海域に生息するジュゴンの全般的な保護方策を検討するため、ジュゴンや海草藻場の分布等を調査しました。また、ジュゴンのレスキュー技術の確立と普及に関する調査を行いました。