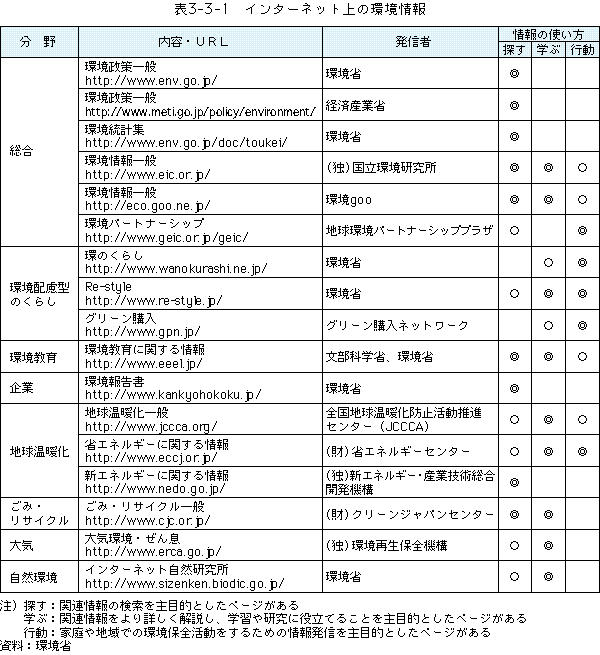
1 基盤としての環境情報
「人づくり」や「しくみづくり」を進めていく上で、その基盤として重要な役割を果たすものに、環境に関するさまざまな情報があります。
(1)環境情報の効果
ア 環境情報を受け取ることによる効果
環境情報には、まず、環境問題に興味・関心を持つきっかけを与え、環境意識を高める効果があります。
「環境の人づくり」では、知識の取得や理解にとどまらず、自ら主体的に行動できる人材を育むことを目標としています。しかし、そのためにはまず環境問題に興味・関心を持ち、環境意識を高めるというステップが必要であり、環境情報はそのきっかけを与えます。
次に、環境情報には、環境保全行動を促進する効果があります。
例えば、グリーン購入をしようとするとき、エコマークなどの環境ラベルが製品に付いていれば、環境負荷の少ない製品を選ぶことができます。また、グリーン購入を行う際には、環境負荷の削減に努める事業者から優先して購入するという考え方もあります。事業者が出している環境報告書を読むことによって、どの事業者が環境に配慮しているのかを知ることができ、その事業者の商品を購入することができます。
また、環境情報は、人と人とをつなぐことによって環境保全行動を促進することができます。例えば、市民団体の活動などの環境情報を受け取り、その活動に参加することによって、一人では行うことのできなかった環境保全活動を行うことができます。
イ 環境情報を発信することによる効果
環境情報を発信すること自体が、自らの環境保全行動を促進します。
例えば、事業者が排出している化学物質の量や廃棄物の量、温室効果ガスの量などを環境情報として発信するためには、自らの事業に伴う環境負荷の現状を把握しなければならず、また削減の方針を明確にし、実施している取組について整理する必要があります。それにより、効果的な環境管理を行うことができます。
また、環境情報を公表することで、他社と比較して自社の環境保全活動を評価することも可能となり、環境負荷をさらに削減しようという動機付けになります。こうした企業の自発的な情報発信は、環境負荷の削減につながるだけでなく、企業の社会的な信頼性を高めることにもつながります。
ウ 双方向で環境情報をやり取りすることによる効果
双方向で環境情報をやり取りすることにより、相互の理解が深まり、より良い改善案が生まれることで、一方向で情報を受発信する以上の環境保全効果をもたらすことができます。
例えば、環境報告書は一方向の情報発信であることが多く、読者のニーズを知ることが困難ですが、ある企業では、環境報告書を題材に一般市民と対話する場を設けています。こうした直接対話は、参加者の意見を企業の取組の参考にし翌年の環境報告書に反映させることができると同時に、企業に対する理解を深めることにもつながっています。
(2)発信されている主な環境情報
政府や企業、市民団体などの各主体が、白書やパンフレット、インターネットなどを通じてさまざまな環境情報を発信しています。公的機関等が発信している環境情報のうち、インターネット上の環境情報を分野ごとにまとめたものが、表3-3-1です。
(3)環境情報に望まれること
環境情報の効果を最大限に発揮するため、情報の発信者は次の点に注意して環境情報の発信を行う必要があります。
ア 環境情報の内容
環境保全行動を促進するためには、一人ひとりの日常生活と環境保全とのつながりを身近な視点から伝えることや、環境の現状だけでなく、具体的な対策の始め方を発信していくことが重要です。
また、環境情報を受け取った人がその情報を用いて製品や活動等を評価できるよう比較しやすい内容にする、発信者側へフィードバックができるよう問い合わせの窓口を設けるといった工夫が望まれます。
さらに、一方的に都合の良い情報だけを発信するのではなく、ネガティブ情報(企業であれば事故や環境汚染物質の排出量など)も開示することによって、情報の信頼性を高めることも重要です。
イ 環境情報の発信の方法
目的に応じてさまざまな媒体を使い分けることが必要です。環境意識を高めるきっかけとしては、目に触れる機会の多いマスメディアやフリーペーパーなどの媒体があります。深く調べたり学んだりする場合は、情報量が多くアクセスしやすいインターネットがあり、企業の環境報告書なども、ほとんどがインターネット上で公開されています。
また、図や写真などを用いて分かりやすく説明すること、受信者を惹きつけるような魅力的な方法で情報発信をすることなども求められます。
なお、情報の受信者の側にも、多様な観点からの環境情報を受け取ることや、受け取った環境情報に基づき自ら主体的に考えることなどが求められているといえるでしょう。