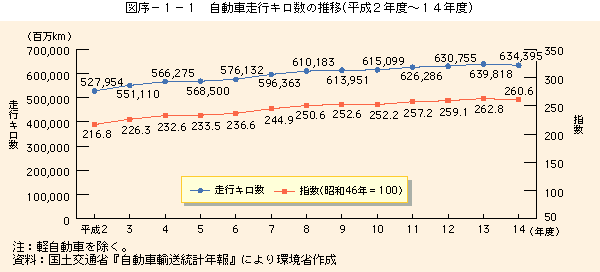
|
序章
|
環境革命の時代へ |
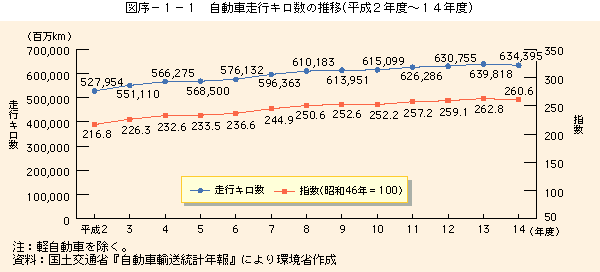
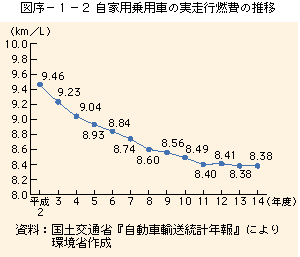
|
 |
| 自動車走行距離の増加と実走行燃費の悪化により、燃料の燃焼に伴うエネルギー消費量が増加しています。輸送機関別のエネルギー消費量の推移をみると、自家用乗用車のエネルギー消費が大きな割合を占めるとともに(平成12年度において全体の43.2%)、消費量が著しく伸びています(図序-1-4)。エネルギー消費は、燃料の燃焼による二酸化炭素や大気汚染物質の排出という環境負荷を生じさせています。
家電製品についても、さまざまな製品の普及率が増加しています。29インチ型以上のカラーテレビの普及率は、平成4年3月時の30.5%から平成15年3月時の53.1%へと増加しました。また、パソコンの普及率は同期間に12.2%から63.3%へ、温水洗浄便座の普及率は同期間に14.2%から51.7%へと、急速に増加しました(図序-1-5)。 |
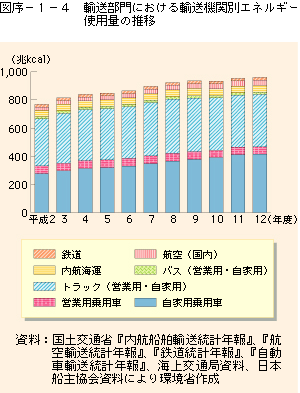 |
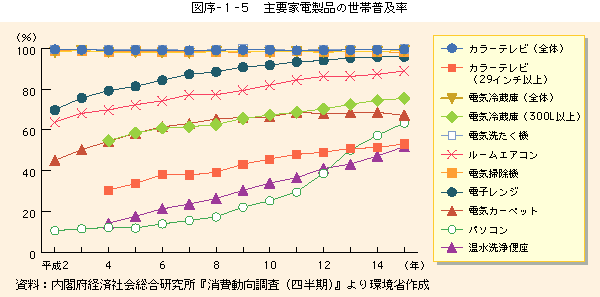
| 家電製品の普及率の増加は、世帯数の増加と相まって、家庭からのエネルギー消費量の増加をもたらしています。家庭の需要電力量は、平成2年度の1,410.8億kWhから平成13年度の1,930.7億kWhへと大幅に増加しました(図序-1-6)。家庭からのエネルギー消費は、発電時の化石燃料の燃焼により二酸化炭素を排出させています。 日本の2002年度(平成14年度)の二酸化炭素排出量は12億4,800万トン、1人当たり排出量は9.79トン/人で、1990年度(平成2年度)と比べ、排出量で11.2%、1人当たり排出量で7.8%増加しました。 部門別にみると、産業部門からの排出量は468百万トンと最大です。一方、1990年度比でみると、産業部門が横ばいからやや減少傾向にあるのに対し、運輸部門、家庭部門、業務その他部門(卸小売、事務所・ビル等)からの排出量が大きく増加しました(図序-1-7)。個々の機器の効率向上の一方で、エネルギー需要は年々増加しています(輸送部門における輸送機関別エネルギ-使用量の推移、用途別世帯あたり二酸化炭素排出量)。 |
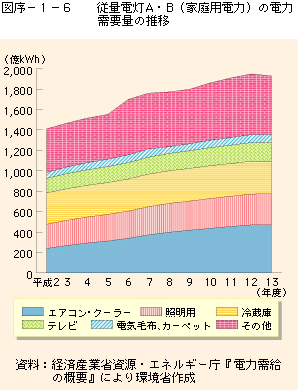 |
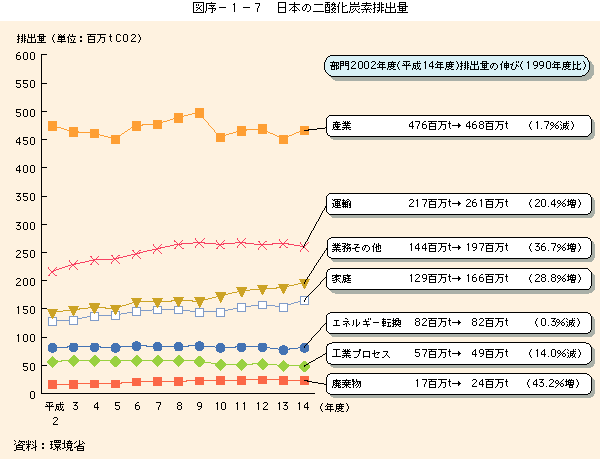
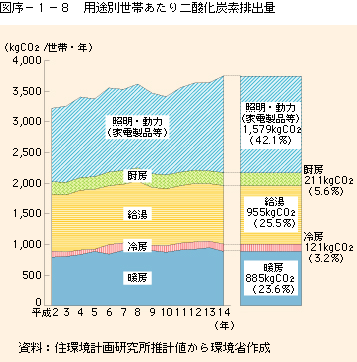 |
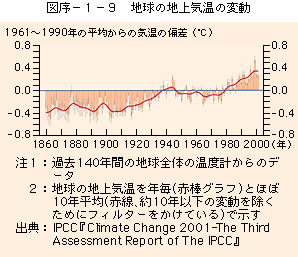 |
| くらしから、多くのごみが排出されています。平成13年度のごみの総排出量は5,210万トン、国民1人当たりで1日に約1.1kgでした。このうち、生活系ごみが約67%、事業系ごみが約33%で、生活系ごみのうち、容器包装が容積比の約61%、湿重量比の約24%を占めています(図序-1-10)。 近年、プラスチック製容器の生産量が増えました(図序-1-11)。プラスチック製容器は、軽くて持ち運びやすい、強くて丈夫、加工しやすいなどの特長があります。その一方で、プラスチック製容器は容積比でみると生活系ごみの約4割を占めており、便利な生活をもたらすプラスチック製容器が廃棄された場合には、廃棄物として環境へ負荷を与えることとなります。 |
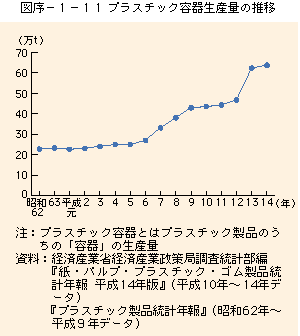 |
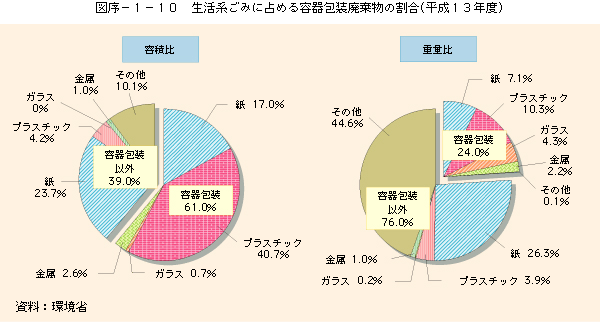
|
コラム
|
産業廃棄物の不法投棄 |
産業廃棄物の不法投棄については、ここ数年、毎年約900~1,000件程度の新たな事例が判明しています。 平成9年に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)が改正され、事業者等の拠出による産業廃棄物適正処理推進センター基金が作られましたが、平成9年の廃棄物処理法改正の施行前からの不法投棄も残っています。このため、これらの不法投棄について都道府県等が自ら支障の除去等の事業を行う場合の必要な経費の国庫補助等を定めた「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法」(平成15年法律第98号)が施行されました。この法律に基づき、香川県の豊島や青森・岩手の県境で以前行われた不法投棄について、除去を行うことになりました。 (※不法投棄の詳細については、平成16年版循環型社会白書の序章参照。) 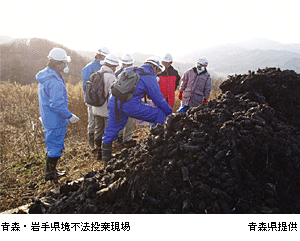 |
|
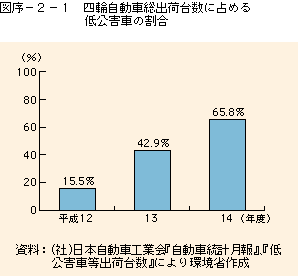 |
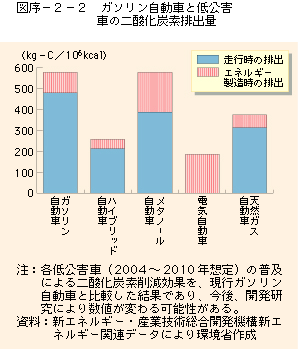 |
|
コラム
|
自動車の環境ラベル |
| 4つ星マークのステッカーが付いた車は、自動車排出ガスがNOx、PM等の有害物質の排出を平成17年基準値より75%以上低減した自動車(3つ星マークは、同基準より50%以上低減した自動車)であるとして、低排出ガス車認定制度に基づき認定を受けた車であることを示すものです(図序-2-3)。 また、新たに自動車の燃費性能を公表・表示する制度(自動車燃費性能表示制度)が平成16年1月から始まりました。燃費性能の表示として「燃費基準達成車」、「燃費基準+5%達成車」は、それぞれ図序-2-4のステッカーを貼り付けることとしています。 自動車を選ぶ際に、環境ラベル(ステッカー)を参考にして、低排出ガスで低燃費の車を選ぶことが、環境負荷の削減に役立ちます。  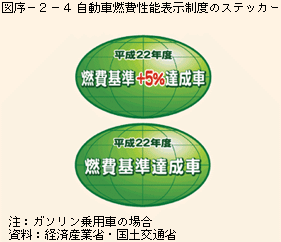 |
|
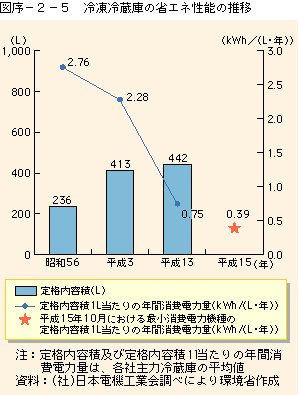 |
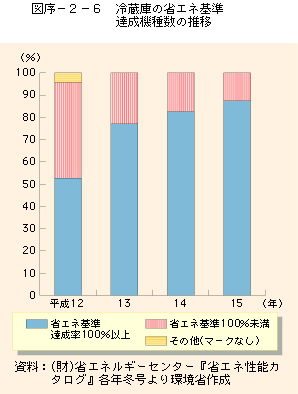 |
|
コラム
|
省エネルギーラベリング制度 |
| 省エネルギーラベリング制度は、現在、電気冷蔵庫、電気冷凍庫のほか、エアコン、蛍光灯器具、テレビ、ストーブ、ガス調理機器、ガス温水機器、石油温水機器、電気便座の10品目が対象になっています。省エネ性能の優れた製品(省エネ基準達成率100%以上の製品)は、緑色のマークを表示することができます(図序-2-7)。 ラベルは、カタログや製品本体などに表示されています。 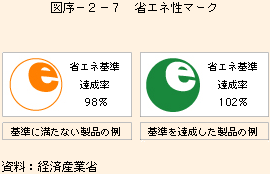 |
|
|
コラム
|
買い物には袋を持って |
| 福井県武生市が設置した知的障害者通所授産施設「ひまわり作業所」では、ペットボトルの再生布を用いた買い物袋を縫製しています。環境を考えてビニール袋に代えて使う買い物袋は、地域によりマイバッグ、エコバッグ等と呼ばれます。武生市は、市を挙げて環境保全に取り組んでおり、このような袋を持って買い物に行くことを勧めています。 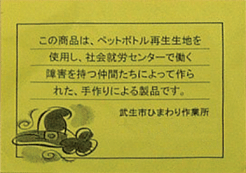  |
|
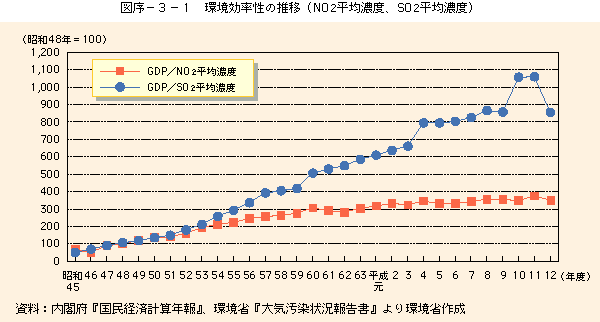
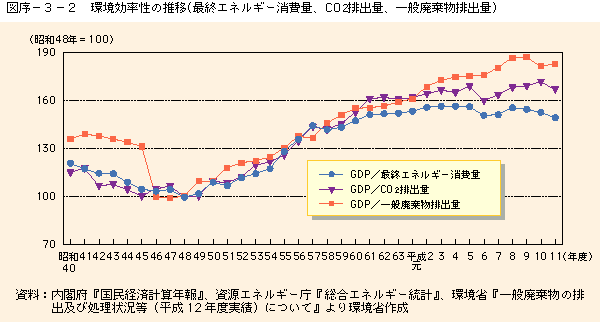
| 環境からより多くのものを得ようとして環境に大きな負荷を与えてきた20世紀は、終わりました。21世紀は、環境の持つ価値を重視し、環境と共に生きる「環境の世紀」にしていかなければなりません。環境負荷を減らし、世代を通じて生活の質を高めながら将来世代と環境の恩恵を分かち合うという意識革命や、これが生み出す技術革新等によって、くらしや社会経済活動にさらに大きな発展が生まれます。こうした発展を「産業革命」や「IT革命」に続く「環境革命」と呼ぶことができます。私たち一人ひとりが行動することで、環境の世紀に新たな可能性が開けます。 | 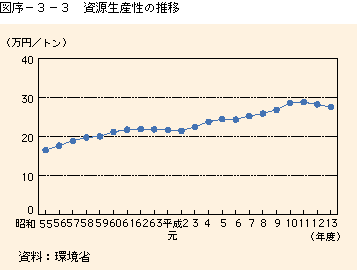 |
|
コラム
|
環境効率性と資源生産性 |
| 環境効率性とは、財やサービスの生産に伴って発生する環境への負荷に関わる概念です。同じ機能・役割を果たす財やサービスの生産を比べた場合に、それに伴って発生する環境への負荷が小さければそれだけ環境効率性が高いということになります。図序-3-1は、国内総生産をNO2、SO2等の環境負荷で割ることによって算出しています。 資源生産性とは、豊かさを増大させながら資源消費の削減を目指す指標です。GDP(国内総生産)を天然資源等投入量(国内・輸入天然資源及び輸入製品の総量)で割ることによって算出しています。 |
|