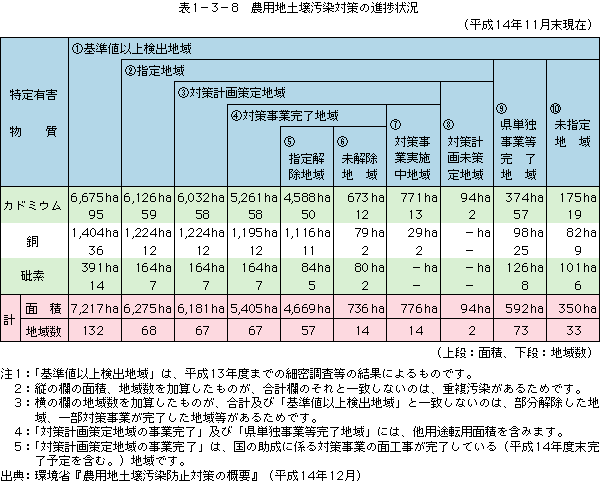
7 土壌環境の安全性の確保
(1)未然防止対策
土壌への有害物質の排出を規制するため、水質汚濁防止法に基づき工場・事業場からの排水規制や有害物質を含む水の地下浸透禁止措置、大気汚染防止法に基づき工場・事業場からのばい煙の排出規制措置、農薬取締法に基づき土壌残留性農薬の規制措置、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき廃棄物の適正処理確保のための規制措置等を講じています。
金属鉱業等においては、鉱山保安法に基づき鉱害防止のための措置を講じているとともに、金属鉱業等鉱害対策特別措置法に基づく鉱害防止事業の計画的な実施に努め、また、休廃止鉱山の鉱害防止事業に係る所要の助成等を実施しています。
地下に埋設される危険物施設については、腐食等の劣化による危険物の漏えい拡散を効果的に防止する方策、危険物が漏えいした場合に早期に検知する方策等に関する調査研究を行うとともに、その有効性について確認実験を実施しました。これらの結果を踏まえ、地下に埋設される危険物施設の安全・環境対策を取りまとめました。
(2)農用地土壌汚染対策
基準値以上検出地域7,217haのうち平成14年11月末現在までに6,275ha(68地域)が農用地土壌汚染対策地域として指定され、そのうち6,181ha(67地域)において農用地土壌汚染対策計画が策定済みです。公害防除特別土地改良事業等により平成14年度末までに5,997haで対策事業が完了する予定です。対策事業の進捗率は83.1%となります(表1-3-8)。
なお、カドミウム汚染地域においては、対策事業等が完了するまでの暫定対策として、汚染米の発生防止のための措置が講じられています。
このほか、農用地土壌から農作物へのカドミウム吸収抑制技術等に関する研究が実施されています。
さらに、農用地における土壌中の重金属等の蓄積防止に係る管理基準に基づき、土壌汚染の未然防止に努めています。
(3)市街地等の土壌汚染対策
市街地等の土壌汚染問題については、近年、企業のリストラ等に伴う工場跡地の再開発・売却の増加、環境管理等の一環として自主的な汚染調査を行う事業者の増加、自治体における地下水の常時監視の体制整備に伴い、土壌汚染事例の判明件数が急激に増加しています。このような状況から土壌汚染による健康影響の懸念や対策の確立への社会的要請が強まっていることを踏まえ、国民の安全と安心の確保を図るため、土壌汚染の状況の把握、土壌汚染による人の健康被害の防止に関する措置等の土壌汚染対策を実施することを内容とする土壌汚染対策法(土壌法 平成14年法律第53号)が、平成14年5月22日に成立し、同月29日公布され、平成15年2月15日に施行されました。
土壌法は、土壌汚染の状況の把握、土壌汚染による人の健康被害の防止に関する措置等の土壌汚染対策の実施を図ることにより、国民の健康を保護することを目的としています。
対象物質(特定有害物質)としては、地下水に溶出してその飲用等に伴う健康被害を生ずるおそれがあるものとして、鉛、砒素、トリクロロエチレン等の25物質を指定して土壌溶出量基準を定め、このうち9物質については、汚染土壌を直接摂取することによる健康被害のおそれがあるものとして土壌含有量基準を定めています。
土壌法においては、以下の2つの場合に、土地の所有者等に土壌汚染の調査(土壌汚染状況調査)を行わせることとしています。
1) 有害物質使用特定施設に係る土地の調査
特定有害物質の使用等をする有害物質使用特定施設が設置されている工場・事業場の敷地を対象として、施設の使用廃止の時点において、土地の所有者等に対し、土壌汚染の調査を実施し都道府県知事に報告する義務を課しています。
2) 健康被害が生ずるおそれがある土地の調査
都道府県知事は、土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれがある土地があると認めるときは、土地の所有者等に調査及びその結果の報告を命ずることができます。
土壌汚染状況調査の結果、土壌中に基準を超える特定有害物質が検出された土地については、都道府県知事は指定区域として指定・公示するとともに、指定区域の台帳を作成し、閲覧に供します。
また、都道府県知事は、指定区域の土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると認めるときは、汚染原因者(汚染原因者が不明等の場合には土地の所有者等)に対し、汚染の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができます。
汚染の除去等の措置としては、土壌汚染の浄化に限らず、暴露経路の遮断による措置を認めています。
なお、措置命令を受けて土地所有者等が汚染の除去等の措置を講じたときは、汚染原因者に対し、これに要した費用を請求できることとしています。
また、指定区域内において土地の形質変更をしようとする者は、都道府県知事に届け出なければなりません。都道府県知事は、その施行方法が基準に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、施行方法に関する計画の変更を命ずることができます。その他、土壌汚染対策法の円滑な施行に向けた調査、対象物質、暴露経路等を拡充した総合的な土壌環境基準等の検討のための調査、低コスト、低負荷型の土壌汚染に係る調査方法や措置技術の検討のための調査、土壌汚染リスクに関するリーフレットの作成、法に基づく指定支援法人の基金に対する補助等を行いました。また、民間事業者による市街地等の土壌汚染対策に対し、日本政策投資銀行が融資を行っています。
(4)ダイオキシン類による土壌汚染対策
ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)に基づき都道府県等が実施する常時監視に助成を行うとともに、平成13年度に都道府県等が実施した常時監視結果を取りまとめました。
また、環境基準を超過し、汚染の除去等を行う必要がある地域として、平成14年度に新たに1地域がダイオキシン類土壌汚染対策地域に指定され、対策計画が策定されました。これまでに指定された2地域について、都道府県が実施するダイオキシン類による土壌の汚染の除去等について都道府県が負担する経費を助成しました。
加えて、ダイオキシン類に係る土壌環境基準等の検証・検討のための各種調査、ダイオキシン類汚染土壌の浄化技術の実証試験等を実施しました。