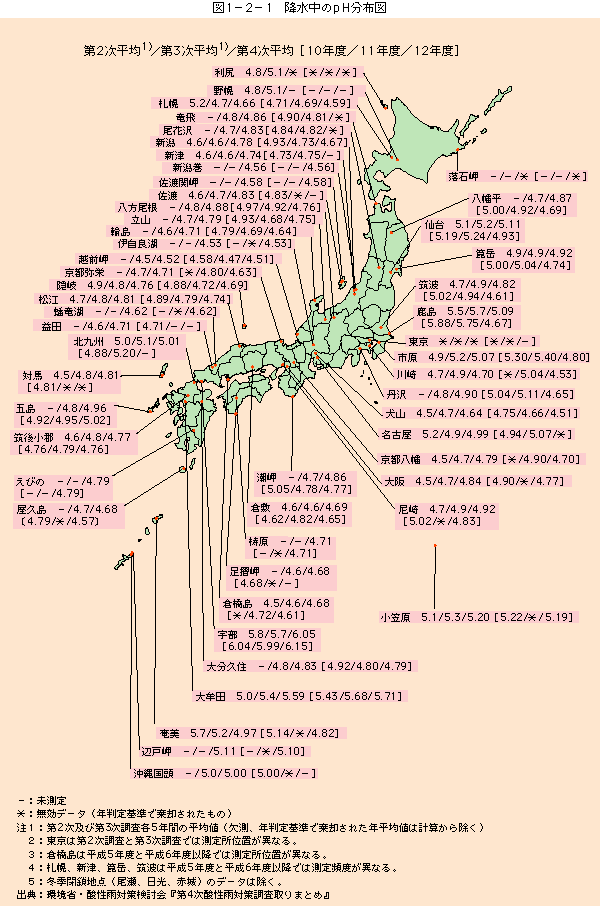
1 大気環境の現状
(1)酸性雨
ア 問題の概要
酸性雨*により、湖沼や河川等の陸水の酸性化による魚類等への影響、土壌の酸性化による森林等への影響、樹木や文化財等への沈着等により、これらの衰退や崩壊を助長することなどの広範な影響が懸念されています。酸性雨が早くから問題となっている欧米においては、酸性雨によると考えられる湖沼の酸性化や森林の衰退等が報告されています。
酸性雨は、原因物質の発生源から500〜1,000kmも離れた地域にも沈着する性質があり、国境を越えた広域的な現象であることに一つの特徴があります。欧米諸国では酸性雨による影響を防止するため、1979年(昭和54年)に「長距離越境大気汚染条約」を締結し、関係国がSOx、NOx等の酸性雨原因物質の削減を進めるとともに、共同で酸性雨や森林のモニタリング、影響の解明などに努めています。
イ 酸性雨対策調査結果
酸性雨は、従来、先進国の問題であると認識されていましたが、近年、開発途上国においても、目覚ましい工業化の進展により大気汚染物質の排出量は増加しており、地域の大気汚染に加え、国を越えた広域的な酸性雨も大きな問題となりつつあります。このような中、2002年(平成14年)8月にヨハネスブルグで開催された「持続可能な開発に関する世界首脳会議」で採択された実施計画においても、酸性雨の軽減のため、国際的、地域的、国家的レベルでの協力を強化すべきであるとしています。
わが国では、第1次酸性雨対策調査(昭和58年度〜昭和62年度)、第2次酸性雨対策調査(昭和63年度〜平成4年度)、第3次酸性雨対策調査(平成5年度〜平成9年度)、及び第4次酸性雨対策調査(平成10年度〜平成12年度)において、降水、土壌・植生、陸水系の継続的なモニタリング、影響予測モデルの開発、樹木の衰退と酸性雨との関連が指摘されている地域における降水、大気汚染物質、土壌・植生などの総合的な調査研究の実施、乾性沈着及び生態影響評価手法の検討を行いました。第4次調査でのモニタリング結果の概要は次のとおりです。
1) 調査期間(平成10年度〜平成12年度)における降水のpHの年平均値(年度ごとの全国平均値)は、4.72〜4.90の範囲にあり、第3次調査(平成5〜9年度、pH:4.7〜4.9)と比較してほぼ同レベルであった。(図1-2-1)。これまで森林、湖沼等の被害が報告されている欧米と比べてもほぼ同程度の酸性度であった。また、日本海側の測定局で冬季に硫酸イオン、硝酸沈着量が増加する傾向が認められた(第3次調査とりまとめにおいては、大陸からの影響が示唆されている。)。
2) 調査期間中の平成12年8月から三宅島雄山の火山活動が活発化した。大気濃度についても、平成12年8月以降、関東地方をはじめとする各地で、環境基準を超える高濃度の二酸化硫黄(SO2)が観測された。また、関東及び中部地方の一部の調査地点において、平成12年度に非海塩性硫酸イオン(nss−SO42-)の沈着量が顕著に増加する傾向が見られた。これらの調査結果については、今後、さらに詳細に解析評価する必要があるものの、湿性沈着についても三宅島雄山の噴火の影響を受けているものと考えられる。
3) 生態系への影響については、酸性沈着との関連性が明確に示唆される土壌酸性化は生じていないと考えられた。また、樹木の衰退現象が見られ、おおむねその原因が特定されたが、一部の森林においては、原因不明の樹木衰退が見られた。
4) 調査対象湖沼の湖心表層pHの範囲は、5.54〜7.87であった。期間中に年平均値が特に高くなる傾向又は低くなる傾向を見せた湖沼はなかった。
このように、わが国における酸性雨による生態系等への影響は現時点では明らかになっていませんが、一般に酸性雨による土壌・植生、陸水等に対する影響は長い期間を経て現れると考えられているため、現在のような酸性雨が今後も降り続くとすれば、将来、酸性雨による影響が顕在化する可能性があります。
(2)光化学オキシダント
ア 問題の概要
光化学オキシダントは、工場、事業所や自動車から排出される窒素酸化物(NOx)や炭化水素類(HC)を主体とする一次汚染物質が太陽光線の照射を受けて光化学反応により二次的に生成されるオゾンなどの総称で、いわゆる光化学スモッグの原因となっている物質です。強い酸化力を持ち、高濃度では眼やのどへの刺激や呼吸器に影響を及ぼし、農作物などにも影響を与えます。
イ 光化学オキシダントによる大気汚染の状況
(ア)環境基準の達成状況
平成13年度の光化学オキシダントの有効測定局(年間測定時間が6,000時間以上の測定局をいう。以下同じ。)は、一般環境大気測定局(以下、「一般局」という。)は663市町村、1,160局で、自動車排出ガス測定局(以下、「自排局」という。)は23市町村、29局です。
光化学オキシダントに係る環境基準(1時間値が0.06ppm以下であること)の達成状況は、例年極めて低く、一般局と自排局を合わせて、昼間(午前5時〜午後8時)に環境基準を達成した測定局及び1時間値の最高値が0.12ppm(光化学オキシダント注意報*レベル)未満であった測定局数は、表1-2-1のとおりです。
(イ)平成14年における光化学オキシダント注意報等の発令状況等
平成14年の光化学オキシダント注意報の発令延べ日数(都道府県を一つの単位として注意報等の発令日数を集計したもの)は184日(23都府県)で、平成13年の193日(20都府県)と比べ、約5%減少しました。高濃度光化学オキシダントの発生は気象条件等に大きく影響されるため、年により大きく増減しますが、平成14年は過去10年間で3番目に発生日数の多い年となりました(表1-2-2)。平成14年の発令延日数を月別にみると、7月が最も多く67日、6月及び8月が各50日でした。なお、平成14年は光化学オキシダント警報*の発令が2日ありました。
地域ブロック別に注意報の発令延日数をみると、東京湾ブロック(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)で111日となっており、全体の60%を占めています(図1-2-2)。また、平成14年の光化学大気汚染によると思われる被害届出人数(自覚症状による自主的な届出による。)は1,347人で、前年の343人に比べて増加し、過去10年間で2番目に当たります。
ウ 非メタン炭化水素の測定結果
昭和51年8月中央公害対策審議会から「光化学オキシダントの生成防止のための大気中の炭化水素濃度の指針について」が答申され、炭化水素の測定については非メタン炭化水素を測定することとし、光化学オキシダントの環境基準である1時間値の0.06ppmに対応する非メタン炭化水素の濃度は、午前6〜9時の3時間平均値が0.20〜0.31ppmC(成分ごとに炭素原子数をかけて合算したppm値に相当)の範囲にあるとされています。
平成13年度の非メタン炭化水素の有効測定局は、253市町村348の一般局と、125市町村178の自排局でした。昭和53年度から継続して測定を行っている6一般局と、昭和52年から継続して測定を行っている8自排局の午前6〜9時における年平均値の経年変化は表1-2-3のとおりです。
(3)窒素酸化物
ア 問題の概要
一酸化窒素(NO)、二酸化窒素(NO2)等の窒素酸化物(NOx)は、主に物の燃焼に伴って発生し、その主な発生源には工場等の固定発生源と自動車等の移動発生源があります。NOxは光化学オキシダント、二次生成粒子、酸性雨の大気汚染の原因物質となり、特にNO2は高濃度で呼吸器に悪影響を及ぼします。
イ 二酸化窒素による大気汚染の状況
(ア)年平均値の推移
平成13年度の二酸化窒素に係る有効測定局は、一般局730市町村1,465測定局、自排局242市町村399測定局です。
年平均値の推移は図1-2-3のとおりで、一般局0.016ppm、自排局0.030ppmと前年度に比べやや減少していますが、長期的にみるとほぼ横ばいの傾向にあります。
(イ)環境基準の達成状況
二酸化窒素に係る環境基準(1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。)による長期的評価は、年間における1日平均値のうち低い方から数えて98%目に当たる値(以下、「1日平均値の年間98%値」という。)と環境基準値を比較して行います。
平成13年度の有効測定局について環境基準の達成状況の推移は、図1-2-4のとおりです。1日平均値の年間98%値が環境基準のゾーンの上限である0.06ppm以下の測定局(環境基準達成局)は、平成13年度は、一般局99.0%、自排局79.4%で、前年度と比較すると、一般局、自排局ともほぼ横ばいでした。大気汚染防止法によって工場等の固定発生源からのNOxの総量規制制度が導入されている地域(施設ごとの排出規制では二酸化窒素に係る環境基準の確保が困難であると認められる地域として、現在、東京都特別区等地域、横浜市等地域及び大阪市等地域の3地域が指定されている。)における環境基準達成率は、一般局89.3%、自排局37.2%でした(前年度は一般局90.9%、自排局40.0%)。二酸化窒素の日平均値が0.04ppmから0.06 ppmまでのゾーン内にあるとされた地域における二酸化窒素の濃度の動向については、表1-2-4のとおりです。
また、平成13年度に環境基準が達成されなかった測定局の分布をみると、一般局については、埼玉県、東京都、神奈川県及び大阪府の4都府県に、自排局については、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、三重県、大阪府及び兵庫県からなる自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物資の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx・PM法 平成4年法律第70号)の対策地域*を有する都府県に加え、茨城県、静岡県、京都府、岡山県、広島県、福岡県、長崎県の7府県にも分布しています(図1-2-5)。
(ウ)自動車NOx・PM法対策地域における環境基準の達成状況等
自動車NOx・PM法に基づく対策地域全体における環境基準達成局の割合は、平成9年度から平成13年度まで39.5〜65.3%(自排局)と低い水準で推移しています(図1-2-6)。また、年平均値は、近年ほぼ横ばいの状況にあります(図1-2-7)。
ウ 一酸化窒素による大気汚染の状況
平成13年度の一酸化窒素に係る有効測定局数は、一般局726市町村1,465測定局、自排局238市町村399測定局でした。年平均値についてみると、一般局0.010ppm、自排局0.043ppmと前度と比べてほぼ横ばいとなっています。
(4)粒子状物質
ア 問題の概要
大気中の粒子状物質は「降下ばいじん」と「浮遊粉じん」に大別され、さらに浮遊粉じんは、環境基準の設定されている浮遊粒子状物質*とそれ以外に区別されます。浮遊粒子状物質は微小なため大気中に長時間滞留し、肺や気管等に沈着して高濃度で呼吸器に悪影響を及ぼします。浮遊粒子状物質には、発生源から直接大気中に放出される一次粒子と、硫黄酸化物(SOx)、窒素酸化物(NOx)、炭化水素類等のガス状物質が大気中で粒子状物質に変化する二次生成粒子があります。一次粒子の発生源には、工場等から排出されるばいじんやディーゼル排気粒子(DEP)*等の人為的発生源と、黄砂や土壌の巻き上げ等の自然発生源があります。
イ 浮遊粒子状物質による大気汚染の状況
(ア)年平均値の推移
平成13年度の浮遊粒子状物質に係る有効測定局数は、一般局730市町村1,541測定局、自排局202市町村319測定局でした。年平均値の推移は図1-2-8のとおりであり、一般局0.030mg/m3、自排局0.038mg/m3と前年度に比べてわずかながら減少し、近年ほぼ横ばいからゆるやかな減少傾向がみられます。
(イ)環境基準の達成状況
長期的評価に基づく浮遊粒子状物質に係る環境基準*の達成率の推移は図1-2-9のとおりであり、平成13年度は、一般局66.6%、自排局47.3%と前年度に比べていずれも減少しています。環境基準を達成していない測定局は全国34都府県に分布しています。
ウ 降下ばいじんによる大気汚染の状況
物の破砕や選別、堆積に伴って飛散する大気中のすす、粉じん等の粒子状物質のうち比較的粒が大きく沈降しやすい粒子は、降下ばいじんと呼ばれています。平成13年度において長期間継続して測定を実施している測定局は2局であり、その年平均値は3.7t/km2/月となっています(表1-2-5)。
エ スパイクタイヤ粉じん
昭和50年代の初めからスパイクタイヤが積雪地域で急速に普及し、スパイクタイヤの使用により発生する粉じんが問題となりました。不快感や衣服、洗濯物の汚れだけでなく、人体への影響も懸念されたため、その後、スパイクタイヤの製造・販売は中止され、さらにスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律(平成2年法律第55号)に基づいてスパイクタイヤの使用を禁止する地域が指定されたことによって、現在ではスパイクタイヤに係る降下ばいじんの状況は著しく改善しています。
(5)硫黄酸化物
ア 年平均値の推移
平成13年度の二酸化硫黄(SO2)*に係る有効測定局数は、一般局672市町村1,489測定局、自排局80市町村95測定局でした。年平均値の推移は図1-2-10のとおりであり、一般局では0.005ppm、自排局では0.006ppmと近年ほぼ横ばい、又は減少傾向にあります。
イ 環境基準の達成状況
長期的評価に基づく二酸化硫黄に係る環境基準*の達成率の推移は表1-2-6のとおりで、平成13年度は、一般局99.6%、自排局100%と近年良好な状態が続いています。
また、短期的評価に基づく二酸化硫黄に係る環境基準*の達成率は、平成13年度は、一般局62.4%、自排局40.0%となっており、短期的評価では三宅島の火山ガスの影響により環境基準の達成率が低下しています。
(6)一酸化炭素
ア 年平均値の推移
平成13年度の一酸化炭素(CO)*に係る有効測定局数は、一般局112市町村131測定局、自排局202市町村312測定局でした。
年平均値の推移は図1-2-11のとおりであり、平成13年度は、一般局0.5ppm、自排局0.8ppmと近年では横ばい、又は減少傾向にあります。
イ 環境基準の達成状況
平成13年度においては、前年度に引き続き、一般局、自排局ともすべての測定局において環境基準の長期的評価(年間における1日平均値のうち測定値の高い方から2%の範囲にあるものを除外した後の最高値が10ppmを超えず、かつ、年間を通じて1日平均値が10ppmを超える日が2日以上連続しないこと。)及び短期的評価(1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。)いずれも達成しています。
(7)有害大気汚染物質
近年、低濃度ながら、多様な化学物質が大気中から検出されていることから、これらの有害大気汚染物質*の長期暴露による健康影響が懸念されています。
平成13年度に環境省及び地方公共団体が実施した、環境基準の設定されている物質(ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタン)に係る測定結果の概要は表1-2-7のとおりでした(ダイオキシン類に係る測定結果については本章第5節参照)。
ベンゼンについて、月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点における測定結果を環境基準値(0.003mg/m3)と比較すると、368地点中67地点において環境基準値を超過していましたが、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタンについては、すべての地点において環境基準値(それぞれ0.2mg/m3、0.2mg/m3及び0.15mg/m3)を下回りました。
(8)騒音・振動、悪臭
大気環境の保全については、大気汚染に加え、主に人の感覚に関わる問題である騒音・振動及び悪臭が重要課題となっています(図1-2-12)。
ア 騒音・振動
(ア)問題の概要
騒音・振動は、各種公害の中でも日常生活に関係の深い問題であり、その発生源も多種多様であることから、例年、その苦情件数は公害に関する苦情件数のうちの多くを占めています。
騒音苦情の件数は減少傾向にありましたが、平成12年度から増加に転じ、平成13年度は14,547件でした(図1-2-13)。発生源別にみると、苦情の総数の4割近くを占める工場・事業場騒音に係る苦情の割合が減少しているのに対して、建設作業騒音に係る苦情が増加しています。また、近年では、低周波音も大きな問題となっています。
一方、振動の苦情件数は、この10年ほどは2千件台で推移しており、平成13年度は2,480件でした(図1-2-14)。発生源別にみると、建設作業振動に対する苦情件数が最も多く、工場・事業場振動に係るものがそれに次いでおり、苦情原因として依然大きな割合を占めています。
(イ)一般地域における騒音の状況
一般地域の騒音については、地域の類型及び時間の区分ごとに環境基準「騒音に係る環境基準について」(平成10年 環境庁告示)が設定されており、平成13年度末現在、47都道府県の656市、1,016町、115村、23特別区において地域指定が行われています。
平成13年度の一般地域における騒音の環境基準の達成状況は、地域の騒音状況を代表する地点で74.6%、騒音に係る問題を生じやすい地点等で69.8%となっています。
(ウ)自動車交通騒音・振動の状況
自動車交通騒音についても一般地域同様に、環境基準が設定されており、一定の地域ごとに騒音レベルが基準値を超過する戸数及び割合を把握することにより評価(以下、「面的評価」という。)がなされています。
平成13年度の自動車騒音の常時監視の結果をみると、面的評価は、78の地方公共団体で行われ、評価の対象となった住居等1,487千戸のうち、昼夜とも基準値を超過していた住居等は、198千戸(13.3%)でした(図1-2-15)。なお、従来行われていた点的評価では、全国の測定地点2,774地点のうち、昼夜とも基準値を超過していた地点は、1,163地点(41.9%)でした(図1-2-16)。
また、自動車交通騒音・振動については、市町村長が騒音規制法及び振動規制法に基づき、都道府県公安委員会及び道路管理者に対して所要の措置を要請する際の基準となる要請限度が定められていますが、自動車交通騒音については、平成13年度に地方公共団体が苦情を受け測定を実施した199地点のうち、要請限度値を超過した地点は30地点で、同様に、自動車交通振動については、測定を実施した121地点のうち、要請限度値を超過した地点は3地点でした。
(エ)航空機騒音の状況
航空機のジェット化の進展等は交通利便の飛躍的増大をもたらした反面、空港周辺の市街化とあいまって、空港周辺地域において航空機騒音問題を引き起こしました。これまで、民間空港2港及び防衛施設5飛行場において、夜間の発着禁止、損害賠償等を求める訴訟が提起されています。
航空機騒音については、地域の類型ごとに環境基準*が設定されており、平成12年度末現在で、33都道府県、63飛行場周辺において地域の指定が行われています。
航空機騒音に係る環境基準の達成状況は、全般的に改善の傾向にあるものの、ここ数年は横ばいとなっており、平成12年度においては約72%の地点で達成しました(図1-2-17)。
(オ)新幹線鉄道騒音・振動の状況
新幹線鉄道騒音については、地域の類型ごとに環境基準*が設定されており、平成12年度末現在で、25都府県において地域指定が行われています。また、新幹線鉄道振動については、「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について」(昭和51年3月)において、振動対策指針値を70デシベルとしています。
新幹線鉄道騒音については、平成9年度までに、東海道・山陽新幹線沿線の住宅密集地域が連続する地域及び住宅集合地域、東北・上越新幹線沿線の住宅集合地域及びそれに準ずる地域において75デシベル以下が達成されましたが、東海道・山陽新幹線及び東北・上越新幹線沿線のその他の地域では、いまだ75デシベルを達成していない地域が残されています。
また、平成9年度開業した北陸新幹線高崎・長野間については、測定地点の46%で、平成14年度延伸開業した東北新幹線盛岡・八戸間については、測定地点の78%で環境基準が達成されました。
新幹線鉄道振動については、振動対策指針値はおおむね達成されています。
イ 悪臭
悪臭は、人に不快感を与えるにおいの原因となる物質が大気中に放出されることで発生します。悪臭は、騒音・振動と同様に感覚公害と呼ばれる生活に密着した問題です。悪臭苦情の件数は昭和47年度をピークにおおむね減少傾向にありましたが、ここ数年は増加傾向にあります。平成13年度は、前年度と比べて2,571件(12.1%)増加し、昭和45年の調査開始以来最高の23,776件の苦情が寄せられました(図1-2-18)。発生源別にみると、畜産農業や化学工場など、かつて問題となっていた業種に係る苦情は減少していますが、平成9年度以降、野外焼却に係る苦情が急激に増加しています。また、サービス業や個人住宅に係る苦情の割合も増加する傾向にあります。
(9)その他の大気に係る生活環境の現状
ア ヒートアイランド現象
都市部の気温が郊外に比べて高くなるヒートアイランド現象*が大都市を中心に起こっています(図1-2-19)。この現象により、夏季においては、熱中症の発症が増加していることに加え、冷房等による排熱が気温を上昇させることにより、さらなる冷房のためのエネルギー消費が生ずるという悪循環が発生しています。また、夏季の光化学オキシンダントや冬季の窒素酸化物(NOx)による大気汚染を助長しています。
イ 光害(ひかりがい。屋外照明器具から発する光のうち、目的の照明範囲の外に漏れる光によって起こる、様々な悪影響。)
過度の夜間照明の使用から生じる漏れ光は、人間の諸活動へ影響を及ぼし、また水稲等の農作物の生育に悪影響を及ぼします。また、夜間の屋外照明は安全確保や防犯のために不可欠ですが、過度の屋外照明はエネルギーの浪費であり、地球温暖化の原因にもなります。