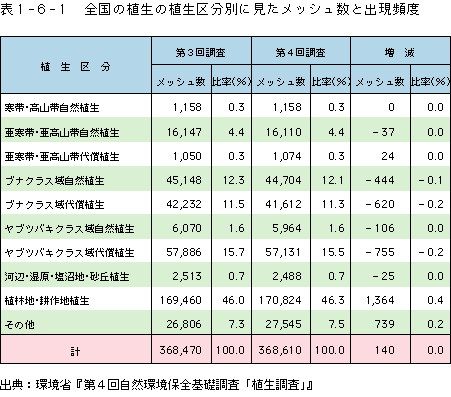
1 自然環境等の現状
(1)自然環境の現状
日本列島はユーラシア大陸の東縁部に位置し、日本海をへだて大陸とほぼ平行に連なる南北約3,000kmに及ぶ弧状列島です。
世界でも比較的新しい地殻変動帯にある日本列島は、種々の地学的現象が活発です。地形は起伏に富み、丘陸地を含む山地の面積は国土の約4分の3を占めます。山の斜面は一般に急傾斜で谷により細かく刻まれており、山地と平野の間には丘陵地が分布します。平野、盆地の多くは小規模で、山地との間や海岸沿いに点在し、その多くが河川の堆積により形成されています。また、気候は湿潤であり、季節風が発達し、四季の別が一般に明確です。
わが国では、全国的な観点から自然環境の現況及び改変状況を把握し、自然環境保全の施策を推進するための基礎資料を整備するために、おおむね5年ごとに自然環境保全基礎調査を行っています。本節では「緑の国勢調査」といわれるこの調査の第4回の結果を中心に国土の自然環境の現状を概観します。なお、現在は第5回の基礎調査を取りまとめ中であり、平成11年度より第6回の基礎調査を実施しています。
ア 陸域〜植生・動物分布の状況
(ア)日本列島の植生
植生は一般に時間とともに変化し、最終的に安定的な生態系である極相となります。日本の気候では、1)南西諸島から東北南部に広がるタブ、カシ類、シイ類といった常緑広葉樹(照葉樹)の森林、2)九州南部から北海道南部までの、常緑広葉樹林より寒冷な地域に広がるブナ林などの落葉広葉樹の森林、3)北海道に広がるエゾマツ、トドマツといった針葉樹とミズナラ等の落葉広葉樹の混成する針広混交林、4)エゾマツ、トドマツ林に代表される亜寒帯針葉樹林等が代表的な気候的極相です。自然性の高い地域ではこうした極相の植生が見られますが、その地域は必ずしも多くはありません。
平成2〜4年度に実施した第4回調査の解析は、植生帯及び自然植生と代償植生との別に分類した植生区分と、植生への人為の加わり度合いにより分類した植生自然度区分の二つの区分により行いました(表1-6-1、表1-6-2、図1-6-1、図1-6-2)。
植生区分別では、森林・草原・農耕地等何らかの緑で覆われた地域は、全国土の92.5%に達します。中でも森林は67.1%を占め、アメリカ合衆国(32.6%)、イギリス(10.4%)、フランス(27.4%)、ドイツ(29.9%)、カナダ(45.3%)(海外の数値はOECD環境データによる1995年時点のもの)と比較しても高い水準にあります。
自然度別では、自然林に自然草地を加えた自然植生は国土の19.1%と2割を切っており、このうち2分の1以上に当たる58.8%が北海道に分布しています。一方、近畿、中国、四国、九州地方では、小面積の分布域が山地の上部や半島部、離島等に点在しているに過ぎません。
総体としては、自然度の高い植生(自然草原、自然林、自然林に近い二次林)、人為の影響を受けた植生(二次林、二次草原)、人為的に成立した植生(植林地)、土地改良の進んだ植生(農耕地、市街地、造成地等)が調査時点ではほぼ4分の1ずつ占めています。しかし、昭和58〜61年度に実施した第3回調査との比較から、自然林、二次林は減少し、植林地、市街地、造成地等は増加傾向にあります。
(イ)日本列島の多様な動物分布
動物地理区上日本列島は、鹿児島県の屋久島・種子島と奄美大島との間の渡瀬線という分布境界線により二分されています。渡瀬線より北は旧北区、南は東洋区と呼ばれていますが、旧北区である本州以北に生息する大部分の日本の動物は、例えばトガリネズミ類、リス類、イタチ類は中国華中以北のユーラシア大陸に生息する動物との類縁性が高く、東洋区である奄美・琉球諸島の動物、例えばケナガネズミは台湾や東南アジア諸国に近縁種が多く生息します。また、島国という地理的特徴による隔離効果により、ヒミズ、ヤマネ、アマミノクロウサギのような固有種も多数存在します。そのほかに動物の分布境界線としては、北海道と本州の間に位置するブラキストン線等があります(図1-6-3)。
イ 陸水域〜湖沼・河川・湿地の状況
(ア)湖沼
わが国には、山岳地帯の湖沼をはじめ、海が後退してできた海跡湖のように平野部や海岸近くにあるものなど多様な湖沼が存在しています。
湖沼調査では、全国の天然湖沼のうち1ha以上の480湖沼を対象に、湖岸の土地利用の改変状況、魚類相等の調査を行いました。
湖岸の状況では、第3回の調査と比較して自然湖岸が減少し人工湖岸が増加しています(表1-6-3)。また、増減の度合いを第3回調査時と比較しても、自然湖岸の減少が大幅に加速していることが明らかになりました。調査時点では、自然地が保全されている湖岸は全体の約57%、人為的改変を受けている湖岸は約43%となっています。
生息魚種数の調査は代表的な湖沼60湖沼を対象として行いました。1湖沼当たりの平均はおおよそ25種です。主要外国産移入魚種では、ブラックバス、ブルーギル、ソウギョ等の生息が調査対象の湖沼の約3分の1で確認されています。こうした外国産移入種は各地の湖沼で定着しつつあり、湖沼の魚類相を含む生態系への悪影響が懸念されるため、今後もその推移に注目する必要があります。
(イ)河川
河川や水路等の水辺環境は、水辺や水生の生物の生息地としてだけでなく、多様な動物の生息地であるさまざまな緑地を繋ぐ移動ルートとしても必要なものであります。また、陸側から水辺に向けて、水辺林、湿性植物、抽水植物、浮葉植物、沈水植物までさまざまな植物群落が見られます。このような水辺の移行帯はエコトーンと呼ばれ、豊かな生態系を形成しています。
原生流域調査では、第3回調査で登録された101の原生流域(面積1,000ha以上にわたり人工構造物及び森林伐採等の人為の影響のみられない集水域)について、空中写真等により第3回調査以降の人為改変状況を調査しました。その結果、伐採、道路の建設等により13流域の原生流域の面積が減少し(合計7,296ha減)、そのうち3流域が原生流域の要件を満たさなくなったため原生流域から除外されました。また、新たに1流域(仲間川、沖縄県、1,346.9ha)が原生流域として登録されたため、原生流域は99流域(総面積205,634ha)となりました。原生流域面積の大きい保全地域は表1-6-4のとおりです。
河川改変地調査等では、全国の主要な1級河川の支川及び2級河川の幹川等の中から良好な自然域を通過する河川等153河川を対象に水際線、河原、河畔の改変状況、生息魚種等を調査しました。水際線の状況は図1-6-4のとおりであり、総延長の26.6%に護岸等が設置されていました。水際線の自然地率の高い河川は図1-6-5のとおりであり、特に、別寒辺牛川(北海道)、岩股川(秋田県)、長棟川(富山県)及び仲良川(沖縄県)は自然地率100%でした。
ウ 海域〜海岸、藻場、干潟及びサンゴ礁の状況
(ア)自然海岸
自然状態を保持した海岸は生物の繁殖及び生息の場として重要です。都市化や産業の発達に伴い、高度成長期には海岸線の人工的改変が急速に進められました。しかし、人工的改変は不可逆のものであり、慎重に行わなければなりません。
海岸調査では、海岸の自然状態について第3回調査以降の変化を把握、分析しました。調査結果は図1-6-6のとおりです。昭和59年の第3回調査結果と比べ、海岸線については本土部分が172km、島嶼部分が135km増加しているものの、全国の自然海岸は296km減少しています。ただし、昭和53年の第2回と第3回の調査の間には自然海岸は565km減少しており、減少傾向の鈍化が認められます。
(イ)藻場、干潟及びサンゴ礁
藻場とは大型底生植物の群落であり、魚介類の産卵場や餌場などの生育場となるなど沿岸地域の生態系として重要な役割を果たしています。
藻場の調査は日本沿岸全域を対象に行いました。調査の結果、全国で201,212haの藻場が把握され、昭和53年の第2回調査以降6,403haの藻場の消滅が判明しました。一続きで最大の藻場は、静岡県の相良から御前崎に位置する藻場で7,891haでした。また、連続したものではありませんが、最も多くの藻場が分布するのは能登半島周辺の海域で、14,761ha(全国の7.3%)でした(表1-6-5)。藻場の消滅の原因の上位は、埋立てと磯焼けが占めています(表1-6-6)。磯焼けは多くの場合原因が特定できませんが、現象としてはよく繁茂していた大型海藻が枯死消失し、その後無節石灰藻類が繁殖するもので、その状態が数年から十数年にわたって持続する例が知られています。
干潟は干出と水没を繰り返す環境条件から、海域環境の中でも海洋生物や水鳥等の生息環境として大切な役割を持ちます。干潟には河川と陸上の両方からさまざまな栄養物質が堆積し、潮の干満の際に空気中の酸素が大量に海水中に溶け込むため、多くの微生物や底生動物が生息し、それを餌とする渡り鳥も数多く飛来します。また、これら微生物が有機汚濁を分解するなど、干潟の水質浄化能力も注目されています。しかし、干潟の多くは水が滞留しやすい内海にあるため、干潟の浄化能力で対応しきれない人的汚染も広がりつつあり、影響が懸念されています。
第4回調査では51,443haの干潟が確認されました。海域別では、有明海で20,713ha(全国の約40%)の存在が認められました。また、3,857haの干潟が昭和53年の前回調査時以降消滅したことが判明しました。最も多く干潟が消滅したのも有明海で、その面積は1,357haに達していました(表1-6-7、表1-6-8)。
わが国のサンゴ礁地形は鹿児島県のトカラ列島以南に多く存在します。八重山列島にはわが国最大の面積のサンゴ礁があり、同海域の造礁サンゴ類の種の多様性は世界でも屈指のものです。
サンゴ礁調査は、1)鹿児島県トカラ列島小宝島以南の「サンゴ礁海域」2)トカラ列島悪石島以北の「非サンゴ礁海域」に分けて実施されました(ただし、小笠原諸島は「サンゴ礁海域」に属するが、本調査では「非サンゴ礁海域」としている。)。サンゴ礁は暖かい透明度の高い海域に発達し、その分布、被度(生きているサンゴの面積割合)等サンゴ礁の生育状況の把握は環境の健全性や人為的影響を知る上でも重要です。
南西諸島海域において、サンゴ礁池で被度を調査した結果、被度5%未満は分布地域の61.3%、被度5〜50%は30.6%、被度50%以上は8.2%で、わが国のサンゴ礁池のサンゴ群集は、大部分が被度の低いものであることが分かりました。礁縁において行った調査では、沖縄島海域以外は被度5〜50%が最大の比率を占めますが、沖縄島海域では被度5%未満が46.2%を占め、礁縁においても被度が低いことが明らかになりました。
小笠原群島海域は、父島列島及び母島列島において調査し、456haのサンゴ群集が記録され、そのうち約70%が被度50%以下でした。
本土海域のサンゴ群集(面積0.1ha以上、被度5%以上)の合計面積は1,409.3haでした。特に面積が大きかったのは、東京都(424.8ha)、宮崎県(292.7ha)であり、この両者で全体の50%を超えます。東京都の分布は八丈島がほとんどを占めています。
(2)野生生物種の現状
ア 生物多様性
日本には、動物は脊椎動物約1,400種、無脊椎動物約35,000種、植物は維管束植物約7,000種、藻類約5,500種、蘚苔類約1,800種、地衣類約1,000種、菌類約16,500種(いずれも海棲のものを除く。)の存在が確認されています。生物種の数は熱帯林を擁する国々と比べると少なく、先進国(特にヨーロッパ各国)と比べると多いといえます。多様な生物種の生息を可能にしている要因は、亜熱帯から亜寒帯にわたる気候帯や起伏に富み標高差のある国土といった多様な自然環境です。また、わが国は四つの主要な島と3,000以上の属島から構成されており、中には特異な生物相を有する島しょも含まれています。
わが国では、特に戦後の経済の高度成長期を中心に開発による自然環境の改変が進行し、全国的に自然林や干潟等が減少しました。また、都市化等に伴う汚染や汚濁など生物の生息環境の悪化・消滅、あるいは希少な動植物の乱獲、密猟、盗掘等も進みました。さらに里地自然地域等と人とのかかわりの減少も、2次的な自然環境に適応してきた生物の生息・生育の場を減少させています。この結果、わが国でも多くの種が存続を脅かされるに至っており、これらの種の絶滅を防ぐことが緊急の課題となっています。
また、国外あるいは地域外からの生物種の移入は、他の種を捕食することや生息場所を奪うことにより在来種を圧迫すること、在来の近縁な種と交雑すること等によって生態系をかく乱し、生物多様性の減少をもたらすこととなります。わが国では南西諸島のマングース、小笠原諸島のノヤギ等、各地で生物多様性への影響が指摘されています。
我々の暮らしは、生物多様性がもたらす恵みによって成り立っています。その価値は次のように分けられます。
生物の活動は、土、河川、地下水、大気中の酸素をつくり、気候を調節するなど、人類を含む生物自身にとって良好な環境を形成し、調節しています(環境の形成・調節)。
日々の生活と経済活動にとって必要な資源の多くは、食料、衣類、医薬品、さらには石油・石炭等生物を起源とするもので占められています(生産・経済的価値)。
また、人間は自然との交流を通して自然の摂理を学び、美意識や情操を養い、自然を芸術や信仰の対象とし、レクリエーションを楽しみ、やすらぎを得る場としてきました(文化的価値)。
現在、農作物、家畜、医薬品等として人間が利用している生物種は、全体から見ればごく少数です。広範な単一種栽培により、地域的な多様性が失われ、環境の変化や病害虫に対して壊滅的な被害を生じるおそれがあります。他方、あまり注目されていなかったマダガスカルのツルニチソウの仲間の中からガンに効果のある薬品が採取された例もあり、未知の生物の中に将来人類の生存を左右するようなものが隠されている可能性もあります。
地球生態系の健全性が生物多様性の上に成り立っていることを考えれば、人類は一つの生物として自らも多様性という自然の摂理に従い、その保全に努めていくことが、持続可能な発展を通じて真に豊かな社会を構築していくことを可能にするものといえます。
しかし、人間の活動は、現在まで生物多様性の減少をもたらしてきており、その速度は今日に至るまで一向に減速したとは思えない状況にあります。このような危機感から、多様な生物とその生息環境を確保することを主目的として、1992年の地球サミット開催を前に「生物多様性条約」が採択され、1993年(平成5年)12月に発効しました。
わが国では、1993年(平成5年)に生物多様性条約を批准し、1995年(平成7年)に条約実施の基本方針等を定めた「生物多様性国家戦略」が定められた。平成14年3月には、近年の環境の現状や社会経済状況の変化を踏まえて見直しを行い、「自然と共生する社会」を政府全体として実現することを目的とした自然の保全と再生のためのトータルプランとして地球環境保全に関する関係閣僚会議で新たに決定されました。
また、平成12年に策定された新「環境基本計画」においては、生物多様性の保全を戦略的プログラムの一つとして位置付け、特に重点的、戦略的に取り組むこととしています。
イ 絶滅の危機にさらされている野生動植物
「種の保存法*」では、本邦に生息・生育する絶滅のおそれのある種を国内希少野生動植物種に、また、「ワシントン条約*」及び「渡り鳥等保護条約」に基づき国際的に協力して種の保存を図るべき絶滅のおそれのある種を国際希少野生動植物種にそれぞれ指定し、個体の捕獲・譲渡等や器官・加工品の譲渡等を規制しています。国内希少野生動植物種については、必要に応じ、その生息・生育地を生息地等保護区として指定し、各種の行為を規制しています。また、個体の繁殖の促進や生息・生育環境の整備等を内容とする保護増殖事業を積極的に推進することとしており、その適正かつ効果的な実施のために保護増殖事業計画を策定することとしています。
*種の保存法
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」。国内外の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を体系的に図るため、平成4年6月5日に法律第75号として公布された。
*ワシントン条約
一部の野生動植物種が野放図な国際取引によって絶滅の危機にある事態を憂慮し、これを規制する目的で1973年(昭和48年)にワシントンで採択され、1975年(昭和50年)に発効した国際条約で、正式名称を「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」という。日本は1980年(昭和55年)に加盟し、同年11月に発効した。
平成14年3月現在、国内希少野生動植物種としては、哺乳類2種、鳥類39種、爬虫類1種、両生類1種、汽水・淡水魚類2種、昆虫類4種、植物8種の計57種を指定しています。また、国際希少野生動植物種として、約650分類群を指定しています。
保護増殖事業計画については、アホウドリ、トキ等について21の計画が策定されています。
わが国の絶滅のおそれのある野生生物の個々の種の生息状況等は、平成3年に、「日本の絶滅のおそれのある野生生物(通称:レッドデータブック)―脊椎動物編―、同―無脊椎動物編―」として取りまとめられました。このレッドデータブックでは、野生生物の生息状況や生息環境の変化に対応するために定期的な見直しが必要であることから、レッドリスト(レッドデータブックの基礎となる日本の絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト)の改訂作業を平成12年4月に終了しています。植物についても平成9年8月にレッドリストをまとめ、平成13年にレッドデータブックを作成しました。
これにあわせて、従来、種の存続の危機の度合いの高い順に「絶滅危惧種」、「危急種」、「希少種」と定性的に分類していたものを、「絶滅危惧I類」、「絶滅危惧II類」、「準絶滅危惧」と定性的要件と定量的要件を組み合わせたものに改訂し、順次新たなカテゴリーに移行しました((総説)表1-1-2参照)。これによると、わが国に生息する哺乳類、両生類、汽水・淡水魚類の2割強、爬虫類、維管束植物の2割弱、鳥類の1割強の種の存続が脅かされています。
ウ 野生鳥獣の保護管理
野生鳥獣は自然環境を構成する重要な要素の一つであり、永く後世に伝えていくべき国民共有の財産であることから、個々の種や地域における個体群を長期にわたり安定的に維持することが必要とされています。
西中国山地のツキノワグマなどのように生息域の分断などにより地域的に絶滅のおそれが生じている野生鳥獣の個体群、シカなどのように地域的に増加又は分布域を拡大して、農林業被害や自然生態系のかく乱など人とのあつれきをおこしている野生鳥獣の個体群に関する問題に対して適切に対応していくためには、種や個体群の維持存続を図りつつ人と野生鳥獣とのあつれきを可能な限り少なくすることにより、人と野生鳥獣との共存を図っていくことが必要です。そのためには、被害防除対策の適切な実施を図りつつ、野生鳥獣の生息数や生息環境を望ましい状態に維持・誘導するという「保護管理」の推進が求められています。
しかし、野生鳥獣の保護管理のあり方については多様な価値観が存在するため、各般の保護管理施策が円滑かつ効率的に実施されるよう、行政、地域住民、専門家など野生鳥獣の保護管理にかかわるさまざまな主体の間において、人と野生鳥獣との共存に向けた施策について、合意形成及び施策間の整合性の確保に努めるよう調整を図ることが必要とされています。
また、地域個体群の安定的な維持又は被害の防止の両面において、保護管理施策の実効性に関する理解を高めるとともに、科学的な不確実性を補い、問題解決的な姿勢で現実に直面している事象に積極的に対応していくため、情報の適切な公開などにより、施策の種類、内容及び効果などに関する透明性を確保するとともに、モニタリングの実施やその結果の保護管理への反映などによるフィードバックシステムを導入することが特に必要とされています。
野生鳥獣の種及び個体群の安定的な維持を図りつつ、野生鳥獣に関する多様な社会的要請に応えるためには、欧米において定着しているワイルドライフ・マネージメントに相当する野生鳥獣の「科学的・計画的な保護管理」を、1)科学的知見及び合意形成に基づいた明確な保護管理目標の設定、2)多様な手段の総合的・体系的実施、3)適切なフィードバックシステムの導入の3点を基本的な考え方のポイントとして、積極的に推進する必要があります。なお、「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」について、鉛製散弾の使用禁止措置等を内容とした改正案を第154回国会に提出し、5月1日現在、審議が進められているところです。
エ 狩猟
狩猟は人間の生業やスポーツ等として行われてきましたが、野生鳥獣を自然の収容力に見合った生息数に維持管理する手段としての役割も果たしています。わが国に生息する哺乳類及び鳥類については、一部を除き全種が「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」によって保護の対象とされており、狩猟ができる鳥獣は47種類に限定されています。狩猟については、期間(狩猟期間)、場所(鳥獣保護区の指定等による狩猟の禁止)、資格(狩猟免許)等の制限が定められており、これらの捕獲規制によって鳥獣の保護を図っています。
狩猟者人口は、昭和51年度の約53万人が平成11年度には約23万人にまで減少しており、しかも高齢化がかなり進んでいます。平成11年度に有害鳥獣駆除の許可証交付件数は約20万件となっていますが、中には従事者の確保が困難なところも見受けられます。
また、狩猟鳥獣の保護管理を科学的・計画的に進めるに当たっては、狩猟鳥獣の生息動向の適時的確な把握が肝要です。狩猟による鳥獣の捕獲実績データ等は、鳥獣の生息動向を把握する上での重要な情報源です。今後は、狩猟者も野生鳥獣の保護管理の一端を担うため、その担い手としての狩猟者の育成等を図っていくとともに、過大な負担とならない範囲内で、必要に応じて狩猟実績の報告等を充実させていく必要があります。
オ 水産資源の保護管理
四方を海に囲まれたわが国は、周囲に寒流・暖流が交錯する生物多様性に富む豊かな漁場を有しています。わが国は伝統的に水産物を重要な蛋白質として活用してきており、多様な水産資源の恩恵を受けています。
水産物の生産量は戦後ほぼ一貫して増加し、昭和56年に養殖業を除く海面漁業の生産量が1,000万tを超え、昭和59年には1,150万tに達しました。しかし、平成元年以降生産量が減少し、平成12年の生産量は昭和59年に比べ約56%減の約502万tにまで低下しました(図1-6-7)。主要魚種別生産量の推移を見ると、まいわし、すけとうだら、さば類及びまあじの生産量がいずれも減少しています(図1-6-8)。わが国周辺水域では漁船性能の向上等による漁獲強度の増大等もあって底魚類を中心に総じて資源状態が低水準にあります。まいわし、まさば、まあじ等の浮魚資源は海洋環境の影響等を受けて資源状態が大きく変動しており、この中で現在減少傾向にあるまいわし資源については今後の動向を注視していく必要があります。