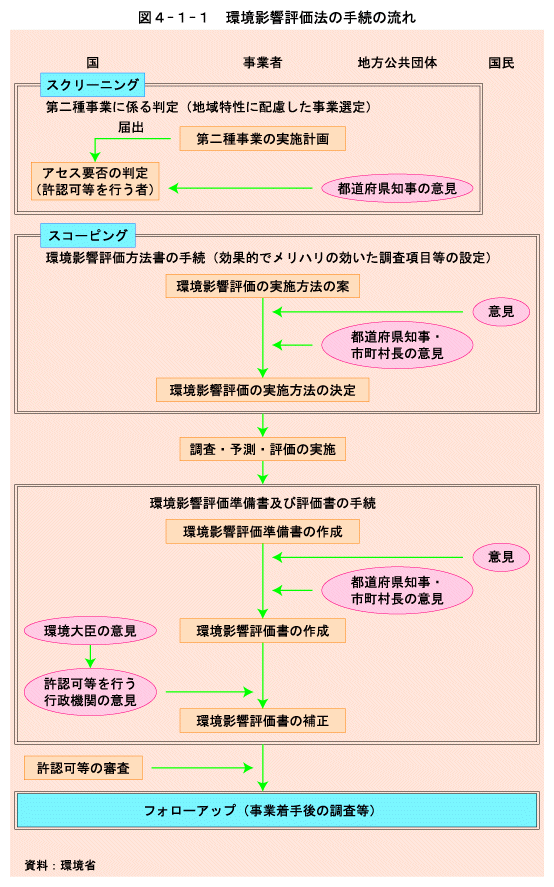
3 環境影響評価の実施
(1)環境影響評価法に基づく環境影響評価
環境影響評価法*は、道路、ダム、鉄道、飛行場、発電所、埋立・干拓、土地区画整理事業等の面的開発事業のうち、規模が大きく、環境影響が著しいものとなるおそれがある事業について環境影響評価*手続の実施を義務付けています(図4-1-1)。
同法は平成11年6月から全面施行されていますが、環境影響評価方法書の手続は平成10年6月から行っており、平成13年3月末までに48件の手続が開始されており、9件の手続が終了しています。
また、条例や行政指導などに従い、同法により作成されるべき各種書類に相当する書類が、同法の施行前に作成されている事業については、同法における該当書類がすでに作成されたものとみなして、中途からこの法律の手続を開始することができるとされています。平成13年3月末までに、同法に基づく環境影響評価手続が終了した事業は41件となっています(表4-1-1)。
*環境影響評価法
平成9年6月13日法律第81号
*環境影響評価
環境影響評価とは、環境に大きな影響を及ぼす事業について、その事業の実施に当たり、あらかじめその事業の環境への影響を調査、予測、評価し、その結果に基づき、その事業について適正な環境配慮を行うことをいう。わが国においては、環境影響評価法等に基づき、道路やダム、鉄道、発電所などを対象にして、地域住民や専門家や環境担当行政機関が関与しつつ手続が実施されている。
(2)環境影響評価の適切な運用への取組
環境の保全に関する各分野ごとに学識経験者による検討会を設けて、環境影響評価法に対応した方法書手続や環境影響評価等の具体的な進め方を明らかにするとともに、各環境要素毎に技術手法の問題点を整理し、改善のための検討等を行いました。
また、国・地方公共団体等の環境影響評価事例や制度及び技術の基礎的知識の提供による環境影響評価の質及び信頼性の確保を目的として、環境影響評価の実施に際して必要となる情報等を集積し、インターネット等を活用した国民や地方公共団体等への情報支援体制の整備を進めました。
(3)個別法等による環境影響評価等
港湾法、公有水面埋立法等の個別法等に基づく環境影響評価について、平成12年度に実施されたものの概要は以下のとおりです。
1) 港湾計画
港湾法に基づいて定められる港湾計画は、港湾における開発、利用及び保全に当たっての指針となる長期的・基本的な計画であり、計画の策定に際しては、「港湾の開発・利用並びに開発保全航路の開発に関する基本指針」を受けて、環境に与える影響についての評価を行っています。平成12年度においては、港湾審議会計画部会が2回開催され、新潟港、平良港等の港湾計画について所要の審議を行いました。
2) 公有水面の埋立て
公有水面埋立法においては、埋立ての免許に際して環境に与える影響について事前に検討することとされており、50haを超える埋立てや環境保全上特別の配慮を要する埋立てについては、主務大臣が埋立ての免許を認可するに際して環境大臣(平成12年12月までは環境庁長官)の意見を求めることとされています。平成12年度においては、常滑港等(中部国際空港等)の埋立てについて検討を行い、所要の意見を述べました。
3) 発電所の立地
発電所の立地については、環境影響評価法及び電気事業法に基づく環境影響評価が実施されています。また、電源開発調整審議会における調査審議の際には、経済産業省(平成12年12月までは通商産業省)の行った環境審査結果などをもとに環境保全についても検討が行われています。平成12年度においては、電源開発調整審議会が2回開催され、島根原子力発電所3号機、泊原子力発電所3号機等の計画について所要の調整を行いました。
4) その他
ア 市街化区域に関する都市計画
都市計画法に基づく市街化区域に関する都市計画については、あらかじめ環境大臣(平成12年12月までは環境庁長官)の意見を求めることとされており、平成12年度においても環境汚染の未然防止の観点から所要の調整を行いました。
イ 総合保養地域の整備
総合保養地域整備法に基づく基本構想の作成及び事業の実施に際しては、その内容に応じて環境保全上の観点からの検討などを行うこととされ、また、主務大臣が基本構想を同意するに際して環境大臣(平成12年12月までは環境庁長官)に協議することとされています。
(4)地方公共団体における取組
都道府県・政令指定都市の多くは、条例や要綱による独自の環境影響評価手続を設けていましたが、環境影響評価法の制定等を背景に、制度の見直しが活発に行われ、全ての都道府県及び政令指定都市において環境影響評価条例が制定されました。
条例の概要としては、環境影響評価の方法について住民等の意見を聴く仕組み(スコーピング)や、事業又は施設が都市計画に定められる場合の特例などについては、環境影響評価法と同じ手続を設けています。
また、審査会等第三者機関への諮問については、全ての団体が導入しており、事業者に事後調査を義務付けするものが多くなっています。
対象事業については環境影響評価法対象の規模要件を下回るものに加え、廃棄物処理施設やスポーツ・レクリエーション施設、畜産施設、土石の採取、複合事業なども対象としており、さらに環境基本法に規定されている「環境」よりも広い範囲の「環境」の保全を目的とし、埋蔵文化財、地域コミュニティの維持、安全などについても評価対象にするなど、地域の独自性が発揮されています(表4-1-2)。