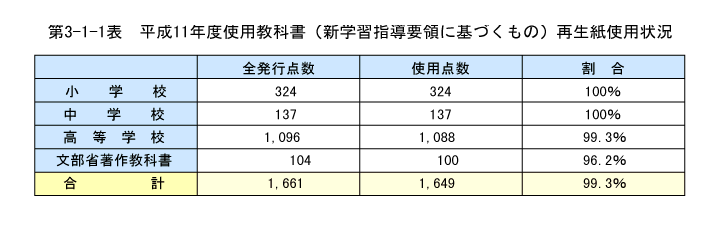
1 環境教育・環境学習の推進
(1) 環境教育・環境学習一般
近年、環境問題においては、主に日常生活や通常の事業活動に起因する都市・生活型公害や地球環境問題の比重が高まるとともに、身近な自然とのふれあいや快適な環境の保全・創造を求める国民のニーズが増大している。こうした複雑・多様化する環境問題に対応していくためには、国民一人ひとりが人間と環境との関わりについて理解と認識を深め、環境に配慮した生活・行動を行っていくことが必要である。今後は、環境基本計画を踏まえ、幼児から高齢者までのそれぞれの年齢層に対して、学校、地域、家庭、職場、野外活動の場等多様な場において互いに連携を図りつつ、環境保全に関する教育及び主体的な学習を総合的に推進することが重要である。
環境庁では、小中学生の環境に関する活動を支援する「こどもエコクラブ事業」を地方公共団体と連携しつつ実施した。平成10年度においては、約4,000クラブ、約70,000人の小中学生に対し、環境に関する分かりやすい情報の提供や、全国交流会の実施、GLOBE計画への参加支援等を行うとともに、子どもたちの活動を身近で支える大人向けの定期的な情報提供を行った。また、各種環境学習プログラム・教材の作成・提供、地方自治体向けの情報誌の作成、NGOとの連携による環境教育ワークショップ、快適環境シンポジウムの開催等、全ての年齢層に対する学習機会の提供、環境保全知識の普及・啓発に関し幅広い活動を行った。
さらに、多様な環境問題についての体験的な学習を行える現場やその相互のネットワークを整備する「総合環境学習ゾーン・モデル事業」を実施した。また、環境庁長官の諮問により、中央環境審議会において環境教育・環境学習の今後の推進方策の在り方について審議を行い、中間とりまとめを公表した。
また、環境庁と文部省は、共同で「環境教育の総合的推進に関する調査」を行うなど、関係省庁間の協力、連携を図った。
文部省では、社会教育による環境保全に関する取組として、環境問題等の各種の学習機会、実践活動の機会の提供や、環境教育に関する事業を独自に企画・開発し、社会教育施設等を中心として実施する地域社会教育活動総合事業を行う市町村に対し、必要な経費を補助した。
建設省では、川を活かした環境教育の推進を図る観点から、子どもたちの水辺での遊びを支える仕組みをつくり、自然環境あふれる安全な水辺を創出する「水辺の楽校プロジェクト」を実施した。
また、省資源・省エネルギー国民運動の推進に当たり、関係省庁により環境問題に的確に対応し、地球環境と調和したライフスタイルの形成に資するための普及啓発等を行っており、国土庁においては水資源問題についての啓発を、経済企画庁においては消費者の自主的活動の推進等を図った。農林水産省に設置されている中央森林審議会は、森林環境教育の推進等が必要であることを要旨とする「今後の森林の新たな利用の方向−21世紀型森林文化と新たな社会の創造−」を答申した。
(2) 学校教育における環境教育
学校教育においては、各教科、道徳、特別活動等の相互の連携を図りながら、学校教育全体の中で環境教育を総合的に推進するため、引き続き環境教育担当教員講習会の開催、環境のための地球学習観測プログラムモデル校の指定(19校)、環境教育推進モデル市町村の指定(8市区町村)等を行ったほか、研究協議や子どもたちの学習成果発表、大学・企業等による研究展示等を行う「環境学習フェア」を実施した。さらに、民間団体等が情報通信ネットワークを活用して学校における環境教育を援助するプロジェクトが実施されており、文部省としてもこれを支援していく。
また、環境教育の充実等を図るため、大自然の中での長期キャンプ等による青少年の野外教育をモデル的に実施する事業について、都道府県に対し必要な経費を補助している。
また、環境への負荷の低減に対応した教科書の使用、施設づくりを通じて、児童生徒の環境教育に寄与している。平成11年度に小・中・高等学校等で使用される教科書においては、99.3%の教科書に再生紙が用いられている(第3-1-1表 )。さらに、公立学校において太陽光発電等環境を考慮した学校施設(エコスクール)の整備推進に関するパイロット・モデル事業(20校)を実施した。また、国立学校施設や私立高等学校等の学校施設においても環境に配慮した施設づくりとこれを活用した環境教育を行うための整備を実施した。
(3) 広報活動
ア 一般広報
関係機関の協力によるテレビ、ラジオ、新聞、雑誌等各種媒体を通じての広報活動や、広報誌「かんきょう」の配布、広報用パンフレット等の作成・配布を通じて環境保全の重要性について広く国民に訴え意識の高揚を図った。また、報道機関に対しては、記者会見や資料配布等による発表などを通じ情報提供を行った。
イ 「環境月間の実施」
環境基本法に基づき、6月5日が「環境の日」と定められている。その趣旨は、事業者及び国民の間に広く環境の保全についての関心と理解を深めるとともに、積極的に環境の保全に関する活動を行う意欲を高めることにある。
「環境の日」を含む「環境月間」(6月)においては「地球と未来の仲間のために 暮らしを変える わたしから」をテーマとし、環境展「エコライフ・フェア」をはじめとする各種行事において、昨年に引き続き地球温暖化防止に重点を置いた様々な催し等を実施するとともに、地方公共団体等に対しても関連行事の実施を呼びかけ、環境問題に対する国民意識の一層の啓発を図った。
ウ 「環境の日のつどい」の実施
6月5日の「環境の日」には、環境保全活動を一層促進するため、「環境の日のつどい」を実施し、環境保全に功労のあった人等の表彰等を行った。