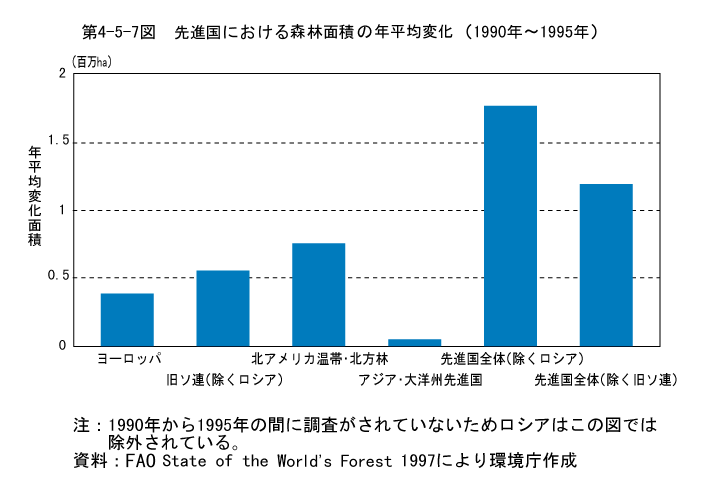
5 海外自然環境の現状
(1) 森林の現状
森林は、世界の陸地の約4分の1を占めており、1995年(平成7年)時点で34億5,400万haの森林が存在している。しかし、国連食糧農業機関(FAO)によると地球上の森林は熱帯林を主として、1990年から1995年の間に全世界で5,630万ha減少している。年平均1,130万haの森林が失われている計算になるが、これは日本の面積(3,770万ha)の約30%、本州の約半分の面積に相当する。森林面積は、1990年から1995年の間に先進国(ロシア連邦を除く)では878万ha増加しているのに対し、途上国ではこの7倍を超える6,515万ha(年平均1,303万ha)が減少している。1980年から1990年までの途上国の年平均森林減少面積は1,226万haであり、途上国での森林衰退は加速していると言える(第4-5-7図、第4-5-8図)。
途上国のなかでも特に熱帯地域で森林衰退が進んでいる。途上国の非熱帯地域における1990年から1995年の間の年平均森林減少面積が43万haであるのに対し、熱帯地域の同期間の年平均森林減少面積は1,259万haとなっている。
熱帯林減少の原因は、農地等への転用、商業伐採、過放牧、薪炭材の過剰採取、非伝統的な焼畑等が指摘されているが、こうした直接の原因の背景には途上国における貧困、人口増加、土地制度等の社会的経済的な要因がある。
熱帯林は、地球上に生存している生物の50〜80%が生息するといわれ、生物多様性の保全に重要な役割を果たしている。熱帯林の減少によりこれらの動植物種が亡びたり、種の維持が困難なほどに生息域が狭められたりすることが懸念されている。
また、熱帯林は二酸化炭素の吸収源としても重要な役割を果たしている。樹木は光合成により大気中の二酸化炭素を有機物に変え、幹や枝、葉、根をつくっている。樹木は乾燥重量の5割を炭素が占めているといわれ、森林減少による大量の二酸化炭素の放出が地球温暖化を加速させるおそれがある。
熱帯林における持続可能な森林経営の確立のために様々な国際的取組が進められている。国連食糧農業機関(FAO)は、森林・林業の分野では、?森林資源の生産力の向上と利用の促進、?森林生態系の保全、?森林・林業政策・計画作りへの助言、?林業に生活基盤をおく人々への技術支援などを目的として、森林資源評価、熱帯林行動計画、国家森林行動計画等の推進などの通常プログラムなどを実施しているほか、フィールドプロジェクトを実施している。また、国際熱帯木材機関(ITTO)は、熱帯木材貿易の安定的拡大のみならず、生態系維持の観点を含む森林の保全・開発を推進するため、森林の管理・保育等に関するプロジェクトを実施している。さらに、西歴2000年までに、持続可能な森林経営が行われている森林から生産された木材のみを貿易の対象とする、という旨を盛り込んだ国際熱帯木材協定(ITTA)を1997年1月に発効している。
我が国は、これらの国際機関の活動に協力しているほか、林業分野を中心とした2国間協力を実施しており、これまで、東南アジア、大洋州、アフリカ、中南米の開発途上国を対象に森林管理や造林技術の開発等の協力事業を実施してきている。
(2) 土壌の現状
土壌には、農業基盤、保水能力及び地下水の形成、多様な生態系の維持等の機能があり、その劣化や喪失は、人間をはじめとする生物の生存や生態系に大きな影響を与える。土壌劣化の態様には、降雨による流失や風により表土が吹き飛ばされるといった侵食、塩類集積やアルカリ化、湛水化等がある。
乾燥地における土壌の劣化や喪失等いわゆる砂漠化の問題には、気候的要因と人為的要因の二つがある。気候的要因としては、下降気流の発生や水分輸送量の減少による乾燥の進行、人為的要因としては、草地の再生能力を超えた家畜の放牧(過放牧)、休耕期間の短縮等による地力の低下(過耕作)、薪炭材の過剰な採取が考えられている。
1991年にUNEPが発表した「砂漠化の現状及び砂漠化防止行動計画の実施状況について」によると、世界には61億ha以上の乾燥地が存在し、そのうち9億haは極めて乾燥した地域、すなわち砂漠である。残りの52億haは、乾燥、半乾燥及び乾燥半湿潤地域であり、耕作可能な乾燥地である。この耕作可能な乾燥地のうち、70%の36億ha(世界の全陸地の約4分の1)が砂漠化の影響を受けており、そこでは54億人(世界人口の約6分の1)が生活している(第4-5-9図、第4-5-10図)。
大陸別に見ると、被害面積が最も大きいのはアジアであり、次いでアフリカ、北アメリカとなる。耕作可能な乾燥地に占める砂漠化地域の割合では、アフリカ(73%)、アジア(70%)の順に大きい。
こうした砂漠化問題に国際的に対処するため、1992年の地球サミットでは、アフリカ諸国を中心とする開発途上国の強い主張を背景に、アジェンダ21で、1994年6月までに砂漠化対処条約を採択することを国連総会に要請することが決定された。これを受けて、砂漠化対処条約政府間交渉会議(INCD)が設置され、1995年6月の第5回会合において砂漠化対処条約が採択された。この条約は1996年12月に発効し、1997年9月に第1回締約国会議が開催された。我が国は1998年(平成10年)9月に本条約を受諾し、同年12月、同条約は我が国について発効した。平成10年12月末の締約国は145ヵ国である。
我が国では、砂漠化対処の取組として、政府開発援助(ODA)による砂漠化の現状の把握と対策のための調査、技術面での協力、資金の貸付などの形で支援を行っている。また、砂漠化のメカニズム、乾燥地での農業の方法、水の有効利用の方法等について調査・研究を行っている。
(3) 国際的に高い価値が認められている環境の現状
世界遺産条約に基づき、観賞上・学術上または保存上等の見地から顕著な普遍的価値を有する自然の地域は、人類共通の財産として世界遺産一覧表の自然遺産に記載し、良好な自然状態が十分保護されるような措置がとられている。我が国では、平成5年12月に、繩文杉に代表されるヤクスギ巨木群等の特殊な植物相を誇る鹿児島県の屋久島地域と原生的なブナ天然林を有し希少な鳥類が生息する青森県と秋田県にまたがる白神山地地域が世界遺産一覧表の自然遺産に記載された。自然遺産に記載されている地域は、アメリカのイエローストーン国立公園、オーストラリアのグレート・バリア・リーフ、エクアドルのガラパゴス諸島国立公園等、1998年(平成10年)12月時点で137地域である(自然遺産と文化遺産の双方に該当する複合遺産20地域を含む。)。
南極地域には、過酷な自然環境とそれに適応した特殊で脆弱な生態系が成立しており、地球環境のモニタリング等の観点からも、人為による汚染の極めて少ないその環境の重要性が注目されている。南極地域は、1961年に領土権の凍結、軍事利用の禁止、科学観測のための国際協力を目的とする「南極条約」が発効し、以来科学観測の場として利用されている。しかし、基地活動や観光利用の増加による環境影響も懸念されている。このため、南極地域の環境の包括的な保護を図るための「環境保護に関する南極条約議定書」が1991年に採択され、1998年1月に発効した。我が国でも「南極地域の環境保護に関する法律」が制定され、南極地域での活動の環境への影響等について事前に審査する南極地域活動計画の確認制度を設けるとともに、鉱物資源活動や動植物の採捕の制限等について定めている。