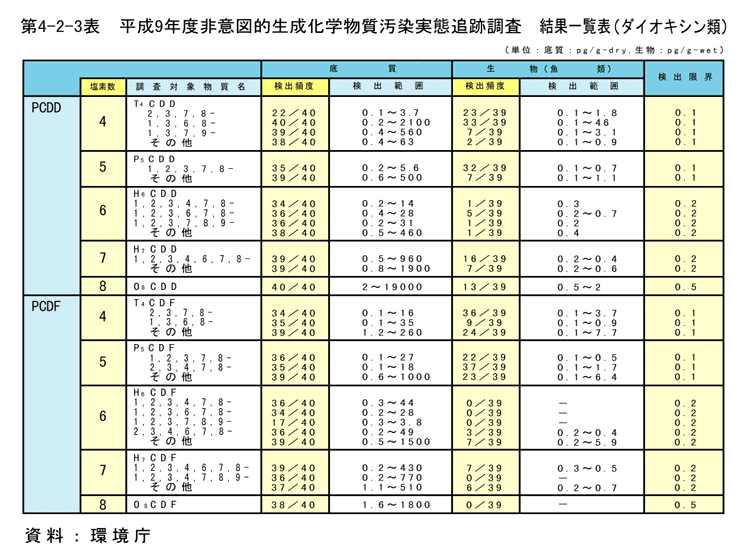
5 化学物質の水環境中の残留状況
環境中の化学物質等は環境や人体への影響を考慮し適正な管理がされなければならない。水環境に関しても、効果的な監視体制を整備し、様々な調査を行っている。
一般環境中に残留する化学物質の早期発見及びその濃度レベルの把握を目的とした、平成9年度の水質及び底質の化学物質環境調査結果によると、水質の調査対象14物質のうち2物質が、底質の調査対象13物質のうち3物質が検出された。これらのうち塩化ビニルは、水質と底質双方から検出されており、今後さらに推移の監視と詳細なリスク評価の必要があると考えられる。また、ノニルフェノールは、底質から検出され、検出頻度は高いことから、今後より詳細な環境調査を行いその推移を監視することが必要である。その他の検出された物質についても、検出頻度や濃度に応じた対応が必要と考えられる。
環境調査の結果等により水質と底質への残留が確認されている化学物質について、残留による環境汚染の経年監視を行うため、水質・底質のモニタリングを実施している。調査の結果、対象20物質のうち、水質から5物質、底質から20物質全てが検出された。底質からの検出状況は水質に比べ全体的に高かった。また、調査対象物質毎の最高値を記録した地点をみると、大和川河口(8物質)、洞海湾(6物質)、大阪港(3物質)及び隅田川河口(3物質)であり、閉鎖性水域の内湾部の汚染レベルが高いことが示唆される。
非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査においても底質についてダイオキシン類等調査を行った(第4-2-3表)。ダイオキシン類の調査は、ポリ塩化ジベンゾ-p-ジオキシン(PCDD)13種類とポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)15種類について、昭和60年度から継続調査をしている。底質では全般に高い頻度で検出されており、特に湖沼及び海域での検出頻度が高かった。ダイオキシン類による汚染状況は前年度までと比較して大きく変化したとは認められないが、広範囲に検出されているため、今後も推移を監視していく必要がある。また、ダイオキシン類の発生源や環境中挙動等の汚染機構の解明に努めるほか、内分泌攪乱化学物質の疑いがあるとの指摘があることから、関連の情報も含め毒性関連知見の収集に努めることも必要である。