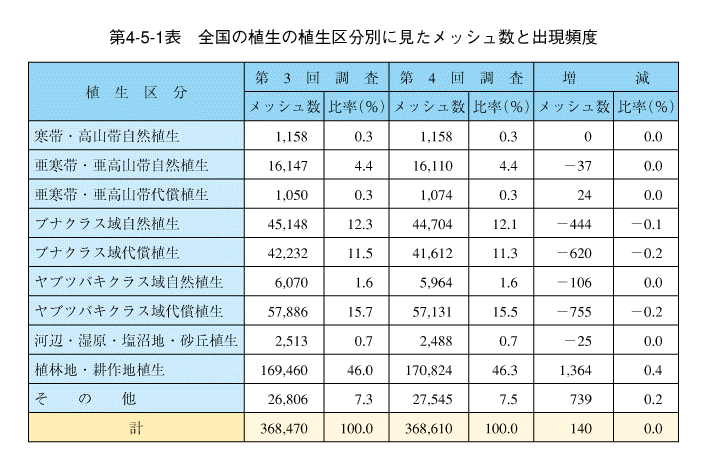
1 陸域に関する調査
(1) 植生調査
植生は一般に時間を経るに従って変化し、最終的に安定的な生態系である極相となる。日本の気候では、?南西諸島から東北南部に広がる、タブ・カシ類・シイ類といった常緑広葉樹(照葉樹)の森林、?九州南部から北海道南部までの、常緑広葉樹林よりは寒冷な地域に広がるブナ林などの落葉広葉樹の森林、?北海道に広がるエゾマツ、トドマツといった針葉樹とミズナラ等の落葉広葉樹の混成する針広混交林、?エゾマツ、トドマツ林に代表される亜寒帯針葉樹林などが代表的な気候的極相である。日本を代表する自然性の高い地域ではこうした極相の植生が見られるが、その地域は必ずしも多くはない。
第4回の調査は、人工衛星画像の解析と各都道府県への委託により第2回及び第3回の調査結果から修正必要箇所を抽出し、集められた植生の情報を約一平方キロの3次メッシュ毎の数値情報に置換し、行われた。解析は、植生帯及び自然植生と代償植生との別に分類した植生区分と、植生への人為の加わり度合いにより分類した植生自然度区分の二つの方法によった。(第4-5-1表、第4-5-2表、第4-5-2図、第4-5-3図)
植生区分別の分析
森林、草原、農耕地等何らかの緑で覆われた地域は、全国土の92.5%に達する。中でも森林は67.1%であり、アメリカ合衆国(32.6%)、イギリス(10.4%)、フランス(27.4%)、ドイツ(29.9%)、カナダ(45.3%)(海外の数値はOECD環境データによる1995年時点のもの)に比較しても高い水準である。自然植生は、自然草地、自然林の合計で19.1%である。このうち2分の1以上にあたる58.8%が北海道に分布している。一方近畿、中国、四国、九州地方では、小面積の分布域が山地の上部や半島部、離島などに点在しているにすぎない。
総体としては、自然度の高い植生(自然草原、自然林、自然林に近い二次林)、人為の影響を受けた植生(二次林、二次草原)、人為的に成立した植生(植林地)、土地改良の進んだ植生(農耕地、市街地、造成地等)が、調査時点では、ほぼ4分の1ずつ占めている。しかし、第3回調査との比較から、自然林、二次林は減少し、植林地、市街地、造成地等は増加する傾向があり、現時点でもこの傾向は続いていると推測される。
(2) 動物分布調査
動物相に関して日本列島は、鹿児島県の屋久島・種子島と奄美大島との間に渡瀬線という動物の分布境界線が引かれており、動物地理区上大きく二分されている。この渡瀬線より北は旧北区、南は東洋区と呼ばれているが、旧北区である本州以北に生息する大部分の日本の動物は、例えばトガリネズミ類、リス類、イタチ類などは中国華中以北のユーラシア大陸に生息する動物との類縁性が高く、東洋区である奄美・琉球諸島の動物、例えばケナガネズミなどは、台湾や東南アジア諸国に近縁種が多く生息する。また、島国という地理的特徴から隔離効果により、ヒミズ、ヤマネ、アマミノクロウサギの様な固有種も多数存在する。そのほかに動物の分布境界線としては、北海道と本州の間に位置するブラキストン線などがある。(第4-5-4図)
動植物調査の一環としては、鳥類の生息地を対象に、これらの分布と生息環境の調査を実施した。調査は集団繁殖地や集団ねぐらをつくる習性がある日本産鳥類22種について行われた。一般に、集団繁殖地や集団ねぐらを形成する鳥類は、その集合性からより正確な生息状況の把握が可能となる。また、それらの生息地の環境変化は個体群全体に大きな影響を持つため、生息環境の調査は環境上大きな意味を持つ。ここでは、コサギ、イワツバメの2種類を紹介する。(第4-5-5図)
コサギは、一般に「しらさぎ」と称される全身白いサギのうち、一番小型のものである。ダイサギ、ゴイサギ等と複数種で集団繁殖することも多く、本州から九州にかけて分布が認められた。生態系の捕食者側であるサギ類の集団繁殖地は、営巣環境と採食環境が共に残された豊かな自然を示している。
イワツバメは、尾の切れ込みが浅く腰部の白い小型のツバメである。九州以北の全国に分布し、海岸や山地の岩の窪み等に巣を作るが、近年は平地の市街地にも多くなっている。調査の集団繁殖地は、ほとんどが建築物のコンクリートの壁面につくられており、50巣以下の小規模のものであった。また、過去の情報と比較して分布域の変化は明らかではなかった。