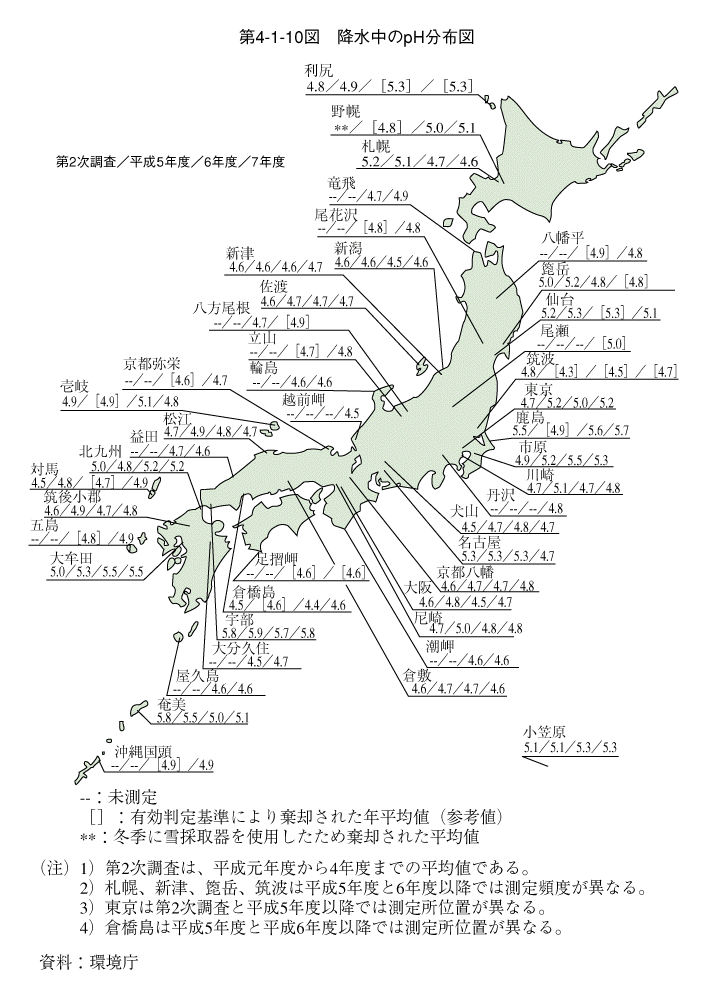
2 移流・反応等により生ずる広域的な問題
酸性雨、光化学オキシダント等は、大気環境への負荷の移流・反応等により生ずる広域的な問題である。現在のような酸性雨が今後も続けば、将来、生態系への影響をはじめ、様々な被害が生じるおそれがある。
(1) 酸性雨
酸性雨とは、硫黄酸化物(SOx)や窒素酸化物(NOx)などの大気汚染物質が変化した硫酸塩や硝酸塩を含んでいると考えられる酸性の強い雨の事である。広義には、霧、雪などの湿性沈着(wetdeposition)、ガスやエアロゾルの乾性沈着(dry deposition)の形態も酸性雨に含まれる。
酸性雨は、?湖沼等の酸性化により底質の有害な金属を溶出させ、魚を死滅させる等の水界生態系への影響、?土壌の酸性化により樹木の成長を妨げ枯死させる等の森林への影響、?酸によって腐食する大理石や金属等で造られた建造物、特に歴史的な遺跡や石像等の被害が懸念されている。欧米ではすでに、酸性雨によると考えられる湖沼の生態系への悪影響や森林の衰退等の深刻な被害が報告されている。
酸性雨は、SOx、NOx等の発生源から数千kmも離れた地域にも発生することがあり、国を越えた広域的な現象という特徴がある。酸性雨は、従来、先進国の問題とされてきたが、近年、開発途上国においても工業化の進展により大気汚染物質の排出量は増加しており、大きな問題となりつつある。
平成5年度から7年度までの第3次酸性雨対策調査の中間取りまとめによれば、調査期間中の降水中のpHは4.8〜4.9(年平均値の全国平均値)と、第2次調査の結果とほぼ同じレベルの酸性雨が観測され、これまで森林、湖沼等の被害が報告されている欧米と比べてもほぼ同程度の酸性度であった(第4-1-10図)。また、日本海側の離島測定局で冬季に硫酸イオン濃度の上昇が認められ、季節風による大陸からの影響が示唆された。一方、原因不明の樹木衰退が見られた地点及び酸性の強い土壌が前回に引き続き確認されるとともに、アルカリ度の低い湖沼が確認された。さらに、湖沼の酸性化の予測シミュレーションモデルを構築し、日本の湖沼の平均的なアルカリ度よりやや大きい値を示す鎌北湖(埼玉県)について、一定の条件を設定して酸性化が始まる年数の予測を行ったところ、早い場合で概ね30年後との結果が得られた。このように、我が国における酸性雨による生態系への影響は現時点では明らかになっていないが、現在のような酸性雨が今後も降り続けば、将来影響が現れる可能性もある。また、東南アジアでは、経済発展に伴い硫黄酸化物、窒素酸化物の排出量が増大しており、酸性雨による悪影響の未然防止のための国際的取組を進めることが急務となっている。
このため、環境庁では、「東アジア酸性雨モニタリングネットワーク構想」を提唱し、平成10年3月には第1回政府間会合を開催した。会合では、ネットワークの具体的な活動について検討が行われ、2000年に予定されるネットワークの正式稼働に向けて試行稼働を平成10年4月から実施すること等が取りまとめられた。
(2) 光化学オキシダント
光化学オキシダントは、工場や自動車から排出される窒素酸化物(NOx)や炭化水素類(HC)を主体とする一次汚染物質が、太陽光線の照射を受けて光化学反応により二次的に生成されるオゾンなどのことであり、いわゆる光化学スモッグの原因となる。光化学オキシダントは強い酸化力をもち、高濃度では粘膜への刺激や呼吸器へ影響を及ぼし、農作物などへも影響する。
光化学オキシダントについては、「1時間値が0.06ppm以下であること」という環境基準(人の健康を保護するうえで維持されることが望ましい基準)が設定されている。光化学オキシダント濃度の1時間値が0.12ppm以上で、気象条件から見てその状態が継続すると認められるときは、「大気汚染防止法」の規定によって、都道府県知事等が光化学オキシダント注意報を発令し、報道、教育機関等を通じて、住民、工場・事業場等に対して情報の周知徹底を迅速に行うとともに、ばい煙の排出量の減少または自動車の運行の自主的制限について協力を求めることになっている。
平成9年の光化学オキシダントの注意報発令延日数は平成8年の99日から95日へ、光化学大気汚染によると思われる被害届出人数は平成8年の64人(5県)から315人(5府県)となった(第4-1-11図)。地域別には、首都圏地域及び近畿圏地域に注意報の発令が集中している(第4-1-12図)。また、平成9年は、警報(各都道府県が独自に要綱等で定めているもので、一般的には、光化学オキシダント濃度の1時間値が0.24ppm以上の場合に発令)の発令はなかった。