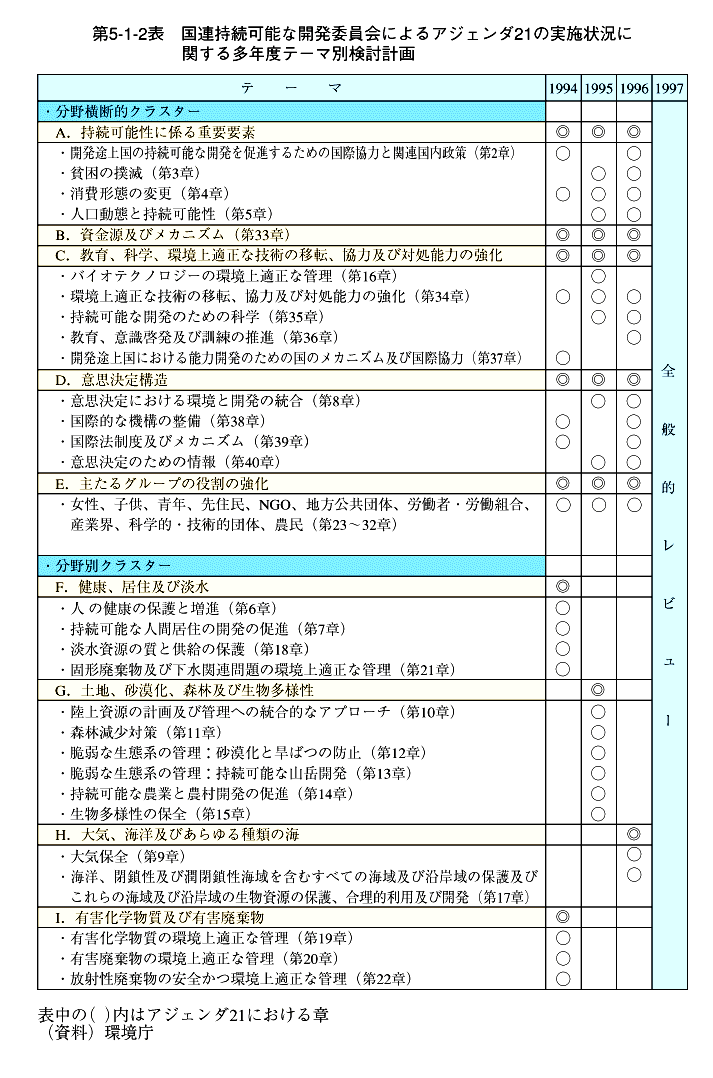
1 地球環境保全に関する国際的な連携の確保
(1) 国際機構等による連携
ア 地球サミットのフォローアップ
(ア) 国際的な取組
a 持続可能な開発委員会(CSD)
平成4年の地球サミットにおいて採択されたアジェンダ21第38章に基づき、平成5年の第47回国連総会における設立の決議を経て、平成5年2月国連経済社会理事会の下部組織として「持続可能な開発委員会」(CSD)が設立された。
CSDは我が国を含めた国連加盟国53か国から成り、その主要目的は、?アジェンダ21及び環境と開発の統合に関する国連の活動の実施状況の監視、?各国がアジェンダ21を実施するために着手した活動等についてまとめたレポート等の検討、?アジェンダ21に盛り込まれた技術移転や資金問題に関するコミットメント(約束)の実施の進捗状況のレヴュー、?リオ宣言及び森林原則声明に盛り込まれた諸原則の推進、?アジェンダ21の実施に関する適切な勧告の経済社会理事会を通じた国連総会への提出等である。
第1回会合は、平成5年6月に開催され、平成9年に開催が予定されている国連環境開発特別総会に向けて、アジェンダ21の実施状況について総括的な評価を行うとの「多年度テーマ別検討計画」が決定された(第5-1-2表)。
平成8年4月、第4回会合が、メンバー国53か国(内約50か国より閣僚レベル)及び非メンバー国他の多数の参加を得て開催され、「多年度テーマ別検討計画」に従い、分野横断的なテーマとして、貿易と環境、資金、技術移転、持続可能な消費パターン等、分野別のテーマとして、大気保全及び海洋保全についての検討が行われ、今後の行動のための提案を含む23の決定及び閣僚クラスのハイレベル会合の「議長総括」を採択した。
b 持続可能な開発に関する高級諮問評議会
科学分野も含め、環境と開発に造詣の深い有識者により構成される「高級諮問評議会」の設置につき、アジェンダ21の第38章(国際的な機構)において、事務総長が国連総会に対し勧告を行うこととされた。
これを受け、平成5年7月、国連事務総長より高級諮問評議会の設置が発表され、9月には第1回会合が、平成8年1月には第7回会合が開催された。
c 国連環境開発特別総会
アジェンダ21において、1997年(平成9年)までにアジェンダ21の全般にわたる審査と評価を目的とした特別総会の開催を検討するとされたことを受け、平成8年12月の国連第51回総会において平成9年6月に国連環境開発特別総会を開催することが決議された。特別総会に向けて地球サミット以降5年間の実施状況を総括するための取組が進められており、平成9年4月に開催されるCSD第5回会合が最終的な準備会合とされている。
(イ) アジア・太平洋地域における取組
a アジア・太平洋環境会議(エコ・アジア'96)
環境庁は、平成8年5月26日、27日に群馬県水上町において、「エコ・アジア'96」を開催した。エコ・アジアはアジア太平洋地域諸国の環境担当大臣を含む政府関係者、国際機関、民間団体、学識経験者等が、ハイレベルの有識者としての立場で参加し、自由に意見の交換を行う機会を提供することにより、域内各国政府の長期的な環境保全に係る取組を推進し、同地域の持続可能な開発の実現に資することを目的としたものであり、平成3年以降、平成4年を除き毎年開催されてきている。
「エコ・アジア'96」は、域内12か国の環境担当大臣を含む20か国の政府高官及び10国際機関の代表者を始めとする多数の参加を得て開催された。会議においては、「アジア太平洋地域の環境と開発に関する長期展望プロジェクト」最終報告書案について概ね意見の一致が見られたほか、「アジア太平洋環境情報ネットワーク(エコ・アジア・ネット)プロジェクト」、こどもエコクラブのアジア地域への普及等の取組の実施が支持された。
b 環日本海環境協力会議
北東アジア地域の環境問題に関する環境行政レベルでの情報交換及び政策対話を行い、アジェンダ21で強調されている地域協力の促進を図るため、平成4年より毎年、「環日本海環境協力会議」が開催されている。
平成8年10月中国北京にて開催された第5回会議では、環境に関する政策、法律、管理等の動向、固体廃棄物管理及び廃棄物違法越境移動防止、クリーナープロダクション及び総合的な汚染対策、地球環境問題及び生物多様性保全について活発な議論が行われた。
c こどもエコクラブアジア会議
環境庁は、平成8年11月2日、3日に新潟県において「こどもエコクラブアジア会議」を開催した。本会議は、平成7年6月より環境庁の提案により全国に発足した「こどもエコクラブ」のメンバーと、アジア各国で環境保全活動を行っている子供たちの交流の促進を図るとともに、これらの国々において子供たちの環境保全活動を支援する政府・NGO関係者が、そうした活動の普及・推進方策について情報交換するために開催したものである。
本会議では、アジア8か国の子供たちによる環境保全への取組の報告を中心としたシンポジウムのほか、9か国の政府・NGO関係者による会議が行われ、子供の環境保全活動が将来の環境保全の鍵となるとの共通の認識の下に、今後の更なる情報交換を進めること等につき意見の一致を見た。
d アジア太平洋地球変動ネットワーク(APN)
アジア太平洋地域における地球環境問題に関する研究計画を支援し、地域的協力の推進等を行うために設けられたAPNについては、我が国は事務局として積極的に活動を支援してきた。平成9年3月には、東京において「第2回科学企画グループ会合」及び「第2回政府間会合」が開催され、今後2年間の科学的活動等について検討がなされた。
(ウ) 国内における取組
a 「アジェンダ21」行動計画の実施
アジェンダ21の国別行動計画については、地球サミットにおいて採択されたアジェンダ21においてその準備及び検討が示唆されており、平成4年のミュンヘン・サミット及び平成5年の東京サミットにおいて、平成5年末までに策定し、公表することとされた。
これを受け、政府は平成5年12月に開催された地球環境保全に関する関係閣僚会議において「『アジェンダ21』行動計画」を決定し、CSD事務局に提出した。
この「『アジェンダ21』行動計画」は、「アジェンダ21」の章立てに応じたプログラム分野ごとに我が国が今後実施しようとする具体的な事項を行動計画としてとりまとめたものである。本行動計画にのっとり、持続可能な開発の達成に向けた種々の取組がなされている。
b ローカルアジェンダ21
アジェンダ21においては、その実施主体として地方公共団体の役割を期待しており、地方公共団体の取組を効果的に進めるため、ローカルアジェンダ21を策定することを求めている。環境庁は、ローカルアジェンダ21の策定のための指針を作成するために「ローカルアジェンダ21策定指針検討会」を発足させ、検討を進めてきたが、平成6年6月に「ローカルアジェンダ21策定に当たっての考え方」として指針を取りまとめ、公表した。また、平成7年6月には、地域の環境計画づくりを通じて得られてきたこれまでの経験では必ずしも十分でないと思われる配慮事項やポイントを特に重点的に取りまとめた「ローカルアジェンダ21策定ガイド」を公表した。
イ 国連における活動
国連環境計画(UNEP)は、昭和47年にストックホルムで開催された国連人間環境会議を契機に、既存の国連システム内の諸機関が行っている環境関係の諸活動を一元的に調整し、かつ、これら諸機関等の環境保全分野での活動を促進することを目的として創設された。UNEPが実施するプログラムは、従来、地球環境監視、環境法、陸上生態系等の12分野から構成されていたが、平成7年5月の第18回管理理事会において、横断的な構造の5分野(自然資源の持続可能な管理と利用、持続可能な生産と消費、健康と福祉のためのより良い環境、地球規模化と環境、地球的及び地域的レベルの支援措置)での計画が採択され、抜本的な再編成が実施された。
UNEPに対して、我が国は、創設当初から管理理事国として、UNEPの管理理事会に参画するとともに、環境基金に対し、平成8年度は900万ドルを拠出する等多大の貢献を行ってきた。
また、平成4年10月に、UNEPの内部機関であるUNEP国際環境技術センターが、日本で初めての環境関係の国連施設として、大阪市及び滋賀県に開設された。同センターは、開発途上国等への環境上適正な技術の移転を目的とし、淡水湖沼集水域の環境管理の技術分野を担当する滋賀事務所と、大都市の環境管理を中心とした技術分野を担当する大阪事務所とから構成され、環境保全技術に関するデータベースの整備、情報提供、研修、コンサルティング等の業務を行っている。
国連アジア・太平洋経済社会委員会(ESCAP)においては、平成4年に設置された「環境と持続可能な開発委員会」の第3回会合が平成8年10月に開催され、アジェンダ21のフォローアップ等について討議された。
平成8年6月、トルコのイスタンブールにおいて、国連主催による国連人間居住会議(HABITAT?)が開催された。本会議では「すべての人に適切な居住を」及び「都市化する世界における持続可能な人間居住開発」の2つの基本課題が設定され、会議の成果としては、これらの課題に対処するため、人間居住に関する目標・原則、公約及び世界行動計画が盛り込まれた「ハビタット・アジェンダ」並びに「人間居住に関するイスタンブール宣言」が採択された。
また、東京に本部をおく国連大学(UNU)では、平成9年3月に、IPCC及び日本政府と共催して、「IPCC統合評価モデルに関するアジア太平洋地域ワークショップ」を開催するなど環境問題に対する取組を行っている。
さらに、国連教育科学文化機関(UNESCO)においても、「環境・人口教育と開発のための情報」プロジェクトを重点的に推進している。また、我が国は、UNESCOが実施する海洋学、生態学、水文学等の地球環境科学に関する調査・研究・訓練事業に協力して、平成8年度においては総額21万ドルの信託基金を拠出し、事業の推進に貢献した。
ウ 経済協力開発機構(OECD)及び国際エネルギー機関(IEA)における活動
OECDは、先進工業国間の経済に関する国際協力機関であり、平成9年3月31日現在29か国が加盟している。最高意思決定機関は理事会であり、毎年1回閣僚レベルの閣僚理事会が開催される。
1960年代末の全世界的な環境問題への関心の高まりを反映し、1970年(昭和45年)7月環境委員会が設置され、1992年(平成4年)3月には、一部改組の上、環境政策委員会へと名称が変更された。
環境政策委員会では、各加盟国政府が環境政策を企画立案する上で重要と思われる問題について検討が行われる。その結果は必要に応じて理事会においてOECD決定あるいは勧告として採択されるほか、調査、研究等の成果がレポートとして公表され広く活用されており、汚染者負担原則(PPP)の確立・普及等の成果を生んできている。
また、近年はOECDのその他の委員会においても各々の視点から環境問題が横断的に取り上げられてきている。さらに、環境政策委員会と他の各委員会との合同の作業も増加しており、例えば、貿易委員会との間では「貿易と環境」に関する合同専門家会合が、農業委員会との間では「農業と環境」に関する合同専門家会合が設置されており、分野横断的な検討を行っている。環境政策委員会では、おおむね5年に1度閣僚レベルの会議を開催しており、平成8年2月に開催された第5回環境政策委員会閣僚会議では、「地球規模化時代の環境政策」という全体のテーマのもと、過去のOECD諸国における環境政策のレビューと、21世紀に向けて各国が共通して抱える課題について討議が行われ、コミュニケとして発表された。
さらに、気候変動枠組条約に基づく議定書交渉の進展に寄与するため、OECD/IEAコモンアクション・プロジェクトとして、先進国間で共通に取り得る費用効果にすぐれた温室効果ガス排出抑制や吸収源強化のための政策・措置について分析・評価が進められている。また、平成7年3月から4月の気候変動枠組条約第1回締約国会議において、OECD/IEA加盟24か国が提示した気候変動技術イニシアティブ(CTI)については、平成8年2月、その具体化を進めるためのタスク・フォースの設立が合意され、我が国は二酸化炭素の固定化等の革新的技術開発についてのタスク・フォースのリーダー国として、本分野での国際協力の促進をリードしている。
エ 世界貿易機関(WTO)における取組
(ア) 世界貿易機関(WTO)貿易と環境委員会の取組
平成7年にWTOの下に設置されて以来、環境と貿易に関する国際的な議論の中心的なフォーラムと見られてきたのは、WTO貿易と環境委員会(CTE)である。すべてのWTO加盟国から構成されるCTEは、平成8年12月、WTO設立後初めて開かれるシンガポール閣僚会議に提出される報告書において、環境保全の観点からWTO諸協定の改正が必要か否か等について結論・勧告を出すこととされていた。CTEにおいては、EUや我が国などがシンガポールで実質的成果をあげることを重視する立場をとったのに対し、シンガポールまでに性急に結論を急ぐべきではないとする立場が途上国だけではなく一部先進国からも表明されたこともあり、作業は難航し、結局、CTE報告書は法的拘束力のない政策声明(policystatement)として全会一致で採択されたが、主要な検討課題で論点を整理しているものの、対立した論点の多くでは結論を出さず両論が併記された形となっている。
このような結末となった直接の原因は、モントリオール議定書といった多国間環境協定(MEA)に基づく貿易措置とWTO協定の関係やエコラベルといった検討事項での成果を優先すべきとする先進国側と、先進国の関心事項のみを優先することに反対する途上国側の対立が最後まで解消されなかったことにあるが、地球環境問題への取組を重視する先進国と、環境を口実にした保護貿易を懸念する途上国の間の立場の違いが大きかったことや、アメリカのとる一方的貿易措置に対する懸念が払拭されていなかったことも合意形成の障害となったことが指摘できる。我が国は、CTEにおける先進国と途上国の溝を埋めCTEの合意形成に資するために、平成8年5月のCTE会合でMEAに基づく貿易措置とWTO協定の関係について法的拘束力のないガイドラインを提案したが、他の主要提案と同じく全体の流れを変えるには至らなかった。
(イ) CTE報告書の主要点
CTE報告書は、貿易自由化が環境に及ぼす影響については、貿易自由化は環境及び開発にとって利益をもたらしうるが、これらの利益が実現するためには、国内の適切な環境政策が実施されることが重要であるとしてアジェンダ21を基本的に踏襲する立場を示した。しかし、具体的に適切な環境政策とは何を意味するのか、実際に適切な環境政策がとられていない場合にはどうすべきか、個別分野で具体的に貿易の自由化が環境にどのような影響を与えるかといった論点については今後の作業にゆだねられることとなった。
自国の管轄外の環境問題に対処するための一方的貿易(制限)措置については、WTO協定上許容されるか否かについてCTEにおいては結論は出ず、CTE報告書は地球サミットにおいて採択されたリオ宣言第12原則(可能な限り避けるべきである)に留意するにとどまっている。また、MEAに基づく貿易(制限)措置を正当化するためにWTO協定(特にGATTの一般的例外規定である第20条)の改正が必要かどうかについては、報告書は、結論は出なかったとしているが、同時に、GATT第20条等のWTO協定の諸規定がMEAに基づくものを含めて環境目的の貿易関連措置を許容しうる、また、そのような許容性が重要であり維持されるべきであると述べている。
エコラベルについては、CTE報告書は、エコラベルは環境政策上重要な役割を果たしうるが、不必要な貿易制限効果を避け、透明性を確保することが重要としている。しかし、任意のエコラベルにWTO協定が適用されるか否かについて結論は出なかった。
オ アジア・太平洋経済協力(APEC)における環境問題への取組
アジア・太平洋地域の経済問題に関する協議システムであるアジア・太平洋経済協力(APEC)は、平成8年11月にフィリピンのマニラで第8回閣僚会議、スービックで第4回非公式首脳会議を開催し、「首脳宣言」、「閣僚共同声明」、「APECマニラ行動会議(MAPA)」及び「経済協力・開発の強化に向けた枠組みに関する宣言」を採択した。この4つの文書は、いずれもAPECにおける持続可能な開発の取組の重要性を指摘している。とりわけ、「経済協力・開発の強化に向けた枠組みに関する宣言」では、経済・技術協力を進める上で、各メンバーは、環境と経済成長を調和したものにする責任があることが明記された。
このほか、平成8年7月には、マニラでAPEC持続可能な開発大臣会合が開催され、持続可能な開発にかかる主要テーマとして、「持続可能な都市」、「クリーンテクノロジー/クリーンプロダクション」及び「海洋環境の持続性」の3つについて議論が行われた。
環境に配慮した活動の一つとして、我が国より提案した「APEC環境技術交流バーチャルセンター」を推進するため、平成8年11月に大阪でAPEC環境技術交流促進シンポジウムを開催した。
カ 先進国首脳会議(サミット)における環境問題への取組
昭和56年のオタワ・サミット以来、経済宣言において環境問題が取り上げられてきているが、特に平成元年のアルシュ・サミット以降地球環境問題が重要な課題として位置付けられていることが大きな特色である。
平成8年6月のリヨン・サミットでは、環境の保護は持続可能な開発を促進する上で決定的に重要であるとされ、環境保護をすべての政策に一層統合していくことが確認された。平成9年は環境にとって極めて重要な年であり、国連環境開発特別総会や地球温暖化防止京都会議の成功に向けて力強い行動をとっていくことが約束された。また、環境悪化による健康への影響に対する健全な科学と予防原則に基づいた措置の必要性、CSDとUNEPの役割分担の明確化及び環境と貿易の相互支持化といった、G7サミットに先立ち平成8年6月にカブール(フランス)においてフランスが開催したG7環境大臣会合において討議された結果についても確認された。
(2) 2国間の枠組みによる連携
ア 環境保護協力協定に基づく取組
(ア) 米国
昭和50年8月に日米環境保護協力協定が締結されて以来、同協定に基づき広範な環境問題を討議するため、閣僚レベルによる合同企画調整委員会を過去10回開催している。第10回委員会は、平成6年11月東京で開催され、両国にとって関心の深い地球環境問題等について意見交換が行われた。
また、同協定に基づき、現在17のプロジェクトが設置されており、情報交換、会議の開催、専門家の交流が進められている。
(イ) ロシア
平成3年4月に、日ソ環境保護協力協定が締結された。平成6年1月東京において、同協定に基づく合同委員会が開催され、両国の環境政策、地球環境問題等について活発な議論が行われた。
(ウ) 韓国
平成5年6月に締結された日韓環境保護協力協定に基づく第3回日韓環境保護協力合同委員会が、平成8年3月に東京で開催され、「東アジアにおける大気中の酸性・酸化性物質の航空機・地上観測」等の既存案件の継続と「先端産業関連物質の環境影響に関する共同研究」等6件の新規案件の実施について意見の一致を見た。
(エ) 中国
平成6年3月に締結された日中環境保護協力協定に基づく第2回日中環境保護合同委員会が、平成8年12月に中国の北京で開催され、両国間の協力が一層促進されるよう努力することにつき意見の一致が見られたほか、既存の14件のプロジェクトに加え、新たに6件のプロジェクトを実施することについて意見の一致を見た。
イ 科学技術協力協定に基づく取組
(ア) 米国
昭和63年6月に締結され、平成5年6月に単純延長された日米科学技術協力協定の下、閣僚級の合同高級委員会がこれまで6回開催された。第6回委員会は、平成8年5月ワシントンにて開催された。
同協定の附属書?においては、七つの主要協力分野が挙げられており、このうち「地球科学及び地球環境」分野においては現在76プロジェクトの実施につき意見の一致を見、共同研究等を行っている。
(イ) カナダ
昭和61年に締結された日加科学技術協力協定に基づき、これまで合同委員会が5回開催され、環境分野における協力が進められている。同協定の下に「北太平洋における地球科学・環境パネル」が設置され、第1回会合が平成8年2月に開催されるなど、協力が進められている。
(ウ) 英国
平成6年6月に締結された日英科学技術協力協定に基づき、第1回合同委員会が平成7年12月に開催された。同協定の締結により、これまでの科学技術協力に基づく研究協力等がより一層推進されることとなった。
(エ) ドイツ
昭和49年に締結された日独科学技術協力協定に基づき、「環境保護技術パネル」が設置され、昭和51年以来15回パネル会合が開催されるなど協力が行われている。平成8年2月に第16回会合が東京で開催され、協力プロジェクトについて意見交換が行われた。
(オ) ロシア
昭和48年に締結された日ソ科学技術協力協定の下、ソ連と継続性を有する同一の国家であるロシアとの間で第3回委員会が平成7年7月に開催された。同協定に基づき、「バイカル湖における地球環境変遷史の復元」等のテーマについて協力が進められている。
(カ) 中国
昭和55年に締結された日中科学技術協力協定に基づき、これまで合同委員会が7回開催され、環境分野における協力が進められている。
(キ) その他
上記のほか、フランス、イタリア、オーストラリア、インド、イスラエル等と、科学技術協力協定に基づく協力プロジェクトを通じ、環境分野の国際協力を実施している。
ウ その他の活動
(ア) コモン・アジェンダ(地球的展望に立った協力のための共通課題)
平成5年7月に行われた日米首脳会談は、環境問題等の21世紀の課題に対処する方策を模索する場として「コモン・アジェンダ(地球的展望に立った協力のための共通課題)」を打ち出し、その枠組みの中で「地球環境の保護」等5つの柱の下で協力を行うことにつき意見の一致が見られた。地球環境の保護については、定期的協議のための「次官級フォーラム(環境政策対話)の創設」及び「保全」、「森林」等の7つの優先課題が合意された。
平成5年9月にワシントンにおいて第1回全体会合が開催されて以来、現在までに6回の全体会合が開催されており、環境をはじめとする協力分野について協議が行われた。また、環境政策対話は、これまでに4回開催され、地球環境問題を中心に協議が行われた。
平成6年5月に開催された第3回全体会合においては、新たな協力分野として「珊瑚礁」、「地球変動研究ネットワーク」等の4分野が追加された。平成8年6月に東京において第6回会合が開催され、地球環境の保護等について協議が行われた。
(イ) 天然資源の開発利用に関する日米会議(UJNR)
天然資源の開発利用に関する日米会議(UJNR)は昭和39年に設置され、第15回全体会議が平成8年9月につくば市で開催された。UJNR傘下の保全・レクリエーション・公園専門部会においても、情報交換等を引き続き行った。
(ウ) 日・EU環境高級事務レベル会合
平成3年7月に出された日・EC共同宣言において、環境分野における日本とEC間の協力の必要性が強調された。これを受けて、平成4年以降5回の会合が開催された。第5回会合は、平成8年5月東京にて開催され、環境分野における日・EU間の協力が着実に進展している。
(エ) 日加環境政策協議
平成7年8月に来日したコップス・カナダ副首相兼環境大臣から、大島環境庁長官(当時)に両国間の環境政策対話の場の設置について提案がなされた。
これを受けて、平成8年3月、第1回日加環境政策協議がバンクーバーで開催された。会合においては、UNCEDフォローアップ、APECにおける環境配慮等について意見交換等が行われた。
(オ)このほか、スペイン、フィンランド、スウェーデン、ノルウェー等との間で、協力プロジェクトを通じ、環境分野の国際協力を実施している。
(3) 海外広報等の推進
我が国が、深刻な公害問題を克服する過程で得た豊富な経験や環境分野での知見を国際社会に提供することや、日本が地球環境問題に積極的に取り組んでいることを国際社会に伝えることは、我が国が国際社会において責任ある役割を果たす上で重要である。
このため、環境庁は、環境白書を英訳した「Quality of the Environmentin Japan」や英文の季刊ニュースレター「Japan Environment Quarterly」を発行するとともに、日本の環境政策の紹介のための広報パンフレット「EnvironmentalProtection Policy in Japan」の監修や目的に応じた海外広報資料の作成や配布を行っている。また、平成9年にはインターネットを通じた海外広報も(財)環境情報普及センターを通じて開始した。