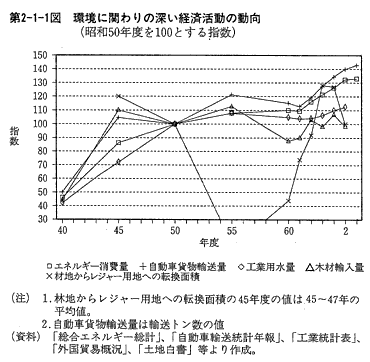
我が国の社会・経済は、これまで景気変動の波を受けながら、構造を変化させ、発展し、成長してきた。ここ数十年の視野で見ると、我が国は、昭和30年代から40年代後半までの高度経済成長期に重化学工業化を成し遂げ、経済は年率10%前後で急速に成長したが、48年の石油危機を契機として、より低い成長率での安定成長に移行した。この中で、62年からは内需、とりわけ民間設備投資と個人消費を牽引車とした長期の好況を迎え、これが平成3年後半頃まで続いた。環境に負荷を与える活動の大きさも、このような経済全体の動きと傾向を同じくして変動しているものが多い。第2-1-1図に見られるように、エネルギー消費量、自動車貨物輸送量、木材輸入量など、環境への負荷と関わりの深い経済活動の動向を表す指標は、40年代後半まで急速に増加したのち、概ね安定的に推移し、61年頃から再び増加に転じている。このように、環境への負荷と経済活動とは密接に関連しており、これらを切り離して考えることはできない。
経済は、様々な立場の人々や企業等が取引を媒介として結びつく相互依存的で有機的なメカニズムによって機能している。その様子を生産、分配、支出という経済の循環によって見てみよう。第2-1-2図は我が国の経済の循環についての考え方を示したものである。財貨とサービスの供給のため生産活動が行われると、これに伴い、一方では付加価値が生み出され、他方では自然資源が採取され、各種の廃物が生まれる。次いで、この付加価値は、国民所得として、営業余剰や雇用者所得の形で企業や国民に分配される。分配された所得は、一部は消費(消費支出)に用いられ、また一部は貯蓄されてから投資(資本形成)に用いられる。この過程でも廃棄物をはじめとした廃物が生まれる。これら消費、投資及び海外への輸出に中間消費を加えたものが、財貨とサービスヘの総需要となる。結局、この総需要に対して、生産活動と輸人とにより供給が行われる。こうして経済の輪が形作られているのである。
このように、経済は、様々な主体の様々な活動が相互に複雑に依存した織物となっており、一部の活動だけを取り出して他の活動とは独立に変化させることはできない。このため、環境への負荷を考える場合には、直接に負荷を生じる活動だけに着目し、その活動だけを制限しようとすると困難が多い。環境への負荷を効率的に減らしていくためには、経済の網の目に遡り、その背景事情を解きほぐし、構造的な対応を取っていく必要がある。以下では、この趣旨から、消費、生産、貿易といった経済活動のそれぞれについて環境との関係を見ていこう。