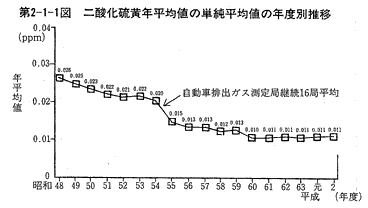
全国に設置されている大気汚染常時監視測定局のデータより、汚染物質別の大気汚染状況をみると次のとおりである。
(1) 二酸化硫黄
ア 年平均値の推移
(ア) 一般環境大気測定局
平成2年度における二酸化硫黄の測定データは、672市町村、1,602有効測定局(有効測定局とは、年間6,000時間以上測定をおこなった測定局をいう。以下同じ。)で得られている。
昭和40年度から継続して測定している15測定局における年平均値の単純平均値の経年変化は、第1部第1-1-3図のとおりであり、42年度の0.059ppmをピークとして、全般的に減少を続けている。平成2年度は0.010ppmで元年度の0.011ppmと比べ概ね横ばいである。
(イ) 自動車排出ガス測定局
平成2年度における二酸化硫黄の測定データは、57市町村、69有効測定局で得られている。
昭和48年度から継続して測定している16測定局における年平均値の単純平均値の経年変化は、第2-1-1図のとおりであり、全般的に減少を続けている。平成2年度は元年度と同じく0.011ppmであった。
イ 環境基準の達成状況の推移と現状
(ア)長期的評価に基づく環境基準の達成状況
環境基準の長期的評価では、年間にわたる1日平均値につき、測定値の高い方から2%の範囲内にあるものを除外した1日平均値(例えば年間365日分の測定値がある場合は高い方から7日分を除いた8日目の1日平均値)が0.04ppmを超えず、かつ、年間を通じて1日平均値が0.04ppmを超える日が2日以上連続しない場合を環境基準に適合するものとしている。
長期的評価に基づく環境基準の達成状況の推移は第2-1-1表のとおりであり、ここ数年概ね横ばいである。
(イ) 短期的評価に基づく環境基準の達成状況
一般環境大気測定局について、1日平均値がすべての有効測定日で0.04ppm以下の測定局数の有効測定局数に対する割合は、平成元年度の97.6%に対し、平成2年度は98.9%であり、また、1時間値がすべての測定時間において0.1ppm以下の測定局数の有効測定局数に対する割合は、平成元年度の94.1%に対し、2年度は96.0%と高い水準で推移している。
自動車排出ガス測定局について、1日平均値がすべての有効測定日で0.04ppm以下の測定局数の有効測定局数に対する割合は、平成元年度の84.6%に対し、2年度は88.2%であり、また、1時間値がすべての測定時間において0.1ppm以下の測定局数の有効測定局数に対する割合は、元年度の92.3%に対し、2年度は94.1%と高い水準で推移している。
(2) 二酸化窒素
ア 年平均値の推移
(ア) 一般環境大気測定局
平成2年度における二酸化窒素の測定データは、636市町村、1,367有効測定局で得られている。
昭和45年度から継続して測定している15測定局における年平均値の単純平均値の経年変化は第1部第1-1-1図のとおりであり、昭和54年度以降減少傾向がみられていたが、昭和61年度から増加に転じ、平成2年度は元年度と同じく0.028ppmであった。
(イ) 自動車排出ガス測定局
平成2年度における二酸化窒素の測定データは、182市町村、318有効測定局で得られている。
昭和46年度から継続して測定している21測定局における年平均値の単純平均値の経年変化は第1部第1-1-1図のとおりであり、平成2年度は元年度と同じく0.041ppmであった。
イ 環境基準との対応状況
二酸化窒素に係る環境基準については、昭和53年7月に環境庁告示第38号(以下、本項において「告示」という。)をもって「1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること」と改定されるとともに、1日平均値が0.06ppmを超える地域にあっては原則として7年以内に0.06ppmが達成されるよう努め(告示第2の1)、また、1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域にあっては、原則として、このゾーン内において、現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努める(告示第2の2)ものとされた。環境基準達成状況の評価は、年間における1日平均値のうち低いほうから98%番目に相当するもの(以下「1日平均値の年間98%値」という。)とこれらの基準値を比較して行う。
平成2年度の一般環境大気測定局1,367有効測定局及び自動車排出ガス測定局314有効測定局(試料採取口が車道にあるものを除く)について、環境基準との対応状況をみると、第1部第1-1-2図のとおりである。
一般環境大気測定局について、1日平均値の年間98%値が環境基準のゾーンの上限である0.06ppmを超える測定局をみると、昭和53年度以降減少し、近年は年度による変動はあるが概ね横ばいで推移してきており、平成2年度は6.3%で平成元年度の4.8%に比べ増加している。
また、自動車排出ガス測定局について、1日平均値の年間98%値が0.06ppmを超える測定局は112測定局(35.7%)であり、東京都、大阪府、神奈川県等の大都市部に集中している。
ウ 二酸化窒素の環境基準に基づき区分されたゾーン内にある地域の動向
二酸化窒素の環境基準に係る1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域の環境濃度の動向については、告示第2の2中の現状の水準にあたる昭和52年度及び62年度から平成2年度までの測定結果によれば、第2-1-2表のとおりである。
エ 一酸化窒素
(ア) 一般環境大気測定局
平成2年度における一酸化窒素の測定データは、636市町村、1,365有効測定局で得られている。
昭和46年度から継続して測定している28測定局における年平均値の単純平均値の経年変化でみると、第2-1-2図のとおりであり、46年度以降減少傾向をたどり、ここ10年程度は概ね横ばいで推移してきており、平成2年度は元年度と同じく0.023ppmとなっている。
(イ) 自動車排出ガス測定局
平成2年度における一酸化窒素測定データは、182市町村、318有効測定局で得られている。
昭和48年度から継続して測定している21測定局(二酸化窒素に同じ。)における年平均値の単純平均値の経年変化は、第2-1-2図のとおりであり、平成2年度は0.068ppmで元年度の0.072ppmに比べ減少した。
(3) 一酸化炭素
ア 自動車排出ガス測定局
一酸化炭素の主要な発生源は自動車である。したがって、その汚染の程度を把握するには、交通量の多い道路端、交差点付近等における一酸化炭素濃度の推移を見ることが必要である。平成2年度における一酸化炭素の測定データは、186市町村、315有効測定局で得られている。
(ア) 年平均値の推移
昭和46年度から継続して測定している14測定局における年平均値の単純平均値の経年変化は、第1部第1-1-6図のとおりであり、年々減少する傾向にあったが、ここ数年はほぼ横ばいであり、平成2年度は2.3ppmとなっている。
(イ) 環境基準の達成状況
環境基準の長期的評価では、年間にわたる1日平均値につき、測定値の高いほうから2%の範囲内にあるものを除外した1日平均値が10ppmを超えず、かつ、年間を通じて1日平均値が10ppmを超える日が2日以上連続しない場合を環境基準に適合するものとしている。
一方、短期的評価では、1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下である場合を環境基準に適合するものとしている。
自動車排出ガス測定局309有効測定局(試料採取口が車道にあるものを除く)すべてで長期的評価並びに短期的評価に基づく環境基準を達成している。
イ 一般環境大気測定局
平成2年度における一酸化炭素の測定データは、158市町村、186有効測定局で得られている。環境基準の達成状況をみると、すべての有効測定局において長期時評価並びに短期的評価に基づく環境基準を達成している。
(4) 光化学オキシダント
ア 平成2年度における光化学オキシダントの測定結果
平成2年度における光化学オキシダントの測定データは、一般環境大気測定局については573市町村、1,056局で、自動車排出ガス測定局については25市町村、39局で得られている。
光化学オキシダントの出現頻度は、気象条件により大きく左右されるため、年度により増減はみられるが、平成2年度は元年度に比べて大きく増加している。61年度から継続して測定している一般局973測定局、自排局36局について1局当たりの注意報発令濃度(1時間値0.12ppm)以上の平均日数は、第2-1-3表のとおりである。
イ 平成3年における光化学オキシダント注意報等の発令状況等
(ア) 全国の注意報等発令状況
平成3年の光化学オキシダント注意報(光化学オキシダント濃度の1時間値が0.12ppm以上で、気象条件からみて、汚染の状態が継続すると認められるとき発令される。)の発令は、延べ121日(15都府県)であった。これは、平成2年の242日(22都府県)の半数に減少し、昭和58年(131日)及び59年(135日)とほぼ同じレベルであった。(第2-1-4表)
発令延日数の月別内訳は、4月に1日、5月に7日、6月に39日、7月に53日、8月に8日、9月に13日となっており、特に6月と7月に発令が多かった。
なお、3年の注意報発令日における光化学オキシダント最高濃度は0.247ppmであった。また、光化学オキシダント警報(地方公共団体により発令基準は異なるが、通例光化学オキシダント濃度の1時間値が0.24ppm以上で、気象条件からみて、汚染の状態が継続すると認められるとき発令される。)の発令は1回もなかった。
(イ) 注意報発令の地域内訳
3年の注意報発令延べ日数の地域内訳をみると、東京湾地域(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の1都6県)で87日、大阪湾地域(京都府、大阪府、奈良県及び兵庫県の2府2県)で12日となっており、これら2地域で全体の約82%を占めている。
(ウ) 被害届出人数
3年の光化学大気汚染によると思われる被害者の届出人数(自覚症状による自主的な届出による)は1,454人で、過去3番目に少なかった昨年の58人に比べ大きく増加し、過去10年間では昭和58年(1,721人)、59年(5,822人)に次いで多い人数となっている。
(5) 非メタン炭化水素
昭和51年8月中央公害対策審議会より「光化学オキシダントの生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針について」が答申され、この中で、炭化水素の測定については非メタン炭化水素を測定することとし、光化学オキシダントの環境基準である日最高1時間値の0.06ppmに対応する非メタン炭化水素の濃度は、午前6〜9時の3時間平均値が0.20〜0.31ppmCの範囲にあるとされている。
ア 一般環境大気測定局
平成2年度における非メタン炭化水素の測定データは、239市町村、338測定局で得られている。
昭和53年度から継続して測定を行っている6測定局の6〜9時における平均値の年平均値の単純平均値の経年変化は第2-1-5表のとおりである。
イ 自動車排出ガス測定局
平成2年度における非メタン炭化水素の測定データは、102市町村、156測定局で得られている。
昭和52年度から継続して測定を行っている9測定局の6〜9時における年平均値の単純平均値の経年変化は、第2-1-5表のとおりである。
(6) 浮遊粒子状物質
平成2年度における浮遊粒子状物質の測定データは、一般環境大気測定局については、622市町村、1,282有効測定局で、自動車排出ガス測定局については117市町村、157有効測定局で得られている。
環境基準の長期的評価については、年間にわたる1日平均値につき、測定値の高い方から2%の範囲内にあるものを除外した1日平均値が0.1mg/m
3
を超えず、かつ年間を通じて1日平均値が0.1mg/m
3
を超える日が2日以上連続しない場合を環境基準に適合するものとしている。
長期的評価に基づく環境基準の達成率は、近年は横ばいで推移してきたが、一般環境大気測定局については、平成元年度の65.2%に比べ、2年度は43.1%と減少した。(第2-1-3図)
また、昭和49年度から継続して測定を行っている40測定局における年平均値の単純平均値の経年変化は第1部第1-1-7図のとおりであり、全般的に減少傾向を示しているが、ここ数年は横ばいとなっている。
(7) 降下ばいじん
降下ばいじんは、大気中の粒子状物質のうち、重力又は雨等によって降下するばいじん、粉じん等である。
平成2年度の測定地点1,342地点中、有効測定時間以上測定を行っている1,290地点について降下ばいじん量別の測定地点数をみると、20t/k?/月以上30t/k?/月未満を示した地点は4地点(元年度4地点)、30t/k?/月以上を示した地点は9地点(元年度8地点)である。
(8) その他の汚染物質
近年、粒子状物資については、単にその量だけでなく、成分等その質的な面で注目されている。全国の主要地域に設置されている国設大気汚染測定所においては、前述の常時監視測定されている物質以外に、ハイボリウムエアサンプラーにより採取した浮遊粉じん中の成分(ベンゼン可溶性物質、硫酸イオン、硝酸イオン、バナジウム等重金属、ベンゾ[a]ピレン等)及びローボリウムエアサンプラーにより採取した浮遊粒子状物質中の成分(アルミニウム、バリウム等31元素)の分析を行っているほか、昭和57年度からは水銀についても測定、分析を実施している。また、アスベスト、水銀、有機塩素系溶剤等については、昭和60年度より順次隔年で継続的なモニタリングを実施しているが、これまでの調査結果では、いずれも直ちに問題になるようなレベルではなかった(第2-1-6表)。
(9) 国設環境大気測定所における測定結果
全国の主要な平野部の端に国設環境大気測定所を設置し、汚染物質の常時測定を行っているが、これらの測定所の測定結果は未汚染地域の濃度(バックグラウンド値)がどの程度であるかを知るための良い手掛りとなっている(第2-1-7表)。