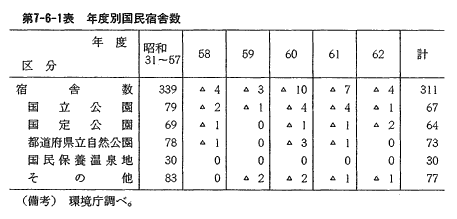
1 温泉、休養施設、野外活動施設地区の整備
(1) 温泉
ア 温泉
我が国は、世界でも有数な温泉国であり、温泉地は国民の保健休養地として極めて重要な役割を果たしている。昭和62年度末現在、全国の温泉湧出源泉数2万1,095か所(うち自噴源泉5,095か所、動力の装置された源泉9,597か所、未利用源泉6,403か所)、湧出量は1日換算約280万tに及んでいる。「温泉法」は、これらの温泉を保護し、その適正な利用を図ることを目的としており、温泉を堀削又は増堀する場合、動力を装置する場合には都道府県知事の許可を、温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする場合には都道府県知事又は保健所設置市のうち政令で定める市の長の許可を受けなければならない旨定めている。全国の62年の許可数は、温泉の掘削846件、増堀59件、動力の装置443件、浴用又は飲用1,915件であった。
イ 国民保養温泉地
国民保養温泉地は、温泉地のうち、温泉利用の効果が十分に期待され、かつ健全な保養地として大いに活用される場を「温泉法」に基づいて環境庁長官が指定した地域である。昭和62年度末現在75か所1万989.38haを指定している。
昭和61年度に、国民保健温泉地(国民保養温泉地のうち、医師の協力を得て温泉の保険的利用を促進することが期待できる条件を備えた温泉地)を7か所指定し、63年度も温泉センター、園地、歩道等の施設整備に対し引き続き補助を行った。
(2) 国民宿舎
国民宿舎は、自然環境に恵まれた休養適地における、国民の低廉かつ快適な宿泊休養を目的とした施設である。昭和62年度末宿舎数は311か所であり(第7-6-1表)、62年度の利用者数は844万人であった(第7-6-2表)。
(3) 国民保養センター
国民保養センターは、自然公園等の休養適地に主として地域住民の日帰りレクリエーション活動と保健休養を目的とした施設である。昭和62年度末センター数は69か所であり(第7-6-3表)、62年度の利用数者は263万人である(第7-6-4表)。
(4) 身近な自然活用地域 −自然観察の森−
自然観察の森は、自然の喪失が著しい大都市及びその周辺において、身近な自然とのふれあいを求める国民のニーズが急速に高まっていることにかんがみ、三大都市圏及び政令市等において身近な自然とのふれあいを促進するための拠点をモデル的に整備し、自然保護教育を推進して行こうとするものである。この事業は、小動物等とのふれあいを通じて、自然の仕組についての理解を深め、自然に対する愛情とモラルを育くむため、昆虫や野鳥の誘致林など、小動物の生息環境の創出を図るとともに、自然観察の拠点となるネイチャー・センターやその他自然観察路、観察小屋等の施設を総合的に整備することを内容としている。計画では全国10地区の整備を行うこととしており、昭和63年度は、継続4地区の整備の他、新規2地区の整備に着手した。
(5) 自然休養林等
国有林野のうち森林を主体とした風景が優れ、かつ、林業経営等との調整を図り得るところで、国民の保健及び休養の用に供することが適当と認められる地域を対象として指定された自然休養林(92か所、総面積約11万ha)については、伐採制限、風致施業等を行うとともに、遊歩道、園地等の利用施設を設け、森林の保健休養機能の積極的な発揮を図った。
また,森林レクリエーションの需要の増大及び利用形態等の多様化に対処して、森林の有する多面的機能との調和を図りつつ、国有林野に各種森林レクリエーション施設を総合的に整備するヒューマン・グリーン・プランを積極的に推進し、昭和63年度は群馬県沼田市など4地域の地域指定を行った。
(6) 観光レクリエーション地区(家族旅行村)
観光レクリエーション地区は、主として家族が恵まれた自然の中で手軽に観光レクリエーション活動を楽しみつつ保養することができるよう、その整備を進めており、昭和63年度においては、9地区の継続整備を行うとともに、新規3地区において実施設計調査を行った。
(7) 少年自然の家
少年自然の家は、少年を自然に親しませ、団体宿泊訓練を通じてその情操や社会性を豊かにし、心身を鍛練し、もって健全な少年の育成を図ることを目的とする社会教育施設であり、昭和63年度は、国立第12少年自然の家(山口県)の設立準備室を10月に設置し、平成元年度の機関設置に備えるとともに、国立13少年自然の家(長野県)以降の施設整備等を推進するほか、公立少年自然の家6か所の建設事業に対して補助を行った。
(8) 国立青少年野営場
青少年が自然の中でのキャンプ生活を通じて自立心や忍耐力を身につけ、自然の美しさや厳しさを体験することができる国立南蔵王青少年野営場(宮城県)の運営のより一層の充実を図るとともに、該当施設の整備を行った。