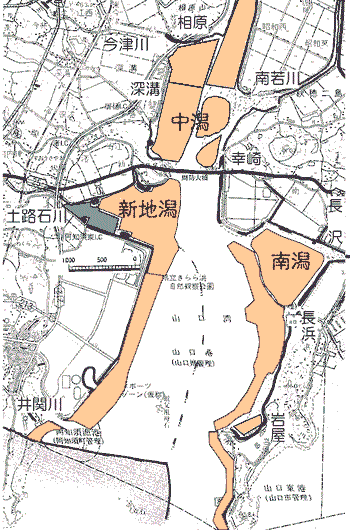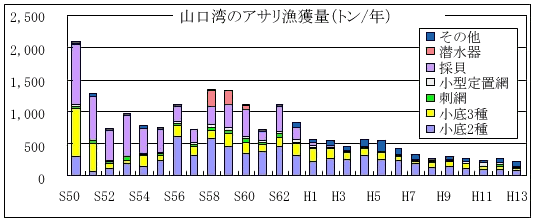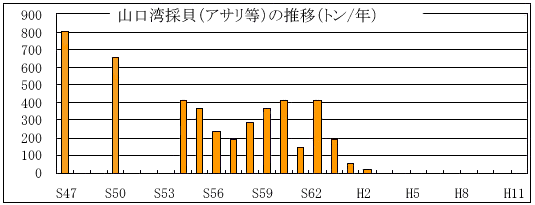ナルトビエイは天然や放流したアサリを食べる「害魚」。ブラックバスも在来種の魚を餌にする人間には迷惑な魚です。そんな魚が立派な料理に変身しました。地元ではナルトビエイの大群が押し寄せている光景が新聞やテレビで報道されているので、委員らは「これがあのナルトビエイですか」と興味津々。「他で食べたという話は聞いたことがありません。この自然再生協議会ならではのユニークな企画ですね」などと、異口同音に満足の感想を漏らしていました。
この自然再生協議会は地域住民、NPO、学識者、行政などの構成メンバーが多彩であるだけでなく、活動の中身も自然を体感する企画などが盛りだくさん。新鮮な驚きがあるのでなかなか好評のようです。干潟の生態系や物質循環などは、まだ未解明の部分が多く、委員の立場や意見も多様です。そうした委員同士の「距離感」は、「できるところから始めよう」「柔軟に考えよう」という自然再生協議会の運営によってぐんと縮まっているように見えます。
試食会のアイデアも柔軟な発想から生まれました。昨年11月に開かれた調査研究・モニタリングワーキンググループの討論で、干潟のアサリがナルトビエイに食べられている話題が提起されました。暖かい海域にいるナルトビエイは、近年夏場になると瀬戸内海に大挙押し寄せ、瞬く間に漁業者が放流したアサリを食べて壊滅的な被害をもたらします。漁獲しても傷みが早いので商品価値はほとんどありません。「利用できれば数を減らすことが可能では。まずどんな魚なのか食べてから対策を考えよう」という提案に、「アサリを食べているのだから、きっと魚肉はおいしいはず」という期待も加わって、試食会実施がすんなりと決まりました。
季節外れのナルトビエイは、県水産研究センターに冷凍保存してあったものを使いました。素早く処理すれば十分食べられる魚なので、採算ベースに合う活用方法が研究されているのです。
試食会に合わせて、隣の県漁協秋穂支店からはエビ、椹野川漁協からはアユやシジミなども集められました。県漁協山口支店運営委員長(漁協組合長に相当)の岩本和美さんは試食会で「以前たくさん採れていたアサリが復活し、協議会で頑張っていただいている皆さんにアサリの吸い物を味わってもらえる日が早く来て欲しい」と、干潟の再生へ期待を述べました。