

|
|
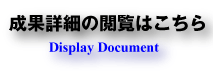 (2.5Mb)
(2.5Mb)
|
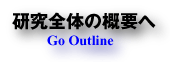
|
研究代表者 |
国立公衆衛生院 労働衛生学部 |
内山巌雄 |
厚生省 国立公衆衛生院 |
生理衛生学部体力生理室 |
佐々木昭彦 |
保健統計人口学部 |
兵井伸行 |
|
建築衛生学部 |
高橋美加 |
|
環境庁 国立環境研究所 |
社会環境システム部環境計画室 |
原沢英夫 |
警察庁 |
科学警察研究所交通部交通安全研究室 |
西田泰 |
筑波大学 |
体育科学系環境保健学研究室 |
本田靖 |
大阪教育大学 |
教養学科健康科学講座 |
永井由美子 |
長崎大学医学部 |
原爆被災資料センター疫学部 |
本田純久・三根真理子 |
公衆衛生学教室 |
門司和彦・竹本泰一郎 |
|
Mahidol University, Faculty of Environment and Resource Studies, |
Laddawan Thong-Nop, |
|
Thailand. |
Kobkaew Manomaipiboon, |
|
Rungiarat Hutacharoen |
||
平成8〜10年度合計予算額 13,743千円
(平成10年度予算額 3,639千円)
温暖化による死亡リスクの予測を1972-1995年既存統計を用いた分析を基に行った。日最高気温と日別死亡率の関係では65歳以上の高齢者では日最高気温が33℃を越えると死亡数が再び上昇するV字型を描く事が確認されたが、1970年代、1980年代、1990年代の3つの期間に分けた時の経年的変化を観察すると、北海道ではV字型の底部の日最高気温が温暖側へ単純シフトしたこと、九州や東京では沖縄県(1981-90年)に見られた様にV字型からL型への移行する傾向が33℃以上の死亡でみられ(1991-95年)、温暖化への異なる適応が生じている可能性が示唆された。これらの気温と外気温の変化に伴う死亡モデルを用いてGISによる地域別の将来リスクの推定を試みた。人口の高齢化を補正しても、各地域で温暖化による死亡リスクが増加したが、死亡以外の影響事象や、都市の環境要因など、複合的かつ時間・空間的に変化する事柄についての分析は十分でなく、今後気温以外の日射量と暑熱負荷量などの指標の選択と、個体と環境を含む動的変化をを考慮したモデルの開発が必要となろう。
一方、タイ国では、既存の正確な死因別死亡統計が入手困難なため、バンコクを中心とする都市部の病院における死亡統計を分析したが、死因が熱帯の感染症や治療の遅れからくる敗血症が中心であり、また気温の季節変動や日内変動が乏しく、影響をどのように評価し、対処すべきかが課題となる。
ライフスタイルの違いによる温暖化への適応機構のうち、生理学的反応を調査する目的で高齢者と若年者の心電図RR間隔変動スペクトル分析(心拍数変動)の調査を行った。60〜75歳の男性の高齢者は健常者でも20代の若年者より明らかに暑熱ストレスヘの自律神経調節能力は低下していたが、その他の生理的指標(直腸温、血圧、脈拍、皮膚温、発汗量)の変化の現れ方は一様ではなかった。すなわち高齢者には暑熱ストレスに対する自覚症状が乏しいこと、暑熱負荷に対して交感神経系が副交感神経系に対して優位を示さなかったり、逆の反応を示すなど、若年者に見られた正常の適応機構が働かない、または著しく遅れる者が存在することがわかった。また、タイおよびわが国で、日常の生活環境温度下におけるこれらの指標を基に温暖化に対する適応機構を分析中である。
今期の研究調査では、以上の結果を総合して、温暖化に対して高齢者がハイリスクグループであること、亜熱帯に属するアジア各国の温暖化による健康リスクの推測は死亡構造や人口の年齢構造が異なるために新たな推測手法が必要であり、今後の研究課題と考えられる。
温暖化、生活環境温度、日最高気温、ライフスタイル、RR間隔変動、健康リスク