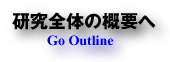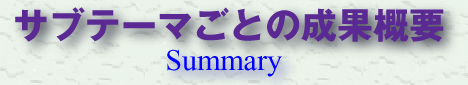
検索画面に戻る Go Research
[B−9 太平洋域の人為起源二酸化炭素の海洋吸収量解明に関する研究]
(5)海洋表層二酸化炭素観測統合データの利用による太平洋・大西洋の比較研究
独立行政法人国立環境研究所
|
|
地球温暖化研究プロジェクト炭素循環研究チーム
|
M. Chierici(EFフェロー)
|
同
|
野尻幸宏
|
同
|
A. Fransson
(日本学術振興会特別研究員)
|
研究協力者
|
|
キール大学海洋研究所
|
H. Lueger
|
|
A. Koertzinger
|
[平成14〜17年度合計予算額]
平成l4〜17年度合計予算額 4,352千円
(うち、平成17年度予算額 0千円)
※上記予算額には、間接経費 1,005千円 を含む)
[要旨]
国際共同観測網の展開として、ドイツキール大学海洋研究所と共同で、大西洋の高頻度表層海洋二酸化炭素分圧測定として、定期貨物船へ観測装置を搭載し、その季節変化、海域分布の観測を2002年2月から開始した。2003年1月までの9往復の大西洋横断航海で、片道16回の測定を行うことができた。航路は北緯35度から50度帯であり、西経35度を境に季節性に大きな相違があることが明らかになった。西経35度より西の米国よりの海域では、CO2変動に与える水温変化項の寄与が大きく、夏の高水温時にCO2分圧が高くなり、年間のCO2分圧振幅が大きい。西経35度より東の欧州よりの海域では、生物過程項の寄与が大きくなり、夏の高水温時のCO2分圧増大を打ち消すように作用して、年間のCO2分圧変動幅が小さくなる。
観測データを利用する海域のCO2フラックスの解析によると、中緯度北大西洋海域は、夏の季節には、ほぼ放出はないか弱い放出であり、秋から冬にかけて吸収があることがわかった。CO2フラックスを算出するひとつの方法は、観測された二酸化炭素分圧差(△pCO2:海洋―大気)と、航路上の風速(QuickSCAT衛星観測)の関係からの計算に基づく。もうひとつの方法は、緯度4度x経度5度のピクセルで平均化した△pCO2と平均化した風速(QuickSCAT衛星観測およびNCER/NCARによる客観解析〉に基づく。両者の方法間では47%のフラックス差を生じ、その原因が風速値の違いによることがわかった。△pCO2の変動の時間スケールは風速変動の時間スケールよりはるかに長いので、ピクセル平均の風速を用いるのが適当である。北大西洋中緯度海域では、北米よりの西部海域が欧州よりの東部海域より大きなCO2吸収源であった。海域の吸収量は50.5GtC/yと見積もられたが、これは、Takahashiらの解析による気候値を用いた結果との違いは少なかった。また、衛星観測と客観解析という2つの風速場の違いはフラックス推定に大きな差を与えなかった。
[キーワード]
海洋表層二酸化炭素分圧、定期貨物船、北大西洋、海域比較、国際共同観測
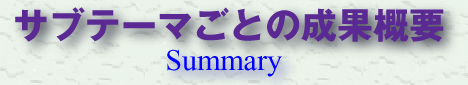
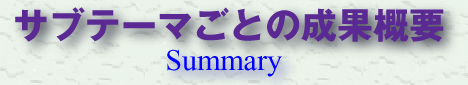
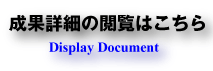 (1.74MB)
(1.74MB)