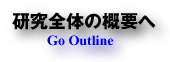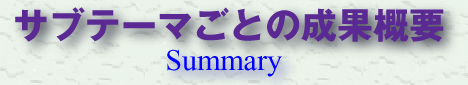
検索画面に戻る Go Research
[B−9 太平洋域の人為起源二酸化炭素の海洋吸収量解明に関する研究]
(2)太平洋の海洋中深層データ解析による長期的二酸化炭素吸収量の解明に関する研究
独立行政法人産業技術総合研究所
|
|
環境管理技術研究部門 地球環境評価研究グループ
|
鶴島修夫・原田晃
|
国土交通省気象庁気象研究所 地球化学研究部
|
石井雅男
|
*北海道大学大学院 地球環境科学研究科
|
渡辺豊
|
[平成13〜17年度合計予算額]
平成l3〜17年度合計予算額 78,691千円
(うち、平成17年度予算額 18,841千円)
※上記の予算額には、間接経費18,168千円を含む)
[要旨]
海洋中深層までの二酸化炭素吸収速度とその変動要因を探るため、太平洋域における海水中二酸化炭素と関連する生物化学パラメータについて既存データの集積と時系列データ解析手法の開発・応用を行った。トレーサーデータを利用した大気から海洋への人為起源二酸化炭素蓄積速度の解析法を用いて、太平洋スケールにおける人為起源二酸化炭素の蓄積速度の時空間分布マップを作成した。その結果、北太平洋全体としては1990年代平均で、0.54±0.01PgC/year(Pg=10g)、また、南太平洋では0.78±0.02PgC/yearの人為起源二酸化炭素を吸収しており、太平洋全体として全海洋の人為起源二酸化炭素の約6割を吸収していることが明らかになった。次に、1970年代以降の北太平洋の二酸化炭素統合データベースを作成した。西部北太平洋定点、東経165度の南北断面、北緯47度東西断面において、海洋中深層における二酸化炭素増加速度を見積もり、約1000m深までの二酸化炭素増加が実測データから検出された。二酸化炭素濃度の観測値そのものの変動は大気との平衡計算により予想される増加速度より3倍程度大きく、海洋の非定常状態が海洋炭素循環にも影響を及ぼしていることが示唆された。太平洋赤道域の海洋表層において、全炭酸濃度やCO2分圧がともに大気CO2濃度の増加応じて増加していることを2種類の方法で評価し、太平洋赤道域の表層にも人為起源CO2が蓄積されていることを明らかにした。エルニーニョ南方振動にともなって、この海域から大気へのCO2放出量が0.1PgC/yrから0.9PgC/yrの範囲で大きく変動したことを推定した。同期間に実施した赤道域の全炭酸濃度の各層観測結果に基づいて、中部赤道域の温度躍層付近でも、全炭酸濃度が同様に増加していることを明らかにした。これらのことから、北太平洋西部亜熱帯域12)やオーストラリア南方の南大洋13)だけでなく、太平洋赤道域でも、他の海域とほぼ同じ速度で全炭酸濃度が増加していることを明らかにし、亜熱帯循環における亜表層の南北循環がCO2の輸送に重要な役割を担っていると推定できた。
[キーワード]
二酸化炭素、海洋、太平洋、人為起源、吸収速度
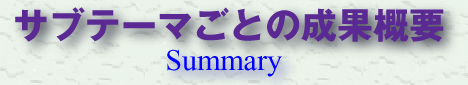
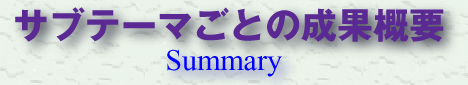
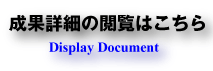 (4.61MB)
(4.61MB)